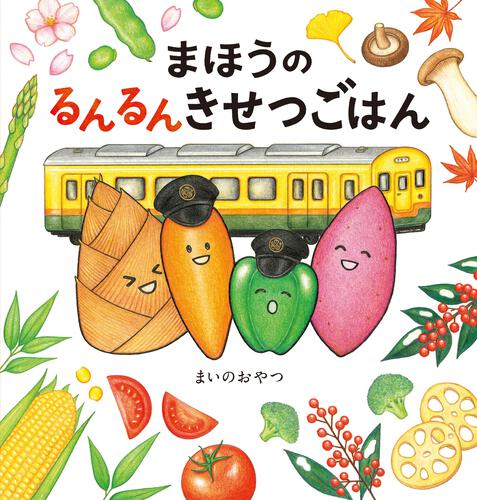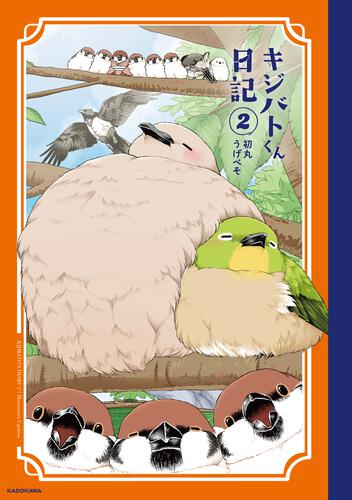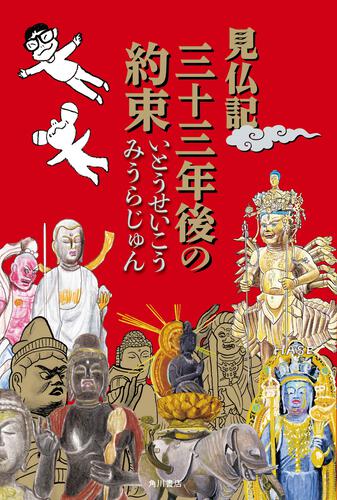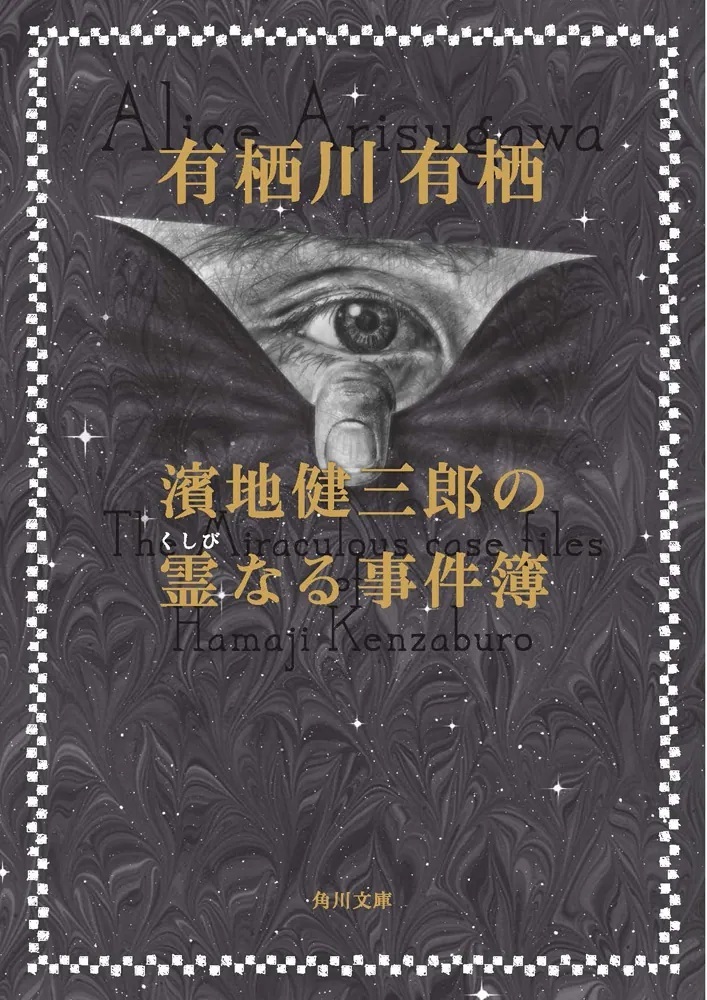2
電車から、流れる朝の風景をぼんやりと眺めていた。ほとんどの人が自家用車で移動するこの地域では、電車の利用者は少ない。腰掛けたシートの足元には暖かい風が流れてきて、凍えていた体がだんだんと感覚を取り戻す。学生服に包まれた
何度かそれを繰り返したのち、今度は高い声が眠気を妨げた。
「アーサー! おっはよ」
跳ねるように電車に乗り込みながら、
「十一月ってこんな寒かったっけ? あー、電車あったけー」
十六歳にしては幼い声が電車の中に響き渡り、まばらな乗客たちがちらりとこちらに視線を向ける。しかしそれを気にする素振りもなく、榎本は話を続ける。
「こんな寒いのにさぁ、教室にあんなヒーター一個だけってありえねえよなあ。しかもあるの教卓の方だし。職員室みたくさぁ、エアコンつけてくれればいいのに」
俺は周りの反応を気にしながらも、声を潜めることなく返す。
「金ないんだろ、きっと。うちの学校貧乏っぽいもん」
「それな! 北高は全部のトイレにウォシュレットあるらしいよ。ずるくね?」
「おっ、さすがエノ、堂々と学校でうんこしてる宣言」
「は、はあ? してねえし! 一般論? ってやつだし!」
高い声で榎本が騒ぐ。変声期を迎えていないその
「てかさぁ、アーサーもクリスマス会参加するっしょ?」
榎本は昨日からこの話ばかりしている。昨日、どこからともなくクリスマス会の話が出てきた。十二月二十四日、クリスマスイブ、学校はちょうど二学期最後の日だ。その日は終業式だけで終わる。なのでその後、学年全体で何かをしてクリスマスを楽しもう、という会らしい。とはいえど家族や恋人と過ごす者も当然いるので、自由参加だ。クリスマス会なんて仰々しく掲げたところで、結局はカラオケやボウリングに行く程度で、いつもの放課後と大して変わりはないことが容易に想像できる。
それでもその話題が出たとき、クラスは盛り上がった。来年は三年生に上がり、受験モード一色になる。修学旅行もなく、文化祭や体育祭への積極的な参加もない。そんな中での学年全体のイベントは、どんなにぱっとしなくても貴重だ。
「あのさあ、まだ十一月入ったばっかなんですけど。そんな前からそわそわしてるのお前くらいだぞ」
「なんでだよー! アーサー楽しみじゃないのー?」
「いやぁ、俺もクリスマスにはもしかしたら予定があるかもしれないしなぁ」
「えっ! 予定入る予定あんの!?」
「いや、今んとこ皆無」
「なんだしー! ビビったぁ」
電車が学校の最寄り駅へ着く。この駅で降りるのはほとんどがうちの学校の生徒たちだ。校則は緩く、色とりどりのコートやマフラーでホームが染まる。榎本が赤いチェックのマフラーに
改札を出ると、徒歩や自転車で通学している学生たちと合流する。白い息があちこちで舞い上がって曇天に溶けていく。駅から徒歩七分程度の道のりで、俺と榎本はくだらない話をしながら学校へ向かう。
「おっす」
急に肩を
「はよー」榎本が返す。「もっち。今日も走ってきたん?」
「おう。めっちゃあっちぃ」
「この寒さの中で汗かいてるの、もっちくらいだよ」
俺の言葉に、まあな、と何故か自慢げににやりと笑う。
「朝から体力有り余りすぎだろ」
「ま、俺はどっかのおっさんとは違って若いからな」
「うっせ、誰がおっさんだ」
毛利の軽口に俺が反論する。毛利は悪天候の日以外は、暑かろうが寒かろうがいつも走って学校に来る。冬でも日に
「ねー、もっちもクリスマス会行くでしょ?」
頭一つ分背の高い毛利を榎本が見上げる。毛利が額に
「まだなんも決めてない。その場のノリかな」
毛利は「ノリ」という言葉をよく使う。要するに、周りの雰囲気や空気の流れのようなものだ。確かに、俺たち高校生にとってノリは大事である。
「ってか、もうクリスマスの話? エノ気ぃ早くね?」
えーっ、と榎本が声を上げる。
「ほーら、やっぱ言われた」
「なんでー!? みんなドライすぎっしょ! クリスマスだよ、もっとわくわくしようよー!」
「それよか、俺はその前にある期末試験の方が
毛利の言葉に「それな」と同調する。「それは言わない約束だろー」と榎本が騒ぐ。
校門が見えてくる。反対側からも同じように生徒たちが歩いてきていて、開け放たれた門の中へと次々吸い込まれていく。俺たちもそれに倣う。
そして校舎が現れる。一年の頃は異質なもののように見えていたその巨大な建物にも、今ではすっかり慣れてしまった。歴史ある、といえば聞こえはいいが、要するに古ぼけているだけだ。榎本の言う通り、エアコンもなければウォシュレットもない。机や椅子などの設備も年季が入っていて、全体的に時代を感じさせるつくりだ。三十人弱が詰め込まれた教室が一学年につき四クラス分の、小さな学校。校庭を取り囲むようにコの字の形をしていて、教室の窓からは体育の授業に
朝練に励む野球部を横目に、校庭の脇を通って校舎の中に入る。自分のクラスの下駄箱に向かおうとすると、集団がその前に陣取っていた。女子生徒たちが、一人の男子生徒を取り囲んで何やら質問攻めにしている。
「だからね、うちんちでクリスマスパーティーしようって話になってて。
「どうかな? もう何か予定とかって入っちゃってる?」
「クリスマス会なんて行かないもんね?」
真ん中に立つ赤崎
「はーい、すいませーん。ちょっとどいてくださいねー」
言いながら俺は、下駄箱を隠す女子を体で押しのける。女子が不満気な声を出してじろりと
「あさくん」
天に名を呼ばれ、顔を上げる。心なしかほっとした表情で俺を見つめる彼に、「天ちゃん、おはよ」と声をかける。天はおはようと返すと、これ幸いと言わんばかりにその群れから抜け出した。考えといてよねー、と女子生徒の一人がその背中に声をかける。
「相変わらずすごい人気だね、王子」
毛利が思わずといった感じで漏らす。そんなことないよ、という
当然、とんでもなくもてる。あまりにもてすぎていて、他の男子は
「王子はさー、クリスマス会は行かないの?」
「お前はさっきからそればっかだな」
「それ、エノ流の朝の挨拶なの?」
毛利と俺がからかうと、榎本が顔を赤くして何やら
「僕は、多分行かないかな」
「えー、まじかー! でもまぁそうだよな、王子ともなると予定の一つや二つ……」
「三つや四つ……」
「いやいや、ないない。そんなないよ」
「天ちゃんは毎年、終業式が終わるとすぐじいちゃんばあちゃんちに行くんだよ」
困ったように笑う天に助け船を出すと、「そうなんだ。毎年恒例で」と慌てたように付け加えてくる。
俺と天は家が近所で、小中高と学校が一緒の、いわゆる幼馴染というやつだ。最近はすっかりなくなってしまったが、中学くらいまでは家族ぐるみの付き合いもしていた。
「なんだー。王子が来るなら女子の参加率上がると思ったのになー」
「エノはそれよりも自分の予定がクリスマス会しかないことを憂うべきだぞ」
「もっちはほんとやなことばっか言う!」
そんなことを言い合いながらたらたらと歩いていると、廊下にチャイムの音が響き渡った。朝のホームルームの始まりを告げる本鈴だ。やべえ、と毛利が呟くのを合図に、俺たちは教室へと走る。途中ですれ違った学年主任が「走らない!」と怒鳴るが、そんな言いつけを守っている余裕はもちろんない。
違うクラスの天と別れ、俺たち三人は自分のクラスのD組に駆け込む。担任の姿はまだなく、息を切らしながらセーフ、と呟くと、アウトだよ、と背後から担任に頭を叩かれた。
「早く席に着け」
「はーい」三人揃って返事する。
そうして、また一日が始まる。