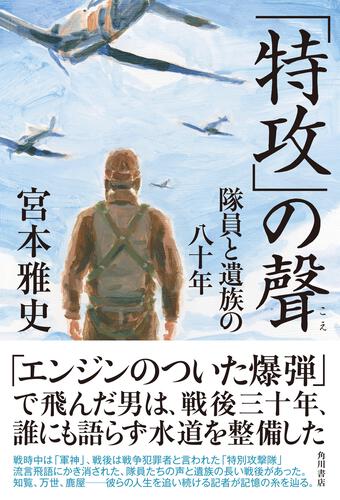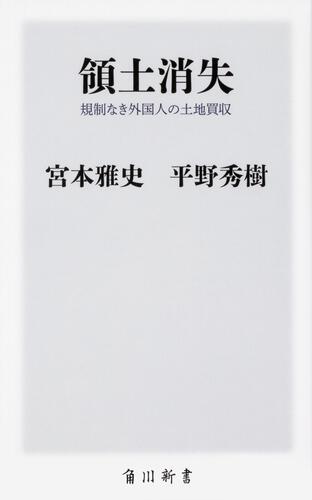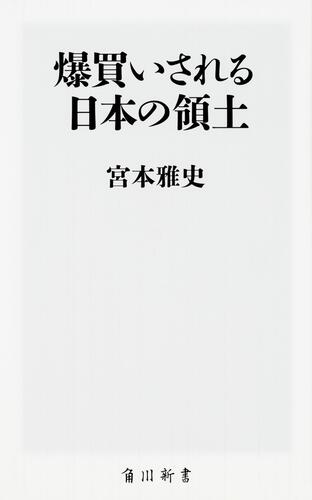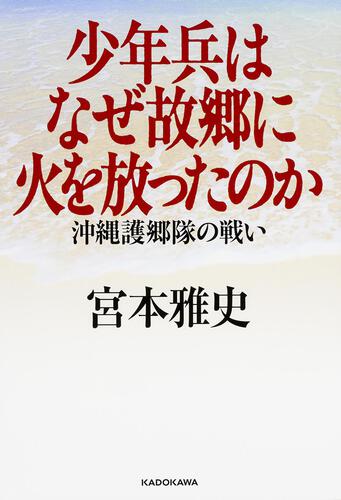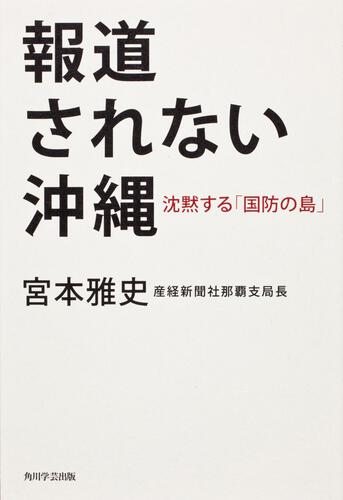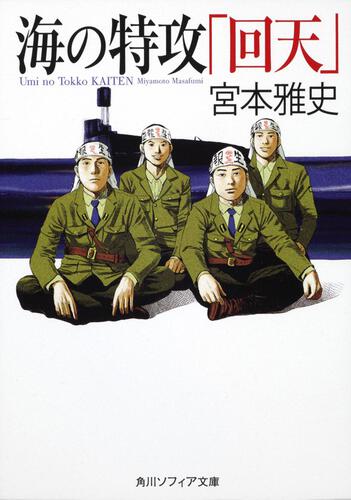2025年は終戦から80年という節目の年。
先の大戦では、多くの日本兵が絶望的な状況で戦地へと向かっていきましたが、そのなかには文字通り命を懸けて「必死必殺」の作戦に臨んだ特攻隊員たちの姿がありました。
なぜ彼らは待ち受ける死に向けて過酷な訓練に耐え、出撃していったのか――。
根源的な問いに突き動かされ、30年以上にわたり、元隊員やその家族、同胞たちの「聲」に耳を傾けてきた取材の旅路を辿ります。
是非、本編でお楽しみください。
宮本雅史『「特攻」の聲 隊員と遺族の八十年』試し読み
※漢数字を適宜アラビア数字に直しています。
※可読性を考慮し、引用した手紙・手記・文献は原文より、原則として片仮名・旧仮名遣い・旧字体は平仮名・新仮名遣い・新字体に修正しました。著者が適宜補足した箇所は( )を付し、一部省略した場合には(前略)(……)(後略)と示しています。
序章 笑顔の奥の真実を求めて
子犬を抱いた少年兵
九州から沖縄までは片道600キロ。航空機で2時間余りの航程だ。現在のように自動操縦装置はない。レーダー誘導もない。風の変化を計算し、羅針盤と航空地図だけを頼りに飛ぶ。航程の大半は、敵のレーダーから逃れるため、海面すれすれの低空飛行だ。神経を研ぎすまし、一瞬たりとも気が抜けない。踏ん張り続ける脚はこわばり、手は
敵艦隊を見つける。雲の合間から敵のグラマン戦闘機が襲い掛かる。隊長が手を挙げ、力強く、前に振る。「突撃」。エンジンを全開にして急上昇する。高度1000メートル。突入態勢を整え、狙いを定めると無電の電鍵をたたく。「ワレトツニユウス」。歯を食いしばり、敵艦隊を見据えて操縦桿を前に倒す。
敵艦船からは対空砲が嵐のように激しく襲いかかる。敵の砲弾が
エンジンはうなりを上げ、急降下する。敵艦隊が目の前に迫ってくる。敵の攻撃をかわすためスピードを上げると、揚力で機体が浮いてしまう。気を失いそうだ。思わず目をつぶりそうになるが、目をつぶれば機体がぶれて、目標を見失う。最後まで、カッと目を見開いて目前に迫る敵影をにらみ、操縦桿をしっかりと押さえる。
突撃開始から目標までは約2キロ。時間にするとわずか10秒足らずだ。
特攻隊に関心を持ったことがあれば、一度は目にしているのではないかと思う写真がある。5人の少年兵の写真だ。
小さな子犬を抱いて微笑む少年を笑顔の少年たちが囲んでいる。全員、飛行服に飛行帽、白いマフラーを巻き、首からは飛行時計をぶらさげている。飛行帽の上には「必勝」と書かれた日の丸の鉢巻きも見える。
真ん中で子犬を抱いているのが
荒木、高橋(峯)は17歳、早川、千田、高橋(要)は18歳。5人は陸軍少年飛行兵で、第七十二
5人は当初、5月26日に出撃する予定で、この写真は出撃の2時間前に作戦指揮所
人は“死”を目前にして、こんなにも冷静に過ごせるのか、こんなにも屈託のない笑顔になれるのか……。特攻出撃を控えた彼らの邪念のない笑顔の奥に、見落としてはいけない何かがある気がした。彼らが伝えようとしているものは何か。この一枚の写真に突き動かされるように、私は元特攻隊員とその遺族たちに話を聞き始めた。
子犬を抱いた荒木伍長については、前作の『「特攻」と遺族の戦後』(角川ソフィア文庫)で詳述したが、伍長らが所属する第七十二振武隊が編成され、特攻出撃を命じられたのは昭和20年3月30日。5月27日未明に出撃するまでの約2ヵ月間は、死へのカウントダウンの日々だった。“死”が確実にそして着々と迫るなか、少年飛行兵たちはどのように過ごしていたのだろうか。
ひたむきに訓練に励む
荒木伍長は14歳の時、
「航空技術者が夢だった」(実兄・
伍長は、訓練時代から特攻出撃するまでの思いを、漢字とカタカナ交じりの簡単なものだが修養録(日記)に残している。
昭和18年11月8日
大東亜戦以来早くも満二年とならんとしているとき、南方では壮烈なる激戦が展開している此 時 に当り、我々は尚 一層勉励致し、国に報ゆるの務めを尚一層固めなければならないと思った。
11月17日
この訓練に打ち勝たねば、立派な操縦者になる事は出来ない。この辛 い訓練の度に、故郷の事を思い、何の此れ位と思い一層奮起せり。
連日のように決意の言葉が
その後、同飛行学校の
昭和19年3月23日
飛行服を着て飛行機に乗る訓練をする。幼少より憧 れの的であったあの堂々たる飛行兵の姿が、今我々も遂に実現したのだ。其の時の気持は只 嬉 しくてたまらなかった。一日も早く立派な操縦士となり国恩に報うべく努力する覚悟なり。(……)今後は益 々 注意事項を良く守り、一意操縦教育に専心し、大空を天 翔 けるべく立派な飛行士となる覚悟なり。
特殊飛行訓練を開始した5月20日には、
最初の飛行であるので少し目が廻 ったが、此れ位で目が廻っては真の操縦者とは謂 えない。(……)空襲其のときは第一番に飛び立ち敵機に打 つかるの気概と技 倆 とを一日も早く向上せねばならないのである。
と書いている。
昭和19年7月24日には目達原教育隊を離れ、朝鮮・
特攻が現実に
荒木伍長がこうした訓練を受けている最中の昭和19(1944)年10月、海軍兵学校第70期の
大東亜決戦も熾 烈 さを加え一大国難に際会致しましたとき特別攻撃隊等の諸先輩に引続き愈 々 皇国の為奮励する覚悟です。
と、葉書を出している。葉書は12月20日に丑次の手元に届いているが、明らかに特攻攻撃を現実のものとして意識した内容だ。
修養録は、昭和20年2月18日に再開しているが、文面は以前とは打って変わり、「死生観」や「特攻」の字が多くなっている。
此の緊迫する一大時機に我空中勤務者として奉公出来るのは真に武人の面目此の上なし。特攻の精神を以 て訓練に内務に勉励せん。敵機来 らば敢然此の腕を以て此の襲撃機を操縦して敵に体当りを敢行し潔く散華せん。
死生観に透徹し、死して汚名を残さず名誉を後世に残さん。
修養録は同年3月17日から5月16日まで再び記されていない。元特攻隊員の
同年5月17日、出撃命令を受けて平壌から目達原基地へ移動した荒木伍長らは、同基地から北西に約3キロ離れた
修養録は、目達原基地へ移動したこの日に再開している。
待ちに待って居た門出である。(……)平壌を出発、決戦続く沖縄へ沖縄へと前進す。必ずやる一撃轟沈より外になし。(……)大刀洗時代の目達原飛行場に到着す。(……)銃後の期待に添わん大戦果を挙ぐ。
5月20日には、
突撃訓練のため飛行場に行く。而 し悪天候のため演習せず、休憩所に待機す。町又は部落人の赤誠にある贈りものと慰問にて大高笑や腹ぶくぶくにて下痢を起す次第なり。
午 后 〇〇時、明日出撃せよとの有難き命令を受く。只感慨無量。
一撃轟沈を期すのみなり。
慰問者絶えず延 数何百人を数う。
最后の秋 を朗らかに歌い別れの
と途切れ、修養録は終わっている。
20日の文章が「歌い別れの」と途中で終わっていることについて実兄の精一は、「最後まで書く時間がなかったのか、それとも感極まったのか……その時の弟の気持ちを考えると胸が詰まる」と目頭を押さえた。
修養録を読み進めると、荒木伍長は、戦局の悪化と共に、国家のために前線に行くことを当然と考えるようになり、特攻作戦が展開されると、自ずと出撃を決心しているように思えてくる。そこには、少しの迷いも
不安と恐怖との戦い
伍長と同じ振武隊の隊員で、移動途中の敵襲で大やけどを負い、特攻作戦に参加できなかった西川信義軍曹(故人)は、終戦直後の昭和20(1945)年11月15日、群馬県桐生市に伍長の父、丑次を訪ねている。
丑次と一緒に立ち会った弟から精一はその時の様子を聞いていた。
「西川さんは、仏壇の前で座ったきり、泣きじゃくっていたそうです。特攻隊員の中には出撃命令を受けて泣いてしまう隊員もいたようですが、弟たちの部隊はいつも明るくて、朗らか隊と呼ばれていたそうです」
この西川軍曹は生前、特攻命令を受けたときの気持ちを次のように書き残している。
負けるためでなく自分が死んで勝つものならと、死を志したものであった。(……)しかし特攻隊は出撃したらもう帰って来ない。帰えられないのは体当たり攻撃をするための、出撃であるので致し方ないが、果たして死ねるだろうか、操縦桿を握って敵艦目指して突込んで行く事が出来るのか、敵空母に眼がくらんで逃げるかも、いやいや、急降下してぐんぐん空母の艦板が眼の前に、眼を閉じて突込むのだろうか――等考えさせられた。いざ死ぬと決めたときはなかなか人間は弱いものだとも思ったり、目標到着までに敵機の攻撃や、艦砲射撃等で交戦する事は何も考えず、敵空母に体当たりが出来るのだろうか、体当たりをする。そのことだけを考えたものであった。
(……)
(平壌では)毎晩のように宴会で飲んで歌って踊って楽しく人生を過ごすかに見えたが、酒の量も増してくると、笑い上戸あり、泣き上戸ありで困った事もあった。隊員の中には郷里が遠いため休暇も取れず田舎に帰れず、最後の家族との暇 乞 いも出来なくて心残りのある者もあったが、班長(私が内務班長であった)と一緒に死ぬのだからとなだめて床に入れた事もあった。
正直のところ死にたくはないのが普通である。ただ、ひたすら国のために体当たりするだけを心掛けて、皆無心になるように勉 めたものである。
みながやすやすと特攻を決意できたわけではないのだ。不安と恐怖にさいなまれながらも、国家のため家族のためにと、気持ちを固めていったのである。
ある時、私は鹿児島で父親が特攻要員だったという男性と知り合った。男性の父親は亡くなる直前、初めて息子に、自分が特攻要員だったと告白したという。話をしたのはわずか30分間だけで、父親は多くを語らなかったが、自分が甲飛第13期予科練習生で、昭和20年8月15日に出撃予定だったこと、出撃前は電信柱を見ても、草木を見ても涙が止まらなかったことだけを話し、質問をしてもそれ以上は教えてくれなかったという。彼は私に「父親の気持ちを少しでも理解したいと思い、
電柱を見ても草木を見ても涙が止まらない。健康なのに避けられない死を直前にした、本人にしか分からない感情に、私は言葉を失った。
空白の一週間
修養録が途切れているため、5月20日以降の荒木伍長の内面は最早知りようがない。それでも、伍長らの最後の1週間を書き残した資料はいくつかある。3月30日に特攻の命を受けた後は、ただ、突撃の時を待つための日々だった。『陸軍最後の特攻基地』によると、同じ部隊の千田孝正伍長の機付長(整備責任者)だった宮本誠也軍曹が伍長の父親に宛てた手紙を、少々長いが紹介する。5人の気持ちに近づければと思う。
(前略)五月十七日、九州佐賀の飛行場に降りると、お寺に一週間程宿泊する事になりました。千田君第七十二振武隊は自ら朗 部隊と名をつけた程愉快な連中だったのです。すこしの酒があれば勿 論 そんな物が全然ない時でも歌の聞えない事は珍しいというわけで隊長殿もおとなしかったので、何のこだわりないはつらつとした若さはそこで一段と発揮されました。その頃のあの人々には何の恐れる物もなかった。人におこられるとか、失敗しないだろうかとか、そんなけちな考えは悠久の大義に生きんと言う大理想の前に全然かきけされてしまったのです。全ての行動が自信に満ち純で神を見る如きでした。佐賀に於 ける村の人々の好意は他の所と問題にならぬ程絶大なる物がありました。(……)隊員の方々は申わけない様な顔をして居られました。勿論「特攻隊でもうじき死ぬんだぞ」などと言う高ぶった所は全然みられなかったのです。
いよ/\明日は鹿児島へ出発という日、五月二十四日の夜、皆めい/\に私物の整理をして居ます。手紙を書いて居る人、飴 をしゃぶりながら話をしたり笑ったりして居る人、村の人からたのまれたらしい一筆を日の丸に書いて居る人、孝正君は古い手紙やノートを火鉢にくべて居ました。ちょっと読んではやぶいて焼き、何か思い出す様に、くすぶる煙を見て居られました。思えばあと百時間もない命をそれとなく整理されて居られたのでしょう。二十五日十二時二十分、佐賀目達原の飛行場を離陸しました(……)最後の基地万世飛行場では(……)ちょっと会った時千田君が言われました。「宮本軍曹殿金はありますか」「かね」「えゝ」「金ならあるよ。どうして?」「いや、明日でおしまいですから金がなかったら上げようと思って」「そうかい有難う。いや金はある家に送れよ」それから「これ上げましょう、パイプとめがね」「有難う」「風 呂 敷 、それからお人形」「すまないね」その外いろ/\のものをかたみとしていたゞきました。
(……)二十七日が来てしまいました(……)その前夜二十六日から愛機のつばさの下にうたゝねして一夜を明した整備班の我々は四時少しすぎて孝正君等の引きしまった顔を向えました。たしかにいつもと変った何物かを感じました。神々しいというか、力強いと言うかそんな物を。
陽はまだ出て居ません。(……)孝正君は飛行機の所へこられました。命令を承 けて、既に此の空母をこっちの方から体当りだと目算ある様で自信満々の御様子でした。ふろしきを出して、「宮本軍曹殿弁当食って下さい。」「いゝよ君の朝めしだろう。」「でももう三時間もたてば突込むんだからいらない。今腹もへってないですから。」「喰 えよ。腹がへっては戦が出来んぞ。」「すぐでかい空母を喰うんだから弁当なんか喰っては喰 すぎて腹をこわしますよ。」と心にくい言葉に私は風呂敷づつみを持たされました。
五時五分前「始動!」(……)車輪止ははずれました。二度と絶対に必要のない車輪止。(……)孝正君がにっこり笑って私に敬礼しました。(……)六番機、千田機です。わらって居ます。手を振って居ます。(後略)
千田伍長は、離陸直前、宮本軍曹に両親に手紙を書いてくれるように頼んでいた。軍曹は上の引用に続けて、
「何も言う事無し。我幸福なり。大君のはなと散り、父母に孝をいたさん。たゞお元気でよろしくお便りされたし、ふるさとに」と若き千田少尉殿の声はぬぐっても消えないひゞきでした。
と伝えている。
宮本軍曹は、千田伍長の父親への手紙の中で、
(西往寺に宿泊していた時期)村の人の好意は非常なものでした
と述べているが、千田伍長は中でも福山芳子の家族と交流があったようだ。
芳子が伍長の父親に宛てた手紙がある。自宅前で家族と撮った記念写真を添えたその手紙には、伍長の日常の様子も綴られている。
(前略)お母さんお母さんと云って御飯頂く時も、私のすぐそばに座してまるで本当の子供が寄りかゝる様にして一処に戴 きました「アラ千田さんは左におはしを持って─と云いましたら自分は小さい時から家に居る時は母のそばで左ギッチョ御飯を頂いて居りました。今日はお母さんのそばだからいいでしょう。(……)お母さん、と云って、それからはお琴をひくのも左の手で、荒城の月と数え歌と、白地に赤くの三つ教えてやりましたら、良くおぼえて下さいました(……)本当にいい子でした。歌がお上手で朗らかに良く歌って下さいました。
そして、5月25日、目達原飛行場を出発する際の様子を次のように報告している。
五月廿 五 日午後五時出発との事でしたので、そのつもりで居りましたところ命令が早くなって正午との急電話に驚いて娘の自転車に同乗してかけつけましたが(……)飛行場についた時は遂 に飛び立って居られました。娘だけ急がせて自転車をはしらせましたところ、やっとお目にかかれたとの事です。
四番機と聞いて居りましたので、一番低空して居る四番機に手を振って千田さん/\と呼びかけました。本当に残念でなりませんでしたが、仕方ありませんでした。
お母さんまだかね/\と、それはそれは待って居て下すったとの事です(……)沢山の花たばを飛行機いっぱいかざって、日の丸のハチマキをしてマスコットを腰に沢山さげて勇ましく出発されました。寸時にして話すことは出来ませんでしたが、残って居られた戦友の言葉です(……)唯 今 では五人前の写真をガクに入れて家の子供と一処に祭棚にお祭りして毎朝晩おがみをして居ります。
『陸軍特別攻撃隊の真実 只一筋に征く』(ザメディアジョン)は、荒木伍長らが西往寺で出撃を待つ間の様子を、隊員らに食事を運ぶなど生活の面倒をみていた南静枝らの証言などを基に紹介している。
隊員たちが寝起きする場所は8畳と15畳の二間続きの大座敷。台所には電話がひかれ、彼らは電話のベルが鳴るたびに、出撃命令かと緊張したという(……)自分たちを「ほがらか隊」と名付けるほど、彼らは底ぬけに明るかった。(……)身の回りのことは自分で行い、洗濯物は裏の川で洗って、庭の木に干した(……)早川勉伍長は「自分が隊長より先に一番機になって突っ込むんだ」と話していたという。荒木幸雄伍長は、出撃と決まった日、私物を整理しながら、「これ、しーちゃんにあげるよ」と言って、ハーモニカを静枝さんに贈った(……)いよいよ鹿児島へ出発するという前日の夜、隊員たちは手紙を書いたり、飴をしゃぶりながら談笑したり、村の人に頼まれて日の丸に一筆書いたりと思い思いに過ごした。千田孝正伍長は古い手紙やノートを読み返しては破いて火鉢にくべ、くすぶる煙をを 見つめていた(後略)
荒木伍長らは、5月25日、西往寺に別れを告げて万世飛行場に移動、出撃に備えたが、沖縄地方の天候不良のため、一日延期になった。最後の夜は、万世飛行場から南東約2.5キロ離れた旧
早川伍長は西往寺に、
(前略)第二の故郷たるべく楽しく過ごした西往寺が思い出となります。今日は万世町はずれの旅館に宿泊致しておりますが、話は皆々様の事ばかりです。静ちゃんより戴いたお人形も静ちゃんが共に居ると思って可愛がっております。そして、共に空母を轟沈させてあげます。何卒安心の程。(後略)
と礼状を残している。
彼らは、それぞれの思いで生への執着を絶ち、出撃していったのである。
別れの
荒木伍長らの出撃を家族はどのように受け止めたのか。
荒木伍長は特攻隊の命を受けた5日後の昭和20(1945)年4月5日、突然、群馬県桐生市の実家を訪れている。
精一によると、伍長は座敷に上がると、神棚に背を向けて正座し、家族全員を座敷に呼んだ。そして、静かな声で「大命が下りました。元気で行きますから」と言い、家族一人ひとりの名前を書いた封筒をそれぞれに手渡した。夕食の際には、父親の丑次に陸軍航空総監賞と刻まれた懐中時計を渡している。食事の間、戦争や特攻の話は一切出なかった。
その数日後、精一は各務原飛行場に弟を訪ねた。
「子供の頃の話や隣近所の話、家の将来のことなどを話した。『かあちゃんは身体が強くないから大丈夫かなあ』『後のことは頼むよ』と言った後、『俺はもういらないから、母ちゃんに渡して』と言って十円札を数枚出して私の手につかませた。私は代わりに『これを持っててくれ』と言って自分の腕時計を渡した」
この日、精一は外泊を許可された伍長とともに軍の指定旅館に泊まった。
「(その翌朝)弟は、旅館で用意した朝食を『部隊で食べるから』と言って断り、私が『元気でな』と言うと、『元気で行くよ。みんなに
と精一は言った。
荒木伍長は家族へ多くの手紙を出している。
昭和20年4月27日消印
(前略)町の有志より歓待を受けたり御送られたり本当に一生の幸福と存じて居ります。(……)自分等は必ずやります。狙う獲物は敵の空母。任務完遂の為には何ものもいといません。我々の死ももう間近に迫って居るのです。
いざ出撃のときは御両親様始め親 戚 方の御期待に添うべく立派なる最期を遂げる覚悟です(後略)
そして、丑次に宛てた最後の葉書にはこうある。
5月27日
最后の便り致します。
其 後御元気の事と思います。
幸雄も栄 ある任務をおび
本日(廿七日)出発致します。
必ず大戦果を挙げます。
桜咲く九段で会う日を待って居ります。
どうぞ御身体を大切に。
弟達及隣組の皆様に宜 敷 く さようなら
伍長は行く先々で、家族に対し、生活の変化と心境を報告し、まるで自分の“決意”を確認するかのように意志を伝え続けている。修養録や手紙、周囲の証言に残された荒木伍長の生きた
出撃前の少年兵の笑顔――。それは、苦渋の末、国家と家族のために“死”を決断した彼らが、目の前に現れた子犬に感じた、生きとし生けるものへのいとおしさの発露だったのではないだろうか。この瞬間、彼らの脳裏には戦争のことも、数時間後には特攻隊として出撃していくという現実も消え
神風特別攻撃隊「
いま一度、彼らの思いに立ち返ることで、未来の日本の姿を考えたいと思う。本書を通じ、読者諸氏に伴走していただけたら幸甚だ。
(続きは本書でお楽しみください)
作品紹介
書 名:「特攻」の聲 隊員と遺族の八十年
著 者:宮本 雅史
発売日:2024年10月04日
彼らは私たちに何を遺したのか? 特攻隊員たちの声なき声に耳をすます
【「エンジンのついた爆弾」で飛んだ男は、戦後三十年、誰にも語らず水道を整備した】
昭和19(1944)年、苦戦を余儀なくされる中で組織された必死必殺の「特別攻撃隊」。大戦中「軍神」として崇められ、戦後は戦争犯罪者と言われた隊員や遺族たちには、胸に秘め続けた想いがあった。
笑顔の写真を残した荒木幸雄、農場経営が夢だった森丘哲四郎、出撃直前「湊川だよ」とつぶやいた野中五郎……自らの命を懸けた特攻隊員たちは、私たちに何を託したのか? 30年以上にわたり元隊員と遺族の取材を続けてきた記者が、今だからこそ語られた証言に耳を澄ます。
最初の特攻出撃を見送った第一航空艦隊副官
「娑婆の未練」を断ち切り二度飛び立った元隊員
沖縄で特攻機の最期を目に焼き付けた女性
晩年、想い人の遺影を病床で握りしめた婚約者
彼らの「戦後」は終わっていなかった――
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322402001102/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら