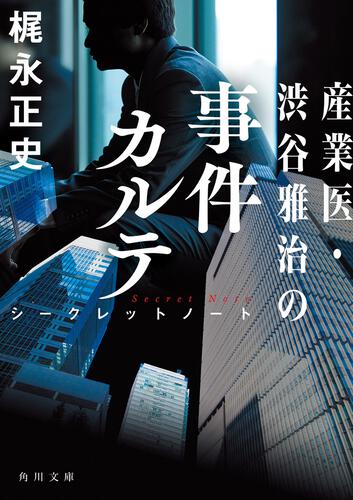産業医・渋谷雅治の事件カルテ シークレットノート
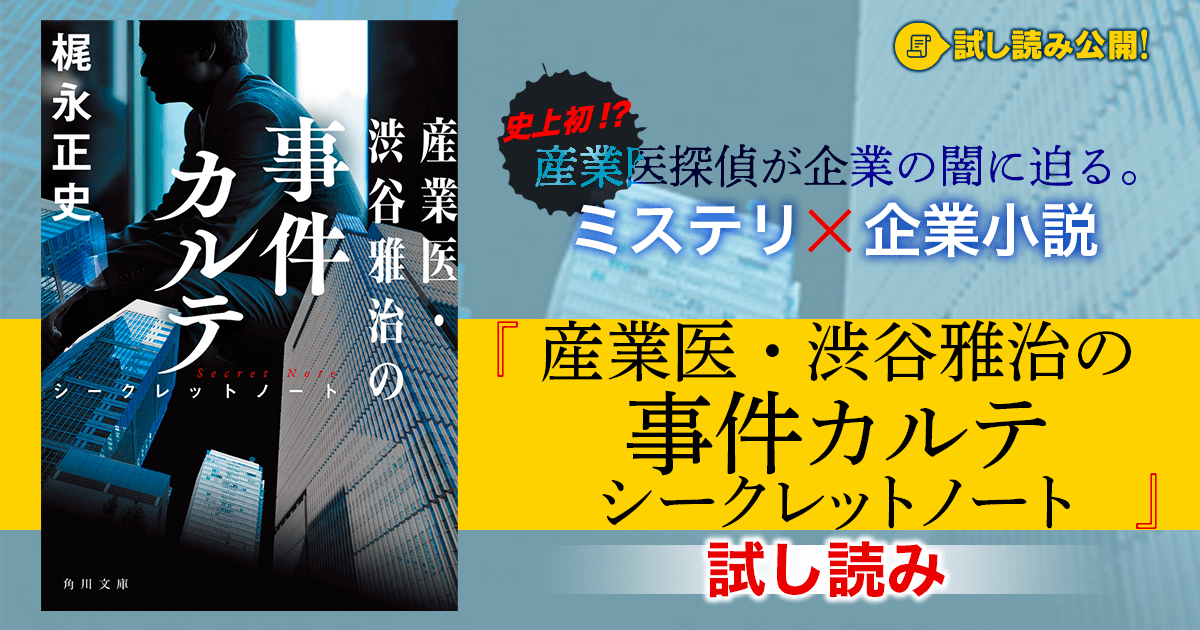
人も、会社も、謎も診る!「このミス」大賞受賞作家の新境地『産業医・渋谷雅治の事件カルテ シークレットノート』試し読み#4
産業医として電機設備製造大手と契約している渋谷雅治は、営業部社員が自殺したことを受け再発防止のために実態調査を頼まれる。実はその死の裏には、会社がひた隠しにする重大な秘密があった――。
「特命指揮官 郷間彩香」「ハクタカ」などのドラマ原作が人気の「このミス」大賞受賞作家、梶永正史さんの最新作『産業医・渋谷雅治の事件カルテ シークレットノート』は、産業医が探偵として活躍する新感覚のミステリ×企業小説です。これまで警察小説を数多く執筆されてきた梶永さんの新境地にして会心作。冒頭部分を公開いたします!
『産業医・渋谷雅治の事件カルテ シークレットノート』試し読み #4
渋谷が自室に戻ってから三十分もしないうちに、友紀がなにやら資料を抱えてやってきた。両手が
ドアを開けてやると、部屋に雪崩れ込み、書類をデスクの上に積み上げた。
「とりあえずこれで全部です。いまだに紙ベースから抜けきれていないから大変」
汗なんてかいていないのに額を
「それで、ざっくりとは見てみたんですけど、長田さんに支払われた残業代はほぼゼロです」
最初に調べようと思ったのは、過度の超過勤務の有無だった。過労死ラインとされる、ひと月の残業時間が八十時間を超えるような状態がなかったかどうかを確認したかったのだ。
「つまり、毎日定時に退社していたということですか?」
「そういうわけでもないんですが、うちは月四十時間までは見込み残業代としてあらかじめ給料に入っていますので、それを超えない場合は申告はいりません」
「じゃあ、申告してないだけで、本当は残業していたってことはないですか?」
友紀は人差し指を立てて見せた。
「いい質問です! そう言うと思いましたよ」
デスクの上で開いたノートパソコンをくるりと回して、ディスプレイを向けてくる。表計算ソフトの出力結果で、縦に日付があり、そのとなりに時刻が分単位で表示されている。
友紀は得意気な顔でスクロールしてみせた。
「これ、長田さんの実際の出退勤時刻です」
渋谷は合点した。
「ひょっとして、ICカードの?」
「そうです、そうです」
社員は皆、ICチップが内蔵された社員証を首から下げており、入退館時に自動改札機のようなゲートを通過する際に、そのカードを読取機にタッチすることになっている。
「こっちがグラフです。直近三カ月で、定時から一時間以内に退社したのは48パーセント。二時間以内まで範囲を広げると、82パーセントまで上昇します」
渋谷はさらに入館時間を見て驚いた。数分のズレはあるにしても、ほぼ同時刻だったからだ。いつも同じ時間に起きて、同じ速度で駅まで歩き、同じ電車に乗っているような人物像を思い描いた。
ときどき遅れが出ているのは電車の遅延だろう。それすら見越して早めに行動しているのか、遅刻は皆無だ。
プロのスポーツ選手などにはルーティーン、つまりそれぞれにきまった所作というものがある。
勝負のときには赤い靴下を履くというような験を担ぐ行為も含め、ルーティーンは心身ともにベストコンディションに近づけることが科学的にも証明されている。
他人には堅苦しく、時に病的にも感じてしまうその行動も、本人にとってみれば安心して物事に立ち向える、心地よいものであるのだ。
長田もそうだったのではないか。
変化を好むというよりも、昨日とおなじ今日があることに幸せを感じ、それを守るために昨日と同じ行動をとりたくなるのだ。
争いを求めない、真面目で穏やかな人物だったのだろうかと想像した。
「ちなみに、これは?」
渋谷は『異常値』と表示されている箇所を指で示した。
「ああ、入退館の時刻が極端に外れているものです。営業活動等で直行直帰することもありますので」
「なるほど」
「というわけで、長田さんは多くの仕事に押しつぶされそうになっていた、というわけではなさそうですよね?」
友紀が同意を求めるように、もっといえば「褒めてくれ」といわんばかりに鼻息を荒くしている。
「そうですね。よく短時間で調べましたね。デキる女ってやつですね」
友紀はご満悦な様子だったが、すぐに
「でも、仕事でそんなに負荷がかかっていなかったのなら、なにが長田さんを苦しめたのでしょうか。ひょっとしてご家族の問題でしょうか」
「そのあたりはまだなんともわかりません。いろんな方からお話を伺ってみないと」
「じゃあ今後の進め方を考えつつ、夕方はちょっと早めに出ましょう」
長田の通夜に行くことになっていた。
そこでようやく、友紀の雰囲気が普段と違っていたことに気がついた。通夜に参加できるよう、喪服を着ていたのだ。
「先生、まさかと思いますけど」
友紀は細めた目で渋谷の格好を
「もちろん、ちゃんと持ってきていますよ」
「先生ならやりかねないから。ちなみに香典袋持ってます?」
渋谷はポケットを
「行く途中のコンビニとかで買おうかと……」
「いいです、あとで持ってきますよ」
友紀は世話焼きの
メモリアル華はJR柏駅から五分ほどの距離にあった。
その道すがら見かけた喪服の群は、すべて同じ方向に歩いていく。まだ早い時間であることを考えると、このあとも多くのひとが訪れるのだろう。長田は顔が広かったのか、それとも自ら死を選んだという悲劇性が、普段は縁遠い多くのひとの足も向けさせているのかもしれなかった。
小さな斎場はすでにひとでいっぱいになっていて、受付を終えても焼香をするまでにさらに待つ必要があった。
渋谷は式場につながる列に並びながら、胃の裏側あたりを針で刺されるような痛みを感じていた。
まるで犯罪現場に戻ってきてしまった犯人のような居心地の悪さだった。
乾いたスポンジに水が吸い込まれていくように、こころが重く、冷たくなっていく。そして流露する記憶──。
あれは二年前の冬のことだった。
渋谷は大学病院に精神科医として勤務していた。多くの患者と接する傍ら論文を読み
日本は先進国のなかで人口あたりの精神科の病床数が最も多く、入院期間も最も長い。これは治療よりも、まず隔離すべきとの考え方が根底にあるからで、事件報道で〝容疑者は精神科の通院歴がある〟と伝えられるたびに世間から懐疑の目をむけられることも、こうした考えに影響しているのだろう。
入院といっても〝精神病患者はなにをするかわからない〟という先入観から、なかば監禁に近い処置を受ける患者もおり、それは人権侵害の温床になっていると国際的にも問題視されている現状があった。
渋谷は世界より三十年遅れているとも言われるこうした古い考え方を嫌悪していた。患者は最先端の精神医療を受ける権利がある。そう思っていた。
ある日、十七歳の少女を担当することになった。
中学三年のときに受けたいじめをきっかけに不登校になり、やがて統合失調症を発症していた。感情の平板化が顕著で、意欲の欠如、思考障害などの症状が見られた。
精神病は健常者の日常生活から離れた世界におくべきものではない。研究が進み、脳内物質の異常であることがわかってきて、それに対応する薬も開発されている。極端なことを言えば、風邪や糖尿病などと同じように、通院し、薬を飲んでいれば日常生活を送ることができるのだ。
少女も、少女の家族も、その説明に安心してくれた。
投薬とカウンセリングの効果もあり、少女がこころを開いてくれるまで、さほど時間はかからなかった。薬と精神科リハビリテーションを組み合わせた治療プランも的確だったのだろう。表情は明るさを取り戻し、診察が楽しみだとさえ言ってくれた。
世界中の論文を読み学会へ参加し、得られた知識を実践してきた。その成果が表れたのだと実感した。
自分は精神医療の最先端にいるのだと、悦に入っていたのかもしれない。
それだけに、少女が自殺したと聞いた時、渋谷の世界は暗転した。それは渋谷と話をしたその日の夜のことで、自室で首を
──先生はひと殺しです。
葬儀に訪れた際、少女の母親に言われた。
その頃、渋谷は精神医療の先進国であるイタリアの大学病院へ留学することになっていた。イタリアでは精神科病院が撤廃されている。どうやってそれを成し得たのか、自分の目で確かめたかった。
その準備のため、担当患者の引き継ぎも進めていた。少女は自分の後輩にあたる医師が受け持つことになったが、優秀な人物だったから問題はないと思っていた。
──先生、本当は私もイタリアに行きたいけど、頑張って待ってるから、おみやげよろしくね。
そう言って病院をあとにした。それが最後だった。
──どうして入院させてくれなかったんですか。
両親は渋谷を責めた。渋谷しか悲しみをぶつける相手がおらず、悪意はない。それは理解していた。
それでも、その言葉は
自分はなんでもわかった気でいた。先人たちの血が
〝知識〟は
──頑張って待ってるから。
大切なサインを、見逃していた。彼女は、頑張らせてはいけなかったのだ。
それだけは間違いなかった。
渋谷は、大学を去った。
渋谷が式場に入れたのは受付から十分が過ぎた頃だった。
祭壇に飾られた長田の写真。ささやかな笑みをうかべるその顔は、真面目で誠実そうな性格を示しているようだった。
同じ会社にいたとはいえ、関わりがなかった──いや、ひょっとしたら社内のどこか、食堂や廊下ですれ違ったことがあったかもしれない。言葉は交さなくても、同じ空気を吸っていた仲間なのだ。
そう思うと、長田の死というものが、とたんに身近に感じられてくる。
やはりどこかで会っていたのだろうか。記憶の沼の奥底から、なにかが抜け出そうともがいているような感覚があった。
顔を見たらはっきりと思い出すだろうかと思ったが、
電車に飛び込んだということなので、遺体の損傷が激しかったのかもしれない。まだ幼い娘に、最後のお別れにひと目、父の顔を見せてやることもできないのか。
それを思うとこみあげてくるものがあった。
参列者の
祭壇に一番近い参列席。親族に挟まれた椅子が二つ欠けていた。
誰から聞いたのか、友紀が体を寄せて教えてくれた。
どうやら、長田の忘れ形見である女児の体調が優れず、先ほど母親に連れられて控室に下がってしまったようだ。
いたたまれない思いを抱えながら霊前に手を合わせる。いまできるのは、せめて安らかに、と祈ることだけだ。
ふたたび目を開けたとき、唐突に、長田の写真に重なるように少女の姿が
渋谷の頭には、大学で研究していた際に出会ったある言葉が蘇っていた。
ダグラス・ホフスタッターというアメリカの認知科学者が、若くして妻を亡くした際に残したものだ。
〝あなたは今、その失意のヒバリ号で航海に出ている。それが、今のあなたがすべきことだから──いずれあなたは戻ってくる。回復には時間がかかるだろうが、落ち着きを取り戻し、元気になって戻ってくるだろう。わたしたちはみなあなたの帰りを待ち、この海岸であなたを出迎えるつもりだ〟
つまり、『こころのなかで生き続ける』という言葉は単なる
『私』という人格は自分の中だけに存在するのではない。人格を語るうえで目の前にそのひとの肉体があるかどうかは必ずしも問題にはならず、『私』を知る者たちによって認識され、脳の中で記憶として存在する。
ひとがひとを失うのは、生命科学的なことだけではなく、そのひとがどんな思いを持っていたのかを理解できず、誤解したまま忘れることだ。
──もしあのひとが生きていたら、こんなときどうするだろう?
──もしいまもそばにいてくれたら、なんて声をかけてくれるだろう?
そういう局面に遭遇したとき、人格を正しく理解していれば、そのひとが言うであろう言葉を迷いなく聞くことができるのだ。
自分にもまだできることがあるとするなら、それは長田の最後の声を拾い上げることだ。彼がなにに心を痛めていたのか。なぜ電車に飛び込んだのか。それを突き止めることができれば、長田という人格は正しく認識され、遺族のこころの中で寄り添い、生きていける。
少女の幻影に追い立てられるように、渋谷の思考はある一点に帰着していった。
──それが、できることのすべてだ。
通夜振る舞いが用意されている控室を案内されたが、そこにも多くのひとが集まっていた。もともと長居をするつもりはなかったが、渋谷の姿を認めた顔見知りの社員が瓶ビールを掲げるので、一杯だけ飲んで退散することにした。
しかし飲み干したと思えば横から新たな手が伸びてきて、ふたたびビールが満たされる。これを何度か繰り返した。
ふと気付くと友紀の姿が見えなくなっていた。参列者の多くは会社関係なので、知り合いにでも会ったのかもしれない。
渋谷はトイレに行こうと集団を離れた。館内マップを見ると半円状の中庭を囲むように、男子トイレと女子トイレへ
案内に従い通路を進むと、突き当たりに友紀の姿があった。
「あれ、筒塩さん、どうしたんです?」
こっちは男子トイレ側だが、間違えたのだろうか。
友紀は声をかけられるとハッと目を丸くしたものの渋谷だと分かると、視線で窓の外を示した。
そこに一組の男女がいた。
「あれは、鍋倉さん?」
友紀は
「女性のほうは長田さんの奥様の
えっ、と千鶴の表情に注目する。
あのひとが──。
喪服をきっちりと着こなしてはいたが、髪はほつれ、
鍋倉が、エスコートするように片腕を背中に、もう片方は反対側の建屋に向けて伸ばした。斎場に戻るように促しているように見えた。
しかし千鶴がその手をはねのけ、鍋倉の胸の辺りを力なく
「そういえば、奥様も元社員だったんですよね?」
「はい、鍋倉さんが営業部長のときで、特に長田さんには目を掛けていたそうです。それで、課は違いますが同じ営業部の千鶴さんを紹介されたとか。一時期、飲み会なんかでは『キューピッドおじさん』って呼ばれてて、ご本人もまんざらではなさそうでした」
「鍋倉さんも、つらいな」
同意を求めた訳ではなかったが、それでも返事がなかったので肩越しに友紀を見やると、小さく握った右手の
「筒塩さん?」
呼びかけると、離脱していた魂が戻ってきたかのようにきょとんとした目を向けてくる。
「はい、なんでしょう」
それから思い出したかのように言う。
「あ、先生どうします? 千鶴さんに長田さんのことを聞きます?」
もう一度中庭に視線を戻す。そこにはもう誰もいなかったが、憔悴した千鶴の姿が目に焼き付いていた。
「いえ、いずれはお話を伺うべきだとは思いますが、落ち着かれるまではそっとしておいたほうがいいでしょうね」
「そうですよね……。じゃあ、私はそろそろ帰りますけど、どうします?」
「僕もそうします」
ふたりはまだ長く続く記帳の列に逆らうようにホールを抜け、来たときよりもやや時間をかけて駅まで戻った。
地下鉄
電車は
(この続きは本書でお楽しみください)
作品紹介
産業医・渋谷雅治の事件カルテ シークレットノート
著者 梶永 正史
定価: 792円(本体720円+税)
史上初!? 産業医の名探偵。人の先に、会社も診る!
産業医として電機設備製造大手と契約していた渋谷雅治は、営業部社員が自殺したことを受け再発防止のために実態調査を頼まれる。関係部署を回り、その社員について情報を集めていく渋谷。すると当初感じていた自殺者の人物像が変わっていき、原因がわからなかったその死が、ひとつの真実を導き出していく。やがて背後にリコールすべき重大案件が隠されていることがわかり……。彼はなぜ死んだのか? 産業医探偵が謎に迫る!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322008000171/
amazonページはこちら