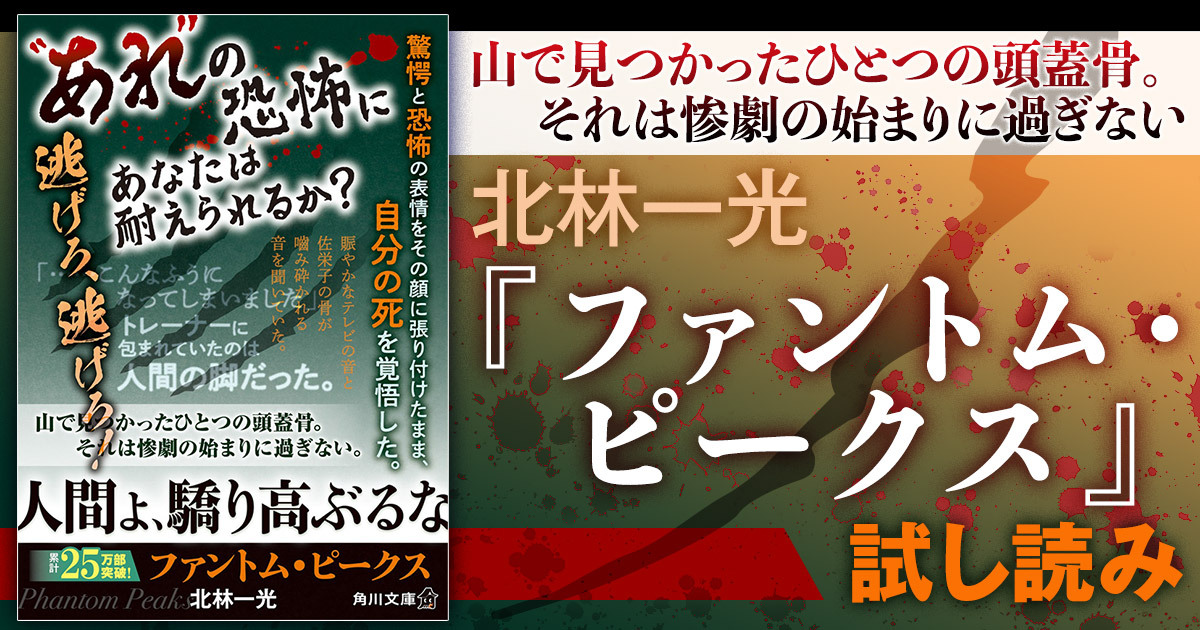15 五月二十三日 烏川林道上部Ⅱ
〈生駒建設〉の作業員が林道沿いの崖に落石防護柵を設置する作業を終えた時、すでに日没がすぐそこまで迫っていた。三、四十分も経てば太陽が山陰に隠れ、あとは足早に夜が忍び寄ってくる。にもかかわらず、陽一がいまだに山から降りてきていなかった。下山の際には林道の作業現場に立ち寄って自分に一言声をかけて行くように──周平はそう念押ししてあった。陽一がその約束を忘れたり、声をかけそびれたということは考えにくい。それよりなにより、今日はまったく現場を離れずにほとんどの時間を崖に組まれた足場ですごしていたから、陽一が林道を通れば周平の方で気づいたはずだ。
周平はいやな予感に囚われた。陽一の身になにかよからぬことが起きたのではないか……。厳密にはまだ日没前だから、取り越し苦労ということもあり得るが、一度心の中に芽吹いた心配は野放図に膨らんだ。生駒にその旨を告げ、単身バイクで林道を駆け登った。今日の陽一の捜索区域の起点である橋を目指して急いだ。
ササ藪の急斜面に異変を嗅ぎつけたのは、バイクが左の急カーブに差しかかろうとする時だった。それは周平だからこそ引き寄せた僥倖といえるかもしれない。杳子の死因に不審を抱いて以来、周平の山中でのバイク走行は脇見運転が常習化している。ちょっとした異変も見逃すまいと、周囲に眼を配ることが半ば習性のようになっている。東向きのその斜面がすでに薄闇に覆われていたことも幸いした。周平は鬱蒼としたササ藪の中に仄かな光の明滅を見たのだ。あとでわかったことだが、それは車のウインカーの灯だった。
周平はバイクを停めて光の方角を眺めた。バイクのヘッドライトを向けてよくよく見ると、ササが薙ぎ倒された形跡が一直線に延びていた。陽一の車が転落したのだと思って血の気が引いた。慌てて斜面を駆け降りようとしたが、頭の片隅にわずかに残されていた理性がそれを思いとどまらせた。
周平は「死ぬなよ」と呟き、後ろ髪を引かれる思いでバイクをUターンさせ、急いで工事現場に戻った。現場にはすでに誰もいなかった。全速力で林道を走った。三分後に〈生駒建設〉のワゴンを視界に捉え、クラクションを激しく鳴らして急を報せた。ブレーキを踏んだワゴンに追いつき、運転席の生駒に事故車のことを告げた。ワゴンには岡村という五十代の作業員が同乗していた。
生駒は「そりゃえらいことだ」と眉毛を吊りあげた。「周さん家にいる坊やの車かい?」
「わかりません」と周平は答えたものの、状況から推してその公算が大であると覚悟していた。「とにかく、まだ中に人がいると思うんです」
「じゃあ、すぐ救けに行かなきゃ」
生駒はいい、車をUターンさせようとしてハンドルを切りかけた。
「ちょっと待ってください」と周平が制した。「ああいう落ち方だと、乗っていた人間は頭などを強打していることも考えられます。素人判断で動かすのはかえって危険かもしれません。申し訳ないですが、社長がこのバイクで走って、どこかで警察と消防に連絡してもらえませんか」
「ああ、それは構わんが……。で、周さんはどうするんだ?」
「岡さんと車であそこに戻って、事故車の様子をたしかめておきます。人がいて、おれたちで運び出せるようならそうしますし、危険と判断したら、救援を待ちますよ」
「よし、わかった」といって生駒は車を降りた。「警察や消防には〈須砂渡ロッジ〉で電話する。連絡がついたら、おれもすぐに引き返すわ」
「お願いします」
それぞれの運転手が交替し、ワゴンとバイクは上手と下手に分かれた。
周平の運転するワゴンが事故現場に辿り着く頃には薄暮が訪れていた。
「おいおい、ありゃ、ひっくり返ってるんじゃないのかい?」助手席から降り立った岡村が事故車を見て顔をしかめた。「えらいところに落ちたもんだな。周さん、あんた、よく見つけたね」
周平は「ひとまずおれが見てきます」といって、ワゴンのラゲッジスペースから四十メートルのロープを取り出し、その一端を近くの木の幹にもやい結びで結んだ。ロープなしでも降りられそうな傾斜だが、あとあと救出のことを考えると、あった方がいいと判断したのだ。
懐中電灯を手に、周平は滑るように斜面を駆け降りた。転落していたのは陽一のハイラックスではなく、オデッセイだった。正直、周平はほっと胸を撫でおろしたが、事故の状況は深刻なものだった。車は横ざまに回転しながら落ちたと思われ、今は完全に腹を上に向けている。そのわりに天井部分が潰れずに原形を保っているのは、おそらくササ藪がクッションになったということだろう。灌木群が車体を受け止めてそれ以上の落下を防いでいるが、車は斜面の下方、運転席側にやや傾いている。ノーズ部分の潰れは衝突の痕跡だと思われた。
周平の眼がまず捉えた人影は、俯せの格好で助手席の窓から上半身だけを晒している女だった。年の頃は六十代半ばくらいに見える。周平はしゃがみ込み、女の手を取った。たしかな温もりがあった。女の顔に自分の顔を近づけてみると、微かに息をしていた。だが、頭に怪我を負っているらしく、流れ出た血が左のこめかみから頬にかけてを染めている。その体勢からいって、おそらく彼女は転落後に自力でなんとかここまで這い出てきたに違いないと周平は思った。
「もしもし、大丈夫ですか」と周平は女の耳元でいった。
返答はなかった。
「聞こえますか」
もう一度、声をかけたが、やはり反応は見られなかった。女は完全に意識を失っていた。陽が落ちて急速に気温がさがりはじめていたので、周平は女の躰が冷えないように自分の作業着を脱いで彼女にかぶせた。それから地面に這いつくばって窓から車の中を覗き込んだ。今は下になっている天井のほぼ中央部分に男が仰向けの格好で横たわり、散乱した荷物の中に埋もれていた。「大丈夫ですか」と窓越しに一声かけた。男はぴくりとも反応しない。セカンドシート部分のドアを開けようとしたが、ロックされていた。もともと運転席側のドアは灌木が邪魔していて開けられない。ためしにリアハッチはどうかと思って手をかけたが、やはり開かなかった。周平は業を煮やし、窓を叩いて「生きているか!」と怒鳴った。返事はなく、男が動く気配もなかった。
「お~い、どんな様子だい?」
斜面の上から岡村の声が聞こえた。
「車にふたりいました」と周平は大声で答えた。
「生きてるのかい?」
「ひとりは生きていますが、怪我をしていて意識もありません。もうひとりは未確認です」
「おれもそっちへ降りて行こうか。怪我人がいるなら、運ばにゃいかんだろう」
「怪我人の搬送は専門家にまかせた方がいいかもしれません。岡さんはそこにいて、社長が戻ってくるのを待ってもらえますか。なにかあったら声をかけます」
「わかった」
周平は自分にできることもなくなってしまった気がしたが、時間を無駄にするべきではないと考え直した。女の脇を抱えて、静かに外へ引きずり出す。小柄な女だが、意識のない人間は砂袋のように重く、扱いにくかった。どこを怪我しているのかわからないので、躰に触れるだけでも相当に神経を使わなければならず、思ったより難渋した。なんとか全身を外に出すと、女が呼吸しやすくなるように俯せだった姿勢を右向きに変えた。そして、周平は開いている助手席の窓に身をくぐらせた。エアバッグや散乱する荷物を掻き分けながら天井をずるように後方へ移動し、腕を伸ばしてセカンドシート部分のドアのロックを解除した。これも周平の大柄な体格ではなかなかの重労働になった。それに、不安定な車体が揺れるので、肝を冷やした。外に戻ってドアの把手を引くと、ドアは軋んだ音を立てて抵抗した。転落の衝撃で歪んでいるらしかった。なんとかこじあけ、あとは一気に引き開けた。旅行バッグ、座席クッション、ティッシュペーパーの箱、道路マップや芳香剤といった雑貨を掻き出すと、男の全身があらわになった。