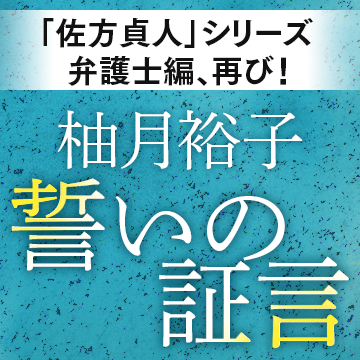七月最後の夜、健次はいつもより早く帰宅した。「お鍋? いい匂い」と、健次はネクタイをほどきながら尋ねてきた。
常に目線は対等だし、家事は女の仕事などと口が裂けても言わない人だ。
「うん、もうすぐできるよ。例によって味の保証はしないけど」
私は料理にまったく自信がない。ネットで拾ったレシピを忠実に再現するだけの料理を、健次はいつも手放しで褒めてくれる。
「大丈夫。ママの料理はたいていおいしい。な、一翔」
「うん。辛いのと緑の豆以外はね」
「緑の豆はパパも嫌いだ。あんなもんは食べなくていい」
「豆なんて納豆だけあれば充分だよね」
「ああ、充分だ」
まるで約束していたとでもいうように連れだって風呂場へ消えていって、あっという間に戻ってきた二人とともに、久しぶりに家族で食卓を囲んだ。
東京、三鷹の2LDKの賃貸マンション。70㎡という広さも魅力だったが、井頭公園まで歩いて十五分という立地がこの家に決めた一番の理由だ。飲料メーカー勤めの健次と、美容師をしている私の収入とでは少し背伸びした物件だったが、一翔が生まれてから引っ越してきたこの家はいつも笑いにあふれている。
「いただきまーす!」と大声で叫んですぐ、一翔がテレビのリモコンを手に取った。二人で食事をするときはテレビを観ることを許しているが、パパがいるときはつけないと普段から約束していた。
「一翔、今日はパパいるでしょ」
私は一翔からリモコンを奪い取った。ちょうど十九時のニュースをやっていた。内容も食卓にふさわしいものと思えず、消そうとしたが、健次が画面を見つめながら「あ、ごめん。ちょっと観ていい?」と制してきた。
去年、日本中が大騒ぎになったニュースの続報だ。死刑執行後に?罪だったことが判明した元女性死刑囚の控訴審が今日から始まったという。
私にはニュースの意味さえよくわからなかった。痛ましい出来事だったのは間違いない。事実が明るみに出たときには警察の杜撰な捜査にも、国のチェック体制の甘さにも腹を立てていたが、世論のうねりが引いていくのと比例して、私の憤りも消えていた。
事件の詳細が明らかになるにつれ、むしろ不可解さが募っていった。その元死刑囚は生前一度も再審請求をしていなかったという。それを理由に「国の金を使った壮大な自殺」などという批判をネットで目にしたこともある。さすがにその意見には同意できなかったけれど、彼女が死を望んでいたのは間違いないのだろう。
すでにこの世にいない女性の控訴審というニュースには、どんな意味があるのだろう。誰が、何を訴えているのか。元死刑囚の女性はそれを望んでいるのか。部外者の私には何も判断できなかったし、健次がなぜこのニュースに興味を抱くのかもわからない。
私の視線に応じるように、健次はやりづらそうにつぶやいた。
「彼女、僕と同い年なんだよね」
そうか、生きていればまだ三十一歳なのか……と思う程度で、その言葉の真意はやっぱりわからない。
「ニュース、つまらないよ。替えるよ」と、一翔が再びリモコンを手に取った。画面が原色のうるさいバラエティ番組に切り替わる。
いつもなら怒ってテレビを消すところだ。でも、空気がかすかに弛緩したのを肌で感じ、私はどこか救われた気持ちになった。
父親と遊べたことによほど興奮したらしく、一翔はなかなか寝つかなかった。家にいるときはたいてい健次が寝かしつけてくれるが、今日はめずらしく早くからお酒をのんでいたこともあり、私が受け持つことにした。
結局、一翔を寝かしつけるのに一時間近くかかり、リビングに戻ると、健次はワイングラスをかたむけながら夕飯時と同じニュースを眺めていた。
「なんかずいぶん熱心に見てるね」
「ああ、ううん。べつに熱心なんてことはないけど」
健次は身体を震わせ、ママものむ? と尋ねてきて、いや、ごめん。いまはダメだもんね……と、私のお腹に目を向けながら独りごちた。
「なんでだろうね。このニュースってどうしても気になっちゃうんだ」
「どうして? 同い年の人だから?」
「うーん、なんでなんだろう。さっきから僕も考えているんだけど、よくわからなくて」
健次は弱々しく首をひねる。私は冷蔵庫から取ってきた炭酸水を少しだけ口に含んで、見せつけるようにテーブルに置いた。健次が発する次の言葉に、慎重に耳をかたむける。
スーパーの安いワインを一息にのみ干して、健次もグラスをゆっくりと置いた。
「この事件って自分に対するナイフみたいなものだと思うんだ」
視線をテレビに戻し、健次は覚悟を決めたように口を開いた。
「実際に事件があった七年前のこと、僕はよく覚えてる。その頃に住んでた横浜で起きた事件だったし、しかも同い年の人間が起こした凶悪犯罪だったから、報道だけじゃなく、ネットでも情報を漁っていた。あること、ないこと、本当にいろんなことが書かれていた」
七年前ということは、私は二十歳になった年だ。地を這うように生きていた地元の愛媛から東京に出てきて間もなかった頃。自分の人生を軌道に乗せることに精一杯で、テレビもほとんど観ていなかった。むしろ、意識して視界に入れまいとしていた。
さすがに去年の?罪証明のニュースはとてもセンセーショナルだったし、七年前とは違い、健次と一緒に暮らしているので、情報は自然と入ってきた。それでも、実際の事件がどういうものだったかということはいまだによく知らないくらいだ。
健次は私を一瞥もしなかった。酔いが回っているのか、懺悔するような語り口調で静かに言葉を紡いでいく。
「さすがにネットの書き込みがすべて事実だなんて思わなかったけど、当然真実は交ざっているんだろうと思っていた。少なくとも、彼女が〝凶悪である〞という前提が揺らいだことなんてなかったし、その上で僕は怒ってたんだ」
「何に対して?」
「そんなの、もちろん無辜の人間の命を奪い取った犯人の身勝手さに対してだよ。僕は正義の立場から怒ってた」
健次はか細い息を一つ漏らした。知り合った頃からナイーブなところのある人だった。異性のみならず、他人に対して徹底して心を閉ざしていた当時の私が彼を受け入れられたのは、この繊細さを信頼できたからに他ならない。
健次がテレビを消した瞬間、部屋に沈黙が降りた。直前の「無辜の人間の命」という言葉に、胸が音を立てている。
それをひた隠そうとした私の動揺を、健次は悟らずにいてくれた。
「だけど、彼女は罪なんて犯してなかったんだよね。僕はそんなこと想像もしなかった。会ったこともない人のことを、会ったこともない人たちの言葉に踊らされて、勝手に黒だと信じ込んでいた。よく言われるように、彼女を殺したのはマスコミかもしれないし、司法制度かもしれないし、彼女の周りの人たちかもしれないし、彼女自身だったのかもしれない。それはよくわからないけど、そういう全部をひっくるめて社会全体があの人を追い詰めたんだとしたら、彼女を殺したのは僕であるとも思うんだ。僕だって間違いなく社会を構成する一要素なんだから」
健次はそこで微笑んだ。私を勇気づけるいつもの快活なものではなく、見たこともない力のない表情。
さすがにナイーブに過ぎると思った。なぜか大切なモノが汚されたという感覚を抱いて、私はムキになる。
「それは考え過ぎだよ。そんなことを言い出したら、ニュースなんて信じられなくなる。家族との会話も、友だちとの話も成立しない。何もかも自分の目で見てからじゃなきゃ判断しちゃいけないなんておかしいよ」
健次は乾いた笑みを浮かべたまま、力なく首を振った。
「それでも、やっぱりダメなんだ。せめて誰かを断罪しようと思うなら、自分の目で見たものでしか判断しちゃいけないんだ。あの殺しに、僕だけは加担しちゃいけなかったんだよ」
試し読み
紹介した書籍

書籍週間ランキング
2025年5月5日 - 2025年5月11日 紀伊國屋書店調べ
アクセスランキング
新着コンテンツ
-
連載
-
連載
-
文庫解説
-
特集
-
特集
-
特集
-
連載
-
試し読み
-
連載
-
連載