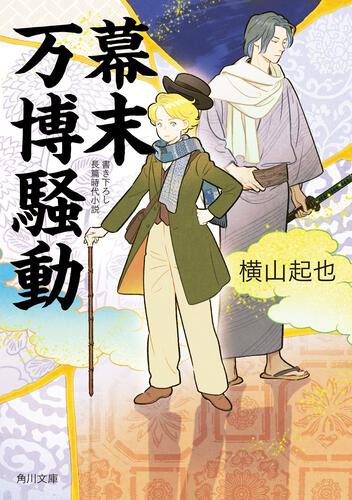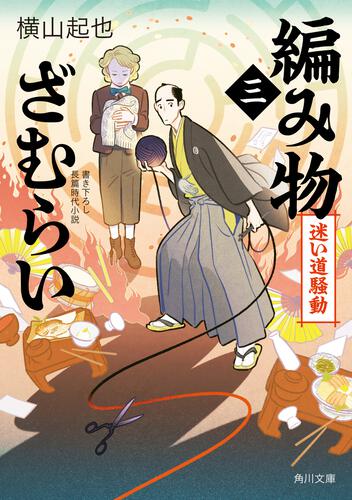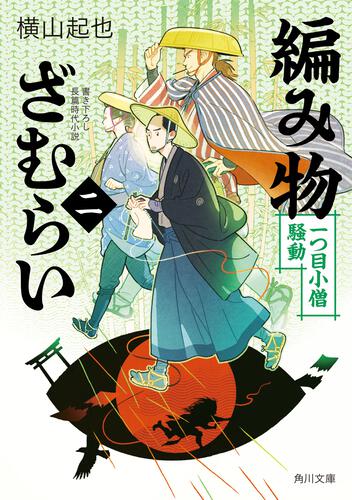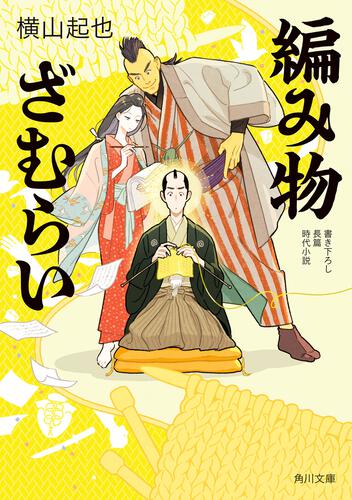幕府がパリ万博に参加したら、
会場では物珍しさから人気を得たらしい――
今年4月から開催している、何かと話題のEXPO2025大阪・関西万博。
各国の最新技術や文化などを体験できる、貴重な機会です。
実は江戸幕府が参加したことがあるって、皆さんご存じでしたか?
時は遡り1967年、パリ万博が開催された年に幕府が参加したそうです。
なんと渋沢栄一も視察したとか。
今回、「編み物ざむらい」シリーズで人気の著者・横山起也さんが描くのは、
そのパリ万博を巡る大騒動!
是非、本編でお楽しみください。
横山起也『幕末万博騒動』試し読み
第一章 朝、悩む
なぜ女なのに男の
顔を洗おうとして、
黒船来航から十数年を経て時代が動こうとはしているが、奇矯な事であるのは間違いなかろう。
巻き癖のついた黄金色の髪は短く切られ、耳のところまでしかない。
切れ長の大きな目に浮かぶ、灰青色に染まる
細く、高い鼻。
滑らかな肌。
人形のように整った顔のつくり。
遊女の母の「血」だ。
そうして水をすくっては己に塗りつけるように顔を洗った。
秋も始まったばかりというのに、ずいぶんと冷える。
寒さに弱いので、ざぶざぶとは顔を洗えぬ。
しばらくそうした後、
男になりたいのか、といえばそういうわけでもない。
もちろん、男の方が認められている世の中だからそう思うこともあるが、自分の場合は興味の域を超えていないと思う。
そうそう本気ではないのだ。
男にしたところで、やたらと窮屈にしか生きられぬようにも見えるし、下手をすると己が悪くないのに腹を切らねばならぬことまである。
おそらく、問題は生き方なのだ。
自分は見た目から江戸に住む多くの者と違う
江戸ではいわれのない
店に入れないこともあるし、歩いているだけでひどい言葉を投げかけられたりすることもある。
そういうことがあるとえらく悲しい気持ちになるけれど、あらがったからといって変わるものでないことも、残念ながらわかっている。
結局、好きに生きるしかないのだ。
だから女なのに、十六という
米利堅人としての名前も持っているが、「朝」という日本名で通す。
しかし、「好きに生きる」ということがそういうことなのか、と言われるとよくわからない。
日本と異国とを橋渡しする通詞として生きていく、ということにしてもそうだ。
己で決めたことではある。
しかし、日本人でも異国人でもない自分の、身の置きどころに困っているだけなのかもしれぬ。
結局、自分は異物なのだ。
日本にとっても、異国にとっても。
なにより、己にとっても。
朝は縁側から部屋に戻って
そこへ
「おお、アサか。相変わらず早いのう」
「おはようございます。そういうジュノさんも最近は早起きですね」
「良いか悪いかわからぬが、座敷仕事に呼ばれることが少ないから夜が早い。楽は楽だが張り合いがない」
朝の住まうこの
寿之丞は三十過ぎの巨漢で、大ぶりの目鼻口がついた派手な顔立ちをしているが、その異形を説くにはそれだけでは足らぬ。
側頭部を
朝も初めて見た時にはこの人の頭で何事が起きたのだろうかと思ったが、実際話してみると優しい気性をしていて、振る舞いも丁寧である。
名前も「寿之丞」というひどく大仰な名前であるが、屋敷に住む者はあだ名で呼び合うことが多いらしく、寿之丞は「
住み始めた当初は皆のあだ名の響きが珍しく、自分は何と呼ばれるのだろうかと楽しみにしていたが、そのまま「アサ」と呼ばれるようになり、残念な思いをした。
「コキリさんはまだですか」
もう一人の同居人である戯作者の
「こんな早くにあやつが起きるわけないだろう。寝とる寝とる……先ほどそれがしの
寿之丞がそう言って傍の握り飯を指差すので
ぱちぱち、と音がして握り飯が焼けていく芳ばしい香りをにおいながら、朝は寿之丞に問うた。
「ジュノさんは何故、その身なりなのですか」
「うむ? この髷のことか?」
「まあ、そうなのですが、着物も選びに選んだものをお召しになっているでしょう」
寿之丞はその
他にも
「まあ、こういう恰好をする理由がなくはない。それがしの体が大きすぎるうえ、こういう顔だからのう、皆が着ているような
真面目な顔でそう言うと握り飯をひっくり返した。
朝は、なるほど、と思った。
確かにそうかもしれぬ。
と納得したその途端、寿之丞がこちらを向いて
「というのが表向きの言い訳。公の理由だ……これは茶漬けにするか、焼き握りのまま食べるか」
茶漬けでお願いします、と朝が答えると、寿之丞は皿にとった焼き握りに
じゅう、と音がして醬油の焦げる香りが居間に立ち込める。
「表向きの理由と言われるならば、裏側の理由もあるのですか」
「裏側も何も、それがしの気持ちひとつの話だがな……いや、元々はそこまで考えずに似合うものを求めて好きなように選んでいただけだったのだが、
「それだけではない、と言いますと」
「髪をどうするか、装いをどうするか、というのは『己がどう見られたいか』について選んでいることだ。それが表の皮一枚のことと若い頃は思っていたのだが、それが意外にも己の心の奥底をあらわしているようにも思えてのう……お待たせした」
寿之丞が出した
礼を言って食べ出すと、醬油のこげた香りとほうじ茶がなんとも合っている。
「
「ちょっとした
「それで、『それだけではない』というのは」
「うん?……ああ、風体の話か。気になるようだのう。まあお主も奇矯といえば奇矯な
途端、朝は
やはり自分は男になりたいのだろうか。
あわてたように寿之丞が顔の前で手を振る。
「ああ、すまんすまん。いま朝が思っていることとはおそらく違うと思うぞ。それがしは言葉が足らぬことがある」
「いえ……でも、僕はもしかしたら心の奥底で男になりたいと望んでいるのではないかと思う時もあるので」
「うむ。本当のことは人の身ではわからんことだがのう。少なくとも朝が己を知ろうとしているのはその風体が示しておる」
「己を知ろうとしている?」
「なかなかわからぬことだからのう」
寿之丞にしてはめずらしく禅問答のようなことを言い放して、そのまま
朝は首を傾げながら焼きむすびを箸でほぐし、茶と一緒に
通詞の仕事を求めに、口入屋へ顔を出さねばならぬ。
異国が日本への影響を強め、新しい時代を迎えようと混乱しているいま、朝にとっては好機なのだ。
朝は早く一人前の通詞になりたいと強く思っていた。
一緒には決して住まなかった日本人の母と、米利堅人の父をつなぎたい、という幼い頃の願いが果たされぬまま、そういう望みになっているというのは自分でも理解している。
が、母が亡くなったとて、そして長じたからとて、おさまる望みではない。
通詞の仕事が数多くあるいま、多少危ない目にあっても仕事を受けるべきなのだ。
大きな首巻きを
この首巻きは自分でこしらえたものだ。
朝は亡くなった母が好きだった手仕事を習っているのだが、これはその
ある部分は
なぜそういう作りになったかといえば、朝が不器用で針仕事、糸仕事がうまくできないからだ。
普段は一回聞いた言葉を忘れることはないのに、手仕事のこつは何度教えてもらってもすぐに忘れてしまう。
縫い物、編み物、針仕事のすべてに苦心した挙句に習作をつくりちらかして
挙句、それらを一枚の布にしたらどうだろうか、と思って形も大きさも違うそれらをすべてつなげてみた。
ただのつぎはぎではない。
それらを作っている技法さえもばらばらなので朝としては赤面するほど恥ずかしい一品であるが、師匠の意見は違った。
「これは良い出来だぞ、朝。ここまで違う材をつなげているのは見たことがない。朝にしかつくれない品だ」
とは師匠の言だが、その性根が柔らかい人だけに、優しさからそう言っているように聞こえた。
そう伝えると「朝にしか見えぬ景色があるということを忘れぬ方が良い」と、心の底を
そうされると納得するしかないが、やはり、意味はわからない。
再三聞いても同じ答えしか返ってこないが、どうやら口上手ではないらしい。
結果、首巻きを普段使いにすることになったが、己の不器用を見せびらかしているようで外に出てから外す時もある。
しかし、今日はそういうわけにはいかぬ。
とにかく寒いのだ。
洋杖を握る手がかじかむほどだが、道ゆく人を見るとさほどでもなさそうだから、やはり朝が寒さに弱いのだろう。
口入屋に飛び込んだ時にはすっかり冷え切っていた。
手をこすり合わせながら土間から上がると、店の主人が誰かと話し込んでいる。
「……いやはや、他ならぬ
「困ったな。狭くても、どんなところでもかまわんのだが」
相手は困りきった様子であるが、どこかで聞いた声である。
「それでも駄目でして、申し上げた通り、三、四日空ければなんとかなりそうなのですが」
「ううむ……仕方なし、まずはどこかで宿でも取るようにするか」
朝が店の奥に入り込んで驚いた。
「師匠!
「おお、朝ではないか。こんなところで会うとはな」
こちらを向いた浪人風のその姿。
二十半ばの
整った顔つきではあるが、妙に主張の激しい
いつも奇妙な騒動に巻き込まれ、困ってばかりのこの男。
誰あろう、朝にメリヤスや糸仕事の稽古をつける師匠、黒瀬感九郎である。
「……師匠、なぜこちらへ」
朝は不思議に思った。
そもそもが通詞の仕事を江戸で探しはじめた頃、この口入屋を紹介してくれた本人であるから、おかしなことではない。
しかし、今の感九郎にはここにやって来る理由がないはずなのだ。
「うむ……」
「ひょっとしてまた
朝は声が高くなった。
感九郎は江戸で一、二をあらそう大魚問屋の
なかでもそのメリヤスの技は随一で、この口入屋の商いがうまいこともあり、随分な高値で売れて依頼が殺到していたと聞く。
「いや、そういうわけではない。相変わらず『魚吉』も繁盛していて人手が足りぬくらいだしな……それでも編もうと夜に鉄針を手にすると、こんどは娘のよりが泣きはじめて寝てくれぬ。結局、糸も針も放り出す毎日だ」
感九郎は濃い
よりとは先の正月、数えの三つになった感九郎の娘である。
メリヤスの稽古を受けに日本橋「魚吉」に行った時にはよりと、感九郎の妻の
「これは朝様、ちょうどよかった。お願いしたい通詞のお仕事があるのですよ。ぜひお話しさせてもらいたいのですが……その前に、もっとおっしゃってくださいませよ、黒瀬様に。わたくしどももぜひメリヤス仕事に復帰して頂きたく思っておるのです。黒瀬様のメリヤスを待っている武家、商人の皆様はたくさんおりますのでね、以前よりはるかに値を釣り上げられますよ」
口入屋の主人が割って入って来る。
それならやはり感九郎がここに来る意味はない。
忙しいなか茶飲み話をしにきた、というわけでもなかろう。
さらに聞こうとして気がついた。
いつも
眺めていると、また口入屋がぺらぺらと
「いや、
「焼けた!? 感九郎様、お店が火事にでもあったのですか!」
すると感九郎は苦虫を
「焼けてはいない。ぼやですんだのだ」
「焼けてるじゃないですか。わたしの所にこうやって
口入屋の言に、朝はさらに驚いた。
火つけは重罪である。
しかし、黒船来航以来のこれからの時代に向かう大事なときに、
その末、江戸はいままでより
盗み、
「ご家族は大丈夫だったのですか」
朝の声がさらに高くなるのへ、感九郎は両手のひらを前に出してうなずいた。
「よりも真魚も、義父母も安泰だ……心配かけてしまったな。朝たちにも知らせねばと思ったのだが、ひとまずは店のことやら家のことやらを先んじてせねばならなかったのだ。すまんな」
朝はかぶりを振った。
「どれほど焼けたのですか」
「いや、焼けたというほどではない。しかしな……店の奥の寝間も居間も
火事が出た時には延焼を防ぐために水をかけたり建物を壊したりする。
そのおかげで火が広がらないですむのだが、火消し人足たちは先んじてそういうことをするから、屋敷に住めなくなってしまうようなこともままあるのだ。
それでも江戸の大工たちは腕が達者で、すぐさまに直しにかかってくれるのだが、「魚吉」ほどの
暮らしが元通りになるまでしばらくかかることは朝にもわかった。
聞けば、かろうじて一人分の布団や寝るところは店に残っていたから、義父には店を守ってもらうことにしたらしい。
「ありがたいことに義母の
「それでわたくしどもの店を頼りにしてくださった次第で……いや、先ほども申し上げた通り数日お待ちくだされば空きも出るのじゃないかと。事によったら別を当たっても良いと思いますが、時節柄、空きは出にくいと思いますよ。宿を取った方が良さそうですな」
店の主人にそう言われて感九郎が腕組みするのを見て、朝はまた声を上げた。
「師匠! 簡単な話ですよ。墨長屋敷にいらっしゃれば良いじゃないですか。いらしていただけたらメリヤスの
「おお、それは良いですな。もし数日経ってやはり住処が必要ならいらしてくださいませ」
「数日でも、しばらくでも大丈夫ですよ。遠慮はいりませんよ、ジュノさんもコキリさんもきっと喜ぶはずですから」
そう言うと、感九郎の
もともと感九郎は婿入りするまで墨長屋敷に住んでいたのだ。
初めて会った頃に感九郎が話してくれたその暮らしが楽しそうに思えて、頼んで住まわせてもらっている経緯がある。
そして実際、この数年は愉快に過ごしているし、学んだことも数多くあるのだ。
だからきっと喜ぶに違いない。
そう思ったのだが、何故か感九郎はがっくりとうなだれた。
「うむ……仕方がない」
そう言って、深いため息をついていた。
なぜか意気消沈した感九郎が、それでも墨長屋敷に来ることに決めて口入屋を去ったあとのことである。
店の主人が朝に通詞の仕事の紹介をしてくれた。
「この間、朝様に通詞を依頼された
朝は江戸に住むようになってから、英語だけではなく仏蘭西語と
時代の流れを読んでのことである。
知り合った仏蘭西人に習っている修行中の身ではあるが、日本にはまだ仏蘭西語に
それで朝にもよく通詞の仕事がくるのだ。
「あのお方が昨日いらして、また朝様にお願いしたい、と」
「わかりました。また前回のように買い付けに随伴して通詞をするだけで良いのですか」
「それが少々違うようで……来年、仏蘭西は
朝はうなずいた。
万国博覧会、通称は万博である。
国際博覧会とも呼ばれるその大会は多くの国の代表が一堂に集まる。
そうして各国の技の
世界一の催し物といっても良いだろう。
「いや、あの万国博覧会というやつは商いの方にも随分と影響があるらしいですな。
それはそうであろう。
転ずれば、万博に展示される物は、その時代で一番高値のつく商品を生むこともあるのだ。
その国の文化が世界的に注目されれば
万国博覧会は世界の様々な国の「立ち位置」が決められてしまう場なのだ。
黒船に乗って米利堅からやってきた朝の父、ロジャー・スミスも万博については神経を
公にされている国際的な行事としては最重要の一つと言っても過言ではない。
「僕の通詞する先では皆、そのようにおっしゃいます。その万博がどうかしたのですか」
「いや、日本の万博参加についての話を聞きたいと」
「僕にですか? いいですけれど、幕府の決めることだから僕のような者にはわからないことも多いですよ」
父に聞けばわかることもあろうが、と朝は胸の中でひとりごちた。
父、ロジャーは通詞でもあり、米利堅からやってきた者たちに日本の文化を伝える役目があるどころか、連邦政府から命ぜられて
それに気がついていない幕府は、ここ数年で様々な相談をしにくるので、父は内情をよく知っている。
父はそれを悪びれずに暮らしているが、朝はそういう父に、なるべく頼りたくはないと思っているのだ。
「わたしもそう思ったのですが、どうも万国博覧会というよりも昨今の日本の事情について知りたいらしく」
「日本の事情? 万博のことではないのですか」
「そこがよくわからないのですよ。わたしは仏蘭西語がわかりかねますしね、お客様のお連れになっていらっしゃる仏蘭西人の通詞は日本語がまだ片言でして、とにかく朝様に話が聞きたい。おかしなことになっていて、わけがわからない、と」
「おかしなこと?」
「まあ、とにかく行ってあげてくださいませ。あのお客様は日本にいらして日が浅いからわからないことも多いのでしょう。
「行くのはいいですが、役に立てないかもしれませんよ」
「いいんですいいんです。あのお客様は払いはきっちりとしていますから、朝様がどうあれ、礼金を支払わないなんてことはないはずです」
口入屋の主人はそう言うと、品川宿の
品川宿まで行き、宿を探すとしても
とにかく冷えるのだ。
陽はよく照っているが、風が冷たい。
寒さをしのぐ物は例のつぎはぎの首巻きしかない。
こういう時に手袋でもあれば良いのだが。
メリヤス手袋をつくれるくらい手が達者になりたいものだ。
師匠の感九郎はもちろんのこと、兄弟子の編む手袋も実に見事だ。
兄弟子は無口であまり語らぬ人だが、相当な剣客だという話を感九郎から聞いている。
江戸に出てから、朝が武術をはじめたのはその兄弟子の影響もある。
もちろん、第一に身を守るためなのだが、朝が己の身体を動かすのが不得手なことと不器用なことは同じだと思いしらされたのだ。
兄弟子がメリヤスを編んでいる姿は力が抜けた、まことに見事な体配りなのである。
一度、どうすればそのように針を操れるのかを聞いたことがあった。
「道具に逆らわず身体を使わねばならぬというのは、針でも刀でも一緒だ」
兄弟子はそう
冷えに耐えながら、早々にメリヤス手袋を編めるくらい器用になってやる、と決意を固めたが、それでも冷えるものは冷える。
四半刻ごとに、茶店に飛び込んでは団子を焼くための大火鉢に手をかざし、熱い茶で暖をとる始末。
三軒目の茶店で、朝の寒がるのをかわいそうに思ったのか、
それを
これ幸いにと急いだが、昼には着くはずの品川宿に到着したのはすでに八つほど。
あと二刻もすれば日が暮れてしまう。
宿に向かうと、頃合いよく仏蘭西人の依頼人は客間にいるらしかった。
帳場の者へ引き合わせを頼むと、先客がいるらしい。
店の間で待たされてしばらく、この寒いのに着流し姿の背の高い男が出ていった。
その後すぐに呼ばれたのでその男が先客だったのだろう。
依頼人の客間に案内された朝は、早速話を聞くこととなった。
「朝さんに来てもらえて本当に助かりました。この国は私ではわからないことが多くて」
ロシェという名の
もちろん仏蘭西語である。
まだ朝にわからぬこともあるが、先方が連れている仏蘭西人の通詞に聞けば英語で言い直してくれるので、仕事に問題はない。
件の仏蘭西人通詞はロシェと朝にお茶を
異国人は日本の茶を好む者が多いと聞くが、ロシェもそうなのだろう。
「またお呼びくださりありがとうございます。仲介してくれた店からは来年の万国博覧会のことについてご不明点があるというお話をうかがっております」
「まさにその通りです」
「残念ながら僕は幕府に出入りしておりませんので、分かりかねる点も多いのですが」
「いえ、それ以前の話なのです。日本という国がわからないのです」
「それ以前?」
「去年、江戸幕府が来年のパリでの万国博覧会に参加を表明しました」
「そうでしたね」
江戸の町に話が回る前に、朝は父からその話を聞いていた。
ロシェは
「そして先月、江戸幕府が各地方の国? principauté ?」
「ああ、日本でいうところの『藩』でしょうか」
「そうです、その『藩』です。日本各地へ『パリ万博の江戸幕府の展示に加わりたい藩は手を挙げろ』と知らせたとも聞きました」
朝は面食らった。
それは知らなかった。
当然、父は知っているだろうが、朝はここしばらく
いずれにしても、異国人とはいえ、一介の商人であるロシェがなぜそんなことを知っているのだろうか。
思っている以上に万博が世界各国の商いに影響を与えているということだろうか。
「……よくご存知ですね」
「欧州人には欧州人のつながりがありますので。それに、私は母国で貴族相手の商いをしているものですから、政治に関わることには強いのです」
ロシェは自慢げに
それを見ながら、朝は自分の額を
集中するときのくせである。
ロシェとの話は慎重に進めなければいけない。
先方は朝の父が、米利堅の要人、ロジャー・スミスだということを知らぬとは思うが、用心するに越したことはない。
父は最近、幕府の相談を受けるほどの地位にあるのだ。
とくに今は相手の方が自分よりも事情に詳しいようであるから、なおさらだ。
「ロシェ様は仏蘭西でも大きなお仕事をされているのですね……しかし、その幕府の布告になにかご不明点でもありましたか」
するとロシェは傍についていた己の通詞に席を外すように言って部屋から追い払うと、声をひそめた。
「……朝さんは通詞の仕事で何が大事だと思っていますか」
そのロシェの眼を見た朝は
鋭く、影のある眼光を放っている。
自分は危険な場に足を踏み込んでしまったらしい。
「……依頼してくださる方と、先方の、共に良い結果になるように通詞することです」
「それはたしかに大事なことです……他には」
「……言葉に表れないものもやりとりできることです」
「素晴らしいですね。良い通詞は言葉の裏に隠れている文化、気持ち、事情もふくめて伝えていかねばなりません。朝さんは良い通詞です……でも、一番大事なことを忘れています。もう一つあるのです」
ロシェの目が暗さを増していく。
鬼一口、という言葉がある。
日本の各地に、一口で鬼に食い殺される説話が残っているが、そのような「尋常ではない危険」のことだと聞いている。
いままで通詞をしているなかでは「鬼一口」と呼ばれるくらいの危険を感じたことはなかった。
商談や買い付けの最中に、依頼人が妙な雰囲気を
そんなときは気を集中して、相手が何を考えているのかを感じ取り、いつもより慎重に、かつ正確に言葉を選んできた。
しかし、今、ロシェを前にして感じていることはそれどころではなかった。
もしかしたら初めての「鬼一口」なのかもしれぬ。
気をつけろ、と心の奥底から
「どうしましたか、通詞にとって一番大事なことがなにか、わかりませんか」
ロシェは問い詰めてくる。
朝はすぐには口を開かず、もう一回、額をなでた。
なぜ、朝を呼んだ挙句、わざわざこんなことを聞いてくるのか。
しかも本題に入る前に。
いま考えなければならぬのはそれである。
そうすればロシェが望む「通詞にとって一番大事なこと」が導き出されるはずだ。
朝はゆっくりと息を吸い、口を開いた。
「通詞にとって大事なことは……決して秘密をもらさないこと。仕事の後は依頼人のことも忘れてしまうくらいに」
「
そう言って笑い声を上げたが、目は穏やかではないままである。
それでも朝が目をそらさずにいると、ロシェはゆっくりとうなずいた。
「……そのうえ度胸もある。いいでしょう。いまから私の話すことは決して口外してはなりません。そうしないとあなたも私も殺されてしまうかもしれません。今から喋ることはそういう類のことなのです」
やはり
まばたき一つのあいだ、朝は
いまなら引き返せる。
話を聞かずに帰れ。
朝の心の奥底がそう囁いている。
しかし一方で、まったく別の声も聞こえてくるのだ。
これは好機だ。
口外できぬにせよ、他の者が知らぬことを知るのは大事だ。
他の通詞たちより一歩先に行くことができるかもしれない。
しかし、心の囁きはそれだけではなかった。
ロシェがここまで慎重になる、その秘密とやらの中身を知ってみたい。
別の方角から、そう囁きかけてくるものがあった。
それは、もしかしたら
しかし、その好奇心には逆らえなかった。
朝は大きく一つ息を吸い、うなずいた。
「決して他言いたしませぬゆえ、ご安心くださいませ。本日、ロシェ様からうかがったのは日本の茶器の名産地についての相談だけでございます。その他のことはいっさい耳にしておりません」
「うむ。いいでしょう。私は今後、朝さんをその場雇いの通詞としてでなく、仕事仲間として扱いましょう。謝礼も今までとは比べ物にならないくらいお渡ししますし、他のフランス人にも紹介させていただきます」
ロシェはにこやかにそう言ったが、やはり目は冷たいままだ。
それでも朝が
「そのかわり、約束を破った時は許しません。フランスの全商人があなたの悪評を広め、今後あなたがしようとするどんな仕事も
ロシェが眼を
あわてて何度もうなずく。
それを見届け、
「私はこの春にフランスから日本にやってきて仕事を始めました。朝さんも知っているように、私が扱うのは日本らしい物、特にフランスの貴族や王族の人たちが大好きな日本の茶器です」
「存じ上げております。先だっての依頼では茶器の買い付けの随伴をさせていただきました」
「そうです。ほかに書画などの芸術品も取り扱いますが、茶器は私の好みでもあるものですから……それはさておき、去年末のことです。茶器をよく買ってくれる貴族のお客様が私に言ったのです。『日本は一つの国かと思っていたが、いくつもの公国があつまって、日本となっているんだね』と」
朝はなるほど、と思った。
日本は一つの国である。
しかし、たしかに、無数にある「藩」は江戸幕府の統制下にはあるが、それぞれの殿様がおさめている。
また、「
だから異国人が「日本はさまざまな国が集まってできている」と誤解してもおかしくはない。
朝が通詞をやっていて、多く問われることであった。
そのあたりのことは朝も
通詞には語学だけではなく、そのような知見も必要なのだ。
朝が日本の藩について「国」という言葉の使われ方について話すと、ロシェは首を振った。
「私もいま朝さんが言った通りのことを話しました。でもその貴族のお客様が言ったことはそういうことではなかったのです」
するとロシェは用心深く障子を開け、廊下に誰もいないことまで確認してからさらに声をひそめた。
「その貴族のお客様の知り合いにモンブラン伯爵という方がいらっしゃいましてね。やはり貴族で、日本にも滞在していた方ですが、その方が日本の
「薩摩藩でしょうか……いったい仏蘭西の貴族の方が何を手続きされたのですか」
「薩摩が万国博覧会に参加するための手続きです」
朝は
何かが違う気がする。
「……その……何かの間違いや勘違いではないのでしょうか。江戸幕府が万博に出るという話か、もしくは薩摩藩が幕府と共に出ると表明したという話がどこかでこじれて」
「私もそうではないかと高を
ロシェの目は血走っていた。
声はひそめているが、興奮している。
「幕府が各藩へ『パリ万博の展示に加わりたい藩は手をあげろ』と布告したと聞くまでは! 私は驚きました。おそらく、江戸幕府とは別に、薩摩がモンブラン伯爵に依頼したのです。思い出してみると、私のお客様は、薩摩が万博へ『単独参加』の手続きと言っていたような気がするのです」
万博へ「単独参加」。
つまり、「日本」ではなく「薩摩」として参加するということだろうか。
よくわからない。
「それはどういうことなのでしょうか」
「……それは良いのです。私が知りたいのは、薩摩藩は日本において一つの国なのか、それとも江戸幕府に従わされている地方なのか、それだけなのです」
だから、それは地方なのだ。
さっきロシェと話したように、藩には殿様がいて藩内で決められることもあるが、勝手は許されない。
幕府の許しがなければ自分たちの城さえ直すことはできないのだ。
だがしかし。
朝は額に手を当てた。
先ほどの会話を経てもロシェは「薩摩藩が一つの国なのかどうか」が気になっているのは何故だろうか。
そこまで考えて朝は思い当たった。
「ロシェ様、その問いに答える前にお聞きしたいことがあります」
「答えられることなら何でも」
「万博には国でないと出られないのですか?」
ロシェの目がさらに暗くなる。
そして、さらに声も低くなった。
「そうです。いや、正しくは違いますね……世界には色々な文化や歴史がありますから、『国』の形も様々です。そしてもちろん私たちの常識に合わないこともあります。だからむしろ、万博に出たところは世界中に『国』と思われるようになる、というのが正確でしょうね」
朝は背筋が冷たくなった。
まさか。
「……ひょっとして万博に『単独参加』したら、薩摩藩がひとつの『国』となってしまうのですか」
「それはわかりません。万博のような国の集まる場では様々なことが起こるのです」
ロシェは首を振った。
しかし、つまりはその見込みもあるということだ。
細かいところはわからぬが、まずい気がする。
いや、これは鬼一口だ。
自分はその入り口に立っている。
心の奥底で警鐘が鳴った。
「つまり……薩摩はこの先『国』として江戸幕府に
国としての喧嘩。
つまりは戦争である。
するとロシェはそれまでとは打って変わって柔らかな表情になった。
「それもわかりません。そのお客様の聞き違いや勘違い、私の覚え違いもあるだろうと思います。だからこそ、朝さんに聞きたいのです。私は日本に来たばかりですから、詳しい事情がわからないのです」
そうして、茶碗を口にして、音もなく茶を飲み干した。
「薩摩は幕府をどう思っているのですか? そして幕府は薩摩をどう思っているのでしょう? 薩摩はどのような歴史を経て今に至るのですか? 私が聞きたいのはそこなのです」
第二章 朝、会う
朝がロシェの滞在している宿から出たのは、すでに日が暮れた後であった。
あれからロシェに黒船来航以来の日本の混乱を話した。
異国人を受けいれない
世界に門戸を開く開国。
天皇を尊ぶ勤王。
幕府に
江戸幕府を打ち倒そうとする倒幕。
天皇を中心とした朝廷と幕府の協力を良しとする公武合体。
それらの主義主張が入り乱れ、藩一つの中でも派閥が生まれてまとまりがつかない。
そこへ、
薩摩藩の当主をになう
外様はいじめられてきたのだ。
薩摩は公武合体を唱えてはいたが、今となってはどう動くかは誰にもわからない。
藩内でも考え方に違いがあるのだ。
なるべく手短に、わかりやすく話をするつもりが、気がつけば随分と時をかけていた。
ロシェは礼金に小判を一枚渡してきた。
「くれぐれも『良い通詞』であることを忘れてはいけませんよ」
そう
ロシェにしたところで身に危険が及ぶ話なのだ。
朝はとっぷりと日が暮れた品川宿を見渡し、右手の
澄んだ空に月が浮かんでいる。
今から
治まりの悪くなっている昨今、無駄に危ない橋を渡ることはない。
それになにより寒いのだ。
冷えに弱い朝は、きっと途中で動けなくなってしまうだろう。
どこか頃合いの良い宿を探して泊まったほうが良い。
そう思ったとき、向こうから誰かが歩いてきた。
急ぎ足である。
どうもこちらへ向かっているな、と
たまらずふらついたところを横道から伸びてきた手が
その
体勢が乱れているから威力はないが、
そのうえ運良く目に入れば相手を倒せる
途端、悪党はうめき声をあげて手を離し、うずくまった。
引きずりこまれた路地の入り口から逃げようとするも、ぶつかってきた男が道をふさいでいる。
逆方向にももう一人の仲間が立ちはだかっている。
朝は迷うことなく
標的は路地の入り口の男である。
鋭く相手の頭を横なぎに払おうとすると、握った手に衝撃が走って杖が跳ね返された。
路地が狭く、脇に立つ家屋の壁に当たったらしい。
そのわずかな隙である。
あっという間に詰め寄られ、入り口にいた男に羽交い締めにされてしまった。
洋杖の一撃に倒れていた男も立ち上がり、相手は三人である。
朝は身をひねり、むやみやたらに暴れようとしたが、逆に締め上げられるばかり。
洋杖も落としてしまい、足も地から浮いて、何も抵抗できなくなった。
絶体絶命である。
「おう、お
路地の奥にいた悪党が低い声を出した。
こいつが三人組の頭目のようである。
そのまま朝の上衣の懐に手を入れ、財布を取り上げる。
「お、どれどれ……すげぇ入ってるじゃねえか。やっぱり異国人は金持ちだな。ん、こいつ、随分きれいな顔してやがるぜ。女だったら
財布の中身を確認した悪党は野卑な声を出し、また手を朝の上着の懐に差し入れてきた。
朝は顔をしかめた。
気持ちが悪い。
その手が
「他にも金目のもんを持ってんじゃねえか……ん?」
悪党の手が止まった。
「こりゃ……さらしか?」
その時である。
「手前ぇら何してやがるんだい? こんな夜道でこそこそと」
その声は決して大きくはなかった。
まるで
だが、胸に響いた。
人の気を
こう喋るのは、たいてい悪い奴なのだ。
朝は、否、悪党たちも皆んな振り向いた。
いや、違う。
振り向かされたのだ。
声の主は路地の入り口に立っていた。
「異国人は俺の客だ。その客相手に何やってんだい?」
月夜に現れたその姿、背は高く、
寒いというのに、着流しの肩に大きな布を引っかけ、その端を首に巻きつけているだけの装い。
頭には
それ以上は夜目には見えぬが、
「うるせぇぞ、引っ込んでろ」
朝の洋杖に顔を打たれた男がそう
「待て……なんだい、若じゃねえですか」
「
「若こそどうしたんでさ、こんなところへ」
「なあに、たまたまだ。品川宿に泊まってる異国人と商いの話さね……ところで、その異人さんも俺の客になるかもしれねえ。放してやってくれ」
「不思議なことを言いやすね。若にも若の商いがあるように、こちらにはこちらの商いがありやすんで」
「そりゃそうだな。ならその商い、俺が買った」
若と呼ばれた新参者はそう言って、何事もないかのように歩み寄ると、懐から小判を一枚出した。
朝を
しかし、三助という頭目はさすがなもので、
「その商い、乗りやしょう。しかし、小判一枚ならこの異人を引き渡すだけでさあ。異人の持ってた財布は俺らがいただいていきやすぜ」
「まずは放してやってくれ。異人さん、come onそれともviensかな」
拘束をとかれた朝は、痛む首や肩をさすろうとして驚いた。
英語と仏蘭西語である。
朝を異国人だと思っているのだろうが、この悪党たちの仲間にしては学がある。
発音も良い。
もしかしたら同業者かもしれぬ。
財布は惜しかったが、身が助かっただけでもありがたい。
もう少しで女だとばれてしまうところだったのだ。
朝は
恐怖を感じていたわけではなかったのに、
それを察した男が手を取り、引き寄せると、足がふらついて抱きついてしまう。
慌てて身を離したが、男の体はあたたかかった。
「三助、稼業の邪魔をして悪かったな」
「いえ、いいんで。いい商いになりやした」
「ところで、この異人さんの財布を返してやった方がいいんじゃねえか」
「若、こちらの商いに口を出しちゃあいけませんぜ」
「いや、お前さんたちのためにさ。俺はさっきの商いは満足してるが、この異人さんの気持ちは別だ。お前ェらに財布を取られたと番屋に駆け込むのを止めることはできねえよ。お前ェの名前も知っちまったことだしな」
「……ちっ」
頭目は舌打ちをして思案に暮れたが、すぐに手下から朝の財布をもぎとって放り投げた。
「くそっ。持って行け」
「おい、まてまて」
素早く路地の奥へかけて行こうとする悪党たちを呼び止めると、今度は懐から一分銀を二つ取りだした。
「三助、忘れもんだ」
「畜生、なんだってんですかい、いったい」
「何もかんも、手間賃さあ」
「手間賃?」
「商いには
「……くそっ、わかりやしたよ」
悪態とも礼ともつかぬことを口走りながら、三助が銀をもぎとると、三人は
それを
「ありがとうございます」
「!……異人じゃねえのか」
男は面食らったようである。
「こんな見かけですが……僕には日本人の血が入っていて、江戸で暮らしています」
「なんでえ、ぜんぜん俺の客じゃねえじゃねえか」
そう言って男は
朝は驚きながらも、こういう笑い方はちょっと好きだな、と思った。
明るいところで見る男は若かった。
二十二、三といったところだろうか。
声の印象の通り、悪い奴の目をしている。
細面に目立つ、少々
逆八の字に真っ直ぐな
身なりは良く、
道すがら、男が寒がる朝の肩にかけてくれたのだが、薄くて軽いのに実に暖かい。
まるで呪術か手妻にかかったようであったのだ。
「まあ吞め、こうなった以上は酒をつきあえ」
男はそう言って朝の
品川宿にある
外にあまり人が歩いていないのは急に寒くなったからのようで、店内は混んでいる。
人の行き来が多い品川宿とはいえ、異国人への風当たりは強い。
数年前には近くで普請中だった
朝の姿を見て出てきた料理屋の主人は「異国もんに食わせる料理はねえ」と、いまにも手に盛った塩を投げつけてきそうであったが、男が耳打ちをすると慌てて謝ってきた。
おかげで料理屋に入れたのだが、そのような不当な扱いに慣れている朝も客たちの視線の厳しさが気になるほどであった。
それに気づいたのか、男が一番奥まったところで手招きをしていて、行ってみれば
小上がりに上がれば、ちりひとつなく清められていて、そこへ腰を下ろして
流れで盃に口をつけた朝はむせた。
「なんでえ、吞めねえのか」
そう言われて朝は大きく首を振った。
噓である。
全く吞めない。
しかし、男に金を出してもらって助けられ、しかも財布まで取り戻してもらったからには何かで報いたかった。
そうでなければ公平でない。
朝はもういちど盃に口をつけ、一気にあおった。
「おいおい、無理することはねえ。お前さん、若いんだろう?」
「……十六です」
「ひよっこじゃねえか。吞めねえなら茶でも飲んであとは飯食っとけ」
店の者を呼ぼうとする男に、朝はまた大きく首を振って
手酌で注いで盃をあおる。
それを見て、男がまたあの明るい笑い声を上げた。
「お前、義理立てしてるつもりか。俺の勘違いで金出したんだから気にすることはねえのによ……そんな奴は初めて見た。馬鹿だが嫌いじゃねえ」
そう言って男も盃をあおる。
朝は改めて頭を下げた。
「先ほどはありがとうございました。僕は朝と言います。先ほども言ったように日本と米利堅の混じり血です。通詞をしています。もしよろしければ……お名前をうかがえますか」
「ん……そうだな。うさぎ、だ」
「うさぎ?」
顔に似合わぬ名前である。
「そうだ。俺をよく知るものにはそう言われている。
白うさぎだろうか。
いずれにしてもうさぎ、よりは呼びやすい。
「失礼ですが、白さんは何のお仕事をされているのですか」
「気になるか」
「いえ……先ほどの異国語の発音がきれいだったので」
「ふん。あんなのは毎日異国人と遊んでりゃああなるさ。そうだな……俺はお前さんの仕事と近いかもな」
「やはり通詞なのですか!」
「いや、通詞とも違うな。酔狂な異国人つかまえてちょっとした商売をしている。小さな商いだが、異国人は金を持っているからときどき驚くほどの額になる。この国でつくられた物の意匠やら形やら、異国ではやたらと人気が出てきたからな」
白はそう言って不敵に笑った。
悪い奴の笑みだ。
日本の茶器や書画が異国で人気なのは、朝も父から聞いていた。
おそらく白はそこに乗じて
「次はお前さんの番だ。さっき
「知ってるんですか」
「ほとんど知らねえ。俺の客の仏蘭西人がごろつき相手にやってるのを見たことがあるだけだ」
白の言う通り、朝は江戸に来てから仏蘭西の洋杖術を習っている。
通詞としての仕事をはじめて一人で外を出歩くようになってから、自分の身を守る必要がでてきた。
それも町の治まりが日々、乱れてきているからだ。
先生は語学も教えてくれる仏蘭西人である。
朝が洋書を読んでいる間の暇つぶしに、その仏蘭西人が洋杖を振り回している姿を見て、その動きに
最初は舞踊かと思った。
転身させ、飛びあがり、洋杖を
が、見ているうちに何度も洋杖を突き出し、やたらと低い姿勢をとって、それがどんどんと早くなっていく。
そして気がついた。
これは武術なのだ、と。
日本の剣術流派のように何か呼び名はあるのか、と問うと、先生は首を振った。
「私の国ではただCanne de combat闘いのための
それを聞いた朝はその洋杖術を語学とともに習うことに決めたのだった。
そう話すと、白は感心したように口を開いた。
「俺は
「はじめから見ていたのですか! それならすぐに助けてくれれば良かったのに」
「ふん。お前さんが俺の客になる異国人だったら、少し待ってから登場した方が有り難みが出るだろうと考えてな」
「ひどい! 人でなしですね」
「そう言うない。俺の商いにもならねえのにきちんと助けたんだから」
「逆でしょう。白さんの利にするために助けたら、たまたま僕が混じり血だっただけで」
そう抗議すると白は面白そうに笑った。
「それでも結局、助けたんだからいいじゃねえか……それにしてもそんな若いのになぜ通詞なんてしてる。昨今、危ねえ仕事だ」
そう言われて朝は返答に詰まった。
つまりは日本人遊女の母と米利堅人の父との仲を取り持ちたい、という幼い頃の気持ちが長じてそういう形になっているだけなのだ。
「……父も通詞をしていて」
「へえ。まあ、頭良さそうだしな、この国の言葉もそこらへんの奴よりお前さんの方がきちんとしている。しかし……」
白が朝の目をのぞきこんでくる。
つくりは良いが、どこか危うさを感じさせる顔が急に近づいてきたので、慌てた。
しかし、そのほのかに鼠色がかった
そうしてしばらく、白が何事もなかったかのように
知らずのうちに呼吸まで止まっていたらしい。
「大変な思いもしているようだな」
白はまるでわかったようなことを言って酒を
朝はなぜかしら
手酌で酒をつぎ、あおる。
「おいおい、無理するねえ。倒れちまうぞ」
そう言われたので、もう一杯ついであおった。
「僕は日本と異国が仲良くできるよう、通詞をしてるんです」
そう言い放ち、口を挟ませないようにまくしたてた。
「言葉が通じないと、お互いの気持ちを確かめないと、良くないことが起きますから」
すると白はわずかの間だけ
悪い奴の笑い方だった。
「なにがおかしいんですか」
「……いや、あまりにお前さんの頭の中が
「馬鹿にしないでください」
朝はぴしゃりと言った。
本気なのだ。
すると白はまた酒を吞み、暗い目になった。
「お互いのことがわからないから良くないことがおきる、って
「違うんですか」
「ああ、違うね。たとえば人殺しなんてのは良くないことだろうさ。しかし、そりゃお互いのことがわからないからやるんじゃねえ。たいてい金のためさね」
「お金のため……」
「そうさ。人殺しの果てが戦争や侵略だろう。それも金のためさ。皆んな、いい生活がしたい。そのためには働かなけりゃならねえ。働くってことはひいては国を富ますことにつながる。国が金持ちになれば自分たちはより豊かになる。その先はどこへ向かう? 決まってらあ。戦争をして他の国を侵略し、金品をむしってくる。奴隷にする。それ以外に何があるんだ」
朝は黙った。
白の言うことは合っているように思えた。
日本に来ている異国人の頭にそういう思いが渦巻いていることは否定できない。
朝はそれを知っているのだ。
しかし、心の奥底から、それは違う、という
朝は景気をつけるようにまた酒をあおると、声を上げた。
「……そういうこともあるのは事実です。しかし、人というものはそれだけではありません。人と人をつなぐ仕事をしているのにそれを信じぬのならば、いったいどうするのですか」
「
「そこをうまく運ぶのが僕の仕事です」
「その良く回る舌でまずはしっかり金を稼ぎやがれ。でねえとご高説を垂れても誰にも相手にされねえぜ。俺がお前さんの
「その商いのせいで戦さがおきるのでしょう!」
「さっきは俺の出した金で商いしたから、お前さんが助かったんだぜ」
「そんな風に言うなら助けないで良かったんです! いつ僕が助けてくれと言いましたか!」
朝は勢いがついて立ち上がった。
途端に、ぐらり、と目がまわり、見えるものが皆んな、崩れ落ちた。
次の
畳の目が見える。
どうやら倒れてしまったようだ。
「おい、大丈夫か……ったく、言わんこっちゃねえな。おい、悪いが水を持ってきてやってくれねえか」
どこかで白の声がする。
ふわふわとして心地が良い。
自分の輪郭が溶けてしまったようである。
皆んなでこうやって溶けてしまえば良いのに。
そうすれば悪いことも起きないから。
朝が目を覚ますと知らない天井が見えた。
ここは、どこだ。
知らないうちに上等な布団で寝ている。
なぜか腰が痛い。
脚の根本や
昨夜の
白に助けてもらい、酒を吞みに行ったことは覚えている。
自らを「白うさぎ」と名のる男。
不思議な、悪い奴。
人よりも金を信じていて、だからこそ世の中を見透かしている人。
混じり気のない明るさを持ちながら、
少なくとも、朝はあのような者に会ったことはなかった。
起きあがろうとして、左手が何かに触れた。
何かと思って見やって、どきりとした。
人の顔だ。
しかもこの
なぜ隣に寝ているのだろうか。
途端、朝ははたと思い至った。
「ああっ……」
思わず声が出て、その拍子にひどい頭痛に襲われた。
まるで
「……まだ暗いうちになんの騒ぎだ……ああ、目を覚ましたか」
白は布団の中でもぞもぞと身じろぎをした。
「どうした。気分が悪いか」
「……頭が、痛い」
「吞めねえのに無理するからだ」
白が何事もないようにそう言うので、朝は怒りを感じた。
足腰が妙なのは寝ている間に変なことをされたからに違いない。
それなのに悪びれもしない。
「……あなたは酒を吞んで前後不覚になった私をどうしたんですか!」
「おいおい、どうしたってんだ。お前さんがしてくれと言うから」
「私はそんなこと言ってない!」
「言ったさ。俺は嫌だと言ったんだぜ」
「酒に乗じてそんなことを……
朝は悔しかった。
悪い奴とは思ったが、心のうちを正直に話しあえる男だと思っていたからだ。
裏切られた。
朝は男を知らなかったというのに。
「卑怯たあ人聞き悪いな。酒に乗じたのはお前さんじゃあねえか」
「そこまで人のせいにするのですか」
「人のせいったってよう、酔い
「え?」
面倒そうな白の言いようを聞いて、朝は我に返った。
慌ててかぶっていた掛け布団をめくると、
どうやら噓ではなさそうである。
でもこの足腰の妙な痛みは、いったい。
「しかもまともに歩けもしねえのに、肩を貸してやろうとしたら『一人で歩ける』とむきになったのもお前さんだ。料理屋から出るだけで大変だったのに、外に出たらやたらと飛びはねたりしやがって……なんども
「ええ!」
これは尻餅の痛みか。
しかも自業自得の。
「道すがら、遅くまで客とってる
「えええ!」
「布団しかせたらしかせたで寝転んであっという間に寝入っちまったうえにいびきがひどかったから俺はさっきまで眠れなかったんだ」
「ええええ!」
なんということだろう。
恥ずかしい。
恥ずかしくてたまらない。
よりによって。
「……すみません」
「あ? いや、気にするこたあねえ。若いっていうのはそういうもんだろう。しかし、これからは気をつけたほうがいいぜ。お前さんは見目がやたらといいからな。俺が衆道の気がなかったからいいが」
その言葉を聞いて朝は、どきり、とした。
白は朝を男だと思っているのだ。
当たり前である。
男装しているのだから。
そんな朝の動揺など露しらず、白は寝返りを打ってあちらを向いてしまった。
「俺はもう寝るぜ」
「……昨日のお礼と、料理屋の代金を」
さらに、朝は酔いに任せて白が自分を救ってくれたことについて「助けてくれなくて良かった」とか「頼んでもいないのに」などと口走ったことを思い出した。
それも謝らなければ。
「いらねえよ。金をもらうより稼ぐことのが性に合ってんだ。次に会った時に酒をおごってくれりゃそれでいい。俺はいつもは横浜にいるから、気が向いたら来てくれよ。他にゃ変な義理立ては無用だ。いい頃合いで帰ってくんな」
「そんな……」
朝は困惑したが、白はもうぴくりとも動かない。
眠ってしまったのだろう。
謝ることはできなかったが仕方がない。
朝は一つ息をついて、布団の上でお辞儀をすると静かに立ちあがろうとした。
その時である。
白が、くるり、とこちらを向いて手を差し出し、朝の
「うわあ」
くすぐったくて声が出てしまった。
が、不思議に嫌ではない。
「昨晩の話だがな……お前さんの言うことは甘すぎて腹が立った」
そう
眠いのをおして言うほどなのか。
「甘すぎますか」
「ああ、甘い甘い。大甘だ」
白が顔をしかめる。
朝はうつむいた。
自分の考えは世間では、そして世界では通用しないのだろうか。
「……だがな、ああいうのが必要だとも思う」
思いもよらない言葉に、朝は顔を上げた。
白はまっすぐこちらを見ていた。
が、すぐに目をそらされた。
「勘違いするな、俺は俺だ。自分の道がある。しかし、お前さんは違う。通詞だろう。通詞には通詞の理ってもんがあるんだろうさ。もしかしたらこれからの時代にはそういうのも必要かもしれねえ、って思っただけさ」
白は寝返りを打ってまたあちらへ向いてしまった。
そうしてまた微動だにしなくなった。
「……白さん」
朝の呼びかけにも
今度こそ眠ってしまったのだろう。
結局、謝れなかった。
朝はまた息を吐くと、身を起こして鏡台に向かった。
身だしなみを整えてから宿をたとう。
そう思って髪を
鏡の中の己が
第三章 朝、うつむく
品川宿から蔵前の墨長屋敷にもどると、騒動が起きていた。
「だからもう
誰かが大声をあげている。
韋駄天とはやたらと足の速いあの神様のことだろうか。
そう思いながら廊下から居間をのぞくと、声を高くしているのは朝の手仕事の師匠、黒瀬感九郎であった。
脇に置いた大きな
小霧は長い髪を結いもせずに
小柄ではあるが、身だしなみを整えればひとかどの美人に数えられようという
さらに江戸で当代随一の人気を誇る謎の戯作者、
たしかに話してみると、その頭のきれは右に出る者がいないほどである。
その小霧がにやけまじりに口を開いた。
「貴様がいくらそう言ったって肝心の真魚はまだ思っているかも知れねえぜ。『感九郎様は優しい
「真魚はそんなことは言わん!」
感九郎は顔を真っ赤にして怒り始めてしまった。
小霧の口汚さは相当なものであるが、それは感九郎も慣れているはずである。
いったいなんでそんなに怒っているのだろうか。
「あの……なんですか韋駄天茄子って」
そう言いながら居間に足を踏み入れると、感九郎がやっとこちらを向いた。
「朝か……むう、なんでもない。コキリ、とにかく今日からしばらく世話になりたい。私は御前のところへ
御前はこの墨長屋敷の女主人である。
「まてまて。貴様にはまだ伝えてなかったが、御前は前にも増して多忙になっちまったんだ。いまこの屋敷を預かっているのはおれ様だぜ」
「な……」
感九郎が
確かにそうなのである。
「さあ、この屋敷に
また韋駄天茄子である。
「朝、真魚は知ってるな」
「はい。師匠の奥方ですね」
大魚問屋「魚吉」の
なぜか性質の違う小霧とうまが合うようで、時々、二人で会って茶を飲みながら話をするほどらしい。
「その真魚に旦那評を聞いたことはあるか」
「いえ」
「いけねえなあ。師匠が奥方からどう思われているかくらい弟子は知っていねえと」
適当なことを言っている。
しかし、興味はある。
朝が腰を下ろすと、感九郎が苦々しげに口を開いた。
「朝、小霧の話を聞くとせっかくの良い頭が悪くなる。部屋に戻っていたほうがいい」
「お、貴様も言うようになったな。父親の威厳ってやつか、しゃらくせえ……いいか、朝、真魚に旦那評を聞いてみたら『感九郎さまはとても優しくて父母のこと店のこともよく考えてくださる素晴らしい旦那様です』ときたもんだ」
たしかに真魚が言いそうなことである。
そして感九郎は、弟子の朝から見ても少々頼りないところはあるものの、たしかに深慮遠謀がきくのだ。
「さすがじゃないですか、師匠」
朝がそう言ってもなぜか感九郎は腕を組んでそっぽを向いている。
そこへ小霧がいかにも楽しそうに話を続けた。
「だよなあ。しかし、人ってのは表もありゃ裏もあるからな、さらにしつこく聞いたんだ。何度もな。そしたら真魚が恥ずかしそうに言うんだぜ。『感九郎さまは、その……夜のことが早いのが玉に瑕で』とよ」
「夜のこと?」
「朝よう、男と女が夜することといったら決まってんだろ。そこで俺様が『韋駄天茄子』という御尊名をつけてやったんだ。韋駄天っていやあ神様だぞ、神様。感謝しやがれ」
韋駄天。
茄子。
そういう意味か。
途端、顔に血が上る。
そういうことがなかったとはいえ、前夜に白と一夜を過ごしたのを思い出したのだ。
しかし、感九郎もコキリもそんな朝に気づきもしない。
とうとう我慢がならなくなったのか、感九郎が立ち上がった。
「だからもう韋駄天茄子ではないと言っただろう。ジュノに言われて
「治るわけねえだろ、そんなことで。あの肉達磨の噓八百、口八丁に
その
寿之丞である。
「噓ではないぞ。水をかぶれば気がめぐり、色事に強くなるのだ」
良く通る低い声でそう言いながら
まだ昼日中というのに
前日の酒がまだ残っている朝は徳利を見て気分が悪くなった。
「おお、朝も帰ったか。昨日は戻らぬから少々心配したのだぞ……コキリよ。それがしは人を騙しているわけではないぞ。あれはあくまで座敷芸。夢を見せておるのだ」
「けっ、なにが夢だ。しゃらくせえ。
コキリはそう言って早くも酒を
寿之丞は座敷に呼ばれて芸を見せる手妻師である。
それも
あるとき寿之丞が手慣らしをしているのに居合わせ、一分銀を渡されたことがある。
握っていろというからそうしていたが、一呼吸おいて今度は手を開けてみろという。
すると、先ほどまでたしかにあったはずの一分銀が影も形もない。
握っている感覚もあったから驚いて手のひらを眺めていると、こんどは下を向けと言われたのでそうすると、頭の上から、ぽとり、と畳に落ちるものがある。
見れば一分銀で、ただただ啞然となった。
そういう手妻芸も見事ならば、大がかりな奇術芸も得意なので、人を「騙す」と言われても間違いではない。
「いずれにしてもだ、久しぶりにクロウがこの屋敷に戻ってきて
朝は安心した。
寿之丞は異装、異形の風体ではあるが、コキリより幾分かまともなのだ。
それに、感九郎が「クロウ」と呼ばれていることにも懐かしいような、
この四人が一堂に会するのは本当に久しぶりなのである。
「おい、肉達磨。貴様ほど言ってることとやってること違うやつはいねえぞ。なんだこの
「なにを言うか! それがしはクロウから相談された流れで責を感じてこうしておるのだ。お主みたいに笑い物にしておるわけではないわい」
と、こんどは寿之丞とコキリで
見かねた感九郎が「二人とも、私のために喧嘩するのはやめてください」と止めに入っているのが妙に馬鹿馬鹿しい。
朝がつい声を出して笑ってしまったその時である。
玄関で
三人が言い争いに余念がなく、気がつかない様子なので朝が玄関に向かうと、若い男がいて文を渡された。
「心付けはたっぷりもらってますんで」と言い残して足早に去る男を見送り、文を見返すと差出人は御前である。
居間に戻って伝えると、騒がしかったのが一転して静かになり、コキリが手を出してきたので渡した。
そのまま乱雑に文を開いて一読するのを寿之丞と感九郎がのぞきこんでいる。
そのうちにコキリが鋭い声を上げた。
「野郎ども、座んな」
その掛け声一閃、寿之丞も、そして感九郎までもが腰を下ろす。
「どうしたんですか?」
その顔に浮かんでいるのは不敵な笑みである。
「朝も聞いておけ……『仕組み』の依頼だ」
「仕組み」とはこの屋敷の住人がたずさわる「裏」の仕事だ。
城中におわす将軍様の血縁から江戸八百八町の裏道まで、さまざまなつながりを持つ墨長屋敷の女主人、御前こと
「仕組み」の相手はこの国の北から南まで、
そいつらを殺しはせぬが、芝居仕立ての
本来であれば御前が指揮をとり、コキリが考えた筋立てをもとに、寿之丞の手妻や感九郎の手仕事の技で悪党たちを騙すという算段ではあるが、今は肝心の御前がいない。
かわりに頭目をつとめるコキリが開口一番、高らかに宣言した。
「よし、貴様らはとりあえず御前代行の俺の言うことを聞け」
途端、寿之丞が抗議の声を上げた。
「待て待て。それがしは御前に、コキリが好き勝手やるのを止めるよう頼まれたぞ」
「そんなことはねえはずだ。御前は俺に『存分にやってくんなまし』と言ってたんだ。とりあえず呼び名を改めるぞ。クロウ、貴様は今日から『韋駄天
またそれか。
さすがに朝も
「さておき、朝に『仕組み』の話をしてしまってよいのか」
そう言って主張の激しい
コキリと寿之丞は互いに顔を見合わせた。
妙な間があいて誰もしゃべらぬ。
仕方がないので朝が口を開いた。
「師匠。
「なんだって!」
「通詞役で何度か参加させていただきました。師匠からも僕の語学力を推薦いただいたと聞いていましたが」
「!……ジュノ、コキリ、朝を『仕組み』に巻き込まないでくれと頼んだではないか」
途端、感九郎が声を高くすると、寿之丞とコキリが珍しく慌てるそぶりである。
「いや、最近、妙に異国人がからむ悪事への『仕組み』が多くてのう。才のある朝につい頼んでしまったのだ」
「朝は若いからよう。これから通詞としてやっていくために経験ってやつが必要だぜ、きっと」
「私の時もなんだかんだと言って巻き込んだではないか。御前にもしっかりと頼んだのに……
感九郎ががっくりとうなだれた。
その御前も随分前に墨長屋敷からいなくなっていたのだ。
あまりに感九郎が気を落としているので、朝は再び話しかけた。
「あの、師匠。無理やり参加させられたのではなく、僕も望んでのことですので」
「しかし……お主も心中複雑ではないのか」
感九郎が声を落とした。
父のことを言っているのだろう。
米利堅の
感九郎もそれを知っていて、かつ墨長屋敷の面々にその事を知らせてくれた。
そうすれば朝を「仕組み」に巻き込むことはないと考えたらしい。
「僕も最初は気にしたのですが、師匠もすすめてくれていると聞いたうえ、その……」
朝はそう言って寿之丞とコキリの方を見た。
寿之丞はそっぽを向いているし、コキリは酒を
「お二人が『気にすることはない、朝が『墨長屋敷』の人質になっているという考えもある』と」
途端に感九郎が声を荒らげた。
「コキリ! ジュノ! 朝をそのように扱うなと念を押しただろう」
「貴様はそう言っていたがよ、朝がその方が気楽じゃねえかと思ったんだよ」
「そうなのだ。朝は頭が良いから、それくらい言わねば気遣いが勝ってしまうのだ」
「何を言っているのだ。ただでさえ朝はつらい立場なのだぞ」
混じり血のことを言っているのだろう。
感九郎は朝のことを心配してくれているのだ。
だが。
朝は感九郎の前に出た。
「師匠……『仕組み』に参加したいと言ったのは、僕なのです」
「朝……」
「僕にはいろいろなことがわかりません。父は米利堅にとって必要なことをしています。しかし、それがこの国にとって良くないことになっているようです。そうするといったい父は何者なのでしょう。善人なのでしょうか。それとも悪人なのでしょうか」
朝は目を落とした。
自分の身に日本と米利堅の血の両方が流れているからこそ、そんなことを考えるのかもしれない。
日本人なのか、米利堅人なのか。
自分は何者なのか、それを知りたい。
心の奥底ではそう思っているのかもしれぬ。
だからこそ女なのに男の
そう思えば昨日の朝、寿之丞に言われたことそのままである。
「僕がそれを知るには通詞の仕事を積み重ね、この国と異国、日本人と異国人のそれぞれの事情をわかっていくしかないと思っています。それには少しでもたくさん、通詞の仕事をしたいのです。でも僕みたいな若い混じり血の者に、なかなか仕事はやってきませんでした。それを見かねたジュノさんとコキリさんが『仕組み』に誘ってくれたのです」
面白いもので、「仕組み」に参加してからだんだんと通詞の仕事が入ってくるようになった。
おかげで少しは名が売れて、口入屋からも依頼されるようになったのだ。
仕事というのはつながっていくのである。
朝がそう話してしばらく、誰も口を開かぬ。
そのうちに、ぽつりと感九郎が
「すまなかったな」
「いえ、師匠が謝ることではないのです」
「いや、違うのだ。私が忙しさにかまけて朝がそういう悩みを抱えているとはわからなかったのだ。前にそんな話をされた時も、口入屋を紹介してすませてしまった覚えがある」
途端、コキリが「そうだ、貴様は無責任なんだ」と騒ぎ始めると、朝はそれに首を振った。
「いえ、神田の口入屋さんをご紹介いただいたのはとても助かっていて、今はほとんどの仕事をあそこで仲介していただいているのです」
「むう……いずれにしても朝がそう言うならば仕方がない。しかし、ジュノ、コキリ、朝を危うい目に遭わしてくれるなよ」
感九郎が珍しく
しかし、そんなことでこたえる二人ではない。
寿之丞はその通りその通り、などといいながらさっそく酒を吞みはじめているし、コキリは感九郎の責め言葉から逃げるようにまた文を開いている。
「わかったわかった……さあ、さっそく依頼の中身を話すぜ。ええと、おお、来年、巴里で開かれる万国博覧会がらみだとよ」
朝は、おや、と思った。
昨日、品川宿で仏蘭西商人ロシェからいささか
「なんだあ? おいおい、『一目連』が薩摩とくっついたらしいぜ」
「ええ!」
朝は声をあげてしまった。
コキリ、ジュノ、感九郎の三人ともにこちらを見る。
「どうした、朝」
感九郎にそう聞かれたが、ロシェとの約束もあって聞いた話を伝えるわけにもいかぬ。
「……すいません。薩摩芋が好きなもので、薩摩が悪事に加担するとなると食べられなくなるのでは、と」
苦し紛れにそう言いながら、まずい、と思った。
こんな言い訳は通用しない。
ところが、コキリは「ありゃ
寿之丞にいたっては、
「たしかに
などと元気づけてくる。
「ああ、それなら安心です……」
朝は困惑しながらそう
寿之丞やコキリは相当に頭の回転が早い方であるが、時々、このように間が抜けていることもある。
それに、すでに二人には酒が入っているのだ。
寿之丞が
「コキリよ、それで薩摩と『一目連』が何を
「ああ、詳しいことは分からねえらしいが……万国博覧会に参加する幕府にあやをつけるんじゃねえか、と御前は先を読んでいる」
「あやをつける? いったいどうやるのかのう」
「だからそれがわからねえんだとよ。ただ、動きがやたらと不穏みたいだ。つまりはそれを探りながら、薩摩や『一目連』の企みを
それを自分は知っている。
ロシェから聞いたことがこの話につながっている。
鬼一口だ。
「朝、顔が真っ青だぞ。大丈夫か」
感九郎が声をかけてくるので、はい、とだけ応える。
コキリもこちらを見やったが、すぐに文へ戻った。
「まあ、薩摩芋は関係なさそうだから安心しろ……ええと、それでどうすりゃいいんだ。ああ、これか……へえ、
「御前試合? 将軍様の前で剣だの
「そうだ」
「とはいっても
先の将軍、徳川家茂が病で
将軍が不在なのである。
「知らねえよ。城のお偉方の前でやるってことだろう」
「まあそうなるかのう。しかし、なんでそれがしたちが」
「どうもな、来年、幕府が巴里の万国博覧会に参加するってんで、いろいろ道具やら書画やら集めてるらしい。まあ博覧会なんて立派な名をつけてるが、やってるこたあ国の自慢大会だからな。見栄を張れる物を集めてえってところだろうぜ」
「身も
「ふん。体裁よくしてるだけで、皮一枚はぎゃそんなもんさ。面白え物、
それはそうなのだ。
コキリは大勢の読み手を相手にする戯作者をやっているせいか、世の中の見方が白と似ているのかもしれぬ。
しばらく黙っていた感九郎が口を開いた。
「それはそうだが、それと御前試合と、どう関係があるのだ」
「それが面白え話でよ、幕府は万博に出して自慢するための茶器や書画を集めて準備してきてるみてえなんだが、ここにきて増やしてえみたいだな。ええと、今日からちょうどひと月あとだな、道具や書画を集めて品定めする『ものづくり御前試合』をやるみてえなんだ。参加枠を御前がとったとよ」
「ものづくり御前試合? 『ものづくり』とはけったいなお題だのう」
「確かにな……ああ、幕府方もしかたなくそう名付けたんだと。書画や茶器、服も刀もすべてひっくるめた物品のなかから、将軍様をはじめお偉方たちが選ぶらしい。困った挙句にこの名前にしたんだと」
「その『ものづくり御前試合』に薩摩藩が出るのかのう」
「いや、それが違うらしい……出てくるのは薩摩藩と『一目連』の息がかかった奴みたいだぜ。佐賀の
「あの『菟田屋』……菟田
思わず、また朝は声を出してしまった。
今日は驚くことが多い。
朝が横浜の
西方では由緒ある名店で、佐賀で舶来の品を取り扱う、いわゆる唐物屋として名を
菟田砂峰はその「菟田屋」現当主である。
「朝は知っとるようだのう」
寿之丞が目を細める。
「横浜に住んでいた時に、菟田砂峰がわざわざ佐賀から父に書画を売りに、僕の家までやって来たことがあります」
「『菟田屋』に会ったことあるのか! でかした、朝! これで面が割れたぜ。どんな奴なんだ」
コキリが身を乗り出した。
確かに「仕組み」を仕掛ける相手の顔がわかるのはずいぶん違うのだろう。
「その時に四十半ばに見えましたから、いまは五十がらみでしょうか。
佐賀は
主家の
その佐賀で有名な唐物屋の主人であるから恰好が
丁寧な物言いだったが、何でも見透かすような鋭い
「結局、父は薩摩切子をいくつか買っていましたが、たしかに扱う物は良かったと思います」
「いやあ、助かったぜ。文によると、『菟田屋』は佐賀にしか店を出しておらず、江戸では異国人相手の商いしかしないようだから、さすがの御前も調べをつけにくいらしいんだよ。お手柄だぜ、朝」
コキリはずいぶんと喜んでいる。
逆に、感九郎は
「それはよかったが……コキリよ。その『ものづくり御前試合』に出るとして、その菟田砂峰をどうするのだ」
「そりゃ決まってんだろ。やっつけるのさ」
「だからどうやってだ」
「んん? そりゃよお、『菟田屋』が腰抜かすような品を……」
「どうやって用意するのだ。向こうは百戦錬磨の唐物屋だぞ。品物を見る目、異国の好み、手に入れるための人脈、すべてが一流ではないのか。それを上回るものを手に入れることは早々、できないだろう」
「まあ、そうだよなあ。なら
「韋駄天茄子ではない」
「なんだよ、面倒言いやがるな。いいだろ、呼び名くれえ。とにかく貴様の手仕事でちょちょっと……」
「先方は歴史を積み重ねた古い物品や、名のある職人のものを揃えてくるに違いない。私の手仕事でできる物品では太刀打ちできないのもわからぬのか……コキリ、精彩を欠くにも甚だしいぞ。どうしたのだ」
「ふん。なんでもねえよ。今日はここまでだ」
コキリは不貞腐れたようにそう言うと、立ち上がって部屋を出ていってしまった。
「コキリ、どこへ行くのだ」
廊下の方から「
感九郎が
挙句に寿之丞が自慢の
「むう。朝は知っておるよな」
「はい。だいたいは」
二人がそう言葉を交わすのに、感九郎は目を、ぱちくり、とさせている。
「どうしたのだ、いったい」
「いや……それがしから伝えていいものか分からぬのだがな」
そう言って、酒を手酌で注いで
「コキリは、恋をしているのだ」
墨長屋敷の生活に感九郎が加わった途端、新たな「仕組み」の依頼が来たわけだが、その
それから十日経っても半月経っても目処が立たず、感九郎が
「いったい誰に恋をしたと言うのだ」
いつもより帰りが早く、朝や寿之丞と顔を合わせた
心配している節さえあるので、出過ぎた真似と思いながらも朝は口を開いた。
「それが、髪結いの人らしいのです」
「髪結い? コキリは髪を結いなどしないだろうに」
「それが、少し前の『仕組み』でコキリさんが芸者に
「仕組み」は芝居仕立ての筋書きで悪党どもをだますやり方が多いので、服装や髪を工夫して、さまざまな変装をすることがある。
「髪結いや服の仕立ては決まった者に頼んでいたと思ったが」
「あの時はいつもの髪結いがどうしても都合がつかなくてな、信頼できる者を紹介してもらったのだ」
寿之丞はいつものように
「そういういきさつか……しかし、あのコキリがなあ」
「ふむ、クロウは知らぬかもしれぬが、
「そうなのか。私はちっとも」
「お主がこの屋敷にいた時期は短いからのう。ああ見えて面食いでな、好みの顔をした男を見るとすぐに
確かに寿之丞の言う通りなのだ。
髪を結わずに
いわゆる、美人のたぐいのつくりをしているのだ。
感九郎は寿之丞に飯をよそってもらった
「それで、首尾はどうなのだ?」
「うむ? ああ、『仕組み』の筋立ては全く手付かずらしい」
寿之丞がつまらなそうに言うのへ、感九郎が首を振った。
「いや、違う。コキリの恋の方だ」
「あれ、師匠。そう言う話がお好きだったのですか」
朝はつい声をあげてしまった。
意外なのである。
感九郎は男女のことにあまり関心がなさそうに思えていたのだ。
「いや、他人の恋を腐そうと思っているわけではないが、あのコキリが恋をするというのはいささか気になってな。真魚は知っているのだろうか。女子同士だと話すことも違うだろうからな。今度あったら聞いてみよう」
結局、面白がっている。
「……それがな、相手の髪結いにかまをかけたらしい」
「そうなのか。それでどうだったのだ」
「いや、それがどうやらふられたようなのだ。相手はえらい色男なのだが『女に興味はない』と言われたそうだ。コキリはまだ
「なんと! それはかわいそうだな……しかし、ジュノはなぜそんな事を知っているのだ」
「いや、朝早くにそれがしが起きてこの居間に来ると、三日に一度はコキリが
寿之丞が刺身を口に放り込むや否や、声を大にした。
「そうですか、
「クロウもしっかりと『魚吉』の
寿之丞が適当なことを言っている。
とうとう朝は口を挟んだ。
「あの……よろしいですか」
「うむ? どうした、朝。一口も食べていないではないか。ひょっとしてお主、烏賊は苦手だったか。今日は烏賊の刺身に烏賊の煮付け、烏賊の塩焼きだからもしそうなら飯のほかには味噌汁しか食べるものがない。他に何かないか探してこよう」
と、寿之丞がとぼけた気遣いを寄せながら腰を浮かし、感九郎の方は、
「いや、惚れた
などと的外れなことを言っている。
「違います違います。僕は烏賊は食べられますし、それにコキリさんの恋も心配なのですが」
そう言うと二人は顔を見合わせ、またこちらを見る。
朝は少々呆れながら口を開いた。
「僕が言いたいのは『仕組み』のことです。もともと、『ものづくり御前試合』までに時間がないではないですか。出るにしろ出ないにしろ何かの策を講じないといけないのに、準備どころか筋書きが全くできていないじゃないですか」
「そうだのう。小霧があの様子では今後も
そう言って寿之丞は烏賊の塩焼きにかぶりついている。
「だからですよ。いったいどうするのですか」
「まず落ち着くといい、朝」
感九郎が
「私だって何も考えていないわけではない。万国博覧会、そして『ものづくり御前試合』がどういうものかに思いをめぐらせ、準備をしている。役に立つかどうかはわからぬがな」
「でも、もう時がないじゃありませんか」
御前試合が開かれるのはあと半月後である。
それでいて何も決まっていないのだ。
「今回の『仕組み』は諦めるのですか」
「いや、それはいただけないのう」
寿之丞が二杯目のご飯を自分の
「御前は普段は
すると、感九郎が
「私がいた時はそういうことはなかったが、礼金がない以外に、なにか罰でもあるのか」
「罰というのではないが……御前はああ見えてうわばみでな、酒を何合でもあけるのだ」
寿之丞は苦虫を嚙み潰したような顔で烏賊の煮物をご飯の上に乗せ、かきこんでいる。
「小言を言いながらのその酒を朝まで付き合わされるのだ。一日二日ではないぞ。十日連続の時もあった」
「それはこたえるな」
「しかも御前は泣き上戸でな、涙ながらに責めてくるのだ。『あたしらにとっちゃあ一時のことでやすが、この国のここそこで悪事をはたらかれて苦しみ続ける人がいるのがわかりやせんか』『これが悪党たちが思い知る最後の機会だったかもしれないのに、どうしてもうすこし踏ん張れなかったでやすか』と、まあこれが夜が明けるまで続くわけだ。今までそれがしとコキリ以外にも墨長屋敷に住んだ者の数は少なくないが、多くの者がその酒の責め苦を理由に出て行ってしまった……まあ、今回も失敗したら屋敷に戻ってきて毎日酒を
「それは嫌だな。そうなったら私はやはりここではなく、他の
「おっ、お主はこずるくなったのう。それは許さぬぞ。
感九郎と寿之丞が
「そういうことではありません! だって『仕組み』をしないことには、悪事がはびこるのでしょう?」
「うむ、まあ、そういう風にも言えるのう」
寿之丞がまたお代わりをよそいながら
「しかしのう、コキリができなければそれがしたちでは何にもならんのだ。『仕組み』において筋書きというのはえらく大事でな。よく考えなければならんが、その実、簡素でなければいかん。その場その場で千変万化しなければ役に立たぬからな。コキリでなければ筋書きは書けんよ。かといって無理やり書かせることもできん。
「でも……」
「朝、ジュノの言う通りだと私も思う。だからこそコキリの恋の行方が気になったというのもあるのだ……が、いかんな。いま聞いた限りではコキリは頼りにならないから、皆それぞれにできることをしておくしかない。及ばずながら私もできることは準備し始めている」
感九郎が嚙んで
寿之丞が早くも丼飯を三杯たいらげ、茶をいれながら低い声を響かせた。
「おお、クロウも
「子もできましたゆえ」
「なによりなにより……朝、お主の言う通りのところもあるが、焦っても始まらん。それにクロウだけでなく、それがしもできることはしておるのだ」
そう言うと、皆の
「『仕組み』の依頼を受けてからこちら、久しぶりに知った料理屋の座敷を流してな、手妻芸を見せて回っていたのだ。座敷には武家だの商人だののなかでも羽振りの良い連中が来るからな、話を聞いているだけでも世情がわかる」
「なにかわかったのですか?」
朝は聞いた。
かなり前のめりである。
それもそのはず、そもそもが今回の「仕組み」が全く進んでいないことに
もし、ジュノが『一目連』の思惑に到達したのならば、それは薩摩藩の不穏な動きとつながっているはずだ。
それを知りたい。
やはり自分は父から
「ずいぶん食いついてくるのう。いや、わかったことは色々あるのだが、はっきりしているのは『菟田屋』の動向なのだ。どうやら菟田砂峰が西国からこちらへ出てきているらしいのだ。道具なども一式、佐賀から持ってきて、そのまま『ものづくり御前試合』に臨むらしい」
「ああ、菟田砂峰ですか」
朝は内心、がっかりした。
わかったのは薩摩の
が、「仕組み」にとっては重要な標的であることは間違いない。
寿之丞は途端に朝の気がしぼんだのを不思議そうにしながらも、話を続けた。
「その裏も取れたのでな、実は今夜、朝に頼もうと思っていたのだ」
「何をですか」
「横浜へ行ってくれないかのう」
「横浜!」
朝の声が高くなった。
横浜には白がいるのだ。
「急に元気になったのう……菟田砂峰の
「行きます行きます!……ジュノさん、きちんと『仕組み』のことを考えていたのですね」
「それがしも御前の泣き酒につきあいたくはないからのう……とにかく、それ以外にも菟田砂峰の弱みでもなんでも良い、片端から役に立ちそうな事を調べてくれい。金はいくらつかっても御前が払ってくれるから気にせんで良い。なにかわかったら文を出すか、即刻戻ってきてくれい」
「わかりました」
朝は声を高くした。
安穏と過ごしているように見えて、その裏で事を進めていたのだ。
頼り
「本当はそれがしが横浜へ同行したいところだが、まだ調べておいた方が良いことがあるので江戸を離れられんのだ。クロウ、お主も行けんだろう」
感九郎が
立場上、「魚吉」から離れられないのだろう。
「というわけで、朝ひとりに任せてしまうことになるが、はたして大丈夫かのう」
「問題ありません。
「四、五日たったらいちど江戸へ戻ってきてくれい。朝が調べたこと、それがしが耳にしたこと、クロウが考えたことをつきあわせようではないか。コキリはあてにならんから今回はそれで『仕組み』をやるしかなかろう」
朝はうなずいた。
思っていたよりも大事な役を仰せつかってしまった。
すると、感九郎が神妙な声を出した。
「朝、戻ってきたら私の相談にのって欲しいのだが」
「なんでしょうか」
師匠たる感九郎が朝に頼み事をするのは珍しい。
「万博という場で、異国が日本にどんなものを望むのか聞きたくてな」
「……僕ではわからないことが多いと思います。米利堅の血が流れているというだけで、万博どころか異国に行ったこともありませんから」
朝はうつむいた。
結局、自分は中途半端に思える。
日本人なのか、異国人なのか。
男になりたいのか、女がよいのか。
朝は、今にも崩れそうな
すると、感九郎は声を穏やかに響かせた。
「確かにそうかもしれぬ。しかし、私たちとも異国人とも違うものを持っている朝に相談にのって欲しいのだ」
「師匠たちとも異国人とも違うもの?」
すると感九郎はこちらを、すう、と見た。
「朝にしか見えぬ景色があるということを忘れぬ方が良い」
いつもの
相変わらずその意味はわからぬが、しかし、なぜかしら心持ちが落ち着いた。
「……わかりました」
「よかった。実に助かる。いや、万博でどのようなものが望まれるかわかれば『ものづくり御前試合』がどういう風に行われるかわかるのではないかと思ってな」
「それなら今晩にでも話しませんか」
「いや、それを聞くために朝に見せるものがまだできていないのだ」
「!……ひょっとして、師匠は師匠は『ものづくり御前試合』のために何かおつくりになっているのですか」
知らぬうちに声が踊った。
しかし、感九郎はかぶりを振る。
「いや、言うほどのこともないのだ。この間も言ったようにまず私のつくるものが万博の場に出品するものとして通用するとは思えぬのだ。しかし、ものづくりというのは面白いものでな、どんなときにも『隙間』がある」
「隙間……?」
「まあよい。とにかく、身に危険のないようにな。本当は私が横浜に同行したいくらいなのだが、どうしても江戸を離れられぬ」
感九郎がそう言うのに
第四章 朝、再会する
「仏蘭西語が話せると聞いたが」
菟田砂峰が抑揚のない声で問うてきた。
一見、微笑んでいるように見えるが、
底が知れぬ。
ところは横浜は異国人の住まう居留地にある
時は朝が江戸を
「はい、英語の他に仏蘭西語、阿蘭陀語を話せます。まだ未熟ではありますが」
朝が
「そうか。それは助かる。
そう言って茶をゆっくりと啜っている。
この異聞館は横浜港や外国人居留地と近いだけに、異国人好みにつくられている。
砂峰の部屋にも卓と椅子が置かれているが、一方で
しかし、野暮というわけではなく、
日本趣味の異国人にでも意匠や
いずれにしても、異国の生活に日本を取り入れたらこのような部屋になるのではないか、と思わせられた。
「さっそくで悪いが、とある仏蘭西人が持ちかけてきている商いの話をしたいのだが」
砂峰は無駄が嫌いなようである。
世間話もなく、会ったばかりの朝を相手に仕事の話を始めた。
朝は異聞館から出ると。
菟田砂峰の話は簡潔で、時間はかからなかったが、非常に濃密で疲れてしまった。
寒さが心地よいが、いささかこたえる。
自作の首巻きをきつくしめ直し、朝は歩き始めた。
横浜に来て早々に、まさか砂峰に会えるとは思わなかった。
しかも、通詞として雇われたのだ。
砂峰のことを探るのに、これ以上
感謝せねばならぬ。
朝は上機嫌で己の宿へ足を向けた。
横浜には父の住まう屋敷があるが、なるべく顔を合わせたくなかった。
嫌いというわけではない。
なぜかしら、一緒にいると息がつまる気がするのだ。
父に会えばなんらかの情報が手に入るかもしれぬ。
なにせ「一目連」の
しかし、こちらのことが「一目連」に漏れぬとも限らないから、それも良い手ではない。
今の所、朝が「仕組み」に
いずれにしても間合いはとったほうが良い。
なので、外国人居留地へと続く関所の内側、いわゆる関内で別の宿をとっていた。
屋号は「
異聞館に遠からず近からず、それに宿代が高くないのだ。
昨夜は到着が遅かったから
「お帰りなさいませ! 朝様」
山屋の玄関に入ると、元気な声が響いた。
途端、
昨日、横浜に着いた時に、宿も決まっていなかった朝を元気よく迎えてくれたのがこの女中であった。
場所柄だろう、横浜へ来てから異国人への
微にいり細をうがち世話をしてくれるのだ。
「朝様、お部屋までお荷物持ちますよう」
そう言って、朝の洋杖と
朝がその勢いに
「そうだ、朝様にお客様がいらしてたんだ。すいません! 先ほどいらして、朝様がまだ戻っていないと申し上げたら、うちの茶屋で待っているから戻られたら伝えるように、と言われたんでした」
朝は、ああ、と声を上げて、右手を頭へとやった。
砂峰へ自分をつないでくれた者と会う
「すいませんが、洋杖も鞄も部屋へお願いできますか」
朝がそう言うと、女中は鞄を口元まで持ちあげ、まるで顔を半分隠すようにして小さく声を出した。
「ずいぶんと二枚目のお客様でしたが、どなたなのですか」
まるで好物のご
朝は少したじろぎながらも、「仕事を助けてくれている人です」と答えて、
背後で「色男の異国人と悪そうな二枚目……」と
仕方なく、首を傾げながら山屋の茶屋の方へと急ごうとして、自作の首巻きに気がついた。
これも部屋に持っていってもらえばよかったな、と思いながらも首回りにそのままにして歩き始める。
山屋は異聞館とは趣が違っており、異国人たちに日本を感じてもらえる作りとなっている。
宿場町の旅籠、そのままなのだ。
面白いのは山屋の隣に茶屋をつくっていて、そこで茶や甘味を出すという趣向をとっており、こちらも異国人に人気があるようだった。
玄関を出て隣の茶屋に入るが、目当ての者が見当たらぬ。
方々にいる客の顔を確かめながら進むと、一番奥で小さな帳面を読んでいる者がいる。
広い額と逆八の字に真っ直ぐな
朝はそちらへと近づいた。
「お待たせしました。『菟田屋』さんに会ってきました」
「おお……朝か。首尾はどうだった」
顔を上げてこちらを見やるのは、細面に目立つ、少々
悪い奴の目だ。
高い背を折り曲げて座り、
誰あろう、品川宿で朝を助けた白である。
「うまくいきました。本当におかげさまです」
「いや、つなぎをつけたからといってうまくいくわけではない。朝の力だ」
「でも、よかったのですか?」
「何がだ」
「仏蘭西語の通詞なら白さんもできるでしょう。せっかくの話を僕にふってしまって良かったのですか」
「いいのさ。『菟田屋』とは色々あってね、俺は会いたくねえんだ」
そう言って悪そうな顔をする。
「何があったのかは聞きません。白さんなら悪いことたくさんしてきてそうですから」
「
「約束通り、白さんの話はせずに、通詞を探している噂を聞いたていにしましたよ」
「ありがたい。しつこく探られたりしたら面倒で仕方がねえ」
「あまり悪いことばかりしていると、どこにもいられなくなりますよ」
そう憎まれ口を
白が帳面を懐にしまい、大きく息をつく。
「昨日、お前さんが飲み屋に現れた時にゃあ驚いたぜ」
「横浜についてから何軒かの料理屋に聞いたら、すぐに居場所がわかりました」
「気をつけなきゃいけねえな。
そう言って顔をしかめている。
「白さんはいつから横浜にいるのですか」
「四年くれえ前からだな。
朝が横浜から江戸に出た年であるから、すれ違いだ。
「またどうして横浜に」
「そりゃお前、仕事だよ。外国人居留地があるからな、客がたくさんいる。お前さんこそどうしてこんなところにいるんだい」
朝は言いよどんだ。
当たり前だが、本当のことを言うわけにはいかぬ。
慎重すぎるきらいはあるが、朝の父が外国人居留地に住んでいることも知られぬほうが良いのだろう。
「……通詞のための勉強です。横浜は日本の玄関。異国への扉があるところですから」
「なぜ昨夜、『菟田屋』について俺に聞いたんだい?」
「それは……もし知っているなら教えて欲しいくらいの気持ちだったのですが」
昨夜、「菟田屋」が仏蘭西語のわかる通詞を探していると教えてくれたのは他ならぬ白である。
酔った白に出会い、白はそのまま酒を
「……『菟田屋』になにか用があるのかい?」
白の目が、すう、と細くなった。
全てを見透かされている気がする。
「いえ、『菟田屋』さんは異国との商いに長じているという噂は耳にしていたのですが、ひょんなことからいま、横浜にいらしているとの話を聞いて……その、僕はこんな見た目ですが、日本を出たことが一度もなく、せめて異国とのやり取りに長じている方から勉強させていただきたく」
「ふうん、そうかい」
そう言って、白は黙った。
朝は
出たとこ勝負の
頃合いよく、茶屋の女中が焼きまんじゅうを持ってきたので、これ幸いにと朝は両手でそれを持ち上げてかぶりついた。
熱い。
よもぎが練り込まれているのだろう、まんじゅうの皮は緑色で、柔らかいそれを
口の中が
ねっとりとしながらも元が小豆だからであろう、どことなしかほっくりともしている。
熱を加えられて甘みが増しているのだが、塩気やこくもこれまた浮き立っていて、ただ甘いだけではない。
見事な味になっているのだ。
朝は一口食べると片手で
こちらは甘味に合わせてあるのだろう、濃いめの緑茶で、きちんと渋い。
舌にのこった、まろみのある甘さを洗い流してくれるので、すでに口が焼きまんじゅうを欲している。
間髪をいれずにかぶりつこうとしたところへ、白の顔が近づいてきて、ぱくり、と朝の持った焼きまんじゅうを嚙みちぎり、半分ほどうばっていった。
「なにするんですか!」
思わず朝は声を高くした。
まるで小さい悲鳴だったので、店の者や客がいっせいにこちらを見ている。
一方、白は悪びれもせずにまんじゅうを、もぐもぐ、と
「お前さんがあまりにも美味そうに食っているからな。つい食べたくなった。甘いものはあまり食わないが、なかなかのもんだな」
「ああ……半分も食べちゃって。僕の焼きまんじゅう」
「すまんすまん。なんだ、朝は甘いもの好きか。まだ子どもだもんな」
「子どもじゃありません! 失礼な! 僕のまんじゅうを勝手に食べたことに怒っているんです!」
「そう怒るな、この間助けてやったし、『菟田屋』も紹介してやっただろうに」
「それとこれとは別です」
「しかたねえなあ、もう一個頼んでやるよ」
白が面倒そうに店の者を呼ぶので、焼きまんじゅうだけではなく、団子や汁粉まで頼んでやった。
次々にやってくる甘味を見て、白は顔をしかめている。
「お前……そんなに食うのか」
「甘いものは好きですから。なにせ子どもですからね」
嫌味を言いながら、朝は汁粉を
こちらもあんこだが、さらっとした口当たりの甘みが口に染み込むようにして、
団子は団子で、やはりあんこが乗っかっているのだが、こちらは甘みに歯応えが加わっている。
同じあんこでも姿を変えると食感が違うのだ。
それらを平らげて、おかわりした渋い緑茶を
「大したものだな。全部食べるとは」
「感心しているのですか、
「両方だな」
そう言って、にやり、と笑った。
つられて朝も笑ったのだが、白とのやりとりが楽しいのか、それとも甘味に満足したからなのかは自分でもわからぬ。
このような時の過ごし方を今まで知らなかった。
楽しいが、穏やかである。
相手のことが気になるが、歯に
初めて会ってから間もないのに、前から知っているようである。
朝はまるで芝居の世界にいるように思えて、それでいて顔を上げると
その時である。
白が低い声を出した。
「朝、一つ相談があるのを聞いてくれねえか」
人の気を
こう
朝はうつむき加減のまま、口を開いた。
「なんでしょうか?」
「お前さんが『菟田屋』の通詞として仕事をしている間に、探って欲しいことがあるんだ」
「!……」
息を吞んだ。
なぜそれを頼むのだろうか。
しかし、それよりも別のことが気になった。
ひょっとして白は初めから朝にそれをさせようと、「菟田屋」につないだのか。
朝の様子を察したのか、白は声の調子を落とした。
「いや、もちろん嫌ならいいんだ。もとよりお前さんに頼む気はなかったんだがな……ちょいとこっちの気持ちが動いちまってな」
「気持ち……?」
目を上げられぬまま、そう
もとより頼む気はなかった、という言葉を信じて良いものなのか、どうなのか。
「ううん……頼むどころかお前さんに話すことではないんだが、言いかけたものをこちらの胸に戻すわけにはいかねえな」
そう言うと、白は懐から小さな
ちょうど朝の目の先である。
「なんですか、これは」
白は何も言わず巾着袋をあけ、親指ほどの大きさの白い小さなものをつまみ出した。
何だかわからない。
目を近づける。
どうやら陶器だか磁器だかのようであるが、欠けている。
いや、むしろ茶碗か皿かのふちが三角に割れて欠けた、その一片である。
「これは……」
いったい何なのだろう。
そこでやっと白が口を開いた。
「金継ぎというのを知っているだろう」
朝はうなずいた。
聞いたことはある。
割れた陶器を漆でくっつけ、その割れ目を金や銀の粉で彩るやり方である。
一度壊れたのにも関わらず、元の器より価値が高まることもある。
割れてしまった茶道具を継いで、城一つ買えるほどまでの高値になったものもあるという。
実に不思議である。
「金継ぎがどうかしましたか」
「うん。ならば、金継ぎの分野で『呼び継ぎ』といわれる手法があるのは知っているか?」
「呼び継ぎ……?」
「知らんか。なかなかに面白い手法でな……普通の金継ぎは簡単に言やあ『壊れた器を元に戻す』やりかただろう」
朝はうなずいた。
「呼び継ぎってやつも基本的にはそうなんだが、別の器のかけらをくっつけちまうんだよ」
「別の器のかけらを?」
なんだそれは。
おかしなことになるのではないか。
「そうするとたとえば、右半分は日本でつくられた陶器で左半分は異国でつくられた磁器の皿なんてのもできあがる。もちろん金継ぎだから、くっついた割れ目は金色や銀色にみえる。そんな皿は
「へえ、僕はてっきり茶道は日本や
「そういう面もあるが、
にわかには信じられぬ話で首を振ると、白は、ふん、と鼻を鳴らした。
「だからよう、そういう皿をうまくつくって、うまく世に出せば価値は出るはずだぜ」
面白い話である。
そんな皿があったらよほど楽しいだろうが、しかし、そもそもがそんなに都合よく「他の器にはまるかけら」ができるように割れるのだろうか。
そう言うと白は下唇を
「そうなんだ。なかなか合うものがなくてな、作るのにめぐりあわせや運も必要となる。見つけるのはなかなかに難しいだろうな……ああ、ものは違うが呼び継ぎのつくりといやあそれに似ているな。それそれ、お前さんのつけているそれだ」
藪から棒に朝の方を指差してくる。
何かと思っていると向かいから、にゅっ、と腕を伸ばして首巻きをつかんだ。
「これだよ、これ」
そう言いながら引っ張るので仕方なしに首からはずすと勝手に、さあっ、とさらわれた。
「この間も思っていたが、こいつはなかなかに奇妙な作りをしている」
そんなことを言って広げたり、透かしたりしている。
「ちょっと、やめてください」
「いや、他でこんな作りは見ねえからな。刺し子だのメリヤスだの、いろんな布地をつぎはぎしているのが面白いし、それぞれの布地の少しやれてるのもいい。変わった景色だぜ」
「景色……」
感九郎の言葉が脳裏に走る。
──朝にしか見えぬ景色があるということを忘れぬ方が良い。
「ああ、俺らは物の表情を『景色』というんだ……なにより『こうしてやろう』という雑念がみあたらねえ。こういうものでは珍しいんだぜ、それは」
真顔でそんなことを言っているので、朝は慌てて首巻きを取り返した。
「もう、やめてください。手仕事の師がせっかくだから身につけろと言うから首に巻いてるだけで、つくった僕は恥ずかしいばかりなんですから」
「なんだ? それをつくったのはお前さんなのか?」
「そうですよ」
「どこかの古道具屋で買ったのかと思った」
「悪かったですね! 僕は不器用で、メリヤス編めば編み目が乱れるし、刺し子をやれば糸の道がうねって、古道具みたいに汚くなってしまうんですよ」
朝はそう言ってそっぽを向いた。
そして、もうこの首巻きは二度とつけまい、と心に誓った。
すると、白は、からから、と笑った。
「……いや、気を悪くしたならすまなかった。しかし、ちげえよ。『古道具屋で買った』ってえのは褒め言葉だ」
「取り繕ってもだめです」
「そんなんじゃねえよ。古道具を異国人に売るのが俺の商いなんだぜ」
白の声が低くなった。
「そして、俺の商いは千両、万両になることをはばからない。いいか、朝。古道具は金になるんだ。まさに値千金なんだよ」
そう言うと、白は黙った。
しばらく、朝も口を開かずにいた。
どうにも口八丁で転がされている感じもするが、仕方がない。
「わかりましたよ。でももうこの首巻きのことは話題にしないでください」
「なんでえ。本気で褒めてんだぜ。いずれにせよ、呼び継ぎってやつはその首巻きみたいに面白みや意外さを秘めてるんだ……それでな、このかけらなんだが」
白はさきほど懐から出した
すっかり忘れていた。
その話だったはずである。
ここにきて朝はふと思い立った。
「ひょっとして、呼び継ぎをつくるためのかけらですか」
そう言うと、白は不敵な笑みを浮かべた。
悪い奴の笑みだ。
白はそれから、ゆっくりと話しはじめた。
あの
どうやら、呼び継ぎはその長益の趣向だったようである。
「その有楽斎が死ぬ前、気に入っていた器を割ったらしく、最後にもう一つ呼び継ぎを作らせようとした、という言い伝えがあってな……それがまた本当かどうかわからねえんだが、俺は子どもの頃からその話がどうしても気になっていてな」
白は静かにそう言った。
ずいぶんと白らしくない、夢を追うような話である。
朝は口を挟んだ。
「ということは、その器は誰も見たことがないのですね」
「それが、それらしいものが見つかったんだ」
「あったんですか」
「いや。それらしいというだけで、本物かどうかはわからない。しかし、とにかくあったんだ。ものは
本物かどうかがわからないのに、なぜその茶碗が『それらしい』などと言われるのだろうか。
そう
「それがな、その呼び継ぎでつくられた茶碗は欠けていたんだ」
わけがわからない。
欠けているのを直すのが金継ぎなのではないだろうか。
そう言うと白は面白そうな顔をした。
「そりゃそうなんだがな……呼び継ぎってのはさっきお前さんが言った通り、もともと別の器が割れたのをくっつけるわけだから、なかなか合うものがないんだ。かけらをつくるために器を割る
「全てが
「そうだな。死ぬ前にできるだけのことはしたかったんだろう。最後の部分については、形が合っても、気が済まない。長益ほどの人が満足するには、形が合いました、ではこれにしよう、ではすまないだろうからな。もともと、どんな器から欠けたのか、という由来やいわれを重んじたろうし、そもそも継いでみた景色が
白の話を聞き、朝は面白く思った。
たかだか茶碗の話である。
しかも壊れたものを直そうとしたが、長益がこだわっていたから直せなかった、というだけの話である。
しかし、そこに何らかの物語を感じる。
「その言い伝え通りの欠けた茶碗が見つかったのですか」
「そうだ。茶碗のふちが大きく割れた最後の部分。三角に切り取られたようなところを残して、後を
実に面白い。
ここまできて、朝はさらに興味が出た。
「白さんは、なぜその茶碗が欲しいのですか」
「そりゃな、もちろんそれだけのいわれのついた道具を手にしたい、自分のものにしたい、と思わなくもねえが、それだけじゃねえんだ……俺は先に見つけちまったんだよ」
「何をですか」
朝がそう問うと、白は手のひらの上の白いかけらを目元まで持ち上げた。
三角の形をしている。
まさか。
「ふん。そうだ。織田有楽斎長益は
朝は、いつのまにか己の呼吸が浅くなっているのに気がついた。
さきほどまで、朝にとってがらくただったその白いかけらが、長い時や長益の情念をまとって、大事な意味がある貴重な物のように見えてきたのだ。
「……そのかけらがはまる茶碗の方は、いったいどこに」
すると白はまた、不敵に笑った。
悪い奴の笑みだ。
「長益の呼び継ぎの茶碗は……」
白はそこまで言ってかけらをつまみ上げる。
朝は
すると白は細い目で、すう、とこちらを見やった。
「つい先日、菟田砂峰が手に入れたらしい。それが本当かどうか、確かめて欲しいのだ」
奇妙なことになった。
朝は山屋の自室に戻り、腕組みをした。
横浜にやってきたのは、「仕組み」のために菟田砂峰を調べるためである。
しかし、よりによって白にまで、その砂峰のことを調べるように依頼をされてしまった。
もとより、品川宿で助けてもらった恩がある。
もしうまく調べがついたら礼をするとも言っていた。
今回も、白は砂峰とつないでくれた。
いや、それは都合よく朝を「送り込んだ」かもしれないのだが。
よくわからなくなった。
白に信頼されているのか。
それとも利用されているのか。
なんだかこれより先のことを考えたくなくなった。
こんなことは初めてである。
朝はため息をついた。
外から差す陽の光が傾き、ほの
(気になる続きは本書でお楽しみください)
作品紹介
書 名:幕末万博騒動
著 者:横山 起也
発売日:2025年04月25日
1867年、パリ万博に日本が初出品!…その裏側にあった騒動とは!?
17歳の朝は、米利堅(メリケン)人通詞と日本人の遊女の間に生まれた子だ。ひょんな事から蔵前の墨長屋敷へ住み、常に洋装である。口入屋から通詞の仕事を紹介され、品川宿へ向かった。依頼主の仏蘭西の商人と話していると、1867年に開催されるパリ万博に、江戸幕府の他に薩摩藩も出るという噂を耳にする。万博参加は、国でないと出られないはずなのに、なぜ薩摩藩が…? 不思議に思いながらも長屋に戻った朝は、墨長屋敷にパリ万博の審査にて、闇組織「一目連」が参加するのを阻止すべしと、「仕組み」の依頼が入ったことを知る。出品物の「長益の茶碗」を巡る騒動のなか、朝は白と呼ばれる人物の協力を得て、佐賀の唐物屋(とうぶつや)に近づく。異国が日本に求めるものとは何か――日本初参加(!?)の万博の裏側を、朝の見た景色と共に描き出す!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000618/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら