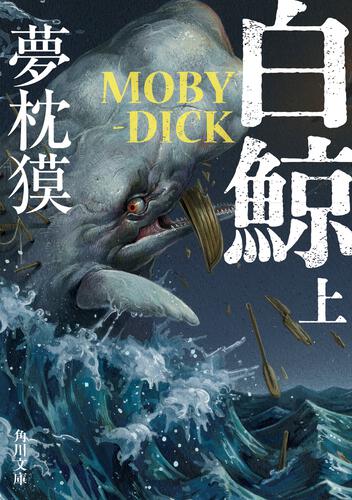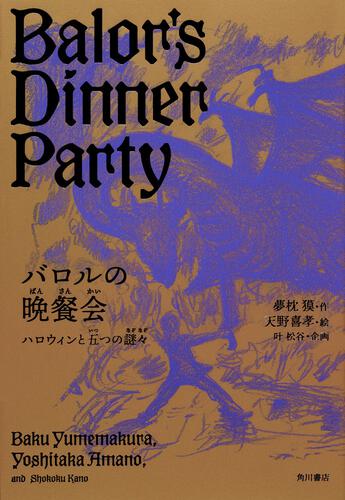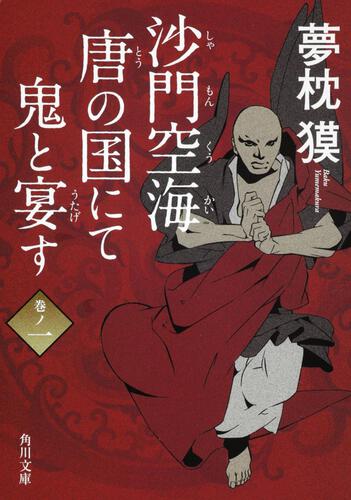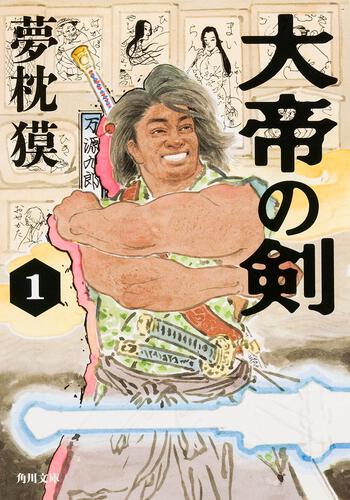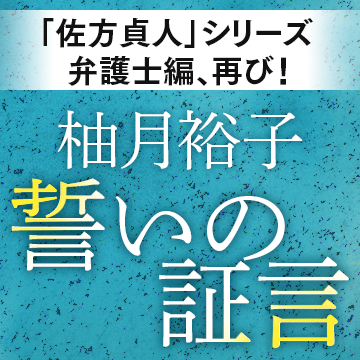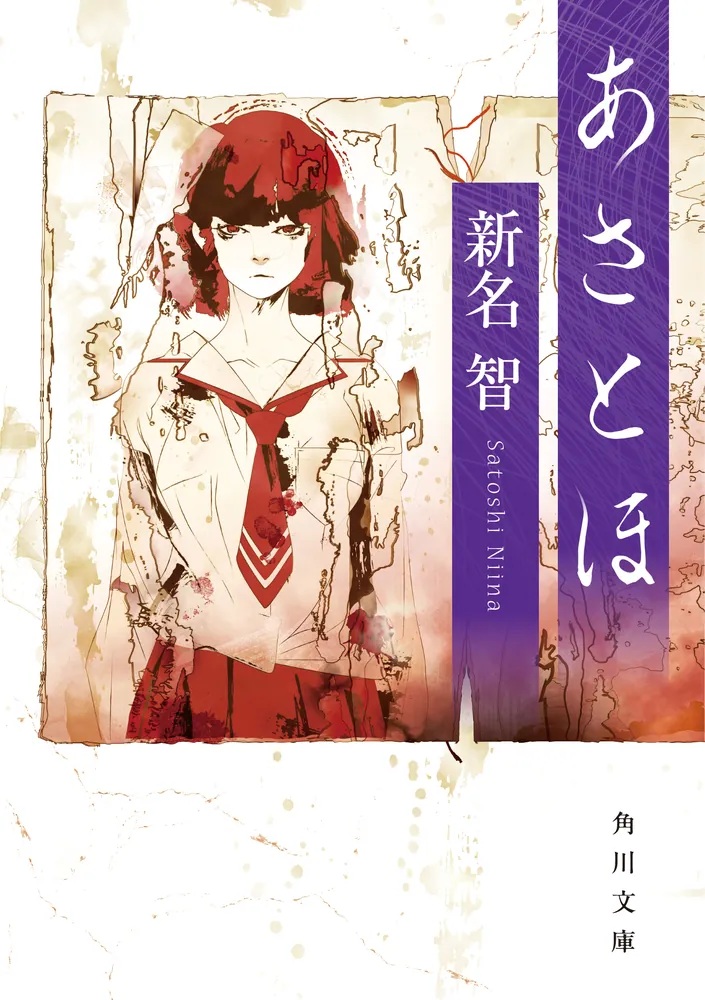五章 キマイラの牙
1
――夜。
深い闇の中を風が渡ってゆく。
雲斎は、独りで囲炉裏に
さやさやと揺れる葉ずれの音が、ここまでとどいてくる。
それに耳を傾けていると、うっとりして眠くなってしまいそうである。
半分閉じかけていた眼を、雲斎はふっと開いた。囲炉裏からたち昇っていく煙に眼をやり、煙とともに上へと移動させる。
煙は、むき出しの
見上げたまま、呆けた顔で煙の行方を追っていた雲斎の眼が、すっと細められた。
「誰かな――」
低くつぶやいた。
「先ほどから、わしをうかがっているらしいが、そんな所で煙たくはないのか――」
屋根に、何者かがいるらしい。
しゅっ、と息を吐く音がして、何者かが移動し始めた。ほとんど音をたてない。
雲斎は、眼で、屋根の上を移動していくものの後を追っている。それは、雲斎を中心に円を描くようにして動いてゆく。
――と。
ふいに、そのものの気配が消えた。
――宙に跳んだのであろう。
雲斎はそう想った。
しかし、家の周囲に着地するはずの気配が伝わってこなかった。近くの樹に跳んだとしても同じである。枝に跳びついたにしろ、幹に跳びついたにしろ、その時、とどいてくる葉ずれの音に、何らかの変化を生じさせずにはすまないはずだ。
――まだ屋根か。
天井を睨む。
やはり気配は消えていた。
もし、まだ屋根の上にいるとするなら、よほど
――それほどの相手が、何故気配をさとられるようなヘマをしたのか。
「ふむ」
雲斎の顔が笑った。
「なるほど――」
楽しそうにつぶやいた。
「技くらべをしたいというわけか」
「喝!」
ストロボの
気の放射を受けて、屋根の上に潜んでいた黒い影が、雲斎の意識の中で一瞬浮きあがった。完全な隠形に入っていれば、雲斎の放った気は通り抜け、その存在は知られることなくすんだであろう。しかし、屋根の上のそれは、下の雲斎に向かってわずかに意識を開いていた。様子をうかがっていたのである。針先ほどのその隙間から、それの本体に雲斎の気が反射したのである。
一瞬浮かびあがったその黒い影も、次の瞬間、再び闇に溶けたようにその気配を断っていた。
「おもしろいわ」
雲斎は、ニヤリと笑みを浮かべて立ちあがった。
まだ左手に
外へ出る。
風が雲斎の頰をなぶる。
いい気持ちだった。
「いい晩だなあ、おい」
雲斎は、深く大気を吸い込み、闇に向かって声をかけた。
「わしはここにおる。好きな時に仕掛けてくるがよい」
雲斎は、いきなり草の上に座り込んだ。
すっと禅定に入った。
影と同じように、雲斎の気配も、大気に溶けるようにして消えた。しかし、姿はまる見えである。
大胆というほかはなかった。
風が、草をゆすりながら過ぎてゆく。
雲斎は、ぴくりとも動かない。草をゆらす同じ風に、白髪をなぶらせているだけである。
約三〇分ほどたった頃、雲斎の背後五、六メートルの所に、闇がそこに凝固したように、黒い影がわだかまっていた。
黒い影も動かない。
雲斎も動かない。
さらに三〇分が過ぎた。
雲斎と、黒い影の距離が縮まっていた。黒い影が動いたのである。大きな
黒い影の体内から、ふつふつと暗い
その瘴気の糸が、雲斎をからめとり、次第に強さを増してゆく。
張りつめた瘴気が、みりみりと空気にひびを入れながらふくれあがる。
しゅっ!
と、鋭い呼気が影の口からもれた。重さのないもののように、影がふわっと宙に舞った。頭上すれすれに雲斎の上を跳んだ。
「くけっ!」
「ぬんっ!」
放電に似た
影が、さらに高い宙に跳ねあがっていた。
雲斎はまだ座したままである。何があったのか、常人にはまるで眼に見えない。
もし、雲斎と同じほど眼の利く者が今の戦いを見たら、それは、次のように眼に映じたことであろう。
青白い炎に包まれた影が跳びあがった瞬間、その青白い炎が、一瞬まばゆく輝いて雲斎にぶつかってゆく。雲斎にぶつかったとたん、その炎と同じ強さで、光が雲斎から放たれる――鏡にぶつかった光が、まったく同じ強さで跳ねかえされたように見えたはずであった。
実際に影と雲斎とが触れあったのは、手と足だけである。閃光のように襲いかかった影の足を、雲斎が右の手のひらで、ぽん、と受けたのだ。
影は、その手を
影は宙で一転し、
影が、
影の手から、何かが空気を貫いて走った。それが、雲斎の顔面にぶつかろうとした時、
カシャン!
鋭い音がした。
陶器の割れる音である。
影の投げた小石を、雲斎が持っていた湯吞み茶碗で受けたのだ。
座っていた雲斎の身体が立ちあがっていた。
左へ走り抜けていく影のゆこうとする方向へ、同じ速さで走った。
手に残っていた陶器のかけらを、影に向かって投げつけた。
影の動きがわずかに乱れた。
雲斎はその足を目がけて、手に持っていた小石を飛ばした。さっき投げた陶器のかけらは、この小石のためのフェイントだった。
手応えがあった。
が、影のスピードは少しも衰えない。
そのまま雑木林の中に走り込み、影は、跳躍した。すばらしいバネだった。
地上五メートルはある樹の枝につかまり、身体を一転させてその上に立ち、枝のたわみを利用して、さらに遠くの幹に跳んだ。
雲斎は足を止めて、影が跳んだ枝に眼をやった。
影も、樹上の闇の中に動きを止めていた。
「おぬしか――」
雲斎が言った。
「いつぞやの晩も、ここへやって来たであろう」
影は答えなかった。
ふっ
ふっ
と、息をつぐかすかな音が響いてくるだけである。
「本物の殺気が、おぬしからは感じられぬ。わしと争うことが目的ではあるまい。何の用だ――」
影は黙っていた。
まるで言葉を知らぬかのようである。
「話す気になったら来るがよい。わしは、また酒を飲んでいる……」
雲斎は、影に背を向けて歩き出した。
小屋の中に入り、戸を閉めて、再び
やがて、戸のすぐ向こうの闇に、何ものかが近づいてくる気配があった。
それは、戸のすぐ向こう側で立ち止まり、そこにうずくまった。
「来たか――」
雲斎が声をかける。
GUUU……
獣が
今、その黒い影は、気配を断っていなかった。一枚の戸越しに、暗い思念が漂ってくる。その思念に、酒を飲みながら雲斎は、そろりと思念で触れた。
影の思念は、重く、苦しいもので満たされていた。それが、黒い泥のように、影の本体を包んでいる。
その重い泥の中で、ぎらぎらしたものが、
己の手で己の首を締め、苦しんでいる――そんな風にも見えた。
「迷うておるのか、おぬし――」
雲斎が言った。
「そうだ……」
影が、しわがれた声で答えた。
「一度や二度ではあるまい。おぬし、何度か夜半にここにやって来ては、そうやって泣いておったのではないか――」
「おおお……」
影が狂おしく声をあげた。
激情を必死に押し殺しているため、声は小さかったが、それは、はっきり雲斎の耳にとどいた。
血の滴るような声であった。
哀しみに身をおしもみながら
影は、泣いているのだった。
「おれを、助けてくれ……」
影が言った。
「助けろとな」
「おれは、おれでなくなってしまう。だから、その前に、おれを……」
声の最後の方は、獣の
「その声、聴き覚えがある」
雲斎が言った。
「おぬし、久鬼だな?」
影が、びくんと身をすくめるのがわかった。
開かれていたものがさっと閉ざされるように、影の思念が消え、気配が消えた。
「待て」
雲斎は立ちあがり、戸を開けはなった。
強くなった夜風が、新緑の匂いを雲斎の顔に吹きつけてきた。
外には、もう誰もいなかった。
影の苦しみの
ラララララルウウ~~~~リイイイ……
るるるるるるうう~~~~るるるる……
風に乗って、遠く、あの不気味な獣の
悲痛な、身をちぎられるような声であった。
2
バーやクラブ、
昼間は閑散としているが、それでも夜になれば、あちこちに
スナック『コシティ』。
宮小路の中ほどにあるその店の入り口を見ることができる路地の暗がりに、うっそりとひとりの巨漢が立っていた。
ジーンズと
酔客が、時おり声をかけてゆくが、巨漢は黙ったまま相手にしない。建物の壁に背をあずけ、じっと『コシティ』の入り口を眺めている。
夜の一〇時。
巨漢は、もう一時間近くも、そこにそうやって立っている。
九十九三蔵だった。
九十九は、今、『コシティ』にいる客のひとりを待っているのだ。
昨夜のことである。
いつものように、円空山に顔を出した九十九に、雲斎が話しかけてきたのである。
「久鬼はどうしている」
と、雲斎は
あいかわらずのようです――そう答えた九十九に、雲斎は軽く顔をしかめてみせた。
大鳳は、三日に一度は顔を見せなくなっていた。その晩も、大鳳は来ていなかった。
九十九と雲斎のふたりだけが円空山にいる。
「わしと、おぬしだけの話だがな」
と雲斎。
「大鳳にも内証ということですか」
「うむ。しばらくの間はな――」
いつも軽口ばかりたたいている雲斎が、いつになく口が重い。
「実はな、昨夜、変なものに
「変なもの?」
「いつぞやの晩、外に潜んでおって、ぬしの服を裂いていったあのもののことよ――」
「やつがまた来たのですか」
「軽くやり合うたのだが、やつめ、人とも獣ともつかぬ、不思議な気を発しておった」
雲斎は、昨夜のことを手短に語り、腕を組んだ。
「では、先生は、あれが久鬼だとおっしゃるのですか」
九十九も、驚きを隠せなかった。
「わからん。そうであろうとは想うのだがな」
「では、もし、あれが久鬼だとして、何のためにやつがここへやって来たのですか。来るなら正面から、堂々と先生を訪ねて来てもよさそうじゃありませんか」
「何か
「理由?」
「あれは迷うておった。迷うたあげくの所業であろうよ。ここへ来たのもな、一度や二度ではないぞ――」
「――」
「迷うておる。迷うておるから、やつはあんな風にしか、わしに近寄っては来れぬのよ。哀れなことさ。争うことでしか、わしに語りかけられぬとはな」
「何に迷っていると」
「わからん。わかっているのは、やつが、わしに助けを求めているらしいということだ」
「助けを、ですか」
「いかにも」
「何を助けろと――」
「自分が自分でなくなっていく――と、やつは言っていた」
「自分が自分でなくなる?」
「そうさ。そこでおぬしに頼みがあるのさ」
「頼み、ですか」
「うむ。久鬼の最近の様子を、それとなく調べてほしいのさ」
雲斎が、九十九の眼を、じいっと
「わかりました」
「しかし、久鬼に直接訊くわけにはゆくまいよ」
「そうですね」
「久鬼はあとだ。まず、何か変わったことがあるかどうか、久鬼の周辺から始めることだな」
「はい」
「で、その周辺のことだが、その中には、大鳳も含まれていることを忘れるなよ」
「大鳳ですか」
「ほう。それほど意外そうな顔も見せぬな」
「ええ。先生が話があると言った時、おれはてっきり大鳳のことだと想いました――」
「大鳳だが、あやつ、変わりおったな」
「はい」
「坂口の一件からひと月以上だが、あやつ、おそろしく強くなりおった。それに――」
雲斎は言葉を止め、その先を九十九に言わせようとするように、九十九の顔を見た。
「それに、あの久鬼に似てきたと、そうおっしゃりたいのですか」
「あの久鬼が、やはりここから出てゆく前、あんな風であったな――」
ついに――と、九十九は想った。
このひと月余り、互いに心のうちに思っていたことを、ついに言葉に出して確認し合ったのだ。
九十九は、大鳳について、一番変わったのは、その闘う姿勢についてだと思っていた。以前はなかった、ギラギラした闘争本能のようなものが、大鳳の内部に育ちつつあるのだ。
自分のことを、ふいにおれと呼んだりして、九十九を驚かせたこともあった。
誰かとやり合いたくて、大鳳がうずうずしているのも、手にとるようにわかっていた。
自分にも覚えがあるからである。
技を覚えてくるに従って、それを誰かに使ってみたくなるのだ。特に、大鳳のように、短期間に極端な
大鳳の内部に、理解し難い、不気味な黒いエネルギーの塊を見て、時おり、どきりとさせられることもある。
三日に一度、ここにやって来なくなった大鳳がどうしているかも、九十九は薄々は感づいている。
由魅である。
ここに来ない日のほとんどがというわけではないが、大鳳があの由魅と会っていることは、まず間違いないはずである。
大鳳の、深雪に対する態度が、次第に冷たいものになっていることが、九十九には無念であった。
久鬼の周辺ということで、雲斎の口から大鳳の名前が出たのも、納得がいく。雲斎がほのめかしたように、大鳳が久鬼に似てきたのも、また不思議な暗合であった。
「そう言えば――」
と、九十九は雲斎に言った。
「久鬼の近くにいる
「西本?」
「剣道部の主将ですが、おれと同じクラスなんですよ。病気らしいと見舞いに行ったクラスの友人が、西本は、病気ではなく、何かをひどく恐れているようだと言ってました――」
「恐れてると?」
「はい。『久鬼さんに言われて確かめに来たのか。おれは何も見てないし、何もしゃべらないぞ』と、ヒステリックに言ったそうです」
「ふむ」
と、雲斎はうなずいた。
それが昨夜のことである。
そして、今日の放課後、九十九は西本の家に顔を出してきたのである。だが、西本はいなかった。母親の話では、この二日間、友人の所に泊まるという電話があったきりで、帰っていないのだという。
九十九は、西本と仲の良かった友人たちに連絡をとり、ようやく、西本が出入りしている場所をつきとめた。
それが、宮小路の『コシティ』だったのである。
九十九は、今、『コシティ』から西本が出てくるのを待っているのだ。
時計は、すでに一〇時三〇分になっていた。
西本が出てきたのは、それからさらに五分ほどたってからであった。
西本は、酔っていた。
顔が赤く染まり、指にはタバコをはさんでいた。
三人の、チンピラ風の男と一緒だった。
九十九は、壁からすっと背を離し、すたすたと西本に向かって歩き出した。
西本が九十九に気がついた。
西本の顔が、
タバコが唇から落ちた。
「ひっ」
西本の口から、ひきつれたような細い叫び声がもれていた。
3
「捜したよ、西本――」
九十九が言った。
「貴様、何しに来たんだ。おれはなんにもしゃべっちゃいないぞ」
「ちょっと話があるんだが――」
「いやだ」
西本は、完全にうわずっていた。
「おまえに話なんてない。帰ってくれ――」
西本の
「にいさん、おれの
「まさか、酒やタバコがいけねえなどと、利いた風なことぬかすんじゃねえだろうな」
九十九をどうあつかうか、まだ決めかねている様子である。いつでも闘いに入れる体勢を作りながらも、九十九の身体の大きさに、恐れをなしているのである。
「おれは、その西本のクラスメートです。別に、説教するつもりで捜してたわけじゃない。彼とちょっと話がしたいだけです。話さえすれば、酒を飲もうが、タバコを吸おうが、そんなのはおれの知ったことじゃない」
「ほう――」
三人の中で、リーダー格らしい男が、九十九の眼を見上げた。ケンカ慣れしているらしい、
三人とも、二〇歳を越えたばかりの、ヤクザの予備軍といったところである。
酒を飲んでいるうちに、西本となじみになったのだろう。知り合って、長くとも三、四日、まだほやほやといったところだった。
「なかなか話せるじゃないか、にいさん。だがよ、この西本がいやがってるんじゃ、どんな話でも、無理にするわけにゃいかねえだろうよ」
「どうなんだ西本、このにいさんと楽しいお話をしに行きてえのかい」
もうひとりが、九十九に聞こえよがしに言う。
「い、いやだ」
「おれたちと、これからもっと楽しい所へ行きてえんだよなあ」
「そうだ。行って酒を飲むんだ」
西本は、赤い顔をしてわめいた。
足がよろけた。
酔っているとはいえ、これが、あの剣道三段の実力を持つ西本かと、彼をよく知っている者が見れば、眼を疑いたくなる姿だった。
「にいさん、また日をあらためて来てくれよ。この通り西本はいやがってるし、おれたちは、今、楽しんでる最中なんでな。ここはひとつ出なおすっていうのが、民主主義じゃあないのかい」
古い
九十九は、その男の言葉を相手にしなかった。
「西本、ちょっとでいいんだ。話を聴かせてくれ――」
「いやだ。久鬼と貴様とは、仲間なんだろう」
「何故、久鬼の話だとわかったんだ。おまえ、やっぱり、久鬼について何か知っているのか」
西本は、押し黙った。
やはり、久鬼について何か知っているのである。
「西本――」
九十九が声をかけた時、存在を無視されて頭に来たのだろう。民主主義などという台詞を口にした男が、いきなり九十九に殴りかかってきた。自分たちが三人――西本を入れれば四人いることを計算してのことであろう。
いいタイミングのパンチであった。
街のケンカの口火を切るものとしては、ほぼ満点のできであったろう。しかし、それは、九十九の顔面には当たらなかった。
ひょい、と九十九が左の手のひらでそれを受けたのである。分厚い手のひらに当たり、男のパンチは、蚊を
それだけで、男は圧倒されていた。
続いてかかってきたのは、いかにもケンカ慣れしていそうな男だった。
体重も乗っていたし、スピード、バランスともに申し分なかった。いくらか体術の心得はあるらしい。
九十九は軽く曲げた
男は、左足で自分の体重を支えながら、不様な格好でバランスを崩すまいとけんけんをした。
「やめましょうよ、ねえ――」
九十九が、のんびりと言った。
「これ以上やると、おれも本気を出さなきゃいけなくなる。そうなったら、こっちも無事にはすまないだろうし、そっちだって、この後のお楽しみをふいにしなくちゃならないでしょう」
こっちも無事にはすまない――と九十九が言ったのは噓である。その気になれば、この三人くらいは、あっという間に叩きのめせるのだ。それを、こちらもケガをするからという言い方をしたのは、相手をたてるためである。身体のでかい相手とはいえ、高校生ふぜいにおどされてひっこんだとあっては、向こうの
かなわぬと見ても突っかかって来る場合だってある。
「わ、わかった。こっちもおめえにケガはさせたくねえし、これから行かなくちゃならねえところもあるしな」
なんとか威厳を保とうという口調だったが、しかし、九十九に片足を取られたままの格好では、まるで様になっていなかった。
「ありがとうございます」
九十九が言った。
「
さすがに、男がわめき出した。
九十九が足を放してやると、男は、さっと後方に跳び下がった。
三人の男が、身体を寄せ合うようにして、九十九を見ていた。この巨漢にもう一度闘いを挑むかどうか、九十九を値踏みしている眼だった。
結論はすぐに出た。
「ちっ」
と、リーダー格の足をとられた男が苦く舌を鳴らして背を向けた。
「飲みなおしだ」
ふたりがその後に続いた。
闘いらしい闘いをせずに、あっさり勝負がついてしまったのだ。
今晩のことは、この三人の心に、しばらく傷となって残るであろう。
残った西本が、
――なんてこった。
九十九は思った。
仮にも剣道部の主将である。普段であれば、今の三人などとは、素手でも対等以上に闘える男である。その西本が、完全に、気力をそがれてしまっているのである。よほどのことがあったのであろう。
九十九が歩み寄ると、
「ひっ」
と、西本がひきつった声をあげた。
「海岸へ行こう」
九十九は、西本の肩に手をかけて歩き出した。
「知らん。おれはなんにも知らん――」
宮小路から海までは、いくらも離れていない。五分とかからない距離である。
波の音が響いている。
バイパスの
九十九が肩から手を離すと、西本はそこにうずくまった。
「言わんぞ、おれは何も言わんぞ――」
子供のようにかたくなになっている。
「なあ、西本、いったい何があったんだ」
九十九が言った。
「うわあっ!」
わめきながら西本が立ちあがり、九十九にかかってきた。
頭を下げた九十九の上を、ひゅんと空気を裂いて棒のようなものが走った。
西本は、手に、一メートル余りの木の棒を握っていた。モップか何かの柄のようである。海岸に打ち寄せられていたのを、今、かがみ込んだ時に見つけたのであろう。
西本の眼は血走り、悪鬼のような形相になっていた。
「せいやっ!」
かけ声とともに、疾風のように西本が襲ってきた。人が変わったような、鬼気迫る攻撃だった。
下が砂地とはいえ、この時の西本の動きは、これまでの彼の生涯でも、最もみごとなものであったろう。
九十九は、休みなく動き続けながら、西本の攻撃をかわしていた。
九十九の顔に、笑みが浮かんでいた。
「そうだ、西本。それがおまえだ。かかってこい――」
十数分、棒をふるい続けると、酒の入っている西本の息があがってきた。
「よし」
九十九はつぶやいて、すっと西本との間に距離をとり、砂の上に仁王立ちになった。
「来い西本!」
九十九が叫んだ。
「りやっ!」
西本が力をふりしぼり、強烈な一撃を、正面から九十九の額に叩きつけてきた。
「ひゅっ!」
九十九の
鈍い音がして、棒が中程から折れ、先端がくるくると回りながら宙に飛んでいた。
九十九の右手首が、頭上で棒を払って折ったのである。
まだ手に残った棒を握り締めている西本を、九十九は両手で抱くようにして立っていた。
突然、西本が
西本は、九十九の腕の中で、激しく身を震わせながら大声で泣いていたのである。
九十九は、泣いている西本を抱えあげ、波打ち際へと歩いて行った。打ち寄せる波が、足を
波が、自分の腰を濡らす所まで来た時、九十九は西本を、寄せてきた波の中に放り込んだ。
全身がずぶ濡れになった西本の胸ぐらを両手でつかみ、九十九は西本を引き起こした。
大きな波が叩きつけ、九十九の全身も海水で濡れた。
「目が
九十九が叫んだ。
西本がうなずいた。
濡れた頭髪が、額にへばりつき、よれて目元まできていた。だが、その眼から、悪鬼のような表情が消えていた。
西本は、もう泣きやんでいた。
九十九は、両手で西本をゆすった。
「さあ、何があったんだ。言え!」
九十九が言うと、
「見たんだ――」
ぼそりと西本が言って、ふいに、恐ろしいものでも見たように、その眼におびえが走った。
「何を見た」
「久鬼さんが、肉を
「肉?」
「うっかり、白蓮庵に入って行ったら、久鬼さんが肉を喰わせてたんだ。おれはそれを見ちまったんだ――」
「どういうことだ」
「怖い顔をしてたよ、久鬼さんが、人間じゃないものに見えたんだ。見たか? とおれに言うから、おれは見なかった、なんにも見なかったと言ったんだ。そうしたら久鬼さんは笑って、おまえは頭がいい、頭がいいやつは長生きができるって、そう言った……。おれは、学校をかえてもらう。西城学園にはもういられない。できることなら、他の土地がいいと想ってるんだ。なあ、そうだろう、九十九――」
西本の身体から、すっかり力が抜けていた。
この男は、これから先一生、竹刀を持って人と闘うことなど、もうないだろうと思われた。さっきの九十九との闘いが、この男の最後の試合であろう。生きていく力、闘争心のようなものの源泉が、根こそぎ消失してしまったようであった。
しかし、九十九は、
「もっとはっきり言ってくれ、久鬼は、いったい何に肉を喰わせていたんだ」
西本は、遠い焦点をした眼で九十九を見、その眼をふせて、低い声で言った。
「久鬼は自分の右腕に肉を喰わせていたんだ」
4
九十九は、白蓮庵の前に立っていた。
目の前に入り口がある。
鬼道館と続いている入り口ではなく、外から直接出入りするための、正規の入り口である。
茶室風に造られているため、入り口は小さく、身体の大きな九十九には窮屈そうだった。
“久鬼は自分の右腕に肉を喰わせていたんだ”
昨夜の西本の言葉が、まだ耳にこびりついていた。
昼休みに、人を通じて連絡を入れておいたので、人を遠ざけ、久鬼が中で待っているはずだった。
「入るぞ」
いきなり、そう声をかけ、戸を開けた。
腰をかがめて上半身を中に入れると、そこに由魅が座っていた。他には誰もいなかった。
「こんにちは、九十九さん」
由魅がにこやかな声で言った。
「久鬼はどうした。まだ来ていないのか」
言いながら、九十九は、巨体を中に入れた。
「来たわ。でも、ちょっと前に出て行ったの――」
「出て行った?」
「そうよ」
「やつと、ふたりきりで会う約束だった。なんで君がここにいるんだ」
九十九が言うと、由魅はふふと声に出さずに笑った。
「なんだか、今、あなたと久鬼を会わせない方がいいみたいな気がしたものだから――」
「なに?」
「ごめんなさい。お話は、わたしがうかがっておくわ」
「君じゃ話にならん。久鬼とおれの問題だからな」
「それと、あとひとり、大鳳くんとでしょう?」
と、由魅が微笑する。
「どういうことだ」
「そんな気がしただけ――。でも、あなたの顔には図星だって書いてあるわ」
由魅にかかっては、九十九もいくらか分が悪いようである。
九十九は、つるりと大きな手で顔を
「いい機会だから言っておこう」
「――」
「大鳳のことだ」
九十九が大鳳の名前を出しても、由魅は、まるで表情を変えなかった。
「彼から手を引けって言うのかしら」
平然と言った。
由魅は、九十九の前で、自ら大鳳との仲を認める言葉を吐いたのだ。
「そうは言わん。あんたが本気ならな――。本気でなく、ただ大鳳を
「わたしを許さないとでも言うの?」
「いいか。久鬼とあんたとの仲がどんなものであろうと、そんなことはおれの知ったこっちゃない。しかし、久鬼と大鳳と両方ということになると、おだやかじゃないぜ」
「わたしはどちらも本気よ」
「たとえその言葉が本当であったとしてもだ、大鳳とあんたのことを知ったら、久鬼は大鳳を許さないだろう。久鬼だって馬鹿じゃない。もう、薄々とは感づいているはずだ――」
「あら――」
と、由魅は、眼を大きく開いて声をあげた。
「おあいにくさまね、久鬼は、もう、わたしと大鳳との仲を知っているわ」
「なんだって?」
「わたしが言ったのよ。もう、大鳳と寝たんだって――」
「なに!」
九十九は由魅に飛びつくようにして胸ぐらをつかんだ。
とたんに、鬼道館との間のふすまが開き、黒い塊が九十九に飛びかかってきた。
ぶん、と九十九の右手がうなり、その塊がふっとんだ。ダン、と音をたてて、白蓮庵の壁にぶつかった。
菊地だった。
むっくりと菊地が起きあがった。
鼻から血が流れていた。
その手に、ナイフが光っていた。
「手を離せ」
低い声で菊地が
白い部分の多い眼の中で、小さな
「その手、離さなければ、おれ、おまえを刺す」
本気の声であった。
それ以上でも以下でもない、掛け値なしの響きがある。おどしや冗談ではなかった。
「とんだところにグルーピーがいたもんだな――」
九十九が、苦笑しながら手を離した。
由魅が男のように笑った。
「こんなところにぐずぐずしてていいのかしら――」
由魅が言った。
「大鳳とのことを久鬼に言ったのは、ついさっきよ。それを聴いて、久鬼は外に飛び出して行ったんだからね」
九十九の背に、おそろしい恐怖が走り抜けた。
「
大鳳が危ない、そう思った。
「大鳳!」
低く叫ぶなり、九十九は白蓮庵を飛び出していた。
5
久鬼は、小田原市内を、足早に、ほとんど無目的に歩いていた。
――まったくおれらしくもない。
そう想ってはいるが、体内から押し上げてくる
こんど、その内圧のエネルギーに身をまかせたら、その時こそ自分の最期だということも感じていた。
由魅から大鳳とのことを聴かされたとたん、その内圧をこれまで抑制してきたタガが、どこかにふっとんでしまったのである。久鬼であったからこそ、体内から頭を持ちあげてくる黒いエネルギーを、これまで抑え続けていることができたのである。
それは、精神を絶え間なくヤスリにかけられるような日々だった。
しかし、今、ようやくその力が解き放たれようとしているのだ。
大鳳が、円空山に向かったのはわかっていた。
しかし、単身円空山に乗り込んで、九十九や雲斎の目の前で、大鳳とやり合うわけにはいかなかった。
大鳳のアパートで彼が帰ってくるのを待ちぶせるのが賢明な方法だった。しかし、それにはまだ時間がある。それまで、この狂おしくつきあげてくるエネルギーを、抑えておけるかどうか。
久鬼は、時間を持てあまし、闇雲に歩を進めているのだった。
久鬼の肩が、どん、と前から来た男にぶつかった。
男は、
ぶつかったのは、久鬼が沼川に気づかなかったためと、沼川がわざと久鬼をよけなかったためである。
「待ちなよ」
沼川が、充分ドスの利いた声で言った。
まちがいなく、ヤクザのプロの発声だ。
「人にぶつかっといて
高級なスーツをあざやかに着こなしていた。沼川は、まだ、三〇歳をいくらも出ていないだろう。
久鬼はふり向き、沼川を
美しい、燃えるような顔であった。
「すまん」
それだけ言うと、また背を向けて歩き出した。
まだ少年の久鬼が、すまんと、大人のような言葉を残し、無視するように背を向けたことが沼川の頭に血を昇らせた。
この時、久鬼に、いくらかでも怯えの表情があれば、それですんでいたかもしれなかった。久鬼のしたことは、あからさまに馬鹿にしたのと同じであった。いや、それよりもっと悪いかもしれない。
ヤクザ社会の中において、まず最も大事にされるのが
無視、というのは、彼等に対する最大の侮辱なのであった。
沼川に従っていた三人の若い男たちが、久鬼の後を追った。
「小僧!」
「待ちやがれ!」
久鬼は立ち止まった。
「何ですか」
久鬼の顔に、
繁華街には遠いが、人通りはある。
歩いてきた勤め帰りのサラリーマンや、主婦たちが、道路の反対側にまわって、通り過ぎてゆく。視線を久鬼たちに向けはするが、声をかけようとする者は誰もいない。
久鬼は、
そのむき出しの腕を、男たちのひとりがつかんだ。
「こっちへ来て、もう一度沼川さんに謝るんだ」
荒々しく久鬼の腕を引いたとたん、男は、絶叫をあげてアスファルトの上に転がった。
「ぐえっ!」
どん、と肩から落ち、路面に身体をこすりつけて転げまわる。
「
久鬼の腕をつかんだ右手から、赤い鮮血が流れ出していた。血が、点々と路面に赤黒い染みをつける。
「どうした」
「おい」
他のふたりが、男を
ふたりにも、何が起こったのか、さっぱりわかっていないのだ。
男の右手から、指が数本消えていた。
何かに
久鬼の顔が、白く見えるほど青ざめていた。
男のひとりが、ギラリと
「てめえ、何をしやがった」
「野郎!」
血相を変えたふたりの男が叫んだとたん、
一瞬、何が自分の身に生じたのか、ふたりの男にはわからなかった。
ひとりの男は
もうひとりの男は、
ララララ~~~~ラルルル……
久鬼の
久鬼は、放たれた矢のように、沼川に向かって走り出していた。
久鬼の身体が跳ねた。
久鬼は、少しもそのスピードを変えずに沼川の頭上を跳び越え、走り抜けた。
沼川は、前につんのめるように、顔面から路面に倒れ込んだ。その身体が、不気味に
身体中の細胞という細胞が、ふくれあがり、沸騰するような異常な興奮に、久鬼は包まれていた。
熱い炎に身を
その久鬼の脳裏に、いつか大鳳と一緒にいたことのある深雪の顔が浮かんだ。
走っている久鬼の唇がV字形に
久鬼は、走りながら、悪魔の笑みを浮かべていた。
6
「ここにいたのか、大鳳」
円空山にやってくるなり、そこに大鳳の姿を見つけた九十九は、ほっとした声をあげた。
大鳳は、
「よかった」
九十九は言いながらあがってきた。
「どうしたんですか。九十九さん」
「久鬼に会わなかったか」
九十九が
「何かあったんですか」
「どうも、久鬼がおまえをねらっているらしい」
「久鬼さんが?」
「それがな――」
九十九は口ごもった。
言いにくそうに、大鳳と雲斎に眼をやった。
「言って下さい」
「言いづらいことなんだが……」
九十九は意を決したように、口元を手でこすった。
「由魅のことさ」
「由魅さんの?」
「久鬼はもう知っているぞ。おまえと由魅のことをな。由魅自身が、今日、久鬼にしゃべったとおれに教えてくれた」
「――」
「久鬼は、おまえの後を追って白蓮庵を出て行ったきりだ」
大鳳の脳裏に、ひと月余り前、久鬼の言った言葉がよぎった。
“由魅には近づかない方がいい”
“あれは危険な女です”
“そのうちに、あなたとぼくと、生命をかけて闘う時が来るかもしれませんね”
「どうするつもりだ」
九十九が言った。
「どうって――」
「深雪ちゃんのことも含めてのことさ」
「どういう意味ですか」
「深雪ちゃんが可哀そうだと言ってるんだ。彼女はおまえに
「――」
大鳳はうつむいた。
「そろそろ由魅とのことも隠せなくなってきてるんじゃないのか」
「ぼく個人の問題です。九十九さんにどうこうしろと言われることじゃありません。ほっといて下さい」
「ほっといて下さい、か。ずいぶん一人前のことを言うじゃないか」
九十九の語調が、微かにささくれ立っている。この男にしては、珍しく言葉に
「久鬼はおそろしい男だぞ。その久鬼を、一人前のおまえがどうあつかうか見たいものだな」
「――」
「久鬼に土下座でもして謝るのか」
「そんなことはできません」
「できない? 昔だったら、土下座してでも
大鳳の顔色がすっと変わった。
「九十九さんこそ、本当は深雪を好きなんじゃないですか。だから、おれにそんな言い方をするんだ」
「――」
九十九は、一瞬、出しかけた言葉を
「当たりましたね」
大鳳がニヤリと笑った。
久鬼の笑顔にそっくりだった。
「いいですよ。九十九さんが深雪を好きだというんなら、深雪は九十九さんにあげますよ」
「馬鹿野郎!」
九十九が叫んだ。
思わず、身のすくみあがる、怒声だった。
「深雪ちゃんは品物じゃない!」
あの九十九が、本気になって怒っていた。
「まあ、まあ――」
その時、のんびりした雲斎の声が割って入った。
雲斎は、これまで、酒を飲みながら、にこにこしてふたりのやりとりを聴いていたのである。その雲斎がようやく口を開いたのだ。
「珍しいのう、九十九。おぬしがそんなにムキになっておるのを、初めて見たわ。これは、大鳳の言うように、おぬし、本気であの娘に
「先生……」
「まあ、よいよい」
雲斎は、とん、と酒の入った
「どうかな、大鳳、少しは自信がついたかな?」
「は――」
「自分でもいくらか強くなってきたと想っておるのであろうが。機会さえあれば、その技を使ってみたい――そうであろう」
「――」
「どうかな、今、この九十九とやって勝てると思うか」
雲斎の眼が光った。
「いえ。とてもまだ九十九さんには――」
「九十九に勝てねば、久鬼にも勝てぬぞ。いずれ久鬼とはやり合うことになりそうなのではないかな。どうだ――」
「――」
「その眼が、九十九などに負けるとは思ってないと言うておるぞ。勝てぬまでも、少なくともやってみるまではわからぬとな。どうだ。やってみたくてうずうずしておるのであろうが――」
図星をさされて、大鳳は身を硬くした。
確かに九十九は強い。町道場のレベルより数段上の実力があろう。いや、強いという以上の、底の知れぬものがあった。
――しかし。
と、大鳳は思う。
九十九とやって勝てるという自信はない。
だが、負けはしない、という不敵な自信はあった。
坂口との一件以来、大鳳の内部にちろちろと燃える黒い炎が、その自信の根源である。やれそうな気がするのである。
久鬼とのこともそうだった。
由魅とのことで、久鬼が自分をねらっているらしいことを、さっき九十九から聴かされた時、大鳳の心に浮かんだのは、恐怖ではなかった。
むろん、怖い、という気持ちはある。しかし、最初に頭に浮かんだのは、まず、困った、という意識である。怖いから困っているのではない。困った、がまず先にあり、その後に怖い、という気持ちがある。その怖い、というのも、ただ恐ろしいという気持ちではない。久鬼の実力をきちんと評価した上での、手強い相手だという認識である。
むしろ、大鳳は、そのことを楽しんでいるようでさえあった。
「やってみるかね、九十九」
雲斎が言った。
「大鳳さえ、その気なら――」
九十九は、大鳳に眼をやりながら答えた。
「九十九さんが、やるというなら、おれはかまいません」
ふてぶてしい眼で、大鳳は九十九の視線を受けた。
「ようし、決まった決まった」
雲斎だけがひとりではしゃいでいる。
「おぬしたちの腕のほどを、わしも見ておきたいと思っていたのさ。今日は、ちょうどいい機会だ」
「ルールはどうするんですか?」
九十九が言った。
「はは、ルールなんぞは、それぞれおぬしたちの胸のうちにあろうが、そのルール通りにやればよいのさ。きんたまを蹴とばしたければ、おもいきり
九十九は、無言のままシャツを捨てた。
たくましい上半身が現れた。
惚れぼれするような
大鳳も、黙ってトレーナーをぬぎ落とした。身体こそ九十九より小さいが、無駄肉のそぎ落とされた肉体は、決して見劣りがしない。この二カ月以上の間に、肉の厚みが増している。四月に、同じように九十九と向きあった時に比べ、体重が四キロは増えている。その四キロは、ほとんど筋肉の重さである。
九十九は、ゆるく足を前後に開き、軽く腰を落として身構えた。右足が前、左足が後方である。
大鳳は、九十九と同じ足の置き方で立った。姿勢はほぼ九十九と同じだが、拳の位置が違っていた。九十九が拳を前後に開いているのに対し、大鳳は、拳を天地――つまり上下に開いていた。
九十九は、まるで岩のようであった。
どの方向から力を加えても、小揺ぎもしそうになかった。
そこに、そうやって立っているだけで、肉の風圧のようなものが大鳳にとどいてくる。肉の細胞そのものが、エネルギーを外にあふれさせているのだ。
意識的にコントロールしなくても、自然に体内から
おそらく、どのようなフェイントをかけたところで、たやすく見破られてしまうだろう。
大鳳は、天に上げた右の拳を開き、リズムをとるように動かし始めた。同時に、軽快なフットワークを使って、左に回り出した。
大鳳に合わせて、九十九が動いた。
太い両腕を、しぼるように小さく揺すりながら、大鳳の右手の動きに合わせている。
――乗ってきたな。
大鳳は心の中でニヤリと笑った。
今度は、大鳳の方から、意識的に九十九のリズムに合わせ始めた。ふたりの
――おれは負けない。
大鳳は、九十九にひと泡ふかせてやるつもりだった。
胸がときめき、心臓が高鳴っている。ようやく、自分の技を試す機会が訪れたのだ。しかも相手は九十九である。そこらのケンカなら、試すほどのものではないのだ。しかし、九十九なら、相手として申し分なかった。
――遠慮はしない。
九十九と
わざとリズムを遅くしたのである。
九十九のリズムが大鳳のリズムを追い越したその瞬間、ふくらんだ九十九の腕の間に、手加減抜きの足蹴りをすべり込ませた。
入った!
そう思った足蹴りが、九十九の深い懐に何の
待っていたのは九十九の方だったのだ。
大鳳の足が、九十九の肘で跳ねあげられていた。九十九がすかさず入り込んできた。跳ねあげられた大鳳の足が床にもどらないうちに、九十九の足がぶんと
大鳳の身体が宙に浮いた。
小型のトラックに跳ね飛ばされたような感じだった。しかし、ダメージそのものは少なかった。
ふわっという感じで、宙を飛ばされた大鳳の身体が、空中で後方に一転して床に立った。
休む
凄いパワーの乱打である。
さすがに正拳で顔面はねらってこなかった。
九十九の拳がまともにカウンターで入れば、骨などあっさりひしゃげてしまいそうである。
完全に圧倒されていた。
大鳳の内部にふつふつとこみあげてくるものがあった。坂口の時に生じたあの感覚である。
大鳳の心の中で、闘争本能がぎりぎりと音をたててきしめばきしむほど、その感覚は強くなってくる。
そうだ。こいつだ。おれは、こいつを待っていたんだ。坂口の時は、恐怖心さえ覚えたその感覚をかきたてるようにして、大鳳は心の中で叫んだ。
それは、すでに、坂口の時に姿を現し、今は、大鳳の細胞のひとつずつにまで染みわたっていた。今度は、それに火を
あの時の坂口の顔と深雪の顔が浮かんだ。
その深雪の顔と、目の前の九十九の顔が重なった。
“九十九さんこそ、本当は深雪を好きなんじゃないですか”
――九十九め!
一瞬、九十九への憎しみが吹きぬけた。
そのとたん、大鳳の肉体の中で、何かがごりっと音をたてて実体化したようだった。細胞や、血管に、不気味な異物感が生じていた。
「くうっ!」
大鳳はおもいきり跳躍していた。
軽々と、九十九の頭上を越えた。
反対側へ着地し、ふり返る九十九に向かって、大鳳は怪鳥のように跳んでいた。
あの
凄い形相をしていたに違いない。
九十九の顔色が変わるのがわかった。
九十九の動作がはっきり眼に焼きついていた。スローモーションのフィルムを見るようである。
九十九の右腕が喉をかばい、左手が刃物のように大鳳の横腹に伸びてきた。
――寸指破!
大鳳がそう想った時、九十九の左手が横腹を貫いていた。
大鳳の視界が、ふいにまっ白な
視界が、ゆっくりと暗黒に変わった。
7
大鳳が気づくと、ふたつの顔が、自分の顔を心配そうに
九十九と雲斎だった。
「気がついたか――」
と、雲斎が言った。
「まったく、このアホは、手加減というものを知らんからな」
「すまん、大鳳。おれもつい本気になっちまったんだ」
九十九は、すっかりいつもの九十九にもどっているようだった。
寸指破を横腹に受けた時の光景が
頭をかいている九十九の右腕に、歯形が残り、薄く血が滲んでいた。
「それ、ぼくがやったんですか――」
「そうだ。おまえが跳んだ瞬間、おそろしい殺気がぶつかって来たのさ。とっさに喉をかばって、つい、寸指破を手加減ぬきで出しちまった――」
大鳳は、九十九の腕についた歯形を見、それを自分がやったのかと、ぞくりと身震いした。
――九十九に負けた。
そう思った。
だが、くやしさはなかった。
うまく言葉にはならなかったが、九十九に負けたことにより、自分がまだ人間であることを確認できたような安心感であった。
九十九がすまなそうに笑っていた。
いつもの九十九だった。
この九十九を、一瞬にしろ、憎しみの眼で見たことが、信じられなかった。
大鳳は起きあがり、トレーナーを素肌に着た。
「九十九さん、さっきはすいません。おれ、ひどいこと言っちゃって――」
「謝るのはおれの方さ。先にそっちを刺激したのは、おれなんだからな。かんべんしろ……」
大鳳は、薄く笑って、眼をふせた。
「おれ、帰ります。カバンは置いといて下さい。今日は、走って帰りたいんです……」
スニーカーを
気持ちの良い風が、大鳳の顔に吹き寄せた。
「久鬼に気をつけろよ」
九十九が言った。
大鳳がうなずいた。
「じゃ、おれ、行きます」
戸を開けたまま大鳳は走り出した。
大鳳の姿はすぐに見えなくなった。
雲斎と九十九は顔を見合わせ、複雑な表情をした。
「久鬼と大鳳か――」
と、九十九がつぶやいた。
「やっかいなことになったな」
雲斎は軽く頭をふって、
「あの娘も、可哀そうにな……」
その言葉を耳にした九十九の顔に、陰が走った。
「どうした?」
「今先生が言った深雪ちゃんのことです」
「――」
「いいですか、久鬼は大鳳を追って、学園を出たんですよ。大鳳がここへやってくることは久鬼も知っています。しかし、まさか、久鬼もここまでは乗り込んではこられないでしょう――」
「待ちぶせか――」
「あの久鬼が、いつ帰るかわからない大鳳を、こんな時間まで待ちぶせたりしますかね――」
「と言うと――」
「久鬼は、言わば、自分の女を大鳳に寝とられたわけでしょう。その
「深雪ちゃんか!」
雲斎が叫んだ。
「ぬかったな。このボケが、何でもっと早く気がつかなかったんだ」
「先生が、大鳳とやらせたりするからですよ」
「あの娘の所へ電話をしてみろ。番号はわかるか」
「暗記してますよ」
九十九が受話器に手をかけながら言った。
九十九が電話をしている間に、何気なく大鳳のカバンに眼をやっていた雲斎が、ふいに
カバンの口から覗いている包みが、雲斎の注意をひいたのである。雲斎は、カバンを開け、その包みを取り出した。
手に持ってみると、やはり、中には思った通りのものが入っているらしい。
その時、電話を終えた九十九が、青ざめた顔で雲斎の所へやってきた。
「先生、深雪ちゃんは、大鳳の友人と名のる男から呼び出され、まだ帰ってきてないそうです」
「いつのことだ」
「三〇分くらい前だそうです」
「やはり久鬼か」
「おそらく――」
「で、行き先は――」
「それが、わからないのです」
「ちっ」
雲斎が
その時、ようやく九十九は、雲斎が手にしているものに気がついた。
「何ですかそれは」
「大鳳のカバンから出てきたのさ」
雲斎は、重さを量るように、その包みを乗せた手を上下させた。
包みには、小田原市内の肉屋の屋号が印刷してあった。
「昨夜の話では――」
雲斎は九十九を鋭い眼で見つめた。
「西本とかいう男、久鬼が腕に肉を
言いながら、雲斎はその包みを開いていった。
中から出てきたのは、まだ新しい生の肉であった。
8
大鳳は、円空山のある
このコースだと、ミカン畑を抜け、雑木林の間をぬって、西城学園の裏手に出ることができる。いったん西城学園に出、そこから小田原駅に下るつもりだった。
小田原駅西口から、足柄のアパートまでは、大鳳の足ならばすぐである。
夜である。
月が出ている。
その月明かりをたよりに、大鳳は山道を走っていた。山道といっても、軽四輪がやっと通れるほどの道で、両側には車の
時おり、木の間がくれに、小田原市街の
きれいな夜景であった。
やがて、西城学園の裏手の雑木林にさしかかった頃、大鳳の鼻に、奇妙な匂いが飛び込んできた。
新緑の匂いに混じり、それは、
――血の匂いだ。
大鳳は、ふいにその匂いの正体に気がついた。
こぼれたばかりの血、まだ、脈うちながら湯気をあげている血――。
頭がふっとしびれるような、不思議な感覚が大鳳を襲った。
おぞましさとなつかしさとが、均等に含まれていた。
その匂いに
匂いが強くなる。
下生えの中で、大鳳の足が何かに当たった。
大鳳は立ち止まった。
――何だろう。
顔を近づけたとたん、むうっとする血の匂いが鼻を打った。
「これは?」
大鳳は、それを見つけて、声をあげていた。
それは、血まみれたサンシロウの首だった。
何か、強い力でねじ切られたような、無惨な姿だった。
「サンシロウ……」
つぶやいた時、大鳳は、さらに奥の草の上に、ひとりの女が倒れているのに気がついた。その女の顔を、木の間からもれる月明かりで確認した時、激しいショックが大鳳を包んだ。
その女は、織部深雪だったのである。
「深雪ちゃん」
深雪を抱き起こし、心臓に耳を当てた。
まだ生きていた。外傷もないようである。
大鳳はほっとした。
その時――
――誰かいる。
大鳳の鋭い感覚が、闇の奥にいるものの気配を捕らえていた。
眼を凝らす。
黒い影のようなものが、草の上にかがみ込んで何かを食べていた。
大鳳の胃がきゅっと縮みあがった。
その影が、何を食べているのか、大鳳にわかったからだった。それは、まだ温かいサンシロウの死体の腹の中に顔を突っ込んで、思う存分、その内臓を
誘われるように、大鳳は数歩前に出た。
それが顔をあげた。
久鬼であった。
あの美しい久鬼の顔が血にまみれていた。
髪が血で
大鳳を見たとたん、闇の中で、久鬼の唇が耳元まで左右にきゅうっと
「ふ、ふ、ふ、ふ、ふ、……」
久鬼は、笑っていた。
「見ました、ね、大鳳くん。ぼくのこの姿を見ましたね――」
幽鬼のように立ちあがった。
久鬼は、自分のシャツに両手をあて、それをおもいきり引き裂いた。
上半身が露出した。
「いいものを見せてあげましょう」
久鬼は、サンシロウの腹の中に手を突っ込んで、赤黒い血ごりのようなものを取り出した。肝臓の一部らしい。
久鬼が、それを自分の胸のあたりに押しつけると、そこの肉が、ざわっと
文字通り、それは口であった。
そこに出現したのは、
ぞぶり、ぞぶりと、その口がサンシロウの肝臓を食べてゆく。
それは、うまそうに久鬼の差し出した肝臓を喰い終えると、久鬼の内部に潜るように消えた。そのあとには、赤いひきつれが、アザのように残っていた。
「これがキマイラですよ。由魅が教えてくれたんです。ぼくは、ぼくの身体の中に、
久鬼はまた笑った。
「そしてね。この
「深雪をどうしたんだ」
「呼び出したんですよ。あなたの名前を使ってね。あなたが、由魅にしたのと同じことをしてやろうと思ってね――」
「なに!」
「いいところで、邪魔が入りました。この犬ですよ。おかげで何もできませんでしたが、かわりにあなたに会えるとはね――」
――ひいっ。
と、久鬼の眼がくるりと裏がえり白眼をむいた。ぞろり、と、久鬼の全身に黒い獣毛が生えた。見る間に、ぞわぞわとその色が濃くなってゆく。
「あなたのことを考えるとね、
しわがれ声になっている。
口の構造そのものまで、変わりつつあるらしい。
「大鳳くん。きみもじきにこうなるのですよ。なに、初めは、つらいでしょうけどね。ぼくもつらかった。けれど、こうなることがこんなに気持ちのいいものだとわかっていたら、もっと早くなっていたでしょうにねえ」
久鬼の手足や背骨が、何か、
「ぼくがぼくでなくなる前にあなたに会えたのを、神に感謝しますよ。こうして、
最後の方の声は、舌の間からもれる、しゅうしゅうという息の音に混じって、ほとんど聴きとれぬようになっていた。
驚くほど赤い舌が、久鬼の口から長くたれ下がっていた。
「ぎいっ!」
久鬼の口から、人間のものではない声がもれ、黒い
再び地に立った久鬼の全身から、おそろしい風圧の気がふくれあがっていた。久鬼の身体が、闇の中で、青白い
人間とは異なる臭気が、熱いヤスリのように大鳳の頰をなぶった。溶鉱炉の口を開け、熱気に顔面をさらしているようだった。
――かなわない。
大鳳はそう想った。
殺される。
この久鬼と対等にやり合えるとしたら、九十九しかいないのではないか――。
だが、不思議と
自分の技がどこまで通用するか、死にもの狂いでやってみるつもりだった。
大鳳は、夜風を感じていた。
耳に、葉ずれの音が響いていた。
死闘の最中に、ふいにそんな感覚がもどってきたことが不思議だった。
草の上を
悪夢のような闘いが始まった。
それでも、十数分、大鳳が、決定的なダメージをこうむらずに久鬼とやり合えたのは、ほとんど奇跡であった。身体のあちこちから血が吹き出していたが、大鳳はまだ立っていた。
雲斎が稚技と呼んでいた技でさえ、こんなに奥が深いものかと思った。短い期間ではあったが、大鳳が習い覚えた円空拳の技が、ここまで大鳳の生命を永らえさせたのだ。
もし、生きて、またあそこに帰れるのなら、死にもの狂いで円空拳を学んでみようと思った。だが、生き残れたとして、自分が久鬼のようになるまでに、いったいどれだけの時間が残されているのだろう。
その時間は、あまり長くないだろうと思われた。
ふたりの身体が離れ、数メートルの距離で向かいあった。
すでに、大鳳は立っているのがやっとだった。
久鬼が、最後の攻撃をしかけてくるのはわかっていた。
大鳳は、深く息を吸い込んでそれを待った。
久鬼が大鳳を見ている。
唇も眼も、異様に吊りあがっている。
その唇の間から、長く伸びたふたつの犬歯が
久鬼の身体の内圧が、見ている間にも高まってゆくのがわかる。その内圧が、久鬼の肉体に満ち、それが外に向かって
ひ~~~~~~~~~~
久鬼の口唇から、その時が近づいたのを告げるような、細い笛の音に似た声が滑り出てきた。
ひ~~~~~~~~~~
その声が伸びあがり、さらに高くなってゆく。
自分に残された技は、もうひとつだけだ。
あれを出すしかない。
あ~~~~~~~~~~
来る。
大鳳が、そう思った時、久鬼の身体が動いていた。
「しゃっ!」
「はうっ!」
大鳳の鋭い呼気が、闇を貫いた。
次の瞬間、大鳳はこめかみに強い打撃をうけていた。
だが、その前に自分の放った、見よう見まねの寸指破が、久鬼の身体のどこかにあたった
大鳳は仰向けに草の上に倒れた。
気持ち良かった。
冷たい草が頰に触れている。
いつかも、こんな気分を味わったように思った。
それが、ここからさほど遠くない所で、坂口とやり合った時のものであることに、ぼんやりと気がついた。
木立ちの間に、月が見えた。
いい月だった。
いい音だ。
誰かが自分の名を呼んでいるような気がした。
なつかしい、聴き覚えのある声だった。
九十九の声である。
深雪のことを想い出していた。
深雪に謝らねば、そう思った。
すまない。
わるかった。
言いわけのように、深雪に謝っている自分の声を大鳳は聴いた。
それがすんだ時、大鳳は、やっと自分は休めるのだと思った。
眼を閉じ、大鳳は微笑を浮かべて、全身の力を抜いた。
9
九十九と雲斎がそこに駆けつけた時、大鳳と久鬼とが正面からぶつかり合っていた。
倒れたのは大鳳であった。
黒い影が大鳳の上にかがみ込もうとした時、九十九が大鳳の名を呼んだのである。
黒い影は、跳ねあがり、頭上の梢に飛びついて、たちまち闇に姿を消していた。
九十九と雲斎は、そこに、ぼろぼろになった大鳳と、意識を失っている深雪を発見した。
「いまのを見ましたか」
九十九が言った。
「うむ」
雲斎が答えた。
「あれが久鬼の変わり果てた姿よ。あの男を救うことはできなかったが、この大鳳だけは、なんとか救ってやりたい」
九十九が大鳳を抱き起こすと、
「深雪……」
と、小さく
ぼそぼそと言う声は、よく聴きとれなかったが、深雪に謝っているらしいことがわかった。
「……おれは、普通の人間じゃない。おれなど好きになってはいけない。九十九さんはいい人だぞ、好きになるならあの人を――」
大鳳はそう言って眼を閉じた。
九十九の眼に涙があふれた。
「こいつ、大鳳のやつ、わざと深雪ちゃんに冷たくしていたんですよ」
微笑を浮かべて気を失っている大鳳は、自分が最後に放った寸指破が、久鬼の打撃を弱め、己の生命を救ったのだということに、まだ気がついていない。
闇の中に、風が吹いていた。
その風に乗って、あの、獣に
るう~~~~るるるるる……
るう~~~~いいいいい……
それは、人間に
電子書籍フェア情報
夢枕獏『キマイラ』新刊配信記念 シリーズ一気読みフェア
期間:2025年7月4日(金)~2025年7月17日(木)
<実施電子書店>
BOOK☆WALKER
作品紹介
書 名:幻獣少年キマイラ
著 者:夢枕 獏
イラスト:三輪 士郎
発売日:2024年09月03日
あの伝説の大河シリーズ、ついに登場!
時折獣に喰われる悪夢を見る以外はごく平凡な日々を送っていた美貌の高校生・大鳳吼。だが学園を支配する上級生・久鬼麗一と出会った時、その宿命が幕を開けた──。著者渾身の“生涯小説”、ついに登場!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/321304000083/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら