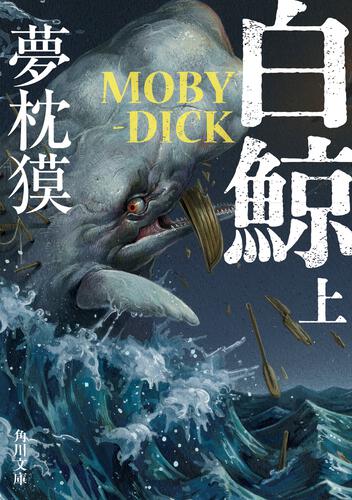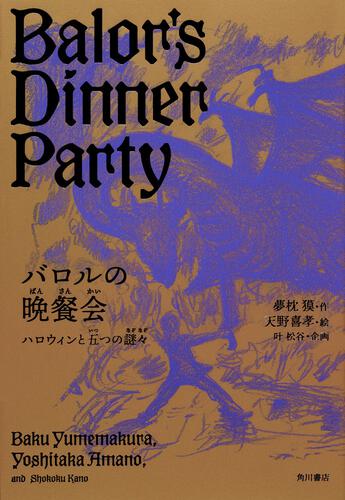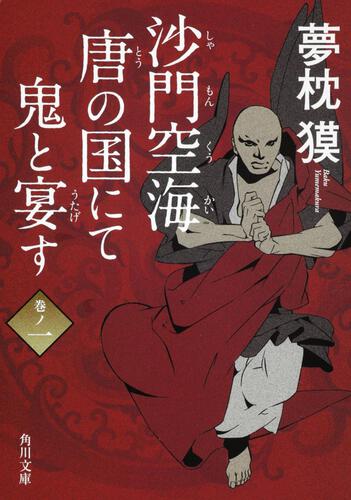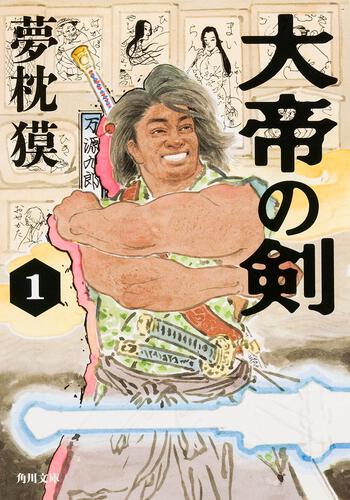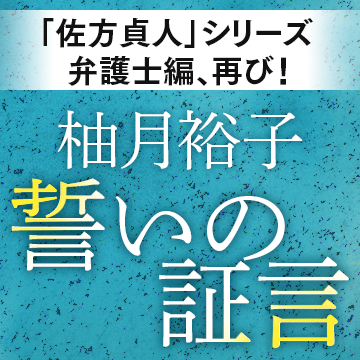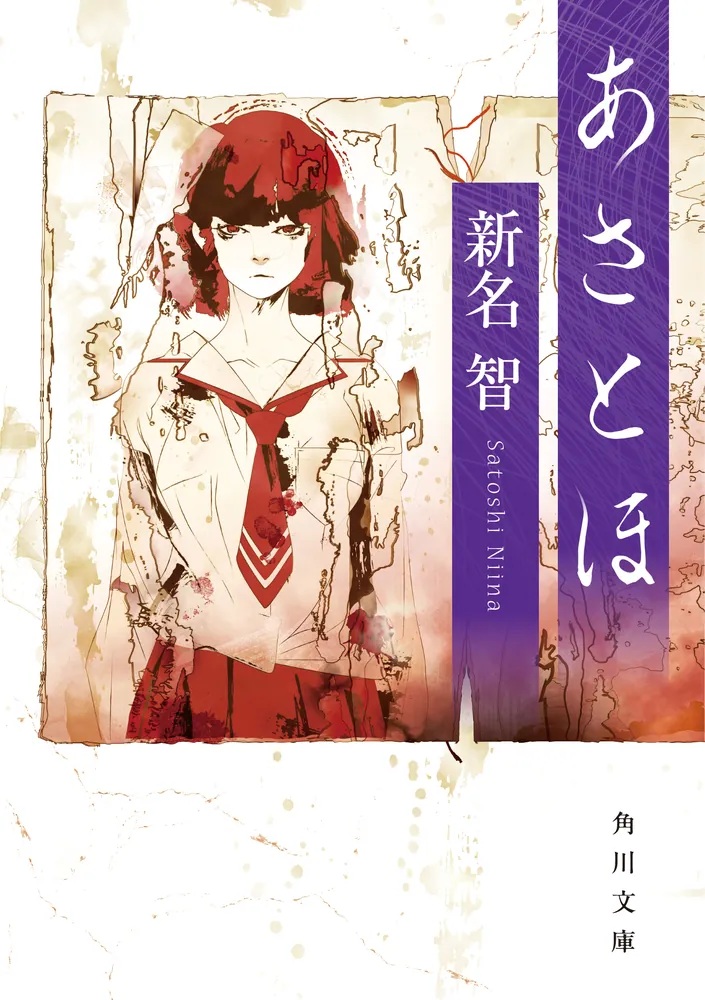四章 甘い罠
1
――
学生服姿の久鬼が、床の間に向かって正座している。
床の間には、
鬼道館へつながるふすまの向こうから女の声がした。
久鬼の答えを待たずに、ふすまが開き、由魅が入ってきた。
手に、小さな包みを持っている。
「肉を買ってきたわ」
久鬼の横に座り、畳の上に包みを置いた。
久鬼は黙って床の間を見ていた。
「鮮やかなものだわ」
由魅は、水盤に眼をやって言った。
「少しの風が吹くのさえ、怖いくらい――」
「確かに――」
と、久鬼がうなずいた。
「
背がぴんと伸びている姿は、とても一〇代の高校生とは思えなかった。
「大鳳という男――」
久鬼は、
この男にしては珍しいことである。
「彼は、ぼくと同じ匂いを持った人間です。しかし、彼には欠点が多すぎる。自分を守ろうとすることだけで、いっぱいです。しかし、おもしろいものがある。泥とダイヤモンドとを、かき回して詰め込んだ袋のようなものです。花を活ける、というのは、その泥もダイヤも、みんなひっくるめて水盤の上にさらけ出してしまうことです。だから、ぼくは、彼の活けた花を見てみたいのです――」
「彼の、泥の方に興味があるんでしょう」
「そう。ダイヤの原石は、皆、泥の中から見つけ出されるのですからね」
「あなたは磨かれたダイヤモンド、大鳳はまだ泥にまみれた原石――」
「あからさますぎる
「気持ちが悪い?」
「気持ちが悪い。しかし、これは言えます――」
「何かしら」
「ダイヤモンドに意思があるなら、どのダイヤモンドも皆、自分より大きくより美しい仲間のダイヤモンドを、快くは思わないでしょうということです」
「で、彼はどうなの」
「まだわかりません。昨日、坂口とやった時に、ぼくは大鳳にひとつのメッセージを送りました」
「――」
「大鳳は、そのメッセージに気がつきました」
「で――」
「それをぼくからの挑戦状と受け取るか、ただの
「挑戦状?」
「むろんただの戯れです。今のところはね。問題は、彼がどう受け取るかということですよ」
久鬼の端整な顔に、
「その大鳳のことだけど――」
「聞きました。昨日、坂口とやったそうですね」
「やられたのは坂口で、それも相当派手にやられたみたい」
由魅の言葉に、久鬼の顔に笑いが浮かんだ。
「当然でしょう。原石とはいえ、ダイヤはダイヤです。ちょっかいを出せば、傷つくのはガラスの方ですよ」
「いくら原石でも、あそこまでやるとは思わなかったわ」
「原石を拾って磨いている者がいるのです」
「九十九さん?」
「あの男もそうです。そしてもうひとり、真壁雲斎という男――」
「真壁雲斎――? あなたが九十九さんと円空拳を習っていたという
「得体の知れない人物です。ぼくを磨いたのも、彼ですよ」
「あなたはどうして、その雲斎とかいう爺さんの所を離れたの?」
「ダイヤはダイヤ自身のものですからね。仕上げのカットは、自分の手でやるのがいい」
「噓。わたしにはわかるわ。あなたは、あそこに未練を持っているんじゃなくて――」
「かなわないな」
久鬼の顔に、思いがけなく、苦い笑いが浮かんだ。
「本当の原因はこれね」
由魅は、畳の上の包みに眼を落とした。
とたんに、久鬼の顔から笑いが消えた。
すうっと表情が消え、能面に似た顔つきになった。
暗い、氷のような
思わずぞくりとするような眼だ。
「わるかったわ」
震えを押し殺した声で由魅が言った。
久鬼は、無言のまま手を差し出し、制服の上から由魅の乳房をつかんだ。相当に力がこもっている。
「痛いわ」
由魅が、小さい声で
久鬼は、そのまま由魅をひき寄せ、唇を重ねた。乳房を握った手にさらに力をこめる。
「おまえはおれのものだ」
唇を離し、低く言う。
ぼくがおれになっている。
「大鳳に興味があるらしいな」
由魅の眼を上から
「そうなんだろう」
「あるわ」
「大鳳とこうしてみたいか」
「――」
「答えるんだ」
「ええ、してみたいわ」
「寝てみたいんだろう」
「その通りよ。寝たらどうなの?」
「殺す」
久鬼が、感情を殺した声で言う。
それだけに、不気味な迫力があった。
「わたしを殺すの?」
「おまえは殺さない。殺すのは大鳳だ」
久鬼は、手を離し、由魅をもとの姿勢にもどした。
由魅が、ほっと息をついた時、ふすまの向こうから、野太い声がした。
「いるか、久鬼」
九十九の声だった。
「入るぞ」
ふすまが開いて、のっそりと九十九が入ってきた。
後足で立ちあがった
九十九は、この部屋が狭すぎるとでも言いたげに、内部を首をすくめて
そのままそこでどっかり
「どうだった」
前置きもなしに、いきなり九十九が訊いた。
「まあ、予想通り、ということになりそうです」
「そうか」
九十九がほっとしたような顔つきになった。
「何の話なの?」
由魅が
「今話していた大鳳くんの件です」
久鬼が言う。
「彼の?」
「あの事件をぼくに知らせてくれたのは九十九です」
「おれも、けっこうな知り合いを持ったもんさ」
いくらかの皮肉をこめて、九十九が言った。
「しかたないでしょう。ぼくにもいくらか責任がありそうですから」
「どういうことなの?」
「久鬼が、裏工作をしてくれたのさ」
「あんなものは、裏工作と言えるほどのものではありませんよ。それに、ぼくが勝手にやったことですから――」
「
「そうです。相手はもともと札つきの人間だし、坂口たちの方が、むしろほっとしていることでしょう。大鳳くんの行為は、正当防衛です。まあ、過剰防衛ではありますがね――」
「織部が、円空山までおれに電話をしてくれたのさ。それで昨夜、久鬼の所に電話したんだ。
「おそらく、織部をのぞく全員が一週間ほどの停学でしょう。坂口たちはともかく、大鳳も一週間の停学というのは、九十九には納得がいかないかもしれませんが」
「そんなことはない。仮にも、数人に重傷を負わせたんだからな。向こうにも親がいることだろうし――」
「形式的なものです。学園側にしても、新聞沙汰は困りますしね。学園内部だけでおさまりがつきそうで、ほっとしているでしょう。今日、一部の教師たちの間で話し合いがもたれ、そういうことになるはずです」
「妥当なところだろう」
九十九が、太い
「大鳳くんの具合はいかがですか」
久鬼が、
「今朝寄ってきたんだが、まだ眠っている。熱がひどい」
「熱?」
由魅が口をはさんだ。
「医者にも原因がわからんそうだ。大鳳自身は、心配はいらないと言っている。年に一度は、そういう状態になるらしい」
九十九が帰ったあと、由魅と久鬼とは、しばらく顔を見合わせたまま、沈黙していた。
「ね」
声を発したのは、由魅だった。
「あなたも、昨年、そんなことがあったわね」
黒い瞳が、意味ありげに久鬼を見つめた。
久鬼は、無言でうなずいた。
2
長い悪夢だった。
どろどろとまっ赤にただれた溶岩の中に閉じ込められ、呼吸もできずに
自分が発熱しているのだということはわかっていた。
それが、一年に一度、夏が来る前に必ずやってくる、あの熱だということもわかっていた。
得体の知れない獣に
いつも、それは六月頃であった。
それが、今年は五月にやってきた。
しかも、いつもよりだいぶひどい。
肉や骨が、きりきりと痛むのである。何かの力に、強引にねじくられ、形を変えられているかのようだった。関節がきしみ、筋肉が悲鳴をあげている。
夢の中で、九十九と織部の顔を見たように想った。
「だいじょうぶか」
と声をかける九十九に、
「いつものことだから心配はいらない」
そう答えたような気もする。
それも、今は、赤黒い悪夢の底で、諸々の記憶の断片と一緒になり、煮えたぎっている。
あの、黒い獣が姿を現し、身体中を暴れまわっているのだと想った。
――そうか、自分はあの獣に全部肉体を喰われてしまったのだな。
そんなことも想った。
大鳳は、黒い塊の中に
「おまえはおれのものだ」
大鳳を包んでいる黒いものが、どろどろと汚汁をしたたらせるような声で言う。
「もう一生逃げられぬぞ」
「助けて――」
大鳳は叫ぶ。
「無理だな」
黒いものが答える。
その声が自分の声であるような気もした。
「無理なのだ逃げられぬのだ助けても逃げられぬ無理なのだ熱い熱いもうおまえはおれのものだおれはおまえのものだおまえはおれのおまえはおれのおまえのおれはおれ……」
大鳳は、いつの間にか、自分自身と激しく言葉のやりとりをしているのだった。
久鬼や由魅、九十九、深雪、雲斎、そして坂口や菊地たちの顔も出てきた。
坂口は、血だらけの顔をふりたくり、痛い痛いと叫んでいた。これはおまえがやったのだ、これはおまえがやったのだと、坂口は叫びながら傷のひとつずつを指さすのだった。
気の遠くなるほど長い責め苦の果てに、いつしか、大鳳はやすらかな寝息をたてていた。
――そして。
大鳳は、自分が
深い水の底から、水面へ浮上してゆくように、意識がもどってきた。
眼をあけると、九十九と深雪の顔がそこにあった。
ふたりが、心配そうな表情で
「やあ」
大鳳は言った。
深雪の顔が、笑顔になり、その顔がたちまちくしゃくしゃに崩れた。眼に、涙があふれていた。
深雪は泣いているのだった。
大鳳は、自分がひどく場違いな
とたんに、失われていた記憶が、伸びていたゴムがもとの姿にかえるようにもどってきた。
「ぼくは、どうしてたんですか……」
「眠っていたのさ、ずっとな」
九十九が言った。
この男が、照れずに、こんな優しい声が出せるのかと想うほど、耳に快い声だった。
深い
「三日間さ。今朝になって熱が下がったんで安心していたところさ」
「今、何時ですか」
「夜の九時だよ」
「身体中の力が、みんな抜けてしまったみたいです」
起きあがろうとした大鳳の手に、痛みが走った。
「まだ寝ていろ。無理するな」
「これは――」
大鳳は拳を見つめながら言った。
「さんざ、坂口たちをぶん殴ったむくいさ」
九十九が笑う。
「何もわからん未熟者が、鍛えてもおらん拳で人を殴ったからだな」
雲斎の声だった。
「先生、来ていらっしゃったのですか」
大鳳が、首を左に向けると、窓に背をあずけ、
胡座の前に、
「おう、勝手にやらせてもらっておる」
雲斎は、手に持った湯吞みを、軽くあげてうなずいた。
「大鳳、この三日間、昼間は雲斎先生がずっといらっしゃってくれたんだ」
九十九が言った。
「夜は、九十九さんがずっと泊まって下さったのよ」
深雪が言う。
「深雪ちゃんが、朝と夕方に来て、おれたちの食事を作ってくれたんだ」
「そうさ。みんなそこのお嬢ちゃんがやってくれたのさ。
雲斎が真面目な顔で言う。
「ほんとですか」
「噓などつくものか」
雲斎は、ぐびりと焼酎を飲んだ。
「そんなこと、わたし――」
深雪があわてて言った。
「冗談、冗談……」
雲斎が笑って言った。
つられて、大鳳の顔もほころんだ。
「おまえのご両親に連絡をとろうとしたんだが――」
九十九が、笑った大鳳に話しかけた。
「担任の大石先生から聞いたよ。アメリカへ行ってしまってるんだってな――」
「はい」
「くわしい話は、そのうち、気がむいたら聞かせてくれ。今はゆっくり休むことだな――」
「だいぶ迷惑をかけちゃったみたいですね」
「お互いさまさ。そのうち、おれのシモの世話をさせてやるさ」
「わしのも頼むとするか。それとも、このお嬢ちゃんのがいいかね――」
深雪の赤くなった顔を見て、雲斎が、ほっほっほと声をあげて笑った。
「今日はおれたちはこれで帰る。今夜からは独りで寝るんだが、
「平気です」
「明日の朝と夜は、深雪ちゃんが食事を作りに来てくれる」
「学校の方は――。それに、坂口たちは今どうしています?」
大鳳は、ようやく気になっていたことを口にした。
夢の中で、何度も坂口の顔を見たように思った。恐ろしい血まみれの顔だった。
あの時、身体の中で、何かが爆発してからの記憶が、とぎれとぎれの夢のように残っていた。だいぶひどい目に遭わせてしまったようだった。
「学校の方は、あと四日、休んでもいいことになっている。久鬼がどこかに手を回したらしい。坂口たちとのことも、もうすんでいる――」
「久鬼さんが?」
「いくらか責任を感じてるのだろうさ。あいつの親父はな、ここらの顔利きさ。市会議員の何人かや、警察や医者にも知り合いが多い。中央にもパイプがあるらしいし、西城学園には多額の寄付もしている」
「知らなかった」
「春に札幌の中学から来たばかりじゃ無理はないさ」
「そんなことまで知ってるんですか」
「かまわんだろう。ご両親のことをたずねた時に、大石先生から聞いたんだ」
「すみません。別に、隠すつもりはなかったんですが――」
「謝ることはないさ、まあ、その話は、気がむいた時にでもすればいい。さっきも言ったが、今は眠ることだ――」
「はい」
その時、大鳳の腹が、おそろしく健康的な音で鳴った。
皆が笑った。
「腹が減っているのか」
大鳳は、突然に、自分が猛烈に腹をすかせていることに気がついた。餓鬼になった気分だった。
「はい。すごく」
「いきなり固形物はやめた方がいい。台所にスープが作ってある。深雪ちゃんが作ってくれたんだ。今日はそれにしておけ。明日からは、具合をみて、何でも好きなものを
「肉を――」
と、大鳳は答えていた。
「肉を、腹いっぱい食べてみたいです」
3
大鳳は異様な飢餓感を覚えていた。
満腹感はあるのに、肉体のどこかで、もっともっとと、
ついさっき、上等の牛肉を、生野菜と共にたっぷり二人前は、
しかし、さすがに、まだ足りないとは、九十九には言えなかった。
九十九が、約束通り、自前で肉を買い込み、深雪が料理してくれたのである。
うまかった。
それが、うまければうまいほど、もの足りなさが残るのである。
九十九と深雪が帰ったあとも、大鳳は、切なさに
昨日、九十九が休みと言っていたのが、実は停学であることを今日知らされた。坂口と、あわせて三人が入院しているという。
それが、自分がやったものだということが、まだピンとこなかった。
殴られた顔の痛みと、両拳の繃帯がなければ、信じられぬことである。
たっぷり寝たせいか、なかなか寝つかれなかった。
とりとめのない映像が、
それでも、いつしか、うとうととまどろんでいたようだった。
ふいに、大鳳は、怪しいものの気配で目を
部屋の中に、誰かいるのである。
ほのかな匂いが、闇に溶けて漂っている。
女の香水の匂いだった。
「目が醒めたようね」
枕元で、女の声がした。
聴き覚えのある声だった。
「由魅さん?――」
大鳳は、ささやくように言って、頭をそちらに向けた。
「そう、由魅よ」
街灯から差し込む光で、部屋の中は、暗い海の底のように見えた。その海の中に、由魅がいた。
由魅は、横座りに、しなを作るようにして、大鳳を見下ろしていた。外からの灯りに、闇の中で、黒い
たっぷりルージュをひいたらしい唇も、ぬれぬれと
由魅が笑ったのである。
大人の、それもとびきり上等の女が、男を誘う、
ぞくりと首筋の毛がそそけ立ち、大鳳は
ごくりと
「あなたが欲しがっているものを、持ってきてあげたの」
「ぼくが欲しがっているもの?」
自分の声がかすれているのがわかった。
「そうよ」
柔らかく、歌うように由魅がささやいた。
“そうよ”と由魅の唇が動かなければ、聴きとれないほど小さな声だ。
大鳳が、上半身を起こしかけると、ふわりと由魅がかぶさってきた。由魅の顔が、思いがけないほど近い所から、大鳳を見下ろしていた。
大鳳の頭の両側に、両手をついているので、身体はまだ触れ合っていない。
香水と、匂うような女体が、大鳳の頭をしびれさせた。
「ね、あなたは弱虫? わたしが怖くはないの?」
「わ、わかりません」
自分の腰の中心が、硬く張りつめているのがわかっていた。それを、由魅に知られるのが恐ろしかった。
由魅は、ふふふ、と笑って、大鳳の腰に、触れるか触れぬほどに体重をあずけてきた。布越しに、大鳳の硬くなっているものが、由魅の体温を感じとっていた。
由魅の顔がすっと下りてきて、紅い唇が大鳳の唇に触れた。表面が
遠のく時に、由魅の温かいピンクの舌が、ちろりと大鳳の唇を
腰と唇とをつなぐ身体の中心に沿って、ぞくりと快感が走りぬけた。
「ね、欲しいんでしょ」
と、由魅が言った。
「な、何をですか――」
「ふふ……。わたしにはわかっているわ。あなたの欲しいものはふたつ――。でも、それを口に出すことができないのよ」
「――」
「足りなかったんでしょう」
「――え」
「もの足りなかったんでしょう。あのお肉。食べても食べても足りなかったんでしょう。食べれば食べるほどもっと欲しくなってたまらなかったんでしょう。わたしにはわかっているわ。あなたはまだ食べたがっている――」
すっと身を引いて、由魅は、畳の上に置いていたものを拾いあげた。
それは、大鳳も見覚えのある、あの、小さな包みだった。
つい数日前、早朝の校庭で、久鬼とこの由魅と顔を合わせた時に、由魅が持っていたのがその包みだった。大鳳は、その中に何が入っているか知っていた。
中身は――
「生のお肉」
お、に、く――と由魅がささやいた時、おそろしいほどの衝動が、大鳳の身体を貫いていた。
そうだ。
そうなのだ。
おれは、その生の肉が欲しかったのだ。
生の肉を、腹いっぱい、胃がパンクするまで詰め込みたかったのだ。血のしたたる肉に顔をうめ込んで、思うぞんぶん、死ぬほど喰いまくってみたいのだ。
大鳳は、その肉に飛びついて、ひったくり、貪りまくりたい衝動を、かろうじてこらえた。
「これが欲しいのね」
由魅が、歌うように言う。
「いいのよ。隠さなくてもいいのよ。ちっとも恥ずかしいことじゃないんだから。これが欲しいのね。さあ、言ってごらんなさい。言えば、あなたはずっと楽になるわ。あなたは、これを、気が狂うほど欲しがっているはずよ――」
「そうだ」
と、大鳳は答えていた。
「頼む。おれにそれを喰わせてくれ――」
切ないほどの欲求に、身がちぎれそうだった。喉の奥で、犬のように
由魅が、笑みを口元にためながら、その包みを開くのを、大鳳は、身体を起こして
久鬼のことも、深雪のことも、九十九のことも、円空拳のことも、すべて、大鳳の頭から消し飛んでいた。ただ、早くその肉を
闇の中に、赤い身に、白く脂のからんだ肉が現れた。
「さあ、お食べなさい」
言われたとたん、大鳳はその肉に飛びついていた。
とろけるような肉の甘みが、口いっぱいに広がっていた。
ひざまずいて肉を貪り尽くし、大鳳はようやく我に返った。
大鳳の背後から、首に、蛇のようにしなやかにからんできたものがあった。白い、ぬめるような由魅の腕だった。
耳元に、熱い息が吹きかけられた。
「あなたの欲しがっているものが、もうひとつあるって言ったでしょう」
白い腕が、ゆっくりと大鳳をふり向かせた。
由魅の顔が、
「それは、わたし。お、ん、な……」
顔がゆっくりと近づいてきて、唇がゆっくりと押しあてられた。大鳳は、それを避けなかった。
ねっとりと、熱く、柔らかな唇だった。
大鳳の口の中に、由魅の舌が忍び込んできた。それは、大鳳の舌をからめとり、
由魅の手が、大鳳の背に回されていた。由魅は、大鳳を抱いたまま、
大鳳が上になった。
唇が離れ、大鳳は、由魅を上から
「まだ、知らないんでしょう?」
由魅が言った。
「女のからだ――」
由魅の眼が、
大鳳はやっとうなずいた。
喉がからからに乾いていた。
さっき、料理を
「わたしが教えてあげる……」
由魅が、そのままの形で、身体を入れ替えた。由魅が上になった。
硬くなったものが、布越しに、由魅の
上になった形で、由魅が、片手でブラウスのボタンをはずす。
大鳳の右手を、由魅の左手が捕らえ、ボタンをはずしたブラウスの布の下へ運んだ。由魅は、その下に何も付けていなかった。
「ああ――」
大鳳は、声をもらした。
初めて由魅に会った時、赤い布を下からまぶしいほど押しあげていたものに、今、自分は触れているのだ。
それは、たっぷりと重く、柔らかく、そして温かかった。手のひらの下に、乳首があった。手を動かすと、それが、たちまち硬く
身体が
大鳳の中に、嵐のように激しくふきあげてくるものがあった。熱い溶鉄の塊が、どっと身体の奥から
大鳳は、手のひらの中のものを、荒々しく
突きあげてくる欲望に、大鳳は我を忘れてのめり込んでいった。
暴風に似たひと時が過ぎ、大鳳は、泥のような眠りにひき込まれていた。身体中の活力を、すべて由魅に注ぎ込んでしまったようだった。それとも、さっき食べた肉の中に、何か薬が入っていたのかもしれなかった。
由魅が服を身に付ける
由魅が服を着終えた。
立ちあがり、由魅は、もう眠っていると思われる大鳳を、ほんの数瞬、見つめていた。
「キマイラが出てくるのも、もうすぐね」
低くつぶやいた。
部屋を出て行こうとする由魅に、大鳳はそのキマイラというのが何なのかたずねようとした。
だがそれは、言葉にはならなかった。
まぶたがほんのわずか、ぴくりと動いただけで、大鳳は、そのまま本物の深い眠りの底へと沈んでいったのである。
4
――大鳳は変わった。
久しぶりに登校してきた大鳳を見て、誰もがそういう感想を持った。
大鳳の内部で、何かが抜け落ちたようであった。代わって、もっと別の何ものかが大鳳に加わり、この少年の印象を、それまでとは違ったものに見せているのである。
そして、以前には、どちらかと言えば女性的であったその美しさが、今ではすっかり男っぽいものに変わっているのである。いや、男っぽい、と言うよりは、野性的、という言い方をした方が、より正確かもしれなかった。
美しい毛皮をまとった
子供がひと皮むけて、大人になったような感じだった。
超然とした野生獣の匂いが、大鳳を包んでいた。神秘的な感じさえあった。
坂口との一件が、噂となって一般生徒の耳にも届いているのであろう。彼等の、大鳳を見る眼もこれまでとは違っているのだ。
一見した時の印象が、久鬼を見た時のそれと似てきたとも言える。似てきた、と言っても、完成された久鬼のそれと違い、大鳳のそれには、まだ粗削りなものがあった。久鬼にない、ふてぶてしさが大鳳にはある。
自分のことを、ぼくと呼ぶより、おれという時の方が多くなっていた。
登校した最初の日、大鳳は、白蓮庵に久鬼を訪ねている。
「変わりましたね、大鳳くん」
大鳳とふたりきりで対面した時、久鬼は素直に感想をのべた。
「みんなにそう言われます。自分ではそういう実感はないんですが」
それも、大鳳の正直なところである。
自分がどう変わったのか、ぴんとこないのだ。ただ、以前よりは人の眼を気にしなくなっているという気はしている。
大鳳は、悠然と久鬼の眼を眺めていた。
挑むような眼でなく、淡々とした眼であった。以前であったら、こんな風に久鬼を見ることなどできなかったであろう。おどおどした感じを必死に隠しながら、眼をそらせているか、挑戦的な眼つきで見ていたにちがいない。
正座している久鬼に対して、素直に
久鬼の視線を、対等に受け止めている。
久鬼が、今はあまり怖くない。
変わったというのは、こういうことを言っているのか、大鳳はそんなことを考えている。
久鬼が、医者やら学園側に対して、色々手をまわしてくれたらしいことは聴いている。
しかし、それは、久鬼がまず己のためにしたのであろうということも聴いている。学園側にしても、坂口たちにしても、一番良い形でおさまりがついたのだ。
自分自身は、特別なことはしていない。ただ巻き込まれただけなのだと大鳳は考えていた。
だが、大鳳は、とにかく、久鬼には礼を言っておかねばと思い、白蓮庵に来たのであった。もうひとつは、久鬼の顔を見ておきたかった。
久鬼がいなかったら、こんな風にはおさまらなかったであろう。その考えが頭に浮かんだとたん、一番良い形でおさまりをつけてくれた久鬼に対して、素直に感謝の念がわいた。
しかし、すぐには礼の言葉が出てこない。
やはり礼を言わねばならないんだろうな――。
礼を言うためにやってきたはずなのに、久鬼を前にしていると、礼の言葉が出てこない。
だが、礼は言うべきであろう。
大鳳は、頭の中に浮かんでくる、そんなとりとめのないものを見つめながら楽しんでいた。その楽しんでいる自分がおかしくなって、大鳳の顔が自然にほころんだ。
「何を笑ったんです?」
久鬼が言った。
「あなたに、お礼を言わなくてはと、そう想っていたんです」
「それで笑ったのですか」
「そうです」
大鳳の返事を聴いて、久鬼は苦笑した。
「やっぱり変わりましたね」
久鬼が言った。
まっすぐに大鳳の眼を見つめている。
「ほら、その眼――」
「この眼がどうかしたんですか」
「ようやく竜が頭を持ちあげてきた、そんな眼をしていますよ」
「竜眼のことですか」
「そうです」
「雲斎先生も似たようなことを言ってましたが、竜眼とはなんですか」
「中国風の言い回しでね、英雄というか、特殊な才能や運命を持っている人間の眼に現れる相のことですよ」
「ぼくが特殊なんですか」
「特殊でしょうね」
「どんな風に――」
「たとえば坂口たちのことですよ。よくあれだけのことをやれたと、自分でも不思議に思いませんか」
言われてみれば、その通りである。
無我夢中で、あの時のことはよく覚えていないが、よくあれだけのことができたものだと自分でも思う。円空拳を習いはじめていたとは言え、わずかひと月ほどの修行で、あれだけのことができるとは思えなかった。
しかし――
では何がどうなっているのかというと、それもよくわからないのだった。
自分の身体の内部で、何かが爆発したとたん、大鳳は、わけがわからなくなっていたのだ。その爆発が荒れ狂い、気がついた時には、血まみれの坂口に馬乗りになっている自分の手に、深雪がしがみついていたのである。
「よくわからないのです」
大鳳は、自分の両拳を見つめながら言った。手には、まだ、白い
「ほんとうに――」
と、大鳳は念を押すように言った。
「ところで、大鳳くん」
久鬼が話題を変えるように言った。
「そこに、ふたつのバラがあるでしょう」
見ると、床の間に、バラを一輪ざしにした細長い花ビンがふたつ、置いてあった。
どちらも、紅色がかったふちどりの花びらを持つ、黄色いバラであった。
「これがね、今日の華道部のテーマなんですよ――」
「これがですか」
「向かって右側のバラを見てごらんなさい。わかりますか」
大鳳は、右側のバラを見、左側のバラを見た。久鬼の言っている意味はすぐにわかった。右側のバラの方に、生命感が欠けているのである。
「造花ですね」
「そうです。造花でも、よくできたものは、遠目には一見本物のように見えたりしますが、こうしてふたつ並べてみれば、その差は一目
大鳳は、久鬼の質問に、どう答えてよいかわからなかった。禅問答を挑まれているような気分だった。
「
「はい」
久鬼はうなずいた。
理解の早い生徒を前にした教師のような気分になっているらしい。
「では、生命がないというのはどういうことですか」
しばらく大鳳は考え、そして言った。
「死なない、ということでしょう」
久鬼の顔に、
望んだ通りの答えを大鳳が口にしたからであろう。
「そうですよ。生命がない、ということは死なない、ということです。それでは、死なないということはどういうことでしょうか――」
久鬼は、大鳳の答えを待たずに、自分の質問に自ら答えた。
「――死なない、ということは、滅びがない、ということです。造花は散りません。散らないから、造花は美しくないのです。花は、散るから花なのです。花は、滅びがあるから美しいのですよ」
久鬼は言い終え、しゃべり過ぎたというように、口をつぐんだ。
大鳳は、自分と由魅との間にあったことを、この久鬼は知っているのだろうかと考えた。おそらく、まだ知ってはいないだろう。
知った時、この男はどんな顔をするのだろう。
それが恐ろしいようでもあり、また楽しみなようでもあった。
その時、大鳳は、自分が由魅の姿を求めて、ここにやって来たのだということに、ふいに気がついた。
あの晩の、狂ったような陶酔感が
生の肉と、女の匂い。
自分の体の上で、また下で、うねり、
由魅が、部屋を去る時に、なにか不思議な響きの言葉を口にしたような気もする。だが、それがどんな言葉なのか、大鳳は思い出せなかった。
大鳳の身体がうずきはじめていた。
大鳳は、自分の身体が、何を求めているのかを知っていた。
生の肉と、そして、熱く喘ぐ女の肉体――。
そのふたつを求めて、大鳳の肉体は、狂おしくうずいていた。
「大鳳くん。今、ふいに思ったのですがね」
久鬼があらたまって言う。
「もしかすると、あなたには不思議な作用があるのかもしれません」
「――」
「坂口たちのことです。いや、彼等だけでなく、灰島や菊地、そしてぼくも含めての話ですがね」
「どういうことでしょうか」
「あなたには、人の肉の奥に眠っている獣性というか、暴力的なものを自然に引き出してしまうものがあるのかもしれません。昔から、あなたは、人にいじめられやすいというか、そういう傾向がありませんか――」
久鬼に言われて、大鳳には、はっと思いあたるものがあった。街で歩いていても、つい、暴力的な匂いを発散させている人間たちを引き寄せてしまうのである。小さい頃からそうだった。
菊地たちにしても、坂口にしても、そんなところがある。
「だとするなら、案外、坂口も菊地も、本当の意味での被害者なのかもしれませんね。結局、大きなダメージをこうむったのは、彼等の方だったのですから――」
それは、少なくとも菊地や灰島に関しては、あなたがやったことではないか――そう言おうとした言葉を、大鳳は
そんなことはないと否定する心の底では、久鬼の指摘を認めている自分があったからである。
「ぼくも、そうでした」
と、久鬼が言う。
「久鬼さんも」
「はい」
うなずきながら、久鬼は、
「今日は、少ししゃべり過ぎましたね。最後に、ひとつだけ言っておきます。由魅には気をつけなさい」
「――」
大鳳は、先ほどの自分の心を見すかされたような気がして、一瞬たじろいだ。
「あれは、危険な女です」
「どういう意味ですか」
「わからなければ、それでけっこうです。しかし、由魅には近づかない方がいい」
「久鬼さんはどうなんですか」
まだ知られているはずはない、そう思いながら大鳳は言った。
さっきの身体のうずきが、まだ残っていた。
久鬼は、黙ったまま、大鳳を見つめていた。
眼の底に、青白い、炎が燃えていた。
「そのうちに、あなたとぼくと、生命をかけて闘う時が来るかもしれませんね」
久鬼が、冷ややかに言った。
大鳳の背に、ぞくりと悪寒が走った。
「坂口に対して使ったあの技、あれはどういう意味だったんですか」
「ほんの戯れですよ」
「おれは怖くなんかありませんよ」
大鳳は言った。
「ほう」
すっと久鬼の眼が眠そうに細められた。
「みんな、あなたを恐れて言うことを聴いているが、おれは違う」
「答えが出たようですね」
「何――」
「あのメッセージの答えがですよ」
久鬼の顔から、ほとんど表情が消えていた。
大鳳は、その顔から眼をそらさなかった。ふいに、久鬼の唇の両端が、きゅうっと
「おもしろい」
と、久鬼が言った。
大鳳は、言葉を発することができなかった。
「いつか――」
と、久鬼が続けた。
「――あなたの活けた花を見せて下さい」
大鳳は、久鬼の
KADOKAWA Group