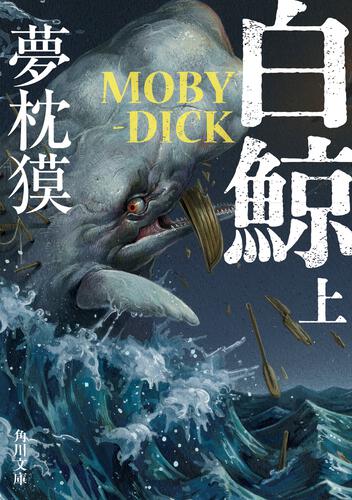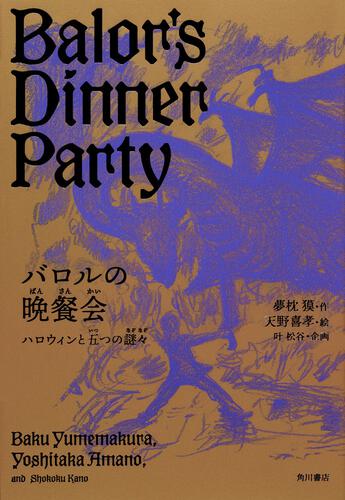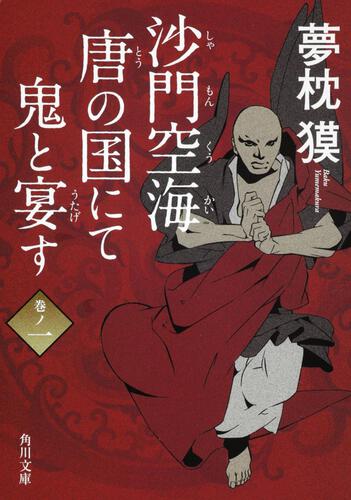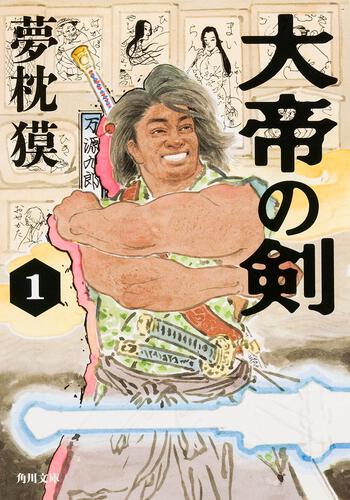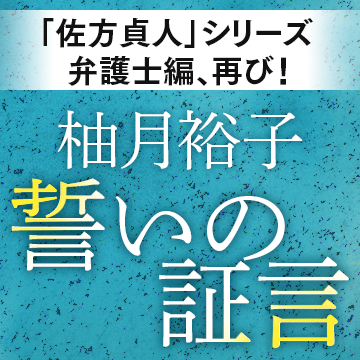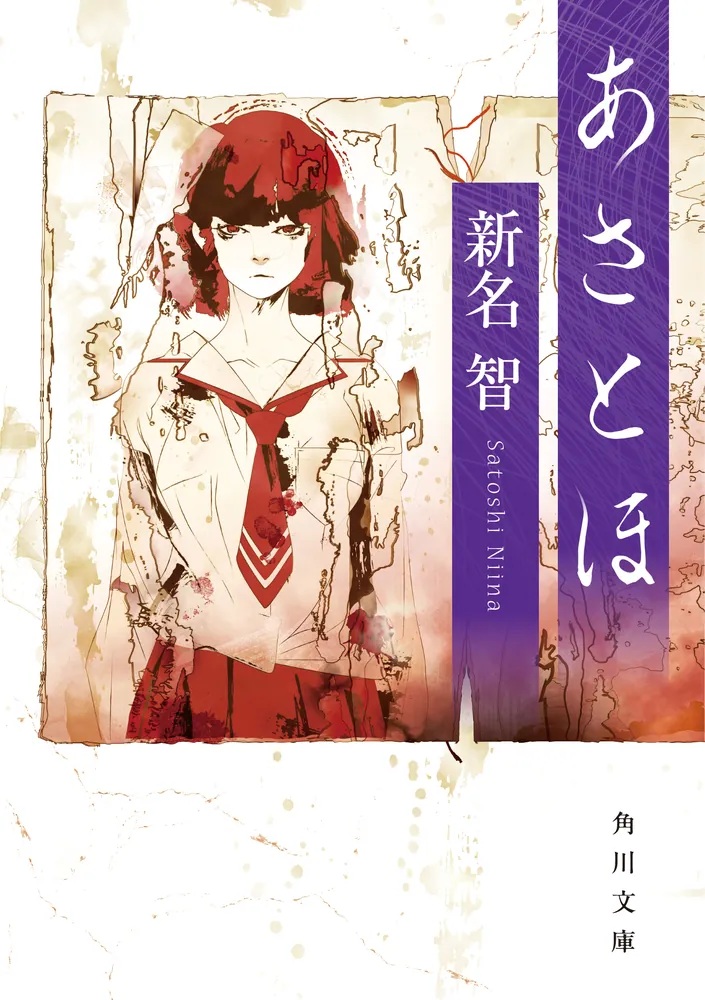三章 死闘変
1
――おれは強くなっている。
それが大鳳の実感だった。
雲斎の所に通いはじめてから、一カ月が過ぎていた。
大鳳の成長ぶりには、眼を見張るものがあった。あの九十九でさえ、舌を巻くほどである。
習う、というよりは、大鳳の肉体がもともと記憶していることを、想い出していく――そんな風であった。
大鳳の持つ天性のものと、九十九の巧みな指導が、その結果をもたらしたのだ。
大鳳は、底の知れない井戸のようであった。
逆にまた、九十九が教えるだけのものを、いくらでも
それが、自分でもわかるのである。
その意識が、
――おれは強くなった。
という実感となって、大鳳の心にわきあがってくるのである。
数日前、雲斎が大鳳に言ったことがある。
「殴りっこの優劣などは、まあ、子供の遊びのようなものよ。しかし、その遊びの技でも人を殺すことくらいはできる。だが、人を殺すというのは、技のはたらきではないぞ。もっとちがうもののはたらきさ。技などは、その道具にしかすぎぬ。おぬしの習うておる技も、
技に
また、こうも言った。
「動物はな、本来、争ったり、殺したりはしない。彼等が殺すのは、食べるためか、守るためのふたつの場合だけさ。
大鳳には半分もわからなかった。
心を磨くといっても、どうしていいかわからない。大鳳にできることは、技を磨くことくらいである。
西城学園にいる以外の時間のほとんどが、その技を磨くために費やされた。休んでいるのは、眠っている時と、食べている時くらいのものであった。
学校が終わると同時に、トレーナーに着替え、サブザックにカバンと学生服を詰め、それを背にして円空山まで走ってゆく。晩飯は、雲斎、九十九と一緒に、円空山ですませた。
朝は早めにアパートを出、早朝の校内で一時間ほどトレーニングをする。その後、買っておいたパンと牛乳で朝食をすませるのが、大鳳の日課だった。
円空拳は、大鳳がそれまで抱いていた空手のイメージとは意外に異なるものであることが、その頃にはわかっていた。
まず、
空手の高段者の中には、タコができて、拳がグロテスクに変形している者がよくいるが、円空拳では、拳をそこまで鍛えぬくことにこだわっていない。力そのものより、動きや、
また、空手に直線的な動きが多いのに対し、円空拳の動きは、基本的には円であった。
人の肉体の内部にある“気”を、外に対して爆発させる、
そこをうまく突きさえすれば、女や子供でも、大の男を容易に倒すことができる。指一本で、人を
だが、時刻や、その時の相手の体調によって、微妙に移動するその点穴をさぐりあて、ある特定の方向から打撃を加えるのは、相手が何もせずに立っていてさえ難しい。ましてや、戦いの最中で相手が動いていれば、まず不可能なことである。
力で相手の力をねじふせることの方が、ずっと手っ取り早いというわけだ。
大鳳がいま吸収しているのは、その力の技であり、強くなったと思っているのは、その力のことである。
大鳳自身も、それをよく承知している。
――その日の早朝。
大鳳は、深雪の作ってきたサンドイッチを、校庭の隅で口に運んでいた。
ふたりは、あれからほぼ毎日、早朝にこの場所で顔を合わせていた。別に申し合わせたわけではない。自然にそうなったのである。
時々は、深雪が手作りの朝食を持ってきてくれることもあった。
この日もそうであった。
初めて深雪と言葉を交わした、あの桜の樹の下である。あの時は満開だった桜が、今はすっかり散り、青々とした葉桜になっている。
ふたりの間に、一頭の犬が寝そべっていた。白い雑種犬である。大鳳と深雪が言葉を交わすようになったきっかけの犬である。
犬は、大鳳が投げてやるサンドイッチを、その都度起きあがっては食べる。このノラ犬も、すっかり自分の日課を大鳳のそれに合わせているようである。
大鳳のトレーニング姿をどこかで見ているらしく、トレーニングが終わり、大鳳が食事を始めると、どこからか姿を現すのだ。
「犬って、ノラ犬でも人になつくのね」
深雪が、犬の背を
「もともと、犬は人なつこいんだ」
大鳳は、飲み終えた牛乳ビンを犬に
口調が、一カ月前より、心なしか男っぽくなっている。自分が強くなったという思いが、そういう感じとなって現れているのであろう。
犬には、サンシロウという名前がつけられていた。サンドイッチと白、を縮めたもので、深雪がつけた名前である。
「ね、あの人、この前の女の人じゃない」
深雪が顔をあげてささやいた。
深雪の視線の方向に眼をやると、校門の所に、ふたつの人影が立っていた。
男と女――久鬼麗一と亜室由魅であった。
ふたりは、そこに立ったまま、じっと大鳳と深雪を見つめていた。
大鳳と深雪が気づいたことを確認して、ふたりは歩み寄ってきた。
「こんなに早く、誰が来ているのかと思ったわ」
由魅が言う。
右手にカバンを持ち、左手に小さな包みを抱えていた。
黒い
「仲のよろしいことね」
視線を深雪にとめて、言った。
深雪は、うつむいていた。
「大鳳くん――」
久鬼が言った。
しばらく会わぬ間に、その顔の美しさがさらに増していた。青白い炎でできた花のようであった。切れるような硬質ガラスのイメージがある。
顔をあげた深雪は、久鬼の
「君のクラスに、坂口というのがおりませんか」
久鬼の眼が鋭く光っていた。
大鳳は、同じクラスの、ひときわ身体の大きい男の姿を想い出していた。
坂口
「いますが――」
「その坂口が、ぼくに挑戦してきました。この学園の番をはりたいのだそうですよ。とりあえず、ぼくのかわりに阿久津が相手をすることになりました。今日の放課後です。よかったら見に来ませんか――」
「というと……」
「鬼道館です。普通の生徒は入れないことになってるんですが、入れるようにしておきましょう」
「何故、ぼくを――」
「円空拳を始めたのでしょう。見ておいて損になるものではありません」
大鳳は何故か
円空山に通い始めてすでに一カ月がたっている。知られていても、別に不思議なことではない。それに、久鬼とは同じ学校で、しかも彼は以前に、雲斎の所で九十九と円空拳を学んでいるのである。
大鳳が沈黙したわずかの間を破ったのは、サンシロウだった。
由魅が抱えている小さな包みに、いきなり跳びついたのである。
「まあっ」
跳びのいた由魅の手から紙包みが落ちた。
とめていなかった紙包みが半分開き、そこから赤いものが
サンシロウが、その赤いものの一片をたちまち口にくわえて走り出した。あっという間に、雑木林の中に逃げ込んでしまう。
「だめよ、サンシロウ!」
深雪が叫んだが、無駄だった。
由魅が包みを拾いあげる。
「うっかりしてたわ」
言いながら包みをカバンの中にしまう。
包みの中に入っていたのは生肉であった。
「ごめんなさい」
深雪が恐縮して頭を下げた。
「いいのよ。あなたの犬ってわけじゃないんでしょ。あの犬、わたしも何度か見たことあるわ。ノラ犬が相手じゃね。こんなごちそうを犬の鼻先で持っていたわたしがうかつだったのよ――」
由魅が言い終わるのを待っていたように、久鬼が口を開いた。
「じゃ、今日の放課後、待っていますよ」
そのまま背を向けて歩き出した。
由魅は、軽く大鳳にウインクして、
「そのうちにね――」
意味ありげに言ってから、久鬼の後に続いた。
「久鬼さん。久鬼さんは、何故円空拳を習うのをやめたんですか――」
久鬼の背に、大鳳が声をかけた。
返事はなかった。
背を向けたまま、久鬼はふり返らなかった。
2
――放課後になった。
大鳳の足は、自然に鬼道館に向かっていた。
独りである。
ついて来たがった深雪をむりに帰らせたのだ。このことは、九十九にも言っていなかった。言えば、おそらく九十九は止めるであろうと、そう思ったからだった。
大鳳は、あの久鬼に、不思議に
自分の内部にある暗いものが、何故かあの久鬼と魅き合っているらしい。
それが何であるのか自分でもよくわからない。その何ものかを見とどけるために、自分は鬼道館へ行くのだ。大鳳はそう考えている。
「来ましたね」
入ってきた大鳳に気がつき、久鬼が笑みを浮かべた。
そこには、五人の人間がいた。
久鬼と阿久津、柔道着を着た男と剣道着を着た男、そしてあとひとりは、あの菊地であった。
坂口の姿はどこにもない。
「まだなんですか」
大鳳は、もう一〇分以上前に、坂口が教室から出て行ったのを見ている。
そのあと、ゆくかゆかぬか、一〇分間自問自答をくりかえしたあげくに、朝から迷っていたことに結論を出したのである。
「そのようですね」
独りだけ学生服姿の久鬼が言う。
久鬼以下、全員が正座している。
もっと殺気立った雰囲気を想像していたのだが、まるでその雰囲気はない。
他の人間の姿が見えないのが不思議だった。
「これで全員なんですか――」
大鳳は、まだ緊張のとれない声で言った。
「むこうが五人だというのでね。人数を合わせたのですよ」
その時、騒がしい気配があり、五人の男と、ひとりの女が入ってきた。
坂口が、仲間を連れてやってきたのだ。連れの四人のうち、ふたりが大鳳と同じクラスの人間であった。
女は、亜室由魅である。
どうやら、由魅が坂口以下、男どもをここまで連れてきたらしい。
坂口の連れの四人は、入ってきたとたんに、この場の雰囲気に
ことさら肩をいからせているのは、虚勢であることが、大鳳にも見てとれた。
そういうことが、円空山に通うようになって、自然にわかるようになっていた。
大鳳の顔に、自然に笑みが浮かんだ。
「大鳳じゃねえか――」
坂口が大鳳を見つけて言った。
「てめえが、なんでここにいやがるんだ」
坂口だけが、普段と変わっていない。わずかに緊張しているだけである。
大鳳の口元に浮かんだ微笑に、いくらか腹をたてているようだった。
「てめえ、前に、久鬼に呼び出されたことがあったが――そうかい、やつらの仲間かい」
「違います」
カメが首をすくめるように、大鳳の口元から微笑が消えていた。
坂口の怒気が、熱気のように大鳳の顔を
「大鳳くんは、ぼくが呼んだのですよ。彼は、今日の立会人です」
久鬼が、ほとんど感情を交えぬ声で言った。
「まあいいさ。あとでゆっくり大鳳に
坂口は、板の間の中央に仁王立ちになって、久鬼を見すえた。
「早いとこすませようじゃねえか。おれたちは話をしに来たんじゃねえんだからな――」
「なかなかの自信家でいらっしゃる。そこの大鳳くんとはまるで逆のタイプですね」
久鬼の顔に、ふっと笑みがよぎった。
「何がおかしい!」
炎に似た殺気が、坂口の全身からふくれあがった。
「もうだいぶ昔のことなんですがね。箱根でネズミが大量発生したことがありました――」
「それがどうした」
「その何十万というネズミが、ある日、一斉に移動し始め、皆、
「――」
「死ぬつもりでいたネズミなんて、一匹もいなかったと想いますよ」
わずかの沈黙があり、坂口のしゃがれ声が響いた。
「おれがそのネズミだってえのかい」
久鬼は、坂口のその質問に、先ほどと同じ笑みで応えた。
一瞬、怒りだすのかと思った坂口の顔に、
学生服の一番上のボタンを、無言ではずした。ごつい手だった。その
町の道場できたえたものであろう。
「言っとくがな、これはケンカだぜ――」
坂口が言った。
「承知していますよ」
「てめえをぶちのめしたら、この学校の番を、おれがはらせてもらう」
「ぼくなどぶちのめさずに、勝手に番とやらをはればよろしいのに」
「そうはいかねえ。ものごとには、筋ってものがあるからな。通すものは通さなくちゃいけねえ」
「お堅いことですね」
「性分だからな」
「存分に――。心配はいりませんよ。この鬼道館の中でのことに関する限り、ぼくにまかされています。それが試合でもケンカでもね。もっとも、あなたが負けてどこかへ泣きつけば、話は少しややこしくなるかもしれませんが――」
「さあ、始めようぜ。口じゃてめえにかなわねえからな――」
よほどの場数を踏んでいるのであろう。
坂口は、リラックスしているようにさえ、大鳳には見えた。
阿久津がぬうっと立ちあがった。
無言で、坂口たちをねめまわした。
それだけで、おそろしい迫力がある。
坂口をのぞく全員が、動揺していた。
「あんたからかい」
「そうだ」
ぐうっと、阿久津の体内に気がふくれあがる。
それを、坂口が正面から受けとめた。
阿久津も坂口も、どちらも見劣りがしない
すごい迫力だった。
大鳳は、さっきから座るのも忘れて、なりゆきを見守っていた。
横に由魅がやってきたのも、ほとんど気づかないくらいだった。
先にしかけたのは坂口だった。
「行くぜ!」
言いざま、右の回し
スウェーバックして、阿久津がそれをかわした。坂口は、蹴った右足でそのまま踏み込み、それを軸脚にして左の後ろ蹴りにつないだ。すごい連続攻撃だったが、まだ、これは相手の手のうちをさぐるためのものであった。
阿久津は、坂口の軸脚に、容赦のない蹴りを放った。坂口は、軸脚をあげて、それを受ける。
基本的なローキック――下段蹴りの受けである。
次の瞬間、阿久津のもう一方の足が、床すれすれに
坂口が床に転がった。
転がっていく坂口に向かって、阿久津の太い手足がぶんぶんと
二転三転しながら、その攻撃をブロックし、坂口がひょいと立ちあがった。
待っていたように、立ちあがった坂口の腹に阿久津の前蹴りが吸い込まれた。
身体を「く」の字に折り、坂口がふっ飛んだ。これだけもろに入れば、身体の小さい者なら倍くらいは飛んでいたかもしれない。
むっくりと坂口が起きあがった。
「
ふてぶてしい笑みが口元に浮かんでいた。
カウンターとは逆のケースである。転がりながら起きあがる方向に蹴られたので、派手にふっ飛んだわりに、ダメージは少ない。
と言っても、これが並みの男であったなら、すでに勝負があったところだ。
「けやっ!」
坂口は、頭から阿久津に突っ込んだ。
坂口は、突っ込みながらも顔面と首を、きちんと両腕でブロックしている。坂口が阿久津にぶつかったのと、阿久津のエルボーが坂口の肩を襲ったのとほとんど同時だった。
ふたりはもつれあったまま、板の上に倒れ込んだ。坂口が上になっている。
坂口の拳を、阿久津が必死にブロックする。隙を見て、下から阿久津が坂口の
ひるんだ坂口をはねのけ、阿久津が立ちあがる。坂口も立ちあがっていた。
ふたりの息が荒くなっていた。
目まぐるしい攻防が始まっていた。
大鳳には、わずかに阿久津が優勢に見えた。実力の上では、はっきり阿久津に分があった。それを、なんとか接戦に持ち込んでいるのは、坂口のケンカ慣れした度胸と、煮えたつ意地であった。
番をはるためとはいえ、坂口は自分のために戦っていた。阿久津は久鬼の代わりである。その差が、実力の違いを縮めているのだ。
そんなことを考えながら、胸を躍らせてふたりの攻防を見つめている自分を発見し、大鳳は、新鮮な驚きを覚えていた。
ふたりが、もつれ合うようにして、また床に転がった。
重い肉が板を打つ音が、ダン、と響いた。
最初に、のっそりと起きあがったのは坂口だった。
阿久津は、うずくまったまま、頭を抱えていた。
肩を荒く上下させながら、坂口は阿久津を見下ろしていた。
阿久津が、頭にやっていた手を離し、それに眼をやった。べっとりと血が付いていた。燃える眼で坂口を見上げた。
「貴様――」
阿久津の低い声が、怒りで震えていた。
「言ったろうが、これはケンカだってよ――」
坂口が唇を
うるんだような
「待ちなさい」
その時、
久鬼だった。
「やらせて下さい。まだやれます!」
阿久津が、手の血を道着のズボンにこすりつけて身構えた。
「下がりなさい、阿久津。おまえが負けたと言っているのではない。ぼくが坂口とやってみたくなっただけです」
久鬼がすっと立ちあがった。
不満をおし殺し、武骨――と言ってもいいほどの顔と
「出てきたな、久鬼」
坂口が
「他にもおまえとやりたがっているのがいるのですが――」
久鬼は、剣道着を着ている男と、柔道着を着ている男を眼で指した。
「ぼくでかまわんでしょう」
「初めからそれが望みさ」
坂口の荒い呼吸が、元にもどっていた。
驚くべき回復力の早さである。
「何かハンデをつけなければいけませんね」
久鬼が、坂口を眺めながら、首をわずかに傾けた。
「ハンデだと――」
「疲れてるあなたに勝っても自慢できませんからね。何でも好きな武器を使って下さい。ぼくは、このケンカを最後まで素手でやることにしましょう」
まるで、戦いを前にした者とは思えぬ口調である。
「勝手にしな。おれの方は遠慮しねえぜ」
坂口は、学生服の下からトンファーを取り出し、それを両手に一本ずつ握った。
トンファーは、木製の武具である。木とはいえ、一撃で骨を砕くこともできる、危険な武器だった。
坂口は、くるくると鮮やかな手並みでそれを回転させ、身構えた。堂々とした構えである。そこらのチンピラ学生が、格好だけでヌンチャクをふり回すのとは、わけがちがう。
ぴったりと決まっている。
「へっ。もともとこいつは使わせてもらうつもりでいたんでな」
坂口が言う。
久鬼は平然とそこに立ったままだった。
坂口も、今度は自分から仕掛けようとはしなかった。
間合いをつめるわけでもなく、ただ、構えたまま久鬼を睨んでいる。
「来なければ、ぼくの方から行きますよ」
無造作に言うと、久鬼はそのまま坂口に向かって歩き出した。ふいに吹き出した風のようにあっけない。
五月の薫風に似て、さわやかささえある。
殺気というものがまるでない。
その雰囲気に押されて、思わず坂口が後ろに
その退がりかける足で、坂口はそこに踏んばった。
「てえいっ!」
坂口のトンファーが、ぶんと唸ってひらめいた。
久鬼の鼻先一センチの所を、トンファーの先端がかすめる。久鬼は眼もつぶらない。
坂口は、どうやって、久鬼が今の一撃をかわしたのかわからなかった。
久鬼に押されながら放った一撃とはいえ、充分に間合いを見切ってのことである。まるで、トンファーが、久鬼の頭部を通り抜けたような感じである。
久鬼の顔が目の前に迫っていた。
坂口の背に、電流が走りぬけた。
びくんと身体をすくめ、坂口は、おもいきり後方に跳んでいた。第二撃を放とうとした腕が、まるで間合いの感覚を喪失してしまっていたのである。
これまで、感じたことのない
おもいきり退がったはずが、久鬼との距離が少しも開いていないのである。
久鬼の、
自分がこれまで相手にしてきた者たちとは、まったくケタの違う人間を相手にしているのだということを、坂口は悟っていた。自分が、生まれて初めての冷や汗をかいていることすら、気がついていなかった。
坂口の唇が
死にもの狂いの反撃に出た。
「しゃっ!」
唇から呼気をほとばしらせ、たて続けに連続技を爆発させた。
おそろしいスピードと、破壊力を秘めた技だった。生涯のエネルギーのすべてを
しかし、坂口の攻撃は、久鬼の身体にまったくかすりもしなかった。攻撃のことごとくが空を切っていた。
「ちいっ!」
坂口の手から、久鬼の顔面に向かってたて続けにふたつのトンファーが飛んでいた。
身を沈めて久鬼がそれをかわしている一瞬の隙に、信じられぬことが起こっていた。
「あばよ」
電光のような速さで身を翻し、坂口の身体は出口に向かって駆け出していた。恥とか、ためらいとかを、ほんの一瞬も感じさせない、水際だったあざやかな逃げっぷりだった。そのみごとさは、気持ちよいほどである。
坂口の仲間の四人は、あっけにとられ、坂口が姿を消した出口の方を見つめていた。四人は、坂口にふた呼吸以上も遅れ、あわてて立ちあがり、あたふたと逃げ出した。
坂口の半分も、その逃げっぷりはよくなかった。
その後を追おうとした阿久津たちを、久鬼が制した。
久鬼は苦笑していた。
「あの男、まさか逃げ出すとはね――」
坂口が逃げ出すとは、久鬼も考えていなかったのであろう。
「久鬼さん――」
大鳳が言った。
久鬼がふり向いた。
何事か期待している眼で大鳳を見た。
「さっき、争っている最中に、彼の足に何かしませんでしたか――」
大鳳が言うと久鬼がうなずいた。
「やはり、見えましたか」
「左手で、彼の足を軽く突いたような気がしたんですが――」
「その通りですよ。きみならあれが見えると想ってました」
「ぼくなら?」
「その竜眼ならね。あれは、ぼくからあなたへのメッセージですよ」
「メッセージ?」
「あなたを試したのです。もし見えなかったのなら、あれは、ぼくからあなたにあてた、片想いのラブレターということにでもなりますか」
「見えたのなら?」
「見えたのなら――さあ、どういうものになるんでしょうかね。あなた次第、とでも答えておきましょうか」
大鳳は、久鬼の瞳の底に、青白い炎のようなものを見ていた。
3
教室に帰ると、深雪がそこにいた。
「帰るように言っておいたのに」
大鳳の口調の中には、怒ったような響きがあった。
あれから、少し久鬼と話し込んできたので、もう遅い時間になっている。深雪がこんな時間まで待っていてくれたことが嬉しかった。その気持ちを、大鳳は素直に出せないだけなのだ。
「いけなかった?」
「いけなくはないさ。でも、もう、こんな時間だ――」
「いいじゃない」
普段の深雪に似合わず、言葉の感じが硬かった。
教室には、大鳳と深雪のふたりだけである。
「あなたを待っていたかったのよ」
「ぼくを?」
深雪がこくんとうなずいた。
子供っぽいその
深雪は、頰を赤くしていた。聴きようによっては、愛の告白ともとれる
その話題から遠ざかるように深雪が
「どうだったの?」
「どうって――」
「久鬼さんと坂口さん」
大鳳は手短に、さっきの出来事を語った。
「よかったわ。わたし、もっとひどいことになるかもしれないって思ってたの。でも、大鳳さんが久鬼さんに呼ばれたの、これで二回目ね。あの人と、いったいどういう関係なの――」
「特別な仲じゃないんだ」
「あの女の人とも?」
言いながら、深雪はうつむいた。
「女の人?」
「今朝、久鬼さんと一緒にいた
ちょうどひと月前、やはり、大鳳が久鬼に呼び出される前、由魅は大鳳に会いに来ていた。坂口とは、それが原因で、ひと
「何でもないよ」
答える大鳳の脳裏に、
――そうか。
ふいに、大鳳の心にひらめくものがあった。
深雪は、由魅に
そう想ったとたん、心臓の鼓動が速くなった。
「でも、あの女は、何だか大鳳くんに興味があるみたい」
「そんな」
「あの女の大鳳くんを見る眼を見れば、わかるわ――」
「――」
大鳳は、何と言っていいのかわからなかった。言葉が見つからないのだ。
由魅にひかれる自分と、深雪を
「素敵な人ね、あのひと……」
「――」
「わたし、子供っぽいから――」
深雪の声が、細く、かすれていた。
大鳳の頭は、かっと熱くなっていた。深雪に対する愛おしさが、かつてない強さでこみあげた。細い、温かい彼女の身体を、できるだけ自分の肉体のそばにひき寄せたかった。女の体温を、心ゆくまで自分の身体に感じてみたかった。
座ったままうつむいている深雪に近づき、大鳳は、その肩に手を置いた。
細い肩だった。
手を伝って、大鳳から深雪に向かってゆっくり流れていくものがあり、深雪から大鳳に流れてくるものがあった。
「おれ……」
大鳳が言った時、深雪が立ちあがってしがみついてきた。
大鳳も、夢中で抱きかえしていた。
腕の中に、柔らかな肉の温もりがあった。深雪の身体が、小刻みに震えていた。
これ以上は、もう無理なくらい、大鳳は腕に力を込めた。
初めて腕にした女の身体だった。それだけで、しびれるような甘い快感が体中に広がっていた。
深雪の髪の匂いが、大鳳の鼻をくすぐった。
髪の中に、大鳳が手を差し込むと、深雪が顔を
ふっくらとした、唇が見えた。
その唇に、大鳳は、自分の唇を重ねていた。
大鳳にとっても、深雪にとっても、それは初めての異性の唇だった。
濃くなりかけた闇が、教室内に、静かに漂っていた。
「いい図だなあ、おい――」
薄闇の中に、ふいに低い男の声が響いた。
ふたりは、びくっとして、あわてて身体を離した。
入り口近くにある灯りのスイッチが入り、パッと室内が明るくなった。
そこに、坂口が立っていた。
まわりに、さきほどの四人の男たちもいた。
「遠慮はいらねえ。続きをやってくれ」
坂口が言うと、男たちが、下卑た歓声をあげた。
「ねえ、あなたン」
「やめちゃいや」
「おっぱいを触ってちょうだい」
女の声をまねて、鼻にかかった声を出す。
「やめてくれ!」
大鳳は叫んだ。
口笛が鳴った。
若い女――それも深雪のような女性にとっては、これにまさる恥辱はなかった。初めての口づけの現場を見られ、しかも、それをネタにからかわれているのである。
深雪の眼に、涙がうかんでいた。
大鳳の身体が、さっきとは別のもので、熱くなっていた。
「やめろ!」
大鳳がどなると、騒ぎがいっそうけたたましくなった。
「一人前なのは、逃げる時と、女をからかう時だけか――」
ほんのひと月まえなら、まるで信じられない台詞が、大鳳の口から飛び出していた。
男たちの顔色が変わった。
ついさっきの、己のみっともない逃げっぷりを人前にさらした心の傷が、まだ残っているのである。大鳳の言葉がその傷をえぐったのだ。
だが、その言葉に一番驚いているのは、男たちではなく大鳳だった。以前なら、どんなことがあろうと、相手の暴力から逃げることだけを必死に考えるはずの自分が、まるで逆の言葉を口にしていたからである。
大鳳の頭に血がのぼっていた。
「ケンカを売ろうてえのか」
坂口が、ドスの利いた声で言った。
ヤクザも舌を巻くほどの
「おもしれえ」
のっそりと歩いてくる。
軽く右足をひきずっていた。
「どうしたんだ、その足は。逃げる時にでも転んだのか」
と、大鳳。
「ふん」
「最後にやった
「なに!?」
「久鬼に、あの時、右足の指をどうにかされたんだろうが」
坂口の顔が、どす黒く
「そうさ。親指の関節をはずされた――」
「それにしてはみごとな逃げっぷりだったじゃないか」
「必死だったからな」
「顔色が悪いぜ」
「やつは人間じゃねえ。あれは、空手の技でもなんでもねえ。生まれつきってやつだぜ。こいつは、野郎と向きあった者にしかわからねえだろうけどよ」
「――」
「おれもな、少しは腕に覚えがある。相手があの阿久津ならともかく、久鬼なら、どんなにやつが腕がたとうがなんとか料理できる自信があった。身体の大きさが違うんだ。二、三発は殴られても、こっちが一発決めればそれで終わりだとな――」
「そうはいかなかったんだろう」
「ああ。向きあったとたんにな、ぞっとしたんだ。ほんとならあそこで逃げ出したかったところよ。あれ以上やっていたら、こんな足の指くらいじゃすまなかったろうよ。ついさっき、久鬼があの女と帰るまでは、学校にはとてももどる気分にゃなれなかったぜ――」
久鬼と由魅とが一緒に帰ったと知らされた時、大鳳の胸に、軽い痛みが走った。
あのふたりがどういう関係なのか――。
深雪と初めての
「おれはよ、この学園をやめるぜ――」
「何だって」
「あたりめえだろう。おれより強いやつがいるところなんぞにいられるか。あの阿久津とぶん殴りっこをして、勝ったの負けたのと言ってるんならいいが、久鬼はいけねえ。あいつは毒ヒルみてえなもんさ。毒ヒルにたかられるよりは、ライオンの口の中に手を突っ込む方が、まだマシってものさ――」
苦々しく吐き捨てた。
すぐ近くから、大鳳をねめあげる。
「大鳳、
大鳳と深雪の背後に、四人の男がまわり込んでいた。
「逃がすんじゃねえぞ」
坂口の眼が、
大鳳は、自分と深雪とが直面している事態の
4
校舎の裏手――
西側の雑木林の中である。
大鳳と深雪を、五人の男が取り囲んでいた。
大鳳の正面に、坂口が立っている。
「ね、やめて――」
深雪の声が空しく響く。
「へ。大声を出すんなら、さっき教室にいる時にすりゃあよかったんだ。ここまで来たら、あきらめるんだな」
背後の男のひとりが言う。
大鳳の興奮はもはや
――何故、あんな挑発的なことを言ってしまったのか。
おとなしくしていれば、こんな目に遭わずにすんだのだ。
熱にうかされていたのだ、と想う。最近になって、精神のバランスがどこかおかしくなっているのだ。
彼等に囲まれ、ここまで来るうちに、大鳳は、これまで自分がよく知っている人間にもどっていた。彼等の、ギラギラする生臭い暴力の波動が、大鳳を極端に
完全に
ついさっきまで、いくらかなりとも、己が強くなったと感じていたことが、まるでウソのようである。
こうなっては、もはやだめである。
足がガクガクと震えそうになるのを、かろうじてこらえているだけだった。そこにへたり込み、泣いて許しを
「さあ、ここで、さっきの続きをやってみろよ」
「全部やっちまったっていいんだぜ」
「やり方がわからねえのかい」
男たちが輪を縮めてきた。
ほの暗い林の中で、彼等の黒い影がいっそうその威圧感を増していた。
「おい、なんだ、こいつ震えてやがるぜ」
男たちのひとりが、驚いたような声をあげた。
それが、たちまち
「見ろよ。この色男、今にもションベンたれそうな面してやがる」
「もらしちまいな。裸で帰ればいい」
「おかあちゃん」
「織部にパンツをかえてもらえ」
先ほど、ぶざまな逃げっぷりを大鳳に見られている分だけ、彼等のいたぶりは
「何とか言えよ」
彼等のひとりが、どんと肩を突いてきた。
大鳳は反射的にそれをよけていた。
「ちっ」
男が軽く
それも大鳳にはあたらなかった。大鳳が身を沈めたのだ。
無意識の動作だった。
男の顔が、さっと赤く染めあがった。
「てめえ!」
本気で突っかかってきた。
自然に、大鳳の身体がその拳をかわし、大鳳は、その男の頰に掌を
大鳳は、頭がかっと熱くなり、ぼうっとなった。生まれて初めて人を殴ったのだ。
おそろしい恐怖が大鳳を捕らえていた。
――殴ってしまった。
もう取り返しがつかない。自分は、男たちに徹底的にやられてしまうだろう。
男が起きあがって頭から大鳳の腹に突進してきた。
ぶつかった。
大鳳は、身体をくの字に折って
「おら、おらあっ」
男が、大鳳の胸元をつかみ、草の上からひきずり起こした。
深雪が悲鳴をあげた。
坂口が、背後から深雪を捕まえた。
「逃げるんじゃねえ。これがすむまでな」
それを視界の隅に捕らえた瞬間、大鳳の顔面に、熱いものが爆発した。男の拳がきれいに入ったのだ。
大鳳は、近くのクヌギの幹に、後頭部をぶつけた。男が、なおも殴りかかってくる。
「やめて、くれ――」
つぶやく大鳳の
幹からひきはがされ、激しく突き飛ばされた。三人の男が、倒れそうになる大鳳を抱きかかえた。
「まだまだ」
「これからこれから」
腹を
口の中が、生臭いものでぬるぬるしていた。血だった。鼻の方からまわってきた血もあった。
「おい、こいつのあれを、この女に見せてやろうぜ」
大鳳は、草の上に仰向けに転がされた。
四人がかりで、そこに押さえつけられた。ひとりが、大鳳のズボンのベルトに手をかける。
彼等の意図を知り、大鳳はめちゃくちゃに身体をゆすって暴れた。
「おっとっと――」
四人が、さらに力を込める。
ベルトがはずされ、ファスナーが下ろされた。強引に、下着ごとズボンを引き下ろす。
「織部、よく見ておけ。これがおまえの好きな大鳳くんのあれだぜ」
「顔をそむけないで見ろよ」
「初めてかい、こいつを見るのは」
「これはよ、早いとこあんたのあそこに入りたがって、うずうずしてんのさ――」
屈辱で、大鳳の顔面がまっ赤に染まっていた。深雪が、眼をそむけていてくれることを願った。
女の眼の前で、こんなに悔辱されて、何もできない自分が情けなかった。自分で自分をくびり殺したかった。
何でこんな目に遭わなければならないのか。
おれが何をしたというのだ。
いつだって、こっちが避けようと思えば思うほど、むこうの方から暴力がやってくるのだ。おれは、磁石のように暴力を吸い寄せてしまうのだ。
およそ一カ月間、円空山で学んだ
「大鳳だけじゃあ不公平だなあ」
坂口が、ぼそりと言った。
自分の思いつきに、舌なめずりしているような声だった。
大鳳の背を、寒気に似た恐怖が貫いた。
「織部のを、大鳳にも見せてやらなくちゃあな」
「やめろ、彼女は関係ないんだ」
「そうはいかんさ。おれは、不公平が嫌いなんでね」
深雪の細い悲鳴が、高く夕闇の大気を貫いた。
坂口の大きな手が、深雪の胸元に差し込まれていた。制服の下、胸のあたりで手が動いているのは、なまじ見えるより
「いや。いやよ。大鳳くん、助けて――」
深雪が大鳳の名を呼んだ。
大鳳は歯ぎしりをした。きりきりと歯が音をたてた。身体中の血が、今にも煮えたぎりそうだった。
「そうれ!」
半分引きちぎるようにして、制服とブラウスがぬがされた。ブラジャーのヒモが切れ、胸があらわになっていた。
両手で胸を隠そうとする深雪を、坂口が後方から邪魔をしている。大鳳を含め、男たち全員の視線が、乳房にそそがれていた。
小ぶりだが、形のよい乳房だった。肌の色が、薄闇に白く鮮やかだった。坂口に、右腕を上後方に捕られているため、右の乳房が薄くなって、少年の胸になっている。
一瞬、それだけの光景が大鳳の眼に焼きついた。
「見ないで! 大鳳くん、見ないで!!」
大鳳は狂おしくもがいた。
今ほど、自分に力が欲しいと思ったことはなかった。大鳳の視界が、赤い闇で閉ざされた。頭に血が昇り、怒りで眼がくらんだのである。
四人でも押さえきれぬほど、
不気味な獣の声だった。
肉体が熱を帯びていた。
熱かった。炎に焼かれているようだった。その炎からのがれるように、大鳳はもがいた。
肉体の底の一番奥――そこに、何かが生じていた。黒い、不気味なエネルギーの塊のようなもの。それが、見るまに大鳳の内部にふくれあがってくる。
獣の叫びを喉からほとばしらせながら、大鳳は恐怖の悲鳴をあげた。
黒い塊――それは、大鳳の肉体につかえていた。まるで、その黒いエネルギーが巨大すぎて、大鳳という通路では小さすぎるかのように――。
ぶっつりと大鳳の肉体が深い所で破けた。
それが、大鳳の肉体をきしませながら、頭を持ちあげた。もぞり、とそれが
それが、どっと体内にふきあげた。
黒いエネルギーが、大鳳の身体に満ち、あふれ、なお足りずに爆発した。
その瞬間、恐怖は消えていた。
大鳳の身体から、四人の男たちが跳ね飛ばされていた。
男たちが地に転がった。
「野郎!」
男のひとりが立ちあがりかけた。
その男に向かって大鳳の身体が、
三人の男が、大鳳に飛びかかる。
ひとりの男の手にはナイフが握られていた。
大鳳の身体が一瞬縮み、次の瞬間に、大鳳は宙に舞っていた。大鳳は、軽々と三人の頭上を越えていた。猿というよりは、もう鳥であった。
三人の男には、まだ何が起こったのか信じられなかった。完全にど肝をぬかれていた。
大鳳の下半身が裸であるというのも、男たちにとっては不幸だった。上が学生服、下が裸の大鳳をなめてかかる気持ちと恐れとが、ぶつかり合い、正常な判断ができなかったのである。
久鬼にそうしたように、男たちはひたすら逃げ出すべきだったのだ。
その戦いは、まるで、
細身の大鳳が、完全に三人の男を圧倒しているのである。
三人の男が、大鳳の足元に転がっていた。
ひとりの男は、あばら骨を折られていた。
もうひとりの男は、前歯をへし折られ、顔面を血だらけにしていた。
最後の、ナイフを持っていた男は、そのナイフで自分の
一番被害の軽かったのは、最初にやられた男であった。
「大鳳、てめえ――」
そこにつっ立ち、燃える眼で自分を見つめている大鳳を見て、坂口は言葉を
大鳳は、幽鬼のような形相をしていた。
美しい顔が
坂口の全身の毛がそそけ立っていた。
大鳳が、走った。
走りながら
人間の声ではなかった。
坂口が、恐怖の叫び声をあげなかったのはさすがであった。
大鳳のその攻撃から己を守ったのは、この男の、したたかな、天性の闘争本能だった。
坂口は、大鳳に向かって、深雪を突き飛ばしたのだ。
大鳳が、横に跳んで深雪をよけた隙に、坂口はおもいきり走り出していた。しかし、逃げきれるとふんだのは、大鳳の能力に対する坂口の誤算であった。坂口は、深雪を離すべきではなかったのだ。
雑木林の出口に達しかけた時、ざっと頭上の
黒い影が、坂口の前に落ちてきて、草の上に立った。
大鳳だった。
大鳳が
すごい
坂口が、腕をクロスさせてそれをブロックした。そのブロックごと、坂口の身体がふっ飛んだ。
木の幹にもろに後頭部を打ちつけ、坂口は気を失ってそこに倒れた。
大鳳は、坂口の上に馬乗りになり、狂ったようにパンチをあびせた。何かの快感のようなものが、坂口を殴るたびに、肉を貫いて走った。
血の匂い。
大鳳は酔いしれていた。
おもいきり殴った。肉がひしゃげ、骨がきしむ。
殴った。
殴った。
何ものかに
「やめて、坂口さんが死んじゃうわ!」
深雪が、血だらけの大鳳の拳にしがみついて、必死に叫んでいた。
大鳳は我に返った。
深雪の、涙で汚れた顔を見たとたん、ふっと意識が遠のいた。
大鳳は立ちあがった。
足がふらついた。視界がまっ暗になっていた。自分はどこにいるのかと思った。
両の拳が、ひどく痛かった。
疲れていた。
たとえようもない脱力感と解放感があった。
身体が、死ぬほど熱かった。
このまま横になったらどんなに楽だろうと思った。
思ったとたん、自分の身体が斜めになっていくのがわかった。
どん、と、地面が身体に触れた。
大鳳は、草の上に、楽々と
草が頰に触れている。
冷たくていい気持ちだった。
女の叫び声が聞こえたように想った。
自分の名を呼んでいるらしかった。
いい気分だった。
最高だった。
その草の感触と、女の声とが、大鳳がその時最後に感じたものであった。
大鳳は、眠りに落ちていた。
深雪が大鳳の額に手をあてると、そこは火のように熱かった。
KADOKAWA Group