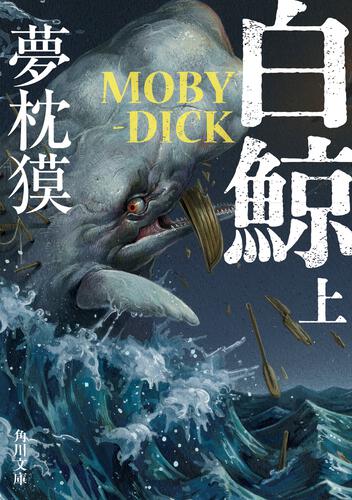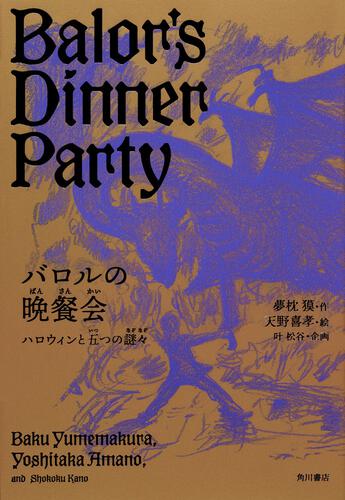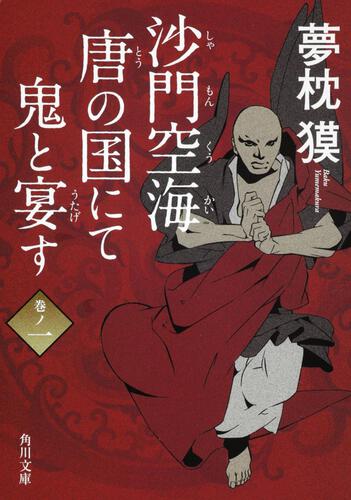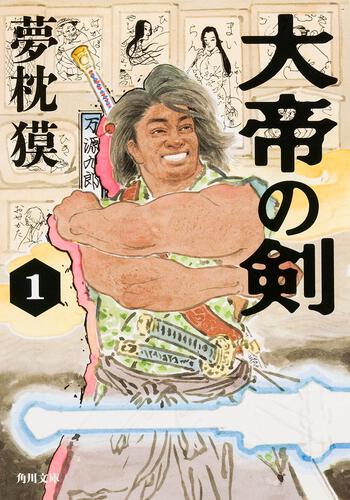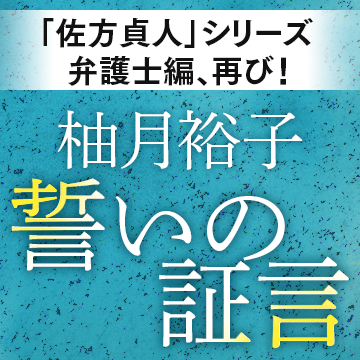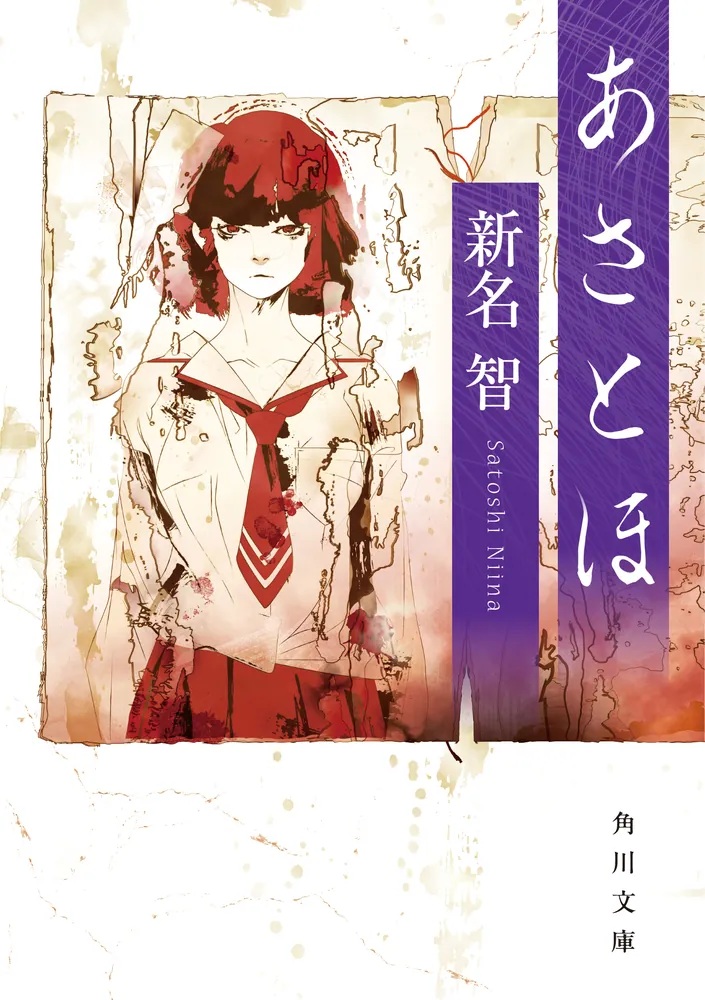二章 円空拳
1
誰もいないと思っていた教室に、ただ独り、織部深雪が残っていた。
「大丈夫だったの?」
大鳳が入ってゆくと、それに気づいた深雪が声をかけてきた。
「大丈夫さ」
「心配しちゃったわ。空手部の人なんかに呼び出しをかけられたんですもの――」
「それで、ぼくを待っていてくれたの?」
言ってしまってから、大鳳は
ひどく露骨なことを
頰が熱くなった。
深雪は、頰を染めて眼をふせていた。
「よかったわ」
眼をふせたまま、深雪が言った。
まぶたが桜色になっている。
大鳳は、ふいに、深雪を抱き締めたい衝動にかられた。
自分のことを待っていたらしい少女に、
男の肉体に突然襲ってくる、あの嵐のような激しい渇望だ。
深雪の、細っそりした身体を抱き締め、服をぬがし、成熟しきってない乳房を、手のひらに思いきり感じてみたかった。
自分が、ひどくいやらしい獣に変わってしまったような気がした。
男は、誰でも、皆、自分の中にこのような獣を飼っているのだろうか、と大鳳は思った。
目の前にいる、この少女の肉体の中にも、このような嵐が吹くことがあるのだろうか。
深雪が眼をあげた。
きれいな黒い瞳が、あどけない、といってもいいくらいの表情で、大鳳を見ていた。
大鳳は、自分の内にふきあげる、暗い欲望を、すべてその眼に
「ありがとう」
恥ずかしさをまぎらわすように、大鳳は、必要以上に大きい声で礼を言った。
外へ出る。
深雪と一緒だった。
校門の前で、九十九が待っていた。
「おやおや」
ふたりを見ると、九十九は太い指で頭をかいた。
「まいったなあ」
まるでまいってはいない口調で言う。
大鳳が深雪を紹介すると、九十九はぬっと巨大な右手を差し出した。
「九十九
深雪の手を握った。
深雪の、白い、
「ずいぶん大きいんですね」
深雪は、九十九を見あげながら言った。
声に賛嘆の響きがある。
まったく
「身長、どのくらいあるんですか」
歩き出しながら、深雪がたずねる。
「一九〇センチくらいかな。もっとも、計ったのはだいぶ前だから、一、二センチは伸びてるかもしれない」
「わたし、一五六センチだから、三五、六センチも違うのね」
三人で歩いていると、九十九だけが、頭ひとつとび抜けている。
九十九も大鳳も、鬼道館でのことは、ひと言もしゃべらなかった。深雪も、気をきかせているらしく、そのことについては訊いてこなかった。
「じゃあ、わたしの家はこっちだから――」
しばらく歩いたところで、深雪が立ち止まった。
別れ際に、深雪は、子供じみた
「さようなら、また明日ね――」
深雪と別れ、歩き出したとたん、九十九が、
「いい
「はい」
「邪魔をしちまったかな」
「違います。まだ、そんな――」
大鳳はあわてて言った。
「何が違うんだ」
九十九が、おもしろがって言う。
大鳳は言葉をつまらせた。
笑いながら傍らを歩く九十九に、大鳳はとりつくろうように言った。
「九十九さん」
「なんだ。女の相談なら断るぞ。そっちの方はからきしだめなんでね」
「そうじゃありません。九十九さんは、前から久鬼さんのことを知ってるんですか」
「ああ」
「小田原には、来たばかりなんでしょう。これまで大阪にいたって――」
「いたよ。しかし、大阪に行く前には、こっちにいたのさ。西城学園には、一年の時に半年だけいた。それが親父の仕事の都合でね、しばらく大阪の高校へ行ってたんだ。もともとは小田原の人間さ。この春、親父がこっちにもどることになったんで、一緒にもどってきたってわけさ――」
「何か、スポーツ――いや、空手か武道のようなものをやっているんでしょう」
「わかるか」
「昨日、指先で、菊地さんの背中のどこかを軽く突いたでしょう」
「おやおや」
九十九の声の中に、
「あれが見えたのか」
「いえ。すごく速くて、よくわかりませんでした。そんなような感じだったんです」
「たいしたものだよ、大鳳。言う通りさ」
「九十九さんは強いんでしょう」
「ああ、強い」
あっさりと言った。
九十九のあっけない言い方は、かえって真実味があった。
普通の者なら、自分の腕にいくら自信があっても、たいしたことはない、と
「どのくらい強いんですか」
「そうさなあ」
九十九は、暮れかけた空を見上げた。
「まあ、相当なものだろうな」
ぬけぬけと言う。
それだけ聴いていると、あまり強そうな感じはないが、実際にその巨体と肩を並べて歩いていると、何気ない言い方でも迫力があった。
「ぼくでも強くなれますか」
考えあぐねて、ようやくといった風に、大鳳が言った。
「さて――」
九十九は立ち止まって大鳳を見た。
大鳳もつられて立ち止まる。
「強くなりたいんです」
大鳳は、挑むような眼で九十九を見た。
「そりゃあ強くはなれるだろうな」
「本当ですか」
「もちろん。少なくとも今よりはね。しかし――」
「――」
「自分より強くなることは無理だぞ」
「自分?」
「そう。本人が、本人より強くなろうとしたら、自分を滅ぼしてしまうだろう」
「どういうことですか」
「わからなくてもいい。今、ちょっとあんたの眼を見ていたら、ふっと、思い出したのさ」
「何をですか」
「久鬼のことさ。あいつも昔はそんな眼つきをしていたよ」
「久鬼さんが?」
「ああ」
「円空山とか言ってましたが――」
「雲斎先生のことか」
「はい。九十九さんは、そこで空手を習ったんですか」
「そんなところだ」
「ぼくをそこへ連れて行って下さい。さっき、円空山へ行くと言ってました」
「ふむ」
九十九は、がっしりした
「それもおもしろいかもしれないな。雲斎先生に、おまえを会わせてみたくなってきたよ」
2
ふたりは、箱根
夕刻である。
あたりはもう薄暗い。
ミカン畑の中を一五分ほど登り、まばらな雑木林の中に入った。雑草の多い
「これが円空山さ」
九十九が言った。
「この家がですか」
「そうさ。もっとも、雲斎先生が勝手にそう呼んでるだけだがね」
「お寺みたいですね」
建物のことを言ったのではない。
大鳳はそのことを思い出したのである。
「そんなところだな」
九十九が、入り口の上にかかった表札を指さした。
『円空山・
とある。
大気の中に満ちている夕陽の残光が、木の板に書かれた墨の文字を、薄く照らしていた。
「どうも留守らしいな」
家の気配をうかがってから、九十九がつぶやいた。
「家の人はいないんですか」
「先生は独り暮らしさ。たぶん畑か山芋だろう。なあに、待っていればすぐに帰ってくるさ――」
九十九が、風雨にさらされ尽くした木の引き戸に手をかけると、留守だというのに意外とすんなり戸が開いた。
「さあ、入るといい」
大鳳を先に入れ、続いて九十九が入ってきた。
まず、土間があった。
続いて板の間があり、
思ったよりも広い。
一見、古風な小屋暮らしと見えたが、九十九が
ビデオ付きのカラーテレビ、最新のオーディオ・セット、冷蔵庫と、ひと通りの電気製品がそろっている。
囲炉裏の前に、
「相変わらずだな」
口に笑いをためて、九十九は、囲炉裏の前に、どっかり
大鳳も、そこに胡座をかいて座った。
――真壁雲斎。
いったいどんな人間なのか。まるで見当がつかなかった。
「どういう方なんですか」
大鳳は、壁の本箱に眼をやりながら言った。
本箱には、動物の写真集から、コミック、小説、科学書が、いずれも同じ比重で収められ、こちらに背表紙を向けていた。
「戻ればわかるさ」
九十九が楽しそうに言う。
真壁雲斎と九十九とは、だいぶ親密であるらしかった。
「そうだな。ちょっと試してみるか」
九十九が、何か思いついたらしく、大鳳に眼で合図した。
「大鳳。いずれ、先生が帰ってくるから、その時、入り口で待ち伏せして、先生をぶん殴ってみるか――」
時代劇めいたことを言う。
「殴るって、ほんとうにですか」
「おもいきりやってもいいぞ。戸の横に立っていて、先生が来たら好きなやり方でぶん殴ってやればいい。そのへんの棒きれを使ってもかまわないぞ――」
「だいじょうぶなんですか」
これが時代劇であるなら、武者修行の若者の一撃を、名人が
「わからんなあ」
とぼけた顔で言う。
「まあ、
「おいおい」
その時、いきなりどこからか声が聞こえてきた。
「ぶっそうな話をしとるなあ」
不思議な温かみをもった、男の声だった。
「先生――」
九十九が本箱の方に向かって言った。
本箱が、ごとごとときしりながら横に動き、そこから白髪の男が出てきた。
「挨拶がわりに
怒ったように言ってはいるが、声には、たっぷりと愛情がこもっているのがわかる。眼が笑っていた。
「そんなところにおられたとは知りませんでした。先生はずるい」
「何を言いやがる。勝手に人の家にあがり込んでおいて」
「いつ、そこにそんな部屋をお造りになったんですか」
「ふふん」
口元をひゅっと
ジーンズに、綿のシャツの
白髪さえのぞけば初老といった感じだが、若者のような服装だった。それが、不思議とよく似合っている。
「大阪で、頭がボケよったか。一年以上もたてば、ここがビルになっておってもおかしくはないわ」
「先生にはかないません」
「殊勝なことを言いおる」
言いながら、雲斎は、どん、とぶっきらぼうに、囲炉裏の前に胡座をかいた。
「みやげはないのか」
「残念ながら――」
九十九が言うと、雲斎は、ちい、ちっ、ちっと舌を鳴らした。
「そんなことでは、出世できぬぞ。せいぜいがわしみたいなところだ」
「その先生のように、なりたくて――」
「ちえっ。大阪でなろうたのは、世辞だけか」
「この大鳳がみやげのかわりです」
九十九が、初めて、大鳳を雲斎に紹介した。
大鳳は、ぺこりと頭を下げた。
「ほほう」
雲斎が、大鳳を見つめて、おもしろいものを見つけたような声をあげた。
大鳳の眼をじっと見すえ、
「
ぼそりと言った。
「やはりそうですか」
「うむ。あれと同じような眼をしている」
「久鬼とでしょう」
「いかにもな――」
「久鬼さんと?」
大鳳がようやく口を開いた。
「さようさ。もう久鬼とは会ったのか」
大鳳はうなずいた。
「この大鳳は、初対面の久鬼に向かって、おまえなど嫌いだと言ったのです」
九十九が、その言葉を用意していたように言った。
「ほう。あの久鬼に向かってか」
「はい」
「そいつは見たかったな」
雲斎が眼を細めた。
「違います。好きになれないと言ったんです」
大鳳があわてて言った。
「同じようなものさ」
九十九が、やはり眼を細めて言う。
「久鬼さんを知っているんですか」
大鳳が、雲斎に向かって言った。
「昔、ここでな、この九十九めと一緒に、わしから
「円空拳?」
「名前はご大層だが、たいしたものではない。赤子の
「空手か何かですか」
「本当は違うが、素人目には、まあ、同じようなものであろうな」
「その円空拳を習えば強くなれますか」
大鳳は、先ほど九十九に言ったのと同じ言葉を口にした。
「ほう」
真剣な大鳳の顔を、含み笑いをためながら、雲斎は眺めた。
「おぬし、強くなりたいのか」
「はい」
「正直な男だな。何のために強くなりたい?」
「強くなれば、自分に正直に生きることができるからです」
「別に、ケンカに強くなくとも、自分に正直に生きることはできようが――」
「それは理屈です」
「ふむ」
「暴力に屈して、自分のプライドを捨てねばならないことが、今までに何度もありました。昨日は、九十九さんが助けてくれなければ、お金をとられるところでした――」
雲斎は、じろりと九十九を見た。
九十九は、どっしりと座ったまま、じっとふたりのやりとりを聴いている。
「何もな、腕力が強いだけが暴力ではないぞ。金のために、おぬしの言うプライドとやらを捨ててきた人間を、わしは何人も知っとるよ。今の世で、本当に自分を守りたかったら、金をためればよろしい。しかし、全てでも万能でもないがな」
「では、人は弱くてもいいんですか」
「そうは言うとらんよ。ケンカに強いか弱いかなんぞは、この世の中のいろんな競争のひとつにしかすぎぬということさ」
「でも、強ければ、自分に自信が持てます」
「金がしこたまあるだけでも、絵がうまいだけでも、自分に自信を持つことはできる」
「ですから、それは理屈です。ぼくは強くなりたいんです」
「強くなる、ということには限度がない。いくら強くなっても、世の中にはもっと強い者がいるだろう。結局その者には、頭があがらなくなる。もし、この世で一番強い人間になったところで、相手が銃を持っていたら終わりだ。ズドンと一発やられ、それまでということだな。それに、人は歳をとる。歳をとれば、いずれ若い者には負けてしまうぞ」
「ではどうすればいいのですか」
「ま、争わぬことだな。争わねば負けることはない――」
「それは
「いかにも詭弁さ」
ぬけぬけと言う。
大鳳は、自分がからかわれているような気がした。
大鳳は黙り込んだ。
「また先生の説教癖が始まりましたか」
九十九が言った。
「まあ待て。よい気分だからもう少し言わせろ――」
雲斎は、一升ビンから
「大鳳は、先生から円空拳を習いたがっているのです」
「わかっておるわ」
残った焼酎を飲み干した。
大鳳は顔をあげ、雲斎に、挑むような視線を向けた。
「ぼくに、円空拳を教えて下さい」
「怖い顔をするな。教えてやらぬと言ってるわけではない。おまえたちに、ちょっと見せておきたいものがある。こっちへ来なさい。話はその後だ」
雲斎は立ちあがり、本箱をごとごとと開けて、中へ入って行った。
「早う来んか、九十九。おぬしのようななまけ者には縁のないシロモノだが、見ておいて損はないぞ――」
大鳳と九十九は、雲斎の後からその部屋に入って行った。
3
「どうかね。ん?」
雲斎が、
「こいつはまた驚いたなあ」
九十九は、それに手を触れて素直な声をあげた。
「パソコンですね」
と大鳳。
せまい部屋であったが、がっしりしたテーブルの上に、でんとそのパソコンとその周辺機器がすえられていた。安ものではないらしい。
ふたりの反応を、楽しそうにうかがっていた雲斎は、とん、と片手をそのパソコンの上に乗せた。
「さよう」
「これを先生がいじられるのですか」
「いかにも、ぬしのお師匠どのがいじられるのさ。今日び、このくらいのものがいじれぬでは、話にならぬぞ」
「多少はやりますが、おれは、どうもこういうのは苦手だ」
「ぬしなどがこいつをあつかうと、脳みそがひきつけを起こしてしまうわ。前からも言っておろうが、九十九。強いだけでは、ゴリラとかわらぬぞ」
「ゴリラというのは、あれでなかなか、気の優しい動物ですよ」
「わかっておるわ。たとえばの話よ」
「それで、何のためにこんなものを買ったのですか」
「道楽よ」
「道楽?」
「今は、もっぱらゲームをやって楽しんでおる」
「なんだ」
「なんだではない。ゲームのソフトは、皆、わしがたたき込んだものばかりだぞ」
「どんなゲームなんですか」
「まあ、見ていろ」
スイッチを入れた。
画面の左側に、小さな人の形が現れた。
大人の女を横から見た像である。
画面の右側に、もうひとり人がいる。それは、やはり裸の男であるらしい。ちょうど、腰のあたりから、棒のようなものが、ちょんと前に突き出ている。
「なんですか、これは」
「男のあれだよ」
雲斎がニヤリとする。
「始めるぞ」
雲斎が言ったとたんに、女が逃げ出した。
画面の中に、道を表す区画があり、女はその中を逃げていく。
男が追う。
あっというまに女がつかまった。雲斎はこのゲームに慣れているらしい。後方から女をつかまえた男の腰から突き出しているあれが、女の尻に差し込まれている。
女の姿が数度明滅し、男と女が離れた。
女の腹がふくれていた。妊娠したという意味らしい。
女の腹から、三人の小さな人の姿が出てきた。
男の腰から突き出ていたものが、下にたれている。こんどは女が男を追い始めた。
男が逃げる。
「どうだね」
スイッチをいじっていた手を休めて、雲斎が言った。
男はたちまち女につかまり、女が男の上に重なった。男の姿が消え、それでゲームは終わりになったようであった。
「いい趣味とは言えませんね」
「これからが、ほんとはおもしろくなる。あの逃げていた男な、あの男が二〇秒逃げ切ることができれば、またあれが立つ仕組みになっておってな、女はまた逃げねばならんようになっておる。それから、三人子供が生まれたろうが。二〇秒するとあれらもまた大人になってな。ひとりは女、ひとりは警官、ひとりはおかまになる。警官の見ている前で女に触れると、警官がとんできて、警棒でなぐられる。しかし、この警官もおかまには弱い。おかまにつかまってほられてしまうと消えねばならぬ。男が女に追いかけられている時は、おかまにつかまれば良い。ほられているあいだは、女は男に手が出せぬようになっている。おかまどうしがぶつかるとふたりとも消えてしまう。それにな、四人にひとりの割合で、警官も男に変身するのだよ――」
雲斎の口調は、まるでくったくがない。
「そいつはひどい」
少しもひどくなさそうに九十九が言う。
「今日はな、一日中こいつで遊んでおった」
「一日中ですか」
「うむ。しかしまだこのゲームの名を考えてなくてなあ。何か良い名はないかね。『鬼ごっこ』なんてのは、いまひとつという感じかな。どうかね、大鳳くん。他にも色々わしの作ったゲームがあるのだが、いい名前を考えてくれんかね――」
「見せたいもの、というのはこのことだったのですか」
大鳳は、何か、肩すかしをくわされたような気分だった。しかし、どこかひょうきんなこの雲斎に、不思議と怒りはわいてこない。つかみどころがなく、憎めないものがあるのだ。
その辺の感じは、九十九とこの雲斎とはどことなく似たものがある。
小田原でも山に近い所で、山小屋のような家に住んでいるくせに、そこでコンピューターをいじくっている。しかも、円空拳とかいう拳法を教えているらしい。底の知れない男だった。いや、男、と呼ぶよりは、老人と呼んでもいいほど、枯れた雰囲気もある。
「いかにも。これを見せたかったのよ。そのうちに、わしの知っている中国拳法の技をみんなこいつにぶち込んでな、色々な派の技が、どのようにしてできあがってきたのか、派と派との関係などを調べて、一冊本でも書こうかと考えてるのさ。ま、しかし、しばらくはこの新しいゲームを考えるのがおもしろくてなあ。そこらで
雲斎は、大鳳の胸の内をさぐるように、大鳳の眼を
「どうかね。月に
ふいに言った。
「――」
大鳳は、何を
「大鳳――。月に一本焼酎を持って来れば、ここへ円空拳を習いに来てもいいと、そう先生がおっしゃってるが、どうだ。焼酎一本で、
「ぬかせ、このたわけが。一人前の
雲斎が苦笑している。
「いいんですか!」
大鳳は声をはずませて言った。
「まあ、な」
「お願いします」
「しかし、ひとつだけ条件がある」
「円空拳だけに
雲斎は
「これは、麻薬よ」
「麻薬?」
「わかりました」
「正直に、手っとり早く言えばな、拳法など、
「はい」
「その竜眼におもしろみがありそうなんでな。まだはっきり眼に出ているわけではないが、竜が全部現れたのを見たくなった」
「竜眼? さっきもそんなことを言ってましたが」
「おぬしの中に埋もれている素質のことさ」
「ぼくにどんな素質があるんですか」
そこへ、九十九の声が割って入った。
「先生、大鳳は、おれの
「ほう」
雲斎は、口をすぼめて、大鳳をもう一度あらためて値ぶみするように見た。
「おぬし、九十九の寸指破を見たか」
「寸指破?」
「昨日、菊地をおれが軽く突いたあの技の名さ」
と九十九。
「見たのではありません。そんな感じに想っただけです――」
大鳳は、昨日、九十九が、指先で菊地の背のどこかをちょんと突くのを見たような気がしたのである。おそろしく素早い一瞬であったので、あるいは眼の錯覚かとも思っていたのだ。
その瞬間、菊地の持っていたナイフは九十九の手に移り、菊地は動かなくなっていたのである。
「これは楽しみだな」
「ええ」
と九十九。
「人はな――」
と、雲斎が大鳳に言った。
「人は、強いだけではいかん。しかし、強くもないのはなおいかん。さっきは色々言うたがな、強い、ということと優しいということとは同じだ。『タフでなければ生きられない。優しくなければ生きる資格がない』と、外国人も言うておる。日本風に言うなら、気は優しくて力持ちと、こうでなければな――」
4
「服をぬいでみなさい」
雲斎が、大鳳に向かって言った。
囲炉裏のある部屋にもどってきていたが、三人ともまだ立ったままである。
大鳳は、学生服をぬぎ、シャツ姿になった。
「全部だ」
上半身裸になり、大鳳がさらにズボンのベルトに手をかけると、雲斎は片手をあげて、それを制した。
「ズボンはよろしい」
大鳳は、上半身裸のまま、床板の上に立った。
冷たい夜気が肌に触れていた。しかし、大鳳の肉は、興奮のため熱を帯びていた。
ひき締まった身体である。
ムダな肉というものがまったくない。腹がそいだように薄いが、
「みごとなものだな。もう、それなりにできあがっておるではないか」
「そうですか」
「何かスポーツをやっていたか」
「いいえ、特にこれというものはやっていません」
「学校ではどうであったのだ。足などはけっこう速かったのだろう」
「はい」
大鳳はうなずいた。
中学の時、いや、もの心ついた頃から、大鳳は何をやっても二番であったことを思い出した。長距離を走っても二番、短距離も二番、他のどんなスポーツをやっても、常にひとりかふたり、自分より上の人間がいた。
自分でもわからなかった。
運動神経そのものは、小さい頃から、他人より
――しかし。マラソンをしている時でも、スパートをかければ楽に相手を抜けそうな気がするのに、どうしてもそれができないのだ。
“本気を出せ”
と、よく担任の教師にも言われた覚えがある。
“本気を出せば、おまえはもっと速いはずだ”
しかし、大鳳には、その本気を出す、ということができないのであった。
抜こうとする相手の、ギラギラするような闘争意識がこちらに伝わってくると、急に気力が
普段は何げなく口をきいていた彼等が、いざこういう勝負になると、大鳳がびっくりするほどのどろどろした情念を燃やすのである。
大鳳は、それを敏感に感じてしまうのだ。
競技のあと、さわやかな顔をしているのは、むしろ彼等の方であった。競技中に、あれほど強かった勝負への執着が、勝った者の心からきれいに抜け落ちているのである。
大鳳がのびのびとやれたのは、器械体操くらいであった。
それも授業だけで、特にクラブに入っていたわけではない。
「けれど、いつも二番でした――」
大鳳が言うと、
「ほほう」
雲斎は不思議そうな眼をした。
「だから、円空拳を習いたいのです」
「なるほどなるほど――」
雲斎は、ひどく納得した顔つきになった。
「資格はあるが、生きてはいけないくちか」
うんうんとうなずき、じろりと九十九を見た。
「おい、この大鳳と、軽く手合わせでもしてみるかね」
「は?」
九十九が
「大鳳と軽くやってみなさい。大阪でどの程度の腕になったか、おまえの方も見ておきたい」
「本気でですか」
心細い顔になって九十九が言う。
「馬鹿たれが。おまえに本気でぶん殴られたら、大鳳はぶっこわれちまうぞ。おまえは手を出してはいかん。大鳳のをよけるだけだ。そのかわり、大鳳の方には本気になってもらう」
大鳳は、ぽかんとしてふたりのやり取りを聴いていたが、どうやら、自分と九十九とが試合めいたものをやらされようとしてるのに気がつき、あわてて口をはさんだ。
「無理です。だめです。いきなり九十九さんとなんて、とてもできません――」
「まあまあ、とにかくやってみなさい。九十九はあんたに手を出さないから心配はいらんよ――」
「ですが――」
「それにな、おぬしの
「九十九さん――」
大鳳が九十九を見ると、九十九は軽く肩をすくめて見せ、
「そういうわけだそうだ。まったく、ひでえ師匠を持っちまったもんだ」
「ぬかせ。さっきは、大鳳にわしを殴らせようとしたくせに。大鳳に
九十九は、雲斎の言葉を苦笑して聞き流しながら、数歩あるいて、板の間の中央に立った。およそ二〇畳近い空間がそこにある。
「大鳳。硬くならずにやろうじゃないか。軽い運動をするつもりでいいのさ」
大鳳は、おずおずと九十九の前に立った。
九十九は学生服をぬいでシャツ姿になっているが、大鳳の上半身は裸である。
「さあ――」
九十九が言った。
柔和な眼が大鳳を見ていた。
大鳳は途方にくれていた。だだっ広い所へ、ぽつんと独りでとり残されたような気がした。
どうしていいか、まるでわからないのである。人を殴ったことなどないし、その殴り方すらわからないのだ。
テレビで、ボクシングやプロレスを見たことはある。しかし、それだけで、自分の身体があのように動くものではない。
目の前に立っている九十九は、まるで岩のようだった。
ほとんど構えというものがなく、両足を軽く開き、両腕をだらんと下げているだけである。しかし、それだけで、大鳳を
「喝!」
いきなり、大鳳の背後で、雲斎の激しい声が響いた。
大鳳の肉体を電流のようなものが走りぬけ、大鳳を縛っていた何かの糸が、ぷつんと切れた。
とん、と背を押された。
初めてのパラシュート降下をためらっていた者が、背を押されていきなり空中に放り出されたようなものであった。
恐怖とも、驚きとも、何ともつかない感覚のスパークがあった。雲斎の声が、鋭い刃のように、大鳳のためらいや、自意識を断ち切っていた。
大鳳の身体は、ほとんど無意識のうちに動いていた。夢中だった。
あとで思い出しても、おそらくは相当に不様な格好で、九十九にぶつかっていったにちがいない。
九十九の受けは絶妙だった。
完全に大鳳の身体をかわしてしまっても、がっちり受けてしまっても、大鳳の動きはそこでストップしてしまったにちがいない。九十九は、大鳳を自由にあやつるように動いたのである。
そのまま前に行ってしまいそうな大鳳を自分の方に向かせ、自然に次の手が出るように動く。大鳳の身体にほとんど触れるか触れないかのように、九十九の手足が舞う。それに誘われるように大鳳が動く。
まるで、舞いを舞っているようである。
大鳳は、九十九のリードのままに、身体を動かせばよかった。
夢中で動いていた大鳳に、余裕が出てきた。
空中に放り出され、無我夢中のうちにパラシュートが開き、やっとあたりを見回す余裕が生まれたというところである。
すぐ目の前で、九十九の顔が笑っていた。
「その調子だ、大鳳――」
大鳳の動きが、ぐんぐん良くなっていった。
肉体中の筋肉がほぐれていくのが、自分でもわかった。
肉体だけではない。九十九の顔を見たとたんに、精神そのものが自由になったようだった。
九十九から伝わってくるのは、闘争心でも、ましてや恐怖心でもなかった。九十九はリラックスし、身体を動かすことを心から楽しんでいるのである。それが大鳳にわかった。
初めてのことであった。
つられるように、大鳳の心も落ち着き、思う様自分の肉体を自由に動かしたい気持ちが、ふつふつと沸きあがってきた。
九十九も同様であるのがわかった。
九十九も、もっと速い動きを望んでいるのである。
「足を使ってもいいぞ」
九十九が言った。
その方法を大鳳に教えるように、安全な
大鳳がそれを真似る。
「そうだ、いいぞ」
ふたりの攻防は、九十九が大鳳に技を使って見せ、それを大鳳が真似る形になっていった。
九十九は、大鳳ができるようになるまで、何度でも同じ技を反復させた。その都度、小さな声でアドバイスをする。
九十九の言うように、自然に手足が動く。
キックボクシングで言う回し蹴りから始まり、膝や
九十九もすごかったが、その要求についていく大鳳の運動神経も並みのものではなかった。初心者とは思えぬほど、足が高くあがる。
大鳳は、自分で自分の能力に舌を巻いていた。
――
凄い。
自分の身体がこんなにも動くものなのか。
大鳳の身体の底から喜びがふきあがってくる。
ふたりの動きは、初めに比べ、倍近く速くなっていた。決められた型を踊る、ペアのダンサーのようである。
大鳳の動きが、少しずつ変化していた。
九十九の指示に従うだけでなく、自分の意志で違う動きをするようになったのである。
自由に。
自由に。
大鳳が自由に動き始めるにつれ、攻防のリズムが違うものになっていった。
手足や腰の動きの
まるでフリージャズのセッションのようであった。
違う楽器をあやつるふたりの奏者が、自在に音をぶつけあい、からめあいながら、音とリズムの
こんな境地があったのかと想った。
いい演奏だった。
大鳳は歓喜していた。
「そこまでだ」
雲斎の声が響いた時、大鳳は、楽しい遊びから引きもどされる子供のような不満そうな顔をした。
「ちょうど一時間だ。ほっとけば明日の朝までやるつもりか――」
大鳳の身体は、湯につかったようになっていた。肌から汗が湯気になって立ちのぼっている。
「すごいな大鳳」
九十九が言った。
賛嘆の眼で大鳳を見ていた。
「これほどとは思っていなかった」
大鳳は、無言のまま九十九を見つめ、荒く胸を上下させていた。
一時間という時間が、まだ信じられなかった。一〇分か、一五分くらいの感覚しかなかった。
「ふたりとも、みごとだった。わしの思っていた以上だよ。特に大鳳、いつでも、どこでも、誰とでも、これだけやることができれば、今すぐにでも空手の黒帯は締められるぞ――」
雲斎は、
5
三人は、囲炉裏の周りで食事をしていた。
“飯を
と、雲斎が誘ったのである。
雲斎の畑でとれたという野菜と肉を、ざっと
「九十九、わかるか」
低い声で言った。
「はい」
「相当なものだな」
雲斎は、視線を、部屋の壁に沿って、ゆっくりとめぐらせた。
大鳳も、その異変に気づいていた。
首のすぐうしろのあたりが、もやもやとしているのである。細い
何かひどく
「このことでしょうか」
首をすくめて、大鳳が言った。
「ほう。おぬしにもわかるか――」
「外ですね」
と九十九。
「うむ」
雲斎が立ちあがり、ふたりも立ちあがっていた。
「気をつけろ、戸のすぐ外だ」
雲斎が言った。
九十九は、もう引き戸に手をかけていた。
板越しに不気味な
ずいと戸を開けはなち、外へ出る。
雲斎、大鳳が後に続く。
外は闇であった。
風がある。
夜の宙空で、ざわざわと
「屋根だ」
雲斎の鋭い声が低く響いた。
屋根の、一番高くなった所に、黒いものが
じりっ、と、それが動いた。
非人間的な、おぞましい動きだ。
「何者だ」
九十九が言ったとたん、屋根の上から、じわじわと闇を伝って、おそろしく暗い気の圧力がよせてきた。殺気とは違う。わけのわからぬ、不気味で不明確な情動の炎だ。
いきなり、屋根の上のそれが跳ねあがった。
黒い影が宙を舞い、ざっと梢を鳴らして森へ跳んだ。すごい跳躍力だ。
飛びついた幹の枝を自重でたわめ、その反動を利用して、影が移動していく。まるで猿である。
九十九が、うねるような身のこなしで地を走り、影の後を追う。
それが地に降りたのと、九十九がそこへ駆けつけたのと、ほとんど同時だった。
ふたつの影が
一方の影はそこにとどまり、一方の影は、そのままのスピードで、たちまち闇の奥へ走り去って行った。
動かずに、そこに立っていた影は、九十九だった。
心臓に近いシャツの布地が、真一文字に裂けていた。
「九十九さん!」
追いついた大鳳が九十九に駆け寄った。
「だいじょうぶだ」
落ち着いた九十九の声が返ってきた。
傷はどこにもないらしい。
大鳳はほっとした。
「おそろしいやつだった……」
九十九が、重い塊に似た息を吐いた。
「何だったんです、あれは――」
「わからん。人のようではあったが、人とはおそろしく異質な気を発散させていた」
「まるで幽鬼のようなやつであったな」
雲斎がそこに来ていた。
酔いが覚めた顔をしていた。
「これから何かが始まる、前ぶれのようなものかもしれんな――」
ぼそりと吐いた雲斎のその言葉が、小石のように、大鳳の心に残った。
すると、闇の奥から、細く、いんいんと獣の
得体の知れない、不気味な魔性の獣が、闇の奥で人知れずひしりあげる声だった。
おぞましく、そして哀切な、
それを耳にした時、大鳳の肉の内部で、暗い生きものが、もぞりと身を
ひゅうううう~~~~るいいいい……
るういいいい~~~~ゆうううう……
その声は、数度ひしりあげ、そして消えた。
あとには、頭上の闇で騒ぐ、梢の音があるばかりだった。
KADOKAWA Group