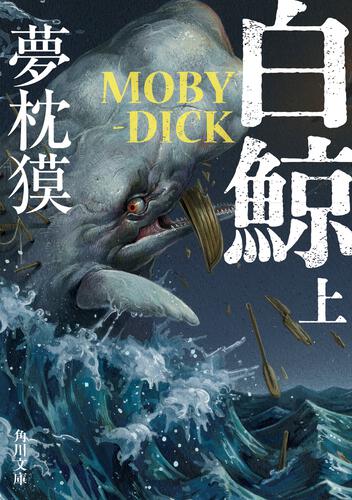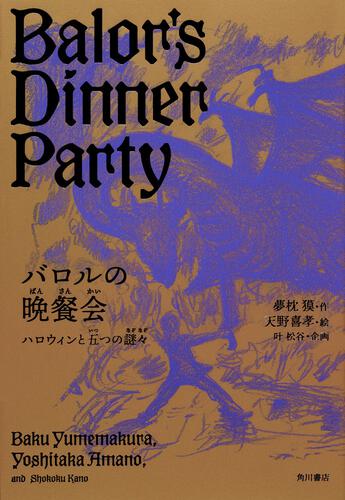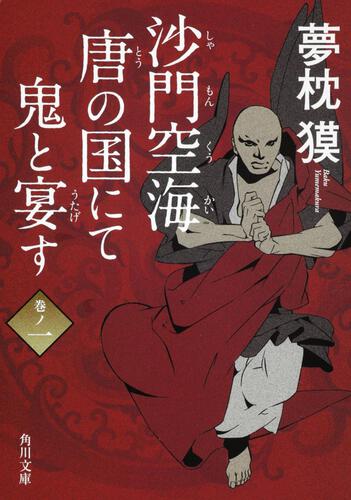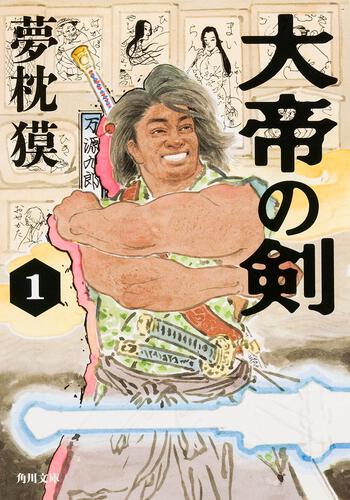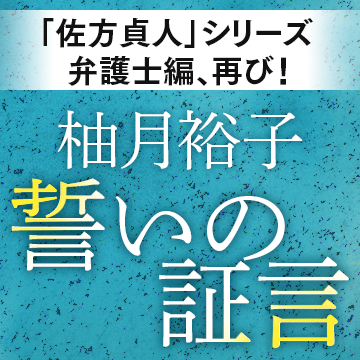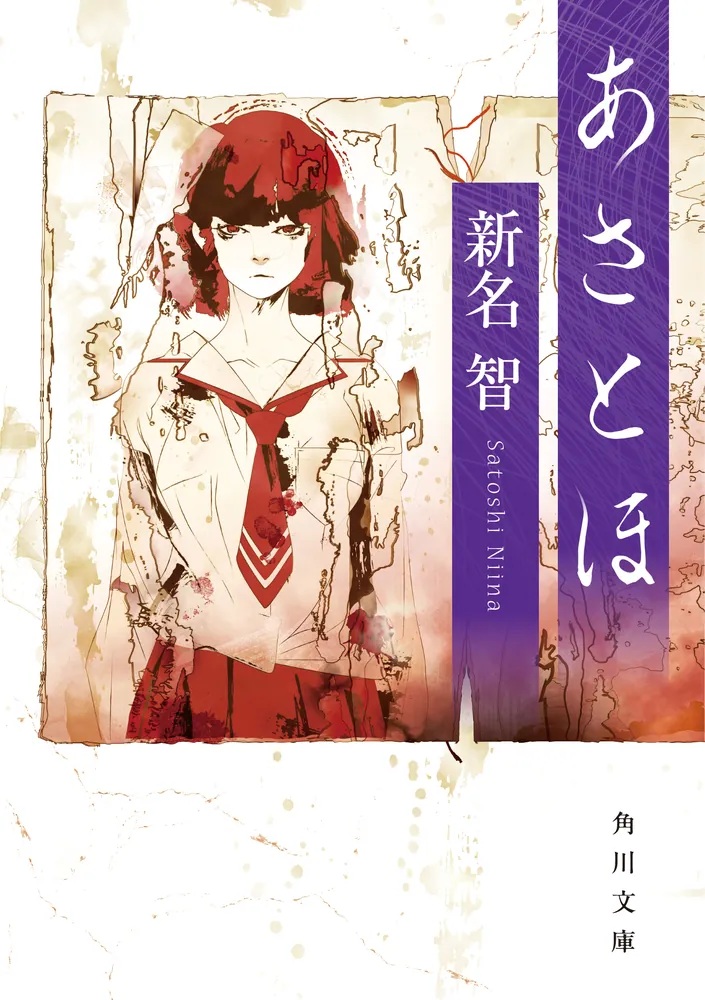一章 異常学園
1
――夕刻。
駅前に近い繁華街は人で
定時で仕事を終えたサラリーマン。
買い物帰りの主婦。
学生。
男。
女。
雑多な人間たちが、それぞれの方向に歩いている。
地方都市の、どこにでも見られるような風景とざわめき。
大鳳吼は、
四月――
まだ、桜が咲いている頃である。
暑くもなく、寒くもない時期。
「おい、待てよ」
大鳳の背後から、ふいに、低く押し殺した声が響いた。
大鳳は立ち止まった。
ふり返ると、そこに、ふたりの男が立っていた。
ふたりとも、大鳳とあまり変わらない年頃だった。おそらくは高校生――間違っても中学生ということはなさそうだった。
どちらも、つい今しがた、大鳳が出てきた本屋の店内で見た顔だ。ふたりとも、ジーンズに、黒い革ジャンパーを着こんでいる。学生服姿の大鳳とは対照的だ。
大鳳の顔に、
「久しぶりじゃねえか」
長身の男が、大鳳の肩に手をかけた。
一メートル七二センチの大鳳よりも、数センチは上背がある。短い髪に、ぴっちりとパーマをかけ、細い金縁のメガネをかけていた。口の中で、しきりにガムを
その口元に、
小男の方は、身長は、一メートル六〇センチもないだろう。低い位置から、押し黙ったまま、大鳳を
どこか、病的なものを感じさせる眼だ。
長身の男は、大鳳の肩に手をまわして歩き始めた。
他人の眼には、久しぶりに会った友人どうしと映るに違いない。しかし、男の手には、有無を言わせぬ力がこもっていた。
大鳳が、このふたりの男と会ったのは、さきほどの本屋が初めてである。むろん言葉をかわしたこともない。
大鳳が連れこまれたのは、通りからはずれた細い路地だった。一方を、灰色のビルの壁面で
人通りは、ない。
通りと十数メートルも離れていない路地の奥には、早くも薄闇がたちこめていた。
路地の奥に大鳳、出口を塞ぐ形で、ふたりの男が立った。
「おめえ、あれを見たな」
長身の男が言った。
メガネの奥から、細い眼が大鳳を見ている。
口元には、あの薄嗤いがへばりついたままだ。
「何を、ですか――」
大鳳は言った。
自分の声が、
「とぼけんじゃねえよ」
長身の男は、ことさら声のトーンを落として言った。その方が、大声で怒鳴るよりも、相手に恐怖感を与えるのを知っているのだ。
長身の男は、革ジャンパーのホックをはずし、
「これだよ」
それは、今人気のある女優のヌード写真集だった。
本から、顔をそむけるように、大鳳はうつむいた。
相手が、何のことを言っているのかは、わかっている。
その本は、長身の男が、さきほどの本屋から万引してきたものだ。大鳳は、その現場を目撃してしまったのだ。
眼が合った時に見せた、長身の男の
あわてて眼をそらした大鳳の頰に、執拗に突き刺さってきた視線の感触が、むず
先に外に出たふたりは、大鳳が出てくるのを待ち受け、後を
「見たんだろうが」
長身の男がさっきの言葉をくり返した。
大鳳はこくんとうなずいた。
「たれこんだりはしなかっただろう?」
もう一度うなずく。
「このボタンは
「一年です」
「今日、入学式をすませた口だな。言っとくがな、先公なんかにたれこんだりするんじゃねえぞ。もっとも、そんな度胸はねえだろうけどよ」
「――」
「おれたちは、おめえの先輩だよ。同じ西城学園のな。それで、ちょっと
しゃべっているのは、長身の男だった。
小男は、さっきから一言も発していない。
「おめえのクラスと名前を聞いておこうか」
大鳳は、ぴくっと身体を震わせた。
クラスと名前を言ったら最後だと思った。
この男は、卒業するまで、自分にまとわりついてくるだろう。
そういう恐怖感に満たされた。
いじめ――
という言葉が脳裏にちらついた。
大鳳は、まだ自分の置かれた状況が信じられなかった。とんでもない冗談に巻き込まれているだけなのだと思った。
よりによって、入学式のあったその日に、同じ学校の、札つきのワルに目をつけられたのだ。
またか、と大鳳は想った。世の中には人にいじめられやすいタイプの人間がいる。本人は意識していないのに、知らぬ間に他人の暴力を誘発してしまうのだ。
大鳳がそうだった。
「言わねえか」
その声には、はっきりした
大鳳は、それでも口を開かなかった。
「調べりゃよ、すぐにわかることなんだぜ」
その言葉を耳にした時、大鳳は、地に沈み込むような絶望感に襲われた。
その通りだった。
今言わなくても、大鳳のクラスと名前くらい、いずれは知られてしまうことだった。顔を覚えられた以上、同じ学校の人間が調べる気になれば、明日にでもわかる。
動揺し、そんなことすら気がつかなかった自分がくやしかった。
せいいっぱい口をつぐんでいた気力が、急速に
今は、できるだけ相手を刺激せずに、一刻も早くこの場を立ち去りたかった。
「一年C組の……」
屈辱で顔が赤くなった。
「――C組の、大鳳吼です」
やっとそれだけ言った。
自分は、これほど暴力に弱い人間だったのかと思った。
「おい、顔をあげろよ」
うつむいたままの大鳳に、長身の男が言った。
言われるままに、大鳳は顔をあげた。
「ほう」
メガネの奥の眼が、
「いい男じゃねえか」
長身の男は、大鳳の顔だちに、あらためて眼をやった。
大鳳は、確かに整った顔をしていた。
肌が、ぬけるように白い。ゆるくウエーブした髪が、耳に半分かぶさり、その下に滑らかな首筋が
まるで、同じ年頃の少女のような顔つきである。
それも、とびきり美麗な少女だ。
しかし、大鳳のその
長身の男は、大鳳の
その光が、大鳳の不安をかきたてた。
「もう、帰ってもいいですか」
「待てよ。まだおめえを信用したわけじゃねえ。ここでだけいい子でいて、後でたれこまれたんじゃたまらねえからな」
獲物をいたぶって楽しんでいる口調だった。
「どうしようか」
自分にとも、横にいる小男にともつかぬ口調で言った。唇の片方が、
小男は、返事をせず、やはり押し黙ったまま、細い小さな黒い眼で、じっと大鳳を
ひどいニキビ面で、くすんだ紙のような顔の皮膚は、夏ミカンの皮を連想させた。背はずんぐりしているが、がっしりした肉厚の
さっきから一言も口をきかないが、それがかえって不気味だった。
常人とは、歯車が、どこかひとつずれている。
「いいことがあるぜ。おめえもよ、あの本屋で、何か本を一冊
長身の男は、
万引を見られた、というのはただの口実で、男たちの目的は、獲物をいたぶることにあるようだった。
「なあ、おい」
横に立って、長身の男は大鳳の顔を
「で、できません」
言いながら、何故こんな目に遭わなければいけないのか、と大鳳は思った。
力が欲しかった。力さえあれば、このふたりをぶちのめしてやるのに。
屈辱と、怒りと、憎悪とが、ごちゃ混ぜになって渦巻いていた。
長身の男が、大鳳の横に来たことにより、小男の右横が、広くあいていた。ふいをついて、いきなり走り出せば、なんとかそこを抜けられるかもしれなかった。
「できねえだと」
「――」
「ならば金を置いていくんだな」
「お金?」
「この本の代金だよ。おめえが払うんだ……」
その言葉が終わらぬうちに、大鳳は走り出していた。
長身の男に、肩がぶつかった。
はずみをくらって、よろけた長身の男の背がコンクリートの壁にぶつかった。
「野郎!」
長身の男が
その時には、もう大鳳は小男の横を走り抜けつつあった。
小男の脇をすり抜けたと思った瞬間、大鳳の身体は宙を舞っていた。ふわりと自分の体重がなくなり、次に、激しい衝撃がどっと背を襲った。
初めは、自分に何が起こったのかわからなかった。肺が
小男のニキビ面が、無表情に大鳳を見下ろしていた。
小男の足が、大鳳の脚をはらったのだ。
長身の男が、まだ
「ずいぶん、なめたマネしてくれたな」
大鳳の後頭部を、ごつん、ごつんとコンクリートの壁に打ちつける。
「この」
強烈な
爆発するような恐怖が大鳳を捕らえた。
ほとんど無意識のうちに、大鳳は首をまげてその拳をかわしていた。自分でも信じられない、一瞬の動作だった。プロボクサー並みの反射神経だ。いや、たとえプロボクサーといえども、胸ぐらをつかまれた状態で、至近距離からのパンチを、こうもみごとにはかわしきれまい。
長身の男の拳は、したたかにコンクリート壁を
しぼりあげるような
「てめえ!」
完全に逆上していた。
革靴の爪先をたて続けに大鳳の腹に
爪先は、正確に大鳳の腹にめり込んだ。
大鳳は、腹を押さえて腰を折った。
激痛に、眼から涙が
頰に左のパンチが叩き込まれた。一発や二発ではなかった。鼻の奥がキナ臭いもので満たされた。ぬるりとした温かいものが、鼻から滑り出てきて唇に伝わった。しょっぱかった。血であった。
殴られた時、大鳳が感じたのは、痛みというよりは温度であった。顔面が、火のようにかっと熱い。
くずおれた大鳳のポケットに、長身の男の手が差し込まれてきた。サイフを探しているのだ。
声がしたのは、その時だった。
「それぐらいでやめておくことだな。強盗までしたんじゃ、ただのケンカじゃおさまらなくなるぜ――」
身体をびくんとさせて、長身の男が顔をあげた。おなじようにふり返った小男の顔に、初めて表情らしきものが浮かんでいた。驚き、というよりは、とまどいに近い表情だった。
そこに、ぬうっとひとりの男が立っていた。
巨漢である。
長身の男が小さく見えるほどだ。一メートル八〇センチは軽く越えていよう。盛りあがった岩のような肩の上に、太い首があり、柔和な顔がその上で笑っていた。
「誰だ、てめえ」
長身の男が
「通りがかりの者だよ。穏やかじゃない雰囲気だったんでな。ちょっとおせっかいをやきに来たのさ」
「すっこんでやがれ。てめえにゃ関係のねえことだ」
長身の男が凄む。
身体のでかい男には、えてして小心者が多い。自分より大きい相手を、凄むことで何度か威圧してきたことがあるのだろう。長身の男の
しかし、巨漢は、毛ほどもそれを感じていないらしい。
「しかしなあ。こうして声をかけちまった以上、これで引き下がっちまうんじゃ、そこの彼が可哀そうじゃないか」
涼しい口調で言う。
「痛い目を見てえのか」
「痛い目を見たがる人間なんぞ、マゾでもなければいるわけないだろう」
「おちょくってるのか、てめえ」
立ちあがりざま、長身の男は、巨漢に殴りかかった。
それを、巨漢はひょいと上体をゆらめかせてかわした。ほとんど身体を動かしていない。両足は地についたままだった。
宙に泳いだ身体をたてなおした長身の男は、自分とその巨漢との力量の違いにようやく気づいたようだった。
べっ、と
「
今度はふいをついたつもりで、巨漢の
巨漢の男は、左足をあげて、その蹴りに空をきらせ、そのまま左足で、半回転した長身の男の
長身の男は、前につんのめって、地面に頰をこすりつけた。
「やっちまえ、菊地!」
倒れたまま、長身の男は、小男に向かって叫んだ。
菊地と呼ばれた小男の、さっきまで何もなかった右手に、魔法のようにスイッチ・ナイフが握られていた。
刃渡りが一五センチはありそうだった。
「きいっ」
獣じみた声をあげ、ナイフの尻を自分の脇腹にためた菊地の身体が、どんと巨漢の身体にぶちあたった。テレビや映画でヤクザがするような格好を、大鳳は、初めてその眼で見た。
自分の眼が信じられなかった。
ひきつった悲鳴が、自分の喉にからまったのがわかった。
大鳳は、てっきり、巨漢が刺されたものと思った。
長身の男もそう思ったのだろう、
「へへ――」
長身の男は、
ぶつかりあったふたりの身体は、二、三秒の間、動かなかった。
「いかんなあ」
場違いな、とぼけた声をあげたのは、巨漢だった。
巨漢は、両手で菊地を抱くようにして、ゆるく足を開いていた。菊地の背に回された巨漢の右手に、菊地の持っていたはずのナイフが握られていた。
「ケンカにこういうものを使うのはいかん」
言いながら、菊地の身体を抱えあげ、自分の足元に寝かせた。
菊地は気絶していたのである。
おそらく、巨漢は、一瞬のうちにナイフを奪い取り、菊地の身体のどこかに、気絶するような打撃を加えたのであろう。恐るべき早技だった。いつ、どのようなことをしたのか、大鳳にはそれが見えなかった。
菊地が、頭をふって起きあがってきた。
まだ、自分に何が起こったのかわかっていないのだろう。困惑の色が、その顔にあった。
大鳳は、巨漢が、菊地がすぐに
巨漢が、その唇に笑みを浮かべていたからである。まだ本気になっていないのだ。
そうだとするなら、あの状態にあって、巨漢にはまだ余裕があったことになる。
長身の男は、もう逃げ腰になっていた。
その時――
「やめた方がいいよ、
通りの方から響いてきたのは、女の声だった。
大鳳たちのいる場所と、通りとの中間あたりに、両手を腰にあてた女が立っていた。
「
灰島と呼ばれた長身の男が、女の名を呼んだ。
その女――由魅は、灰島の声が聞こえなかったように、巨漢を見つめていた。
「お久しぶりね。
「由魅か」
巨漢の顔に、笑みが浮かんだ。
由魅は、四人のいる所まで、みごとな足どりで歩いてきた。背筋がぴんと伸びている。黒いスカートに、燃えるような
由魅が現れたとたんに、場の中心が、さっとそこに移動してしまっていた。鮮やかな登場のしかただった。
ブラウスの胸元が大きく開き、白い肌が惜しげもなくさらけ出されている。胸のふくらみが、ブラウスの布地を、下から大きく挑発するように押し上げていた。紅い布の間に
布越しに乳首の位置が見てとれる。ブラジャーをしていないのだ。
ウエストのくびれも、腰の張りぐあいも、申し分なかった。スラリとした脚も、ファッションモデルそこのけだ。足首もしまっている。
同性の女が見ても、思わずため息をもらすほど、みごとな身体つきだった。
由魅は、ぐるりと見回してから、
「なるほどね」
と、大鳳に視線を止めた。
「だいたいのところは想像がつくわ。灰島と菊地がこの子からカツアゲでもしようとしてたところに、あなたがやってきたってとこね――」
「まあ、そんなとこだ」
「あいかわらずね、九十九さん」
由魅の視線は、大鳳に向けられたままだった。大鳳の、並みはずれた
アイライナーに縁どられたキラキラ光る
心臓を、素手でつかまれたようなショックがあった。あわてて視線をそらし、大鳳は、
自分の顔が、赤くなっているのではないかと思った。
由魅の
アイライナーのいらぬほどくっきりとした眼。ブラウスと同じ色のルージュをひいた唇。肩まで垂れたくせのない髪――。いや、それ等よりも何よりも、その貌にたたえられた、不思議な微笑が、鮮やかに大鳳を捕らえていたのだ。
それは、欲情した女の貌であった。
大鳳の本能が、敏感にそれを感じて、眼をそらせたのだ。大鳳自身もまた欲情していたのである。だが、大鳳の意識は、まだ自分の肉のうずきに気づいていないのだ。
大鳳は、自分の心臓の鼓動する音が、この場にいる全員に聴こえてしまうのではないかと思った。
由魅の赤い唇がすっと横に広がり、白い歯がこぼれた。大鳳の心のうちを見すかしたような笑みだった。
「いつ大阪から帰って来たの」
由魅が、巨漢に向かって言った。
眼は、もう巨漢に向けられている。
「今日さ。久しぶりに街を歩いていたら、偶然にこの現場を見ちまった。まあ、本当は、小便をしにこの路地に入っただけなんだがね――」
「あなたらしいわね」
「ところで、
「ええ。元気すぎるくらい」
久鬼の名が出たとたん、灰島の顔が驚きでこわばった。
「由魅さん。この野郎――いや、こちらは久鬼さんを知ってるんですかい」
灰島は時代がかった言い方をした。
「あなたたちよりはずっとね」
灰島の顔が、何とも言えない表情になった。
由魅が九十九と呼ぶこの巨漢を、心の中であつかいかねている顔つきだ。敵なのか、仲間なのか、計りかねているのだ。
小男――菊地は、さっきから恐ろしい顔で、九十九を
「今日はこれでおしまい。帰るのよ――」
由魅が、灰島と菊地をうながすように言った。
灰島はうなずいたが、菊地は、その言葉が聴こえなかったように、九十九を見すえていた。
「ほら、これを返しとくぜ」
九十九が、スイッチ・ナイフを菊地の足元にほうった。菊地は、それには見向きもしなかった。
「いいかげんにしなさい。今、あっさりやられたばかりでしょう。あたしが来なかったら、あんなものじゃすまなかったかもしれないのよ――」
由魅の言葉に、菊地の顔がどす黒くなるのを、大鳳は見た。激しい憎悪の炎が、陰火のように、その眼にめらめらと燃えあがっていた。
――この男、由魅を好きなのだ。
大鳳は、直感的にそう思った。
由魅を好きだからこそ、その前で恥をかかされた九十九に怒りを覚えているのである。
「行くわよ」
由魅が歩き出すと、ねじ込むような視線の
由魅の背に、ぴったり寄り添うように従う菊地を見た時、大鳳の心に、苦痛に似た、熱い、得体の知れぬものがこみあげた。
それが、菊地に対する
「久鬼によろしく言っといてくれ」
九十九が由魅の背に声をかける。
「わかったわ」
由魅がふり向いた。
「またすぐに顔を合わすことになりそうね。それから、そちらの可愛い方ともね――」
三人の姿が消えた。
夜になっていた。
通りの
「さて、おれも行くか」
九十九が歩き始めた。
巨体に似合わず、おそろしく軽い足どりだ。
「ありがとうございました」
大鳳は、あわてて九十九に声をかけた。
「礼を言われるほどのことじゃないさ」
九十九が立ち止まり、ふり返った。
「気をつけろよ。あんなのにからまれてケガをしたんじゃ合わないからな」
あの、太い笑みを浮かべた。
人を安心させる、温かい笑顔だ。
九十九が去った後、その路地には、大鳳とナイフだけが、ぽつんと取り残されていた。
2
西城学園――
神奈川県
小田原城の西、山の手の城山に校舎がある。
屋上からは、西に箱根外輪山の山々、北に
東京から新幹線で四〇分、新宿から
大鳳吼のアパートは、小田急線で一区間新宿よりの、
市街地よりも、家賃がずっと安い。
安いとはいっても、高校生で、しかも独り暮らしとあっては、ばかにならない額である。
大鳳は、早めに家を出た。
一般の生徒が登校しはじめるより、一時間早く校門をくぐっていた。
さすがに誰もいなかった。
構内は、静まりかえっていた。
グラウンドの奥にある散りかかる寸前の桜が、朝陽を浴びて、しんと明るく輝いている。
大鳳は眼を細めた。
グラウンドは、あっけらかんと広い。
ひどくつまらぬことをしたような気がした。
昨日のふたり――灰島と菊地と顔を合わせぬように早く登校したことが、馬鹿ばかしくなった。
――気にしすぎているのだ。
昨日のことも、今は悪い夢のようである。
悪夢は早く忘れることだ。そう自分に言いきかせようとするのだが、それで肩の荷が軽くなるわけではない。
あれは、もうすんだことなのだ。このまま、あのふたりが自分にかまってこないのなら、この新しい環境の中でも、なんとかやっていけるだろう。
ふいに、由魅のことが頭に浮かんだ。
あの胸のふくらみと、大鳳をじっと見つめた眼――。
何かの残り
大鳳は、それをふりはらい、桜の木の下に向かって歩いていった。
腹が減っているのに気がついた。
朝食を食べていないのだ。カバンの中には、駅前で買った、サンドイッチと牛乳が入っている。
幹の下に腰を下ろし、それを食べる。
最後のサンドイッチを手に取った時、大鳳は、一匹の犬が、じっとこちらを見ているのに気がついた。すぐ隣の桜の幹の陰から顔だけを出し、大鳳の手の中のサンドイッチに視線をそそいでいる。切ないほどに腹をすかせている眼だ。
大鳳は、犬と自分との中間に、サンドイッチを投げてやった。
犬は、走りよってくると、あっという間にそれを食べた。
大鳳は笑った。昨日殴られた個所が痛んだ。四発はきれいに殴られたのだ。痛みが残ってあたりまえだ。
顔をしかめながら、大鳳は、まだ牛乳の残っているビンを、犬に向かって差し出した。犬は、
ビンを傾けてやると、こぼれてくる白い液体を、犬はきれいに
「よしよし」
大鳳はまた笑った。
「優しいのね」
ふいに、すぐ
制服を着た女生徒が立っていた。笑いながら犬を見ている。
「残念だわ。わたし一番最初だと思っていたのに――」
犬に眼をやったまま言う。
ロングヘアの、ほっそりした少女だった。
「え――」
「わたしより早く登校してくるなんて、よっぽど早起きなのね」
少女が大鳳に向きなおる。
二重の優しい眼が、大鳳に向かって微笑んでいた。黒い髪に、桜の花びらが一枚とまっている。
大鳳は、理由もなく、
何か、ひどく恥ずかしい現場を見られてしまったような気がしていた。自分は、どんな顔をして犬にビンを舐めさせていたのだろう。だいぶ子供じみていたかもしれない。
「ごめんなさい。驚かせちゃったかしら――」
少女が軽く唇をすぼめると、淡いピンクの唇の表面に、清潔なしわがよった。
同年齢の少女に比べ、いくらか成熟の遅れた、まだあどけなさの残る娘だった。中性的で、
「君も新入生かい」
大鳳が言った。
牛乳ビンは、もう地面に転がっている。
「ええ。あなたもでしょう。ね、もしかしてC組? 昨日のクラス編成の時に、あなたの顔、見たような気がするわ」
「君もC組なの?」
「そう。担任は
「君は、いつも、こんなに早く学校に来るのかい」
「中学の時からよ。この、誰もいない明るい雰囲気が好きなの」
「へえ」
「あなたもそうなんでしょう」
声を出しかけて、大鳳はあわててうなずいた。本当のことは言えなかった。
「あら、その顔――」
少女は、ようやく、大鳳の顔に気がついたようだった。
「ケンカ、したんでしょう」
「これは――」
大鳳は、殴られた個所に手をやって立ちあがった。ビンを舐めていた犬が、とびのいた。
「転んだことにしておいてもいいのよ」
「そうしてくれると助かる」
大鳳は、ほっとして言った。
少女の顔が、やけにまぶしかった。
3
少女の名前は、
大鳳は、その名前を、ホーム・ルームの自己紹介で知った。
深雪の方も、これで大鳳の名を知ったはずだった。
席決め、自己紹介、委員の選出で午前中が終わった。
昼休み――パンで昼食をすませた大鳳の所に、織部深雪がやってきた。
「やあ」
「面会よ、おおとりさん」
「面会?」
「三年生ね。今、私が外に出ようとしたら声をかけられたの。教室の入り口の所で待ってるわ」
不安が大鳳の胃をじわりと締めあげた。
昨日のふたりの顔が、すぐに浮かんだ。
「女の人よ。とても
声の中に、どこか怒ったような響きがある。
しかし、大鳳は、その響きには気づかない。
ほっとすると同時に疑問がわいた。
「誰だろう」
立ちあがり、深雪に礼を言って廊下に出た。
「大鳳さん」
と、声をかけてきた女がいた。
大鳳は女を見た。はっきりした顔だちの、確かに綺麗な女だった。大鳳よりは小さいが、女としては大柄な方である。
「わたしよ。わかる?」
黒い
「どう、その顔。まだ痛むんじゃないの?」
「由魅、さん?」
言葉が大鳳の口をついて出た。
「そう、由魅よ。
「まるでわかりませんでした――」
「無理はないわね。あの格好とこの姿じゃあね。どう、驚いた?」
昨日とは、言葉づかいまでが違う。
大鳳はうなずいた。
目の前にいる由魅が、昨日の由魅と同一人物だというのはわかる。しかし、昨夜の映像と、今ここにいる由魅の姿が、まだぴったりと重ならないのだ。
昨日の由魅は、どう見ても二〇歳か、それより上に見えた。化粧を落としただけで、女はこうも変わるものかと思った。
目の前にいるのは、どう見ても高校生である。
しかし、由魅の魅力が、わずかも損なわれているわけではなかった。匂いたつような、なまめかしい肉体の雰囲気は、制服の下からも、色濃く漂ってくる。それが、磁気を帯びたオーラのように、由魅の肉体を包んでいる。
あの、燃えるような
顔が赤くなった。
「何か用だったんですか」
「あなたの顔を見に来ただけよ。それが目的――」
含み笑いをする。
廊下を通る新入生たちが、不思議そうな顔で、ふたりを見てゆく。しかし、由魅は、それをまるで気にしていない。
「からかわないで下さい」
「からかってなんかないわ」
「からかっています。用件を言って下さい。昨日のことですか」
「そのことだったら、後で、ちゃんとあなたを呼びに来る者がいるわ――」
「――」
「驚かなくてもいいわ。あなたをどうにかしようってわけじゃないんだから。わたしの見るところでは、むしろその逆ね――」
「逆?」
「たぶん、ね。久鬼の考えていることは、わたしにもわからないところがあるの。とにかく、あなたは、何も気にしないでいらっしゃい。怖がることなんてないんだから」
「その久鬼さんていうのは――」
「だめだめ」
由魅は、大鳳の言葉をさえぎった。
「言ったでしょ。わたしはあなたの顔を見に来ただけ。でも、もうその目的はすんだわ。じゃあ、放課後ね――」
にっと微笑んで、由魅は去って行った。
大鳳が教室にもどると、とたんに
「いい女じゃないか」
「色男は手が早いからなあ」
「もう、やっちまったのかい。すんだらこっちにもまわしてくれるんだろう?」
「俺にも、少しは女を残しといてくれよな」
口笛と笑い声。
五、六人の男子生徒が、輪になって大鳳を見ていた。騒ぎの中心は彼等である。
彼等の
それは、すでに、大鳳にとっては
――またか。
と、大鳳は思った。
またなのだ。初対面の、大鳳と同年齢の男たちの多くが、いつも決まって同様の反応を見せる。彼等は、大鳳の
程度の差こそあれ、まず、そうである。
たとえ、彼等が口にしなくとも、大鳳は敏感にそれを感じることができた。
いつ頃からそうなったのかはわからない。
気がついた時には、そのような雰囲気がまわりにあった。彼等の反応が、自分の美貌に対してのものであることを知ったのは、中学に入ってからだった。大鳳は、彼等を無視することを覚えた。
それ以来、大鳳は、ほとんど友人らしい友人を持ったことがない。
自意識が過剰になって、大鳳の
すでに、一年C組の内部でも、大鳳の美貌は話題になっていた。
大鳳は、彼等にいいきっかけをあたえてしまったのだ。
「見せつけてくれるじゃねえか」
野太い声をあげたのは、騒いでいる男たちの中心になっている
大鳳は、彼等を無視した。
席についた大鳳の貌から表情が消え、超然とした顔つきになる。
自然に身につけた、自分を守る方法である。
貌が美しいだけに、効果は抜群だった。しかし、それは、薄くもろいガラスの仮面だ。わずかの暴力で、たやすく素顔が露呈する。昨日がいい例だった。
大鳳の
かえって反感をあおりたてることになる。
坂口の場合もそうだった。
ぬうっと立ちあがって、大鳳の席に向かって歩いてくる。
心臓がすくんだ。
しかし、それを表情には出さない。
――能面のような貌。
深雪が、痛いほど見つめているのが、大鳳にはわかった。
すぐ横に、坂口が立った。
「もてるんだなあ、大鳳」
ささやくように言う。
教室のざわめきが、すっかりやんでいた。
すべての視線が、ふたりに集まっている。空気がぴりぴりと張りつめている。
大鳳の神経は、限界近くまで緊張していた。いっぱいに張ったゴム風船と同じだ。針先が軽く触れるだけで、簡単に破裂してしまうだろう。
それでも大鳳は黙っていた。
いや、声を出せなかったのだ。声を出せば、それは、昨日以上に震えた、だらしないものになるのはわかっていた。
「いい度胸じゃねえか。え、その
ダン!
と、
坂口が、
大鳳が声をもらさなかったのは、ほとんど奇跡に近かった。表情もそのままだ。
その音が、あまりに突然だったからである。すくみあがってしまったと言ってもいい。机への一撃が、もう少し加減したものであったなら、大鳳は、おそらく声をあげていたろう。
坂口は、にやりと笑った。
教室中の者が、かたずをのんだその時、前の戸がふいに開いて、ひとりの男が入ってきた。
大きな男だった。
ひと目で上級生とわかる。昨日の九十九ほどの上背こそなかったが、体重はほとんど同じくらいであろう。
学生服の下に、分厚い肉の塊が、ぎっしり詰まっている。それが、鍛えあげられ、引き締まっているものであることが、布越しにもわかる。
肉の風圧のようなものが、その肉体からむうっと漂ってくるようである。
男は、
眼をそらさずにその視線を受けたのは、坂口だけであった。
「この中に大鳳というのはいるか」
男が言った。低く、落ち着いた声である。
全員の眼が、大鳳にそそがれた。
「おまえか」
大鳳は、
「空手部の
「はい」
気づいた時には、返事が大鳳の口から滑り出ていた。
由魅が言っていたのは、このことだったのだ。
「そうか。約束したぞ。むかえの者をよこす」
それだけ言うと、男は、大鳳の横に立っている坂口に数瞬視線を止め、何も言わずに教室を出て行った。
「けっ」
吐き捨てるように言ったのは坂口だった。
「おかしな眼で俺を見やがって――」
阿久津の出現によって、大鳳に関しては、完全にタイミングをずらされたのであろう。くるっと背を向けて、仲間のいる方へ歩いて行った。
その時になって、大鳳は、ようやく、自分がとんでもない返事をしてしまったことに気づいていた。
4
鬼道館は、校舎の西側に建てられた、木造の建物である。
西城学園の、剣道部、柔道部、そして空手部が共同で使用している。鬼道館のすぐ西側に、背中合わせの棟続きで、
白蓮庵の方がせまく、その一部は、大きめの茶室風になっており、ここは茶道部と華道部が使用している。
もっとも、茶道部、華道部共に、部室そのものは別にあり、そちらの方はそちらの方で、一般の部員が使っている。
白蓮庵のすぐ先は雑木林である。雑木林は、そのまま、箱根外輪山の
鬼道館と白蓮庵――ひとつの建物をこのようにふたつに分けたのは、肉体は鬼神のように強く、心は白い
鬼道館の内部は、畳敷きと板敷きとに分けられていた。
畳敷きの方が二〇畳、板敷きの方が三〇畳ほどで、仕切りの壁はない。畳のある方を柔道部、板の間の方を空手部と剣道部が使用していた。
大鳳は、空手着を着た男の後から、鬼道館の中に足を踏み入れた。
中は、しんと静まりかえっていた。
人がいないのではない。ざっと五〇名近くの人間がいる。その五〇名近くの人間全員が、両側の壁際にきちんと正座をして眼を閉じているのである。
ほとんどの人間が、空手着、柔道着、剣道着を着ている中で、ひとりだけ学生服姿の人間がいた。
学生服姿の男は、左右に皆を従えるように畳の間の一番奥に座って、左手を軽く前に出し、考えごとをするように首を傾けていた。左手に握られているのは、紫の花を付けた
その男は、目の前の水盤に、花を
大鳳を連れてきた小柄な空手着の男は、学生服姿の男に向かって一礼し、列の一番端に、皆と同じように正座をした。学生服姿の男は、ふたりが入ってきたことにまるで気づいた風もなかった。
じっと、左手の菖蒲を見ている。
大鳳は、どうしていいかわからずに、そこにつっ立っていた。下は板の間である。靴下を通して、硬い板のひんやりした感触が伝わってくる。
鬼道館に入る時、
あがってすぐが板の間、その奥が畳の間だった。左右の列の端に座っている何人かは、直接板の上に正座している。
「大鳳くんですね」
ふいに、菖蒲を手にした学生服姿の男が、眼をあげて言った。
落ち着いた声だった。
その声が響いたことにより、部屋の静寂が一層増したようだった。
「はい」
「こちらへ来て座りませんか」
大鳳は緊張した足取りで、男の前までゆき、そこに正座をした。
男の眼は、再び菖蒲にそそがれていた。
その
その男は、大鳳に優るとも劣らない、美しい貌をしていたのである。貌の造りそのものはむろん違う。しかし、その優美さには、大鳳にも共通した、あの、どこか人間離れしたものがあるのである。
だが、男と大鳳を比べてみると、決定的に違うところがある。
男の全身からは、大鳳にはない、己に対する絶対的な自信が漂ってくるのである。ひ弱ではない、内側から光る完成された美だ。
わずかな仕種や口調、表情にも、強い意志が一本通っている。
それは、ストイックな者にありがちな、その肉体を硬くおおうものではなく、内側から
「どうしますか」
花を見つめたまま男が言った。
「――」
「これを、あなたならどうしますか」
驚くほど深い色をした黒い
大鳳に向かって、菖蒲が差し出されていた。
男は、大鳳に、おまえならこの菖蒲をどう活けるか、と
大鳳はようやくそのことが吞み込めた。
大鳳は水盤に眼をやった。
南の窓から、西に傾きかけた陽光が、大鳳の
「どうしていいか、ぼくにはわかりません」
どこにその一本を活けても、水盤上にできあがった調和をこわしてしまいそうだった。
「そうですね」
大鳳の気持ちを読みとったように、男がつぶやいた。
「どうするかは、もう決まっているんです。今、ここへ入ってきたあなたの顔を見て、ちょっと考えを訊いてみたくなったんですよ」
「決まっている?」
「はい。こうするのです」
男は、右手の花バサミで、手に持った菖蒲の花を無造作に切り落とした。
とん、と、まるで音でもたてたように、紫色の花が畳の上に落ちた。
「この花も、確かにみごとに咲いてはいるのですが、こちらでは、もうすでにひとつの美が完成されています。その美にとっては、この花がどんなに美しく咲いていようと、もはや邪魔なだけです」
花バサミを畳の上に置いた。
「自己紹介をしていませんでしたね」
男が言った。
正面から、大鳳の眼を見すえた。
「
その時、背後に人の気配がした。
新たに、誰か入ってきたらしい。
大鳳はふり返った。
ひとりの、学生服姿の大きな男が、あの由魅に連れられて入ってきたところだった。
男は、頭をかきながら、きちんと正座をしている男たちを、困ったような顔で眺めていた。
その顔に見覚えがあった。
大鳳と眼が合ったとたん、その男の顔が、人なつっこい、
「よう。また会っちまったな」
その男は、昨日、大鳳が助けられた巨漢――九十九だったのである。
5
九十九は、大鳳の横に、どっかりと座した。
堂に入ったみごとな姿勢だ。まるで岩である。
「元気そうですね」
久鬼が言った。
「ああ。そっちも相変わらず、と言いたいところだが、なかなかご大層な様子じゃないか――」
九十九が、左右に並んで座っている者たちを、ぐるりと見渡した。
久鬼は、口元に、わずかに笑みを浮かべただけだった。
「
久鬼が言った。
「まだだよ。ここの用がすんだら、
「もう一年以上も会ってない。顔を出したら、久鬼がよろしく言っていたと伝えてくれませんか」
「わかった。ところで、足を崩させてもらうよ。どうも正座というのは、性に合わん」
九十九は、
「あんたも足を崩したらいい。ここの連中につきあって正座なんかしてると、足がしびれちまうぜ」
大鳳に向かって九十九が言う。
「かまいませんよ」
と、久鬼がうなずく。
「このままで、平気です」
大鳳は、頰をひきしめて言った。
足は、すでにしびれかけている。しかし、九十九のように胡座をかく勇気はなかった。この場の雰囲気に、すっかり
自分が来る前から正座をしている人間の前で、後から来た自分が、先に膝を崩すわけにはいかなかった。大鳳の、せめてもの意地であった。
が、そんな自分の気持ちも、すっかり久鬼と九十九には読まれているような気がした。
「そろそろ用件を聴かせてもらいたいな。もっとも、この大鳳がここにいるところを見れば、だいたいの想像はつくがね」
九十九が言った。
昨日、ナイフをつきつけられた時の口調と、少しも変わってない。
久鬼も、九十九も、どちらも自信に満ちた大人びた雰囲気を感じさせるが、その個性にはまるで異質なものがあった。
「灰島と菊地。前へ出てきなさい」
久鬼の声が凜と空気を打った。
右手の列から、ふたりの男が立ちあがった。長身の男と小男、灰島と菊地だった。ふたりとも、空手着を着ていた。
ふたりは、前に出てくると、九十九の横に、いくらか距離をとって立った。
「このふたりが、昨日は、たいへん失礼をしたそうですね」
灰島が、気の毒になるほど緊張しているのが、大鳳にはわかった。菊地の方は、細い眼で宙を
「たいしたことじゃない。もうすんだことだ」
九十九が言った。
「聴くところによると、ナイフさえ使ったらしいですね。大鳳くんの顔には、まだ殴られた跡が残っていますね。それは、この灰島がやったのでしょう」
大鳳は、黙っていた。
久鬼の意図がわからぬうちは、何とも答えようがなかった。
「灰島――」
と、久鬼は、大鳳から灰島へ、質問の相手を変えた。
「おまえは、大鳳くんを殴りましたね?」
「久鬼さん、そ、それは――」
灰島が、やっとという感じで声を出す。
「答えなさい」
「殴りました」
「何回ですか」
「四発――たぶん四回だったと思います」
灰島は、哀れなほど
「菊地は、大鳳くんには手を出していないのですね」
「大鳳に手を出したのは自分だけです」
「わかりました」
久鬼は、大鳳に向きなおった。
「大鳳くん、今、この場で、あなたが殴られた数だけ、灰島を殴りなさい。ぼくが許します」
平然と言った。
大鳳は、一瞬、その言葉の意味がわからなかった。が、雷の
「後の心配はいりません。遠慮は無用です」
声を出せずにいる大鳳を、久鬼がうながした。
しかし――
大鳳はどうしていいかわからなかった。
今まで、本気で人を殴ったことなどなかった。どう殴っていいか見当がつかない。昨日ならばともかく、今は、灰島を殴りつけたい、という意志そのものが欠如しているのだ。
いや、正確に言うなら、現在でも、灰島に
大鳳の心には、暴力を恐怖する気持ちと、暴力そのものを、自分の力として思う存分駆使してみたいという願望があった。暴力を憎む気持ちが強ければ強いほど、また、その願望も強かった。自分のひ弱さが
時には、己の中に潜む、暴力への激しい渇望に、
しかし、それは断じてこのようなものではなかった。今、目の前で畏縮しきっている男を、他人の力をかりて殴りつけるものではなかった。
やるのなら、自分がもっと強くなって、自分の力で、灰島を叩き伏せるのでなければならなかった。
「できません」
大鳳は言った。
緊張で声がかすれたが、せいいっぱいの意志を、その言葉にこめた。
「そうですか。しかたありませんね」
久鬼がつぶやくと、灰島が、いきなりわめき出した。
「殴ってくれ、大鳳!」
悲痛な声だった。
「頼む。おれを殴ってくれ。でないと――」
「黙りなさい」
久鬼が、言った。
低い、静かな声だが、拒否を許さぬ、断固としたものがあった。
久鬼は、両側に並ぶ道着姿の男たちに、悠然と視線をめぐらせた。
久鬼の眼が、ひとりの男の上で止まった。
「阿久津――」
久鬼が言った。
「は――」
と、その男が、頭をそびやかした。
それは、昼休みに大鳳を訪ねてきた男――空手部の阿久津だった。
「灰島も菊地も、空手部の人間でしたね」
「はい」
「主将のおまえが、大鳳くんにかわって始末をつけなさい」
灰島の身体が、硬直した。
ぬうっと、阿久津が立ちあがった。
巨大な
灰島の前まで歩いてくると、そこに立ち止まる。眼が、すっと細められた。
「いくらか手加減しなさい」
久鬼が、阿久津に声をかけた。
「わかっています」
答えるのと、手が繰り出されるのと、ほとんど同時だった。
灰島の頰に正拳がふたつ、腹に
灰島が、腹を両手で抱え、畳の上で身体をねじくって
大鳳は、そっと由魅の方を盗み見た。
由魅の眼は、熱く
逆に、九十九の顔には、あからさまな不快感が現れていた。その顔を見た時、大鳳はほっとした。正常な人間がこの場にいてくれることが、ひどくありがたかった。
「次は菊地ですね」
冷ややかな、久鬼の声が響いた。
菊地は、心持ち
「おまえは、ぼくの友人の九十九に、刃物を向けたそうですね。知らなかったとはいえ、許されないことですよ。もっとも、相手が悪かったようですがね。いや、相手が九十九で良かったと言うべきかな。これが、ぼくであれば、腕の一本も折られていたでしょう」
菊地の顔が、
昨日の屈辱を思い出したのだろう。
「阿久津、菊地には手加減は無用です。おもいきりやりなさい。ただし、ひとつだけです。急所はちゃんとはずすのですよ――」
「やめろ」
重い声で九十九が言った。
「これは
ほとんど何事にも動じない九十九の顔が、苦いものを
「やめなくていい」
硬い声でつぶやいたのは、菊地だった。
普通よりも小さい黒眼が、ぎらぎらと憎悪に燃えていた。
「おまえ、おれが殴られるの、見ろ。おまえ、見なくてはいけない。おれが平気なのを、ちゃんと、見ろ――」
菊地が、ぶつぶつと
その言葉が終わらないうちに、阿久津の強烈な前蹴りが菊地の腹にぶち込まれていた。充分に体重の乗った、みごとな一発だった。
菊地の身体は、数メートルもふっとんでいた。
阿久津とでは、身体の大きさが違っていた。身長で三〇センチ、体重では五〇キロ以上の差があるだろう。
素手の戦いの場合、
菊地は、げえげえと、昼に腹に入れたものを吐き出していた。
吐きながら、燃える眼で九十九を見ていた。
暗く青白い陰火の
「どうなってやがるんだ、まったく――」
九十九が、苦いものを吐き捨てるように言った。
「用事というのはこれだったのか」
「そうだ」
「おれは帰らせてもらうぜ」
九十九が立ちあがった。
「これで、昨日からのことは全部すんだと、そういうことにさせてもらう」
きっぱりと久鬼が言った。
「かってにするんだな。おい、大鳳、これ以上こいつらにつきあうことはない。出よう」
九十九にうながされて、大鳳は立ちあがった。足がもつれた。しびれて半分感覚がなくなっていた。
「無理をするからだ」
九十九が苦笑する。
大鳳はほっとした。この巨漢の笑顔には、見る者を安心させる力がある。
「大丈夫です」
大鳳は、ほっとした気持ちを面に現さないようにしながら、怒っているようにも聞こえる声で言った。足のしびれたことに対する気恥ずかしさが、そうさせたのである。
背を向けようとした大鳳に、久鬼が声をかけた。
「大鳳くん。よかったら華道部に入りませんか――」
久鬼の涼しい眼が、大鳳を見ている。
「――」
「まだ入部先を決めてないんでしょう」
「華道部、ですか」
「ぼくが部長をしています」
「でも、ここは――」
大鳳は、まわりに座っている道着を身につけた男たちを見回した。
「鬼道館の管理は、ぼくにまかされているのです」
大鳳は、平然とそう言ってのける久鬼に、寒さにも似た驚きを覚えた。
“まかされている”というのは、むろん学園からまかされているという意味であろう。それが、どの程度のことを意味するのかはわからなかったが、この場の雰囲気には、単にまかされているという以上のものがあった。
久鬼は、この場にいる男たちに対して、絶対的な支配権を持っていた。独裁者のようである。
体力的に、久鬼に劣ると思われない、阿久津や、柔道、空手、剣道の
この分では、久鬼が、死ねとひと言言えば、死ぬ人間だっているかもしれない。
「君の活けた花を見てみたい」
久鬼の眼が、静かに大鳳を見あげている。
「ぼくは――」
大鳳は、久鬼から視線をそらしてうつむいた。
「どうですか」
「ぼくは、花は好きです。けれど――」
大鳳は口ごもった。
「どうぞ、言って下さい」
久鬼が言う。
大鳳は、どもりながら言葉を探した。
とまどっているうちに、大鳳の意思に反して、その言葉の方が自然に口からすべり出ていた。
「――けれど、ぼくはあなたを好きになれません」
言ってしまってから、大鳳はその言葉の意味に気づき、びくっと身体が震えた。
その言葉を聴いた男たちが息を
一瞬静まりかえった部屋の中に笑い声が響いた。
大声ではないが、
九十九だった。
「こいつはいいや。見直したよ、大鳳」
九十九が、大鳳の肩に手をかけた。
「一本とられましたね」
と、久鬼が言った。
見ると、久鬼も口元に笑みを浮かべていた。
「じゃ、行くぜ」
久鬼に声をかけ、大鳳の肩に手をかけたまま、九十九は歩き出した。
KADOKAWA Group