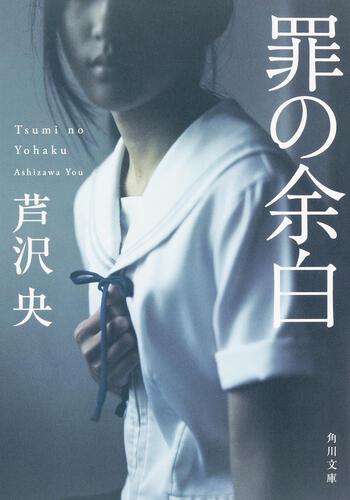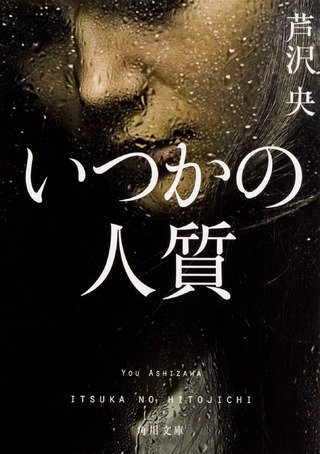「まさか、こうきたか」幕が上がったら一気読み!
いま、最も注目される作家・芦沢央による驚愕・痛快ミステリ『バック・ステージ』。
9/21(土)の文庫版発売を前に、第二幕「始まるまで、あと五分」を大公開します!
>>前話を読む
その日は未完の名作と言われていた王宮ファンタジーの六年ぶりの続刊の発売日で、奥田は自宅の最寄り駅前の書店ではなく、わざわざ電車に乗って高田馬場の書店に向かった。脇目もふらずにライトノベルコーナーへ進み、一冊だけ残っていたその本をまず確保してから、他にめぼしいものがないかと物色していた。
腕の中に抱き込んだ本をちらりと見下ろし、前日に読み返しておいた前巻のラストを思い出してホクホクしていたときだった。
「奥田くん?」
背後から自分の名前を呼ぶ声が聞こえて、ぎくりと背中が強張った。引きつるように固まった首をぎこちなくひねって振り返る。
そこにいたのが誰だか、すぐにはわからなかった。アッシュがかった長いストレートの髪、微かに垂れた丸い瞳と口角がくるりと上がった質感のある唇には、小動物のような愛らしさがある。スキニージーンズに包まれた脚はすらりと長く、高いヒールの靴を履いているのかと思って視線を足元に落としたら、ぺたんこのバレエシューズのような靴があった。腰の位置が高いんだ、と気づくのと同時に、こんなかわいい子知り合いにいたっけ、という疑問が湧いてくる。
えっと、と言ったまま視線をさまよわせた奥田に、彼女は口元に手を当てて首を傾げた。
「あれ、二中の奥田くんだよね?」
「え」
「覚えてない? わたし、伊藤だけど」
え、ともう一度バカみたいに繰り返して、目の前の女の子を凝視した。それくらい意外だったからだ。
──女の子って、こんなに変わるのか。
けれどたしかに、言われてみれば面影がないわけでもない気がする。小さな頭に整った顔立ち──中学の頃は髪形もあってかボーイッシュなイメージが強かったけれど、今やどこからどう見ても女の子だった。それも、かなりかわいい部類の。
「いや、覚えてるけど……ごめん、ちょっとびっくりしちゃって。伊藤、さん」
「呼び捨てでいいよ」
「伊藤……変わったよな」
伊藤は、ちょっとー、と言って奥田を上目遣いににらむ。
「それ、どういう意味?」
「あ、ごめん」
「うそうそ、大丈夫。変わったっていう自覚はあるから」
彼女は声のトーンをさらりと変えて、大きな目を細めて笑う。艶やかな髪を耳にかけ、そのままの流れで手をすっと持ち上げた。
「ところで、それ」
長く節の目立たない指の先を身体の真ん中に向けられて、奥田は反射的に後ずさる。腕の中に抱いていた本の存在を思い出し、「あ、いや」と口ごもった。
「これは……ちょっと落ちてたから拾っただけで」
「そうなの?」
彼女は言いながら奥田の方に手を伸ばした。えっと思う間もなく、奥田の腕の中にあった本をつかむ。ぐい、と引っ張られた瞬間、
「いや、これは俺の……」
奥田は、思わずそう言ってしまっていた。しまった、と思ったときには遅かった。よりによって表紙には、ドレス姿の女の子がマントをつけた男にお姫様抱っこをされたイラストがある。
妹に買ってくるように頼まれただけで。もし万が一誰かに見咎められたらそう答えようと用意していたセリフが、今さらのように浮かんでくる。今さらのように、ではなく、完全に今さらだ。
彼女の手が、本からそっと離れた。
「そうなんだ……」
ぽつりとつぶやく声が、深くうつむいた奥田の額の延長線上から聞こえた。
どうしよう、絶対に引かれた。
何で、こんなところで買おうとしてしまったんだろう。ネットで買えば、届くのが数日後になってしまったとしてもこんなふうに見つかることはなかったのに。いや、せめて本を手にしてすぐにレジに行っていれば──
奥田は頰の内側を嚙む。立ち去ってしまいたい。せめて、笑われる前に。
けれど、つむじに降るように聞こえてきたのは嘲笑ではなく、しょんぼりとしたため息交じりの声だった。
「そうだよね。ごめんね、つい、やった! って思っちゃって」
奥田は、顔を上げた。
「……驚かないのか?」
「何を?」
伊藤は不思議そうに首を傾げる。耳にかけられていた髪がさらりとこぼれるように流れ、奥田はふいに湧き上がったシャンプーの香りにたじろいだ。
「いや、だって俺がこういうの……」
そこまで言って口ごもる。すると、伊藤は「あ、そっか」と初めて気づいたように口を手で押さえた。
「でも、知ってたから」
「……知ってた?」
「うん」
伊藤は細く尖った顎を引いてうなずく。奥田は目を見開いた。いつから、と絞り出した声がわかりやすくかすれる。彼女は一瞬だけ迷うようにまつ毛を伏せた。
「中三のとき、市立図書館で見かけたことがあったから。西山弘美の新刊を持ってたから好きなのかなって」
奥田は口を金魚のようにパクパクと開いては閉じる。たしかに、中学時代はよく市立図書館に通っていた。だけど、同じ学校の知り合いに好きな本を借りているところを見られるのは嫌だったから、放課後や休日に行ったことは一度もない。図書館に行くためにわざと遅刻して、みんなが授業を受けているはずの時間に行くようにしていたし、誰にも気づかれずに済んだのだと思っていた。
誰からも、からかわれることがなかったからだ。
「だって、奥田くんがあのシリーズの話してるの聞いたことがなかったから、きっとみんなには知られたくないんだろうなと思ったの」
伊藤は、はにかむように頰を緩めて微笑む。
「だけど本当は話してみたいなって、ずっと思ってた」
柔らかく弾んだ声で続けた。
「面白いよね、このシリーズ。わたしも大好き」
もうこのときには、彼女のことが好きになっていたのだと思う。
それが、彼女との再会だった。
結局、その本は奥田が買って帰ることになった。
奥田は譲ろうとしたのだが、伊藤が「それは奥田くんのでしょ」と言って聞かなかったからだ。
「でも、本当にいいのか? これ欲しかったんだろ?」
奥田が繰り返すと、伊藤は端整な顔を惜しげもなくくしゃりと歪めた。
「もう、せっかく決めたんだから揺るがせないで」
「いや、だったら」
いいよ、と続けかけた奥田を、彼女は身体の前に両手を伸ばすことで遮る。その代わりにと言っては何だけど、と低いトーンの声で言って顔の前で手を合わせた。
「ちょっとだけ見せてくれない?」
「もちろん、そんなことでいいなら」
伊藤の顔はパアッと音が聞こえそうなくらい瞬時にわかりやすく輝いた。
「やった! ずっと楽しみにしてたの。どんな展開になるんだろうっていっぱい想像して」
「ああ、それわかる」
奥田は頰をほころばせながら袋ごと伊藤に渡す。彼女は飛びつくように袋をつかみ、中から本を取り出した。キラキラしたイラストが現れ、奥田は思わず周囲をうかがってしまう。けれど彼女は気にするふうもなく、匂いさえ嗅ぎかねない勢いで顔に本を近づけた。へえ、と無防備な声を上げ、つぶらな瞳を細める。
「どうしたの?」
奥田がうずうずして訊くと、伊藤はうん、と上の空でうなずいてから、また数秒の間を置いて、うわあ、と感嘆の声を上げた。
「え、何?」
堪えきれずに覗き込むと、彼女は内容紹介のところを指さして声のトーンを上げる。
「これ、すごい予想外じゃない?」
奥田は促されて裏表紙に書かれた数行に目を通し、うわ、とうめいた。
「ほんとだ……やばい、これは予想できなかった」
「でしょでしょ? え、奥田くんはどんな展開だと思ってた?」
奥田は、答える代わりに、せっかくだからお互いの予想を話しながらお茶でもしないか、と口にしていた。口を閉じてから、自分が彼女を誘ったのだという事実に気づき、そんな自分に驚いた。
自分から他人と距離を縮めようとしたのは初めてだった。
伊藤は、はしゃぐように手を叩き、「それいい!」と高いままのテンションで同意してくれた。
奥田たちは喫茶店に場所を移し、近況報告もそこそこに物語の展開予想を始めていた。まず彼女が口にして、奥田はそれに勇気づけられて話す、という形で。
奥田は、それまで溜め込んできたものをすべて吐き出そうとするかのようにしゃべり続け、途中で授業が始まる時間が過ぎたことに気づいたけれど、気づかなかったふりをした。
さらにそのシリーズのスピンオフについて話題が移る頃には、奥田たちは四年のブランクなどなかったかのように、そもそも中学時代にもほとんどしゃべったことがない関係だとはわからないくらいに打ち解けていた。
伊藤の予想や感想はどれも面白かったし、彼女は奥田が何を言っても面白がってくれた。新鮮だった。自分が好きなものについて、夢中になって話せる相手がいるということが。
彼女は興奮してくると、奥田のことを「奥ちゃん」と呼んだ。一度目はぎょっとしたものの突っ込むタイミングを逸して流してしまい、二度目に呼ばれたところで「奥ちゃん?」と聞き返す。
「あ、ごめん。何か……心の中でそう呼んでたからつい」
彼女が頰を赤らめながら髪を耳にかけるのを見ると、胸の奥がくすぐったくなった。いいよ別に奥ちゃんで、と何でもないように言ってみせてから、思いきって奥田も「みのり」と呼んでみた。
「え?」
「みのりって呼んでいい? ほら、俺も心の中でそう呼んでたし」
言い終わる頃には、既に自分が調子に乗って踏み込みすぎたことに気づいた。伊藤の視線がテーブルの縁をなぞるようにさまよう。
「あ、いきなりごめん」
何となく気まずくなって謝ると、伊藤は、ううん、と小さく首を振った。
「……ごめんなさい、わたし、名前で呼ばれるの苦手で」
「そっか、じゃあ伊藤で」
奥田はできるだけ明るく言って、キャラクターの話に戻った。
それぞれにコーヒーとカフェオレを飲み終わっても、さらに水が空になるまで粘っても、まだまだ話し足りなかった。
奥田は試しに「やばい、全然話し足りないな」とつぶやいてみた。すると伊藤は、「ね」と言って目を細める。奥田はごくりと生唾を飲み込んだ。
そろそろ腹も減ってきた。この感じならご飯に誘っても断られないかもしれない。まずはこのあとの予定を聞いて──膨らんだ思いが、ふいにつぶれた。さっきの彼女の困った顔が浮かんできてしまう。また踏み込みすぎだと思われたら、と思うと喉の奥がきゅっと締まるように詰まった。
奥田は、本を彼女に差し出した。
「これ、やっぱり伊藤が先に読んでいいよ」
「え、でも」
「だからまた会ってくれないかな? 好きなものについて人と話すのがこんなに楽しいなんて正直思ってなかったし」
伊藤と話すのが楽しいから、と言う勇気はまだなかった。
「連絡先教えてくれない?」
奥田が言いながら携帯をポケットから取り出すと、伊藤も「あ、うん」と言って鞄の中を覗き込んだ。携帯を見下ろし、何かの操作をしたところで動きを止める。
「俺がQRコード出すんでいい?」
奥田が画面にQRコードを表示しながら言うと、彼女は携帯をテーブルに伏せて置いた。
「ねえ、奥ちゃん。せっかくだから古風な待ち合わせにしない?」
「古風?」
「うん、携帯で連絡を取り合うんじゃなくて、携帯がなかった頃みたいに会うの。来週の同じ時間、同じ書店で。もし三十分待っても来なかったら都合が悪くなったってことにして」
「いいね、それ」
そう答えながらも、内心では心許なかった。連絡先を交換したくないということだったとしたら、という疑念が拭えなかった。実際にもう一度彼女と会えるまでは。
次の週、書店に現れた彼女に、奥田は正直に不安だったことを告げた。すると彼女は「そっか、そうだよね」とうなずいた。
「じゃあ、交換しようか」
あっさりと言って、鞄から携帯を取り出す。
そして今度こそ連絡先を教えてくれたのだった。
〈第5回へつづく〉
ご購入はこちら▶芦沢央『バック・ステージ』|KADOKAWA
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。