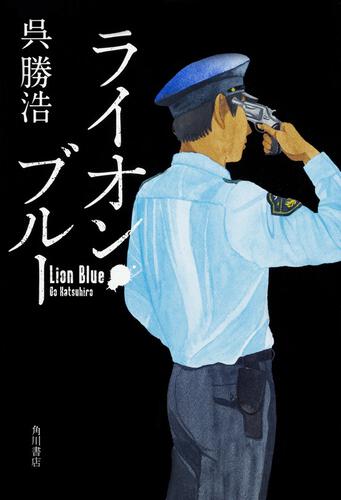「お前、よく生きていられるよな。」連続銃殺事件が生んだ、もう一つの悲劇。呉勝浩「スワン」#16
呉勝浩「スワン」

誓って、悪意はなかった。
おなじ一組にいた古館小梢に、初めいずみは気づかなかった。高校一年生とは思えないプロポーションや、くりっとした二重瞼がうらやましい。ストレートの長い髪は艶っぽくて上品で、立ち振る舞いは華やかで、クラスの男子も女子も、そろってお近づきになろうとしているのも納得だ。クラシックバレエという、世間的にはぱっとしない習い事に没頭している自分とは住む世界がちがう人。その程度の認識だった。
だから、まだクラスメイトの顔と名前が一致しないくらいの時期に、とつぜん話しかけられたときはびっくりした。
片岡さーん。
次の授業のため教室を移動しているところだった。
片岡さんもこの学校だったんだね。準備に手間どったいずみはひとりきりで、小梢の周りにもめずらしく取り巻きがいなかった。
あ、うん─と、いずみは返した。息を殺してひっそり過ごしている自分に、クラスの中心で咲く花みたいな女の子がなぜ話しかけてきたのかわからずに戸惑った。
その戸惑いはすぐ、小梢に伝わったらしかった。
え? 嘘でしょ?
初めは笑い半分だった。
ほんとに? ほんとに、わたしのことわからないの?
わからなかった。おなじ学校のクラスメイトという以外、ほんとうに。
……ふざけんな。
イメージしていた彼女からは想像もつかない乱暴なつぶやきに、いずみはいよいよ混乱した。
ちょっと踊れるからっていい気になんなよ!
そう吐き捨てて去っていく小梢の背中を、呆然と見送った。
次のレッスンで気づいた。小梢は、いずみとおなじバレエ教室に通っていたのだ。つい最近、いずみがごぼう抜きにした練習生のひとりだったのだ。
レッスンのときは周りが見えなくなるタイプで、そもそも古舘さんとはレッスンクラスがちがってて、わたしはずっと下手くそのクラスで、それに途中からやる気も失ってて、最近ようやく本気で取り組むようになったばかりで、だから─。
だから? だから、いずみが追い抜くまで同世代のトップだった彼女に気づかなかった?
ちがう。そうじゃない。
たんに興味がなかっただけだ。バレリーナとしての古館小梢に、これっぽっちも。
本音を隠した弁解は空回りし、関係はこじれる一方だった。ほどなく周りのクラスメイトからも白い目を向けられるようになった。教室の姫君に無礼をはたらいた身のほど知らずは懲らしめるべき。そんな空気が、ごく自然に広まっていた。
陰湿ないじめは、最初じゃれ合いのヴェールをまとっていた。休み時間、わざわざいずみが座る席を囲んでおしゃべりをし、けれどいっさい無視する。その場を離れようとすると、「ああん、片岡さん、冷た~い」と茶化す。体育祭では創作ダンスのリーダーを無理やり押しつけられた。片岡さん、踊りは本職だもんね? 小梢のゆがんだ笑みがクラスに伝染していた。誰ひとり、ダンスに協力的な者はいなかった。放課後の練習はたんなるおしゃべりの場と化し、そのうち見かねたように小梢が振り付けや配役を仕切りだした。片岡さんは先頭にいてくれたらいいから。練習なんてしなくても平気でしょ? ほら、バレエの練習に行かなくていいの? 体育祭当日、クラスメイトはいずみが知らない振り付けで踊った。先頭に立たされ、棒立ちになり、ふり返ると、みな必死に、笑いをこらえていた。なかには吹きだす者もいた。ダンスが終わり、肩を組んではしゃぐ輪を外から眺めるうちに、いずみのなかで区切りがついた。
かまうもんか─。吹っ切ってしまえば日常化した陰口も、教科書にされる落書きだとかも鼻で笑ってやり過ごすことができた。小梢とはバレエ教室でも顔を合わせたが、教室は完全実力主義だったから、よけいな嫌がらせに悩むことなく練習に打ち込めた。ならばいい。かまわない。
時間も思考も情熱も、自分に許されたエネルギーのすべてをバレエにぶつけた。一日ごとに上達していくたしかな手応えが楽しかった。いままでわからなかった上級者と自分のちがいに気づくようになり、そのちがいを埋めていくたびに達成感が込み上げた。
小梢との差はぐんぐん開いた。開いたぶんだけ彼女のプライドは傷ついたのだろう。引き返せなくなるほどに。
ある日、男子に写メールが出回った。レッスン教室でのいずみの写真だ。胸をそらしているものや、大きく開脚しているものもあった。レオタードは身体にぴったりフィットしていた。練習着もポーズも、それがあたりまえだから、いずみに恥ずかしいという感覚はなかった。とはいえ男子のスケベ面は不愉快だったし、女子の冷やかす眼差しもうっとうしかった。
何より、がっかりした。バレエをいじめの道具に使った小梢に、はっきりと失望した。
そうか。わかった。あなたはその程度の人間なんだ。
いずみは完全無視の態勢をつくった。学校ではいっさいの感情を殺した。ここは舞台裏の、やかましい控室なのだといい聞かせて。
それがまた、小梢にはおもしろくなかったのだろう。取り巻きをけしかけ、クラスメイトを味方につけ、教師すら手玉にとって、いじめは少しずつエスカレートしていった。
そのうち、いずみは気づいた。もはやクラスメイトたちは小梢の意思に従っていずみをからかっているわけではなかった。クラスの姫君が与えた最下層の人間というお墨付きが定着し、いつの間にかいずみは、彼らにとっておなじ人間のカテゴリーに入っていないものとみなされていた。何をしても許される、架空のキャラクターであるかのように。
ちょっとした暴力沙汰が起こった。男子と女子の四人組にからまれ、馬鹿にされた。無視していると、片方の男の子に足を蹴られた。瞬間、いずみは手近にあった花瓶を彼らの足もとに投げつけた。ガシャンと音が響いて、教室が静まった。呆気にとられた観客のなかに、小梢もいた。
わたしの足に、さわるな。
そう、彼らにささやいた。このときばかりは、殺してやろうか─、という凶暴な感情がこぼれかけた。
結局、彼らは強がりのような捨て台詞を残し引き下がった。花瓶は不注意で倒したことにした。適当にごまかしたのは、いじめを真澄に知られるのが嫌だったからだ。
鮎川快と、初めて言葉を交わしたのはその直後くらいだ。放課後に呼び止められ、「ちょっといいか?」と物理教室に招かれた。そして「悪いな」と謝られた。
古館は、まだ子どもなんだ。許してやれとはいわないけど、おれからも釘を刺しておくから、だから─。
だから、なんなのか。
目をそらし、ぼそぼそしゃべるさまは、まるで世話のかかる姪っ子の尻ぬぐいをさせられているお兄ちゃんといったふうで、呆れる思いと気の毒な思いと、同時にいずみは、そんな鮎川をかわいらしく思った。
この先、ほっといてくれるなら気にしない。いずみは彼にそう伝えた。それからすぐに冬休みになったから、小梢とはレッスン教室で顔を合わせる程度になった。三学期になり、そして春休みになり─。
ピロリン、とスマホが鳴った。いずみは電車の座席でそのメッセージを受信した。真澄からだった。職場の休憩時間なのだろう。ちょっと疲れたから早退する。明日も登校できると思う─学校を出た直後に送ったメッセージに、〈オッケー。ゆっくりやってこう〉と返ってきた。ああ、北代のアドバイスを受けているんだなと納得しながらスマホをしまう。少しだけ負い目を感じた。
ちょっと疲れたのも嘘じゃないけど、早退のほんとの理由は、内緒の買い物がしたかったからだ。
電車に乗る前に寄った家電量販店。これを使って、上手くやれるだろうか。
やる必要が、あるのだろうか。
電車が川の上の鉄橋に突入する。いずみは身体をかがめ、目をつむる。
翌日もいずみは相談室に陣取り、昨日こなせなかったテストに挑んだ。ゆうべ、仕事を早く切り上げた真澄はデパートで少し高級な中華料理をテイクアウトしてきた。食事を終えるまでずっとご機嫌だった。
もう大丈夫だといずみは告げた。明日は最後まで学校にいるつもりだから気をつかわないでほしい。いつもとおなじように働いてくれていい。
すべて自分の都合だったが、嘘ではなかった。じっさい朝から昼休みを越え、五時間目になるまでちゃんと勉強に励んだ。手洗いのとき以外、この狭い部屋に閉じこもったままではあるけど。
窓から茜色の光が差し込んでいた。風は涼しさを増している。パーカーを持ってきて正解だった。放課後の予定を考えると制服の着替えもほしかったが、さすがにそれは我慢した。
放課後の予定。心はまだ、ふらふらしている。
ぼんやりと、さえない裏庭の景色を眺めた。塀の向こうを車のエンジン音が、どこか眠たげに過ぎていった。
こうしていると、やがて何もかも、ふつうに落ち着いていくんじゃないかという気がした。そのうち教室に顔をだし、新しいクラスメイトとあいさつを交わし、ほどほどの距離でつき合う。勉強もできるだけ追いつこう。真澄はよろこぶにちがいない。感情の乱高下もマシになるだろう。そうなれば、いずみもうれしい。
でも、まあ、授業に追いつくのは、ちょっと厳しそうだけど。
まっ白なテスト用紙に、いずみは猫の落書きをする。
ホームルームが終わる前に学校を出た。帰りがけ、二学期のうちに教室に顔をだそうな、と牛倉にいわれ曖昧にうなずいた。けれど、そのとおりだなとも思う。
今日、鮎川は姿を見せなかった。ほっとしたような、拍子抜けしたような気持ちでパーカーを羽織り、駅を目指した。
この期におよんでなお、迷いは消えていなかった。このままあの場所へ出向くべきなのか。出向いて、どうするべきか……。
ふいに、足が止まった。駅の改札の手前にちょっとしたすり鉢状の広場のコンクリートの階段に、思わぬ人物がいた。まるで待ち受けていたかのように、いずみを見つけ立ち上がる。
「よっ」
その気さくさに、面食らってしまった。
「なんで……」
「ガッコ行きはじめたって真澄ちゃんに聞いた。ここにいたら会えるかなって思ったら、マジで会えた」
そういって、芹那は歯を見せた。爆発したような黒髪、ギザギザに破れたジーパンに、ギトギトなイラストが描かれた黒地のTシャツ。ぴったりしたジャケット、ブーツ。西日に照らされたいずみの幼友だちは、最後に会ったときより三倍くらいとんがり度が増していた。
「元気そうじゃん」
芹那の足もとから声がした。階段に寝そべるように座っているごついニット帽の男子がいずみを見上げていた。トシくんというふたつ上の先輩で、夜遊びをしていたころ、エンジンがうるさいビッグスクーターによく乗せてもらった。
「ひさしぶり」
トシくんのとなりにいる甘いマスクのひょろ男はユージくんだ。トシくんのツレで、やっぱり夜遊び仲間だった。芹那が、彼らといっしょにライブハウスの手伝いをしているという話はちょくちょく本人から聞いていた。
「もう一年以上になるのかあ? 片岡あ、おれはさみしかったぜえ。おめーにすっかり避けられちゃってよお」
トシくんの口ぶりに嫌味な感じは少しもなかった。やんちゃな見た目をしているけれど、みんな気の良い奴らだと、そこを疑ったことはない。
「仕方ないんだってば。バレエって、けっこうアレな業界らしいから。ホシュ的。わかる? ホシュって」
「あん? あれだろ、伝統をリスペクトみたいな」
「まあ、トシの脳みそにしては上出来かな」
芹那とトシくんの掛け合いに、いずみは胸が熱くなった。懐かしかった。そしてうれしかった。
「で? どうなの、ガッコは」
とっくにドロップアウトしている芹那に訊かれ、「まあ、なんとか」と返す。
それより片岡さあ、その頭、ちょっともさくねえかあ? うっさいよ、トシ。いや、マジで、たぶん片岡って、やりようによっちゃあすげえいけてるはずだぜ。
他愛ないおしゃべりがつづいた。以前のように打ち解けることはできなかったが、それでもいずみはあたたかさを噛みしめた。連絡を絶っていたことを馬鹿らしく思うほどに。
「たまにはさ、会おうよ」
芹那がいった。「店にきてくれたら一杯おごる。トマトジュースでもグレープフルーツジュースでもリゲインでも」
「うん」
鼻の奥がツンとした。自分の都合で距離を置いた仲間たち。ほんとうに身勝手だと思うけど、いまは彼らがありがたかった。
大丈夫なのかもしれない。この人たちがいてくれるなら、もしかして─。
涙声にならないよう気をつけた。「ぜったい行く。もうちょっと、いろいろ落ち着いたら」
「メッセージしてよ。いつでもいいし、なんでもいいから」
うん、といずみがくり返したとき、
「でも、片岡さ」
甘いマスクのユージくんがもらした。
「ぜんぜん元気でびっくりした」
こちらを見るユージくんの目に、問いかけるような気配があった。「だっておまえ、すげえことになっちゃってさ。おれだったらたぶん無理。耐えらんない」
芹那が何か口にしかけたが、ユージくんのほうが早かった。
「あんなことになったのに、よく生きていられるよな」
ひゅっと息がつまった。まばたきを忘れた。
「おい」芹那が頭をはたいた。ユージくんはピンときてない顔だ。
「いず」
「大丈夫。気にしてない。ユージくんのいうとおりだし」
このわずかな時間で、西日はくすみ、短かすぎる夕方が終わろうとしていた。
「ごめん。わたし、もう行かなくちゃ」
「バレエ?」
いずみは、芹那を見返し、
「ううん。バレエは終わり」
ふっ切るように改札へ急いだ。
お茶会の時刻が迫っていた。
〈このつづきは、単行本『スワン』でお楽しみください!〉
初出:「カドブンノベル」2019年9月号
(掲載時から登場人物の名前を一部変更しております)