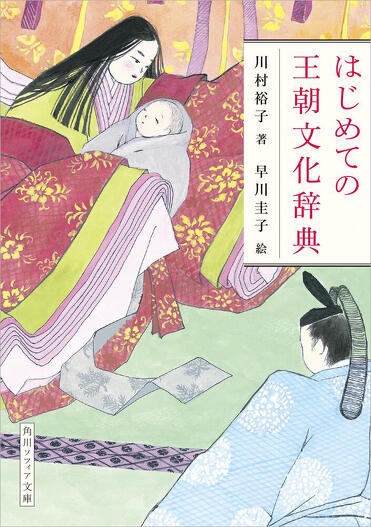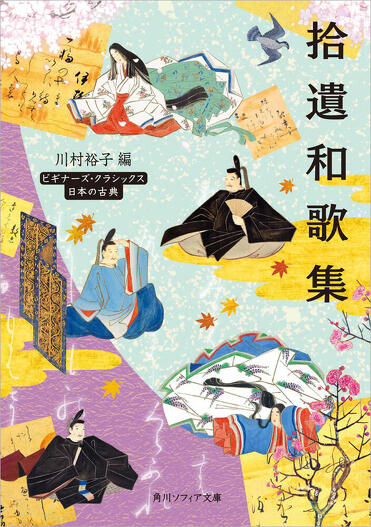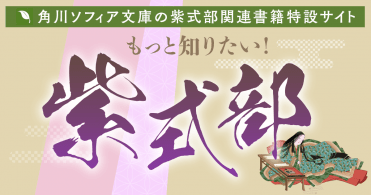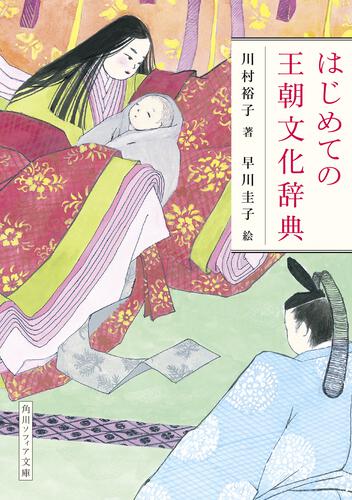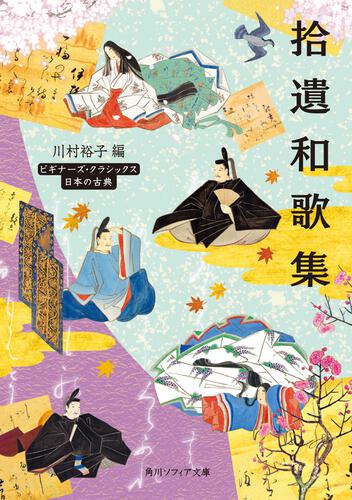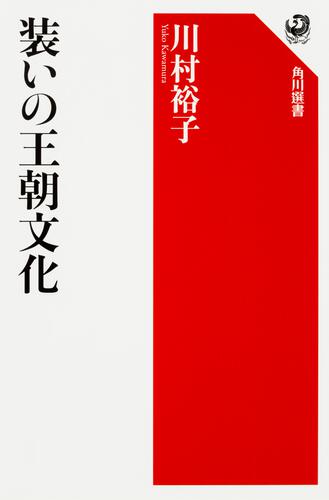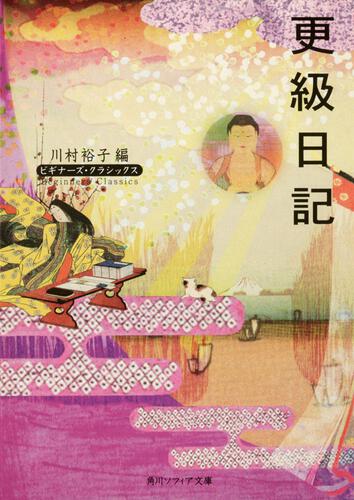第三回 ライフ・オブ・平安! 【大河ドラマを100倍楽しむ 王朝辞典 】
大河ドラマを100倍楽しむ 王朝辞典
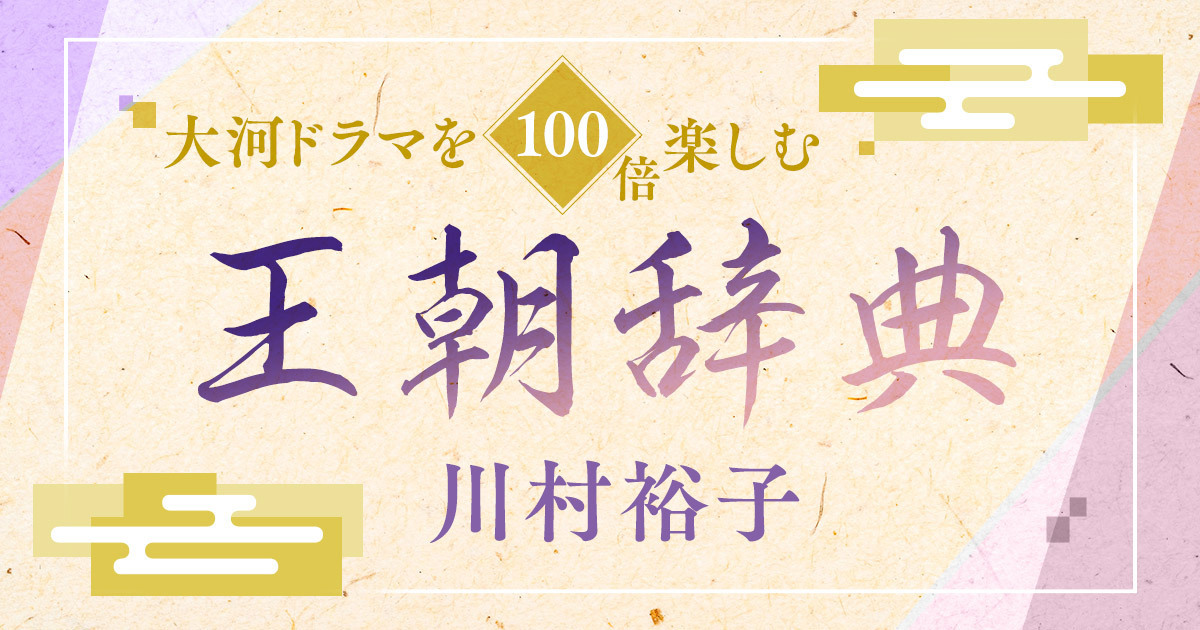
第三回 ライフ・オブ・平安! 【大河ドラマを100倍楽しむ 王朝辞典 】
さて、今までは登場人物についてやさしめに語ってきました。これから登場人物の合間合間に平安人のライフについてもお話しいたしますね。
偉い政治家でも普通の人でも一日の生活はそれほど違いません。今だってそうですよね。朝起きて夜寝る生活が基本となってます。こんなライフのなかで、彼らはどのような暮らしをしていたか。それって知りたいですよね。涙も笑いもみんな生活のなかから生まれるのだから……。
それでは、彼らの生活の二十四時間をざっくり、本当にざっくり見ていきましょう。
平安男性の二十四時間
朝は何時ごろから始まるのでしょう。一回目の太鼓は、まず夜が明ける合図。それは四時半から六時半。そして二回目の太鼓が出勤の合図となります。それが、だいたい五時半ごろ(夏)~七時五十分ごろ(冬)。どうでしょう。早いですよね。
さて、この一回目と二回目の太鼓の間に出勤前のバタバタがあります。朝の仕事はたくさんあるみたい。出かける前に、前日の日記を書いたり、
それで食事は? 実は平安ライフのなかで、食事は二回なんです。だから朝食はとらないのが普通。時としてお粥みたいなものを食べるけど……。
『蜻蛉日記』のなかで
さて、着替えて出勤。ここではエリート公務員の一般例で
さて、蔵人は、まず「
出勤簿のセッティグが終わったので次は会議に参加。やっぱり昔から会議はあったみたいです。ストレスフルですね。
主に
そして、午前中の勤め(午前十一時ころ)で一区切り。それは今と違うでしょうか。この半ドン勤務は
ということは月に十日はフルタイム。夜中までなんですね。かなりハードでブラックな職場です。こんな毎日大変そう。過酷なオフィス事情ではありますが、平安男性はそのなかで、恋をして楽器をひいて、歌を作ってました。「いったい、いつ?」と思いたくなりますよね。でもね、彼らはハードのなかにミヤビを求めていました。忙しい、忙しい、なんて言ってるのは、情けないし、野暮。
どんなに忙しくても、ゆったりと恋をする、これが平安男性のミヤビ! だったのです。
平安女性の二十四時間
さて、それでは平安女性にいきましょう。当然、平安マダムたちは、だいたい男性と同じ時間に起きます。だから早いのね。四時半から六時半ぐらいでしょうか。
それから、重要なお仕事は夫のファッションコーディネート。変な格好をしていると、貴族の間では噂がすぐに流れてしまいます。噂の早さはTwitter(X)以上。そんなわけですから、リキが入ります。
もちろん素材やら色やら縫い方も大切ですが、それ以上に気を遣ったのはなんでしょう。それは「着た姿」なんです。どんなに良い物を着ていても、着方が悪かったり、ぶかぶか過ぎたりすればアウト。これは今も同じですね。
ゆったりと着るのですが、背筋はピシッと伸びている。そんな姿に合った着付けが必要なんです。背中の筋が真ん中ではなく、ずれていたりすると左右アンバランスになってだめ。また、首が前のめりに見える「抜き襟」も男性の着付けとしてはみっともない。そんな姿をチェックしながら整えていくのが平安マダムの役目でした。
なお、この装束関係を得意とする人物がいました。それは『蜻蛉日記』作者の道綱母です。染色、仕立て、仕立直しなどの装束調整は妻の仕事。兼家は、いつも仕立ての上手な道綱母に頼みます。なんと離婚していても道綱母に装束の調整を頼んでいるのです。
さて、あと家にいる平安マダムの仕事としては、食事の用意など。男性編で述べたようにご飯の用意ですね。ブランチです。おうちご飯の多いブランチは午前十一時から十二時ごろでした。
また、ルーティンワークではないけれど大変な出産や子どもの教育も大仕事。出産は五分の一の母親が亡くなるので、命がけです。また子どもの教育もお習字や和歌を教えていました。こんなことをしながら、夫が家に来たら、それなりの家事や世話をして、一日を過ごしていたのです。
さて、それでは、お勤めの女性のビジネスライフはどうなのでしょうか。
朝はやはり最初にお話ししたように出勤時間が五時半ごろ(夏)~七時五十分ごろ(冬)ですので、それに合わせて起きます。
それと身繕いですね。このファッションコーディネートは、いったい何時間かかるのでしょう。まず大変なイベントの記録が残ってます。それをお話ししますね。
このイベントは、『紫式部日記』に出てくる一条天皇の
彰子は一条天皇の息子の
そんななかで、一世一代のセレモニーなので、紫式部たちもセッティングに余念がありません。さてさて、いったいどれくらいの時間が、メイク&装束コーディネートにかかるのでしょうか。
御幸は午前八時ごろということで、まだ夜明け前から、女房たち(貴人の世話をする女性たち)はお化粧をして、準備をしています。(『紫式部日記』)
おお。夜明け前だから、午前三時~四時ごろでしょうか。そのころから午前八時に備えています。四時間前ぐらいですかね。すごい。ちなみにこのイベントの年月日がわかるのですよ。それは一〇〇八年十月十六日。大きなイベントだから、かなり大変な準備をしたのだと思います。
イベントだからセットもメイクもリキが入りますよね。『枕草子』のなかにも「
さてファッションコーディネートのお話に、時間がかかってしまいましたが、女房たちは時間に決められたルーティンワークはありません。というのも、仕えている女性の世話が主な仕事なんですね。髪を整えたり、お話相手をしたり、はたまたいろいろなことを教えたりします。そのなかで一番大切なのは、なんと取り次ぎ役。
そう、女主人の言葉を伝える役目です。なんで大切か、というと女主人の言葉をそのままダイレクトに伝えるのではなく、そこに改良を加えるから。美しい言葉を使ったりして、少し「盛る」のです。
そうすると女主人について「すてきな人だ!」「ハイセンス!」といったような噂が広がり女主人の評判がグッと上がります。
このように、彼女たちのビジネスライフは、お仕事をこなしながら、仕えている女主人を盛り上げることでした。
プロフィール
1956年東京都生まれ。新潟産業大学名誉教授。活水女子大学、新潟産業大学、武蔵野大学を経て現職。立教大学大学院文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程修了。博士(文学)。著書に『はじめての王朝文化辞典』(早川圭子絵、角川ソフィア文庫)、『装いの王朝文化』(角川選書)、『平安女子の楽しい!生活』『平安男子の元気な!生活』『平安のステキな!女性作家たち』(以上岩波ジュニア新書)、編著書に『ビギナーズ・クラシックス日本の古典 更級日記』『ビギナーズ・クラシックス日本の古典 拾遺和歌集』(ともに角川ソフィア文庫)など多数。
作品紹介
王朝の文化や作品をもっと知りたい方にはこちらがおすすめ!
『はじめての王朝文化辞典』
著者:川村裕子 絵:早川圭子
https://www.kadokawa.co.jp/product/321611000839/
『源氏物語』や『枕草子』に登場する平安時代の貴族たちは、どのような生活をしていたのか?物語に描かれる御簾や直衣、烏帽子などの「物」は、言葉をしゃべるわけではないけれど、ときに人よりも饒舌に人間関係や状況を表現することがある。家、調度品、服装、儀式、季節の行事、食事や音楽、娯楽、スポーツ、病気、信仰や風習ほか。美しい挿絵と、読者に語り掛ける丁寧な解説によって、古典文学の世界が鮮やかによみがえる読む辞典。
『ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 拾遺和歌集』
編:川村裕子
https://www.kadokawa.co.jp/product/322303001978/
『源氏物語』と同時期に成立した勅撰和歌集。和歌の基礎や王朝文化も解説! 「拾遺和歌集」は、きらびやかな貴族の文化が最盛期を迎えた平安時代、11世紀初頭。花山院の勅令によって編まれたとされる三番目の勅撰和歌集。和歌の技法や歴史背景を解説するコラムも充実の、もっともやさしい入門書。
角川ソフィア文庫の紫式部関連書籍特設サイト
https://kadobun.jp/special/gakugei/murasakishikibu.html