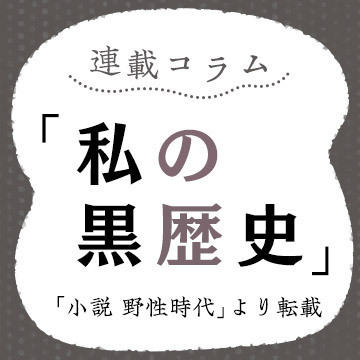万葉集に、親しもう。
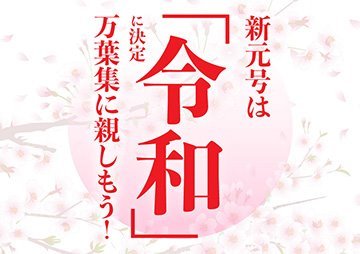

新元号となる「令和」がでてくる『万葉集』の「梅花の宴 序」。この文章を記したといわれている大伴旅人は、いったいどんな人物だったのでしょうか。また、どんな思いでこの序文を記したのでしょう。
国文学者の中西進先生の著作『古代史で楽しむ万葉集』から、大伴旅人について、梅花の宴について記された部分を一部試し読み!
----------
旅人は神亀三、四年(七二六、七)のころ大宰帥に任ぜられて筑紫に赴く。先立って征隼人大将軍として炎熱の九州に下向したことはすでに述べたとおりで、旅人としては二度目の九州生活ではあったが、以前の軍事の艱難に代わって、また別の精神的苦境にあった。
大宰帥はけっして軽職ではないが、この赴任は藤原氏の策略であろうといわれている。つまり旅人は辺境に追いやられたのである。そして旅人はこの辺土まではるばる同行した妻を、その地で失っている。赴任後一、二年のことである。その悲しみは万葉集に十三首(巻三、四三八─四四〇、四四六─四五三。巻五、七九三。巻八、一四七三)の歌となってあらわれる。しかもおりにふれて、幾度にも。これはほかに例のないことである。
さらにこのとき旅人は六十二、三歳の身を九州に運んでいた。すでに、意気壮んといった年齢ではない。老齢といってよいだろう。目に見えない藤原氏の圧迫と、明らかな敗北感の中に、老いの身を筑紫に運んだ旅人を待ちうけていたものが、妻の死だったことになる。
万葉集には、この大宰府時代以前と思われる旅人の歌が、たった一種類しかない。中納言旅人の吉野従駕の長歌とその反歌(巻三、三一五・三一六)だが、しかもそれは何かの都合で奏上するにいたらなかったものである。
また大宰帥から大納言に栄転して帰京したのちの歌にしても、二首を除いて大宰府時代と関係をもつ。つまり旅人は、ほぼ大宰府の関係において万葉集に歌をとどめているといえる。
われわれはその大宰府の歌から、彼がどのような心情でその地にあったかを、つぶさに知ることができるが、それらを通してもっとも大きなひびきを伝えて来ることは、彼の心がつねに現実にはない、ということである。亡き妻をしのぶということも、そのひとつである。
愛しき 人の纏きてし 敷栲の わが手枕を 纏く人あらめや
(巻三、四三八)
その内の任意の一首(愛する人が枕としたわが手を、他に枕とする人はいない)だが、妻の「纏きてし」という過去の回想の中に旅人はいる。そして現在は、纏く人はいないという否定の中にある。過去を回想するにしろ未来をねがうにしろ、旅人の現実感はとぼしい。
だから心はつねに望京の念にさいなまれる。
隼人の 湍門の磐も 年魚走る 吉野の滝に なほ及かずけり
(巻六、九六〇)
(隼人の瀬戸の岩も美しいが、鮎が走る吉野の急流に及ばない)
筑紫の新鮮な風土に感動することは、必ずやあったはずである。しかしその結論とするところは、やはり吉野の方がよい、ということだ。「いざ子ども 香椎の潟に 白妙の 袖さへ濡れて 朝菜つみてむ」(巻六、九五七)という一首でさえ香椎の清遊に興ずるだけの旅人を、われわれは考えがたい。「袖さへ」というのは、裾に対していうのだから、全身を濡らすことになる。全身濡れそぼちながら朝の菜を拾おうという旅人は忘我の中にはいっていこうとする姿である。現実を離れて。
こうした感情のあり方こそ、いくつかの旅人の大宰府歌を解く鍵となる。そのひとつが梅花の宴である(巻五、八一五以下)。旅人が三十一人を集めて梅花の歌宴を催し、蘭亭の序をまねた漢文の序を書き、しかも以後しばらくを興奮さめやらぬかのごとく追和の歌を重ねるというのは、ただごとではないだろう。これも「袖さへ濡れて」という感情である。
また玉島の淵に遊んで仙女と逢ったといって遊仙窟まがいの空想をする(巻五、八五三─八六三)。対馬産の琴を房前に送るといって、夢の中で琴の娘子とみずからとが贈答した形の歌を送るという趣向(巻五、八一〇・八一一)も同じである。
旅人はなぜこのように夢想的にならなければならないのか。実は「酒を讃むるの歌」という風がわりな十三首(巻三、三三八─三五〇)をつくるのも、それにほかならないだろう。その第一首、
験なき 物を思はずは 一坏の 濁れる酒を 飲むべくあるらし
(巻三、三三八)
「思ってもかいない物思いをやめて、酒を飲むのがよい」というのは、彼の本心である。
それを裏側から証明するものが、松浦佐用姫の歌だと思われる(巻五、八七一─八七五。ただし全部が旅人の作かどうかは不明)。祖先の英雄大伴佐提比古の征韓の船を見送って領巾を振ったという佐用姫の伝説を取り上げた旅人の気持には、引きかえてあまりにもいたましい現実の大伴氏の姿があったのではないか。「万代に語り継げ」と領巾を振ったのかと、旅人はいう。大伴氏栄光の日のロマンを、万代に忘れがたいものとしたいのである。しかしこの五首の中四首までに「けむ」「けらし」という過去推量のことばが用いられている。過去は結局過去でしかなかったことも、旅人は知っていたのだった。
そして、この寂寥をいやすものは都に帰ることしかない。望郷の念はここに生ずる。「平城の京師」を思う(巻三、三三一)と同時に、旅人は香具山を思い(巻三、三三四)、また後には平城の都にあって故郷飛鳥の神名火の淵や栗栖の小野を思っている(巻六、九六九・九七〇)。その子家持も越中にあって同様の思いを抱いたが、それはただ一つ、奈良の都だった。その父旅人には、なお飛鳥への思慕が生きていた。
大和への思慕が彼の寂寥をなぐさめたのであった。
---------------------
還暦をすぎ、遥か大宰府の地に任ぜられ、妻も亡くした寂寥。そして、その気持ちをなぐさめる大和への思慕の思いを込めた歌……。いかに歌が万葉の人々にとって重要なものであったかがわかります。
『古代史で楽しむ万葉集』には、ほかにも万葉集にまつわる読み解きがたっぷり記されています。改元に沸くこの機会、ぜひ中西進先生による案内とともに、古典の世界を味わってみてはいかがでしょうか。
書誌情報はこちら≫『古代史で楽しむ万葉集』