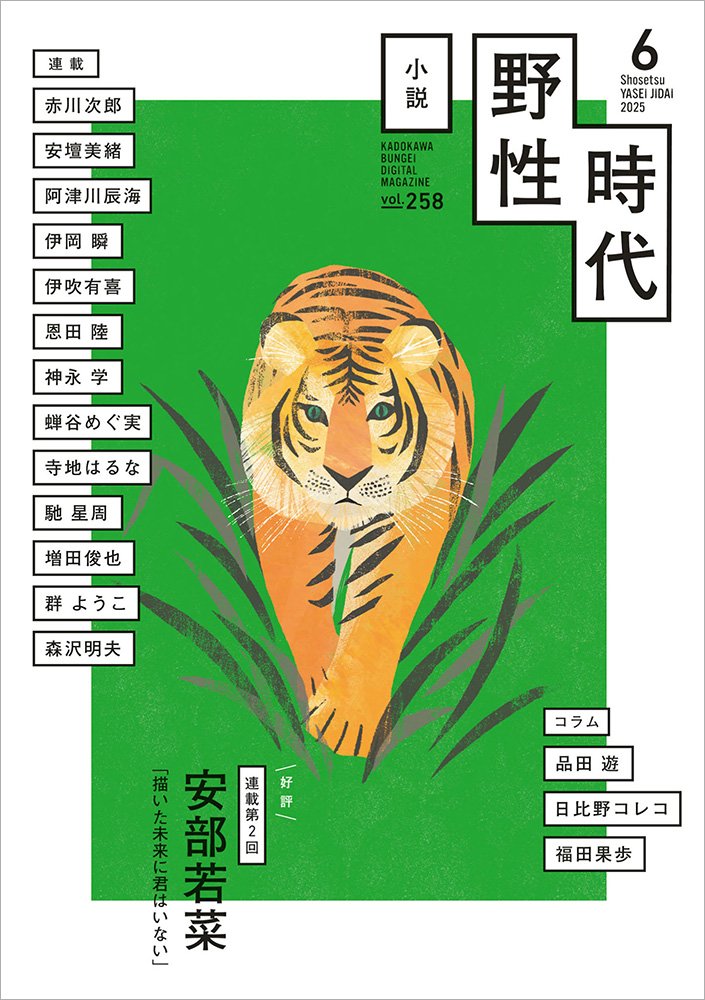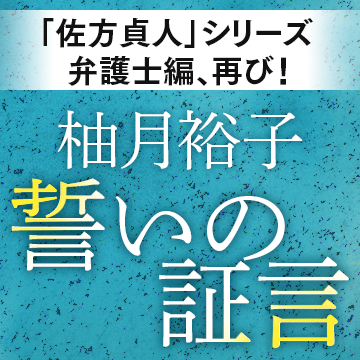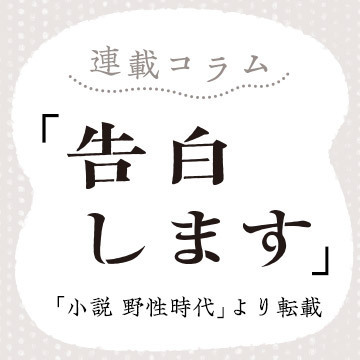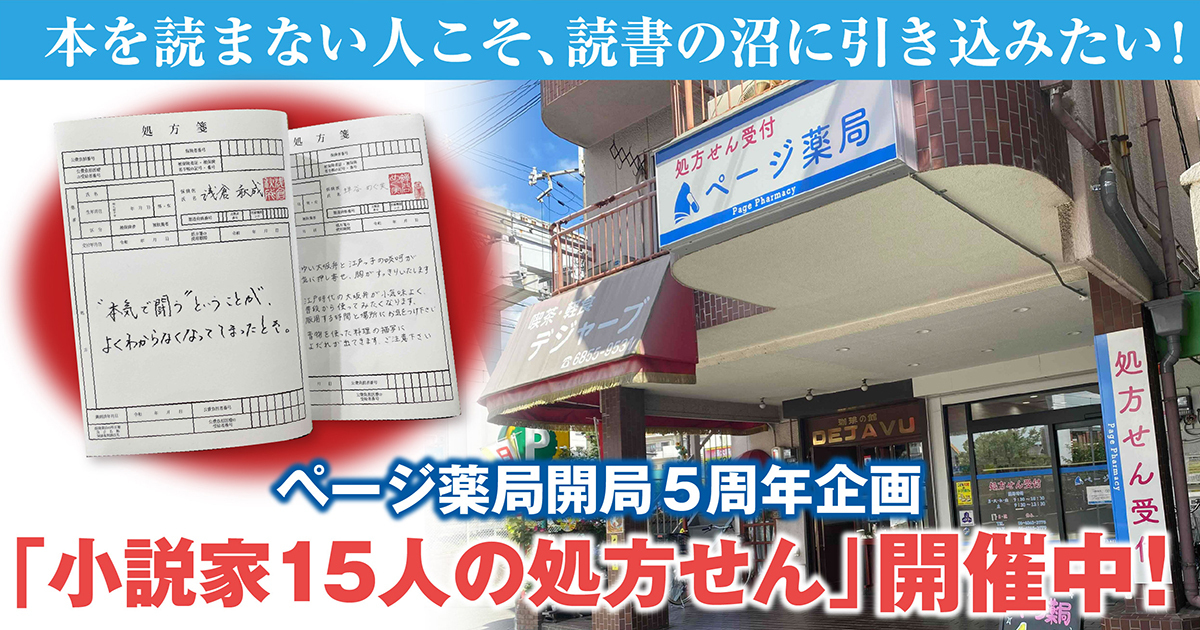行き場所をなくした少女は、恩師を尋ねて一人街を彷徨うが……。赤川次郎「三世代探偵団4 春風にめざめて」#1
赤川次郎「三世代探偵団4 春風にめざめて」

プロローグ
当てにするのが無理だったかもしれない。
それは分っていた。分っていたけれども……。
でも、頼れるのは、そのひと言しかなかったのだ。誰だって──教師なら誰だって生徒を送り出すときに言うだろう。
「何か困ったことがあったら、いつでも相談に来いよ」
というひと言。
それだけを頼りに、遠い町から列車を乗り継いで、八時間もかけて東京へ出て来るなんて、無茶なことだ。
「でも……仕方ないよね」
と、駅のホームに降り立って、
手にしたボストンバッグは、結構重かったが、別に金目の物が入っているわけではない。好きで、どうしても手放したくない本やCDが重いのだった。
「ああ……」
駅の改札口を出ると、猛烈にお
午後の五時になろうとしていた。──何か食べないと、動けない。
駅前には、幸いTVのCMなどで良く見るカレー専門店とかラーメン屋とかが並んでいる。十八歳の胃袋は、その看板を見ただけで大きな音をたてた。悲鳴を上げていたのかもしれない。
値段と、お腹の持ち具合を考えて、散々迷ってから、ともかく「ご飯が欲しい」と思って、カレー専門店に入った。
びっくりするくらい早く出て来て、香は感激した。
何だかこの先、うまく行きそうな気がしたのである。カレーもおいしかった。
それでも、一緒に店に入っていた、サラリーマンらしい男の人の食べるのが早いことには驚いた。これが東京のスピードなのかしら?
食べ終って外に出ると、どこか
「ああ、春だな」
と思った。
旅立ちの季節。──矢ノ内香も例外ではなかった。しかし、旅立って広い世間へ出ても、行くべき場所はない。
たった一つ、ポケットに入った、二つに折ったハガキの住所以外には……。
その駅から、十分くらい歩くと着くはずだった。香は不安な思いに封をして、ともかくどの道を行けばいいのか、駅前に立って見渡した。
駅前に、この周辺の地図があった。──香はハガキの住所を何度も見直しながら、必死で地図の中にその住所を捜した。
「──これだ」
そう詳しく出ているわけではなかったが、およその所は見当がついた。
「あの道を行って……三つめの角を右……」
口に出して何度もくり返した。
でも、もう行かないと。暗くなり始めている。
香は、思い切って、目指す道へと歩き始めた。
──
矢ノ内香が頼りにしていた教師は、そういう名前だった。
香が高校二年生になるとき、宮里は東京の私立高校の教師になるために、町を出て行った。香は宮里に
今どき珍しい「文学少女」だった香にとって、宮里は「本のガイド」として、香を導いてくれる人だったのだ。
それから二年。──香は何度か宮里に手紙を出したが、返事は今ポケットに入っているハガキ一枚しか来なかった。
〈新しい学校で、とても忙しい〉
というひと言が、香を納得させていた。
忙しくて、返事出すどころじゃないんだ……。
そう自分に言い聞かせて、香はともかく二、三か月に一度、手紙を出し続けていた。
東京へ行きます、とは知らせなかった。
やめておけ、と言われるのが怖かった。ともかく行ってしまおう。会えば、きっと……。
香の抱える事情を知ったら、きっと先生は分ってくれる。
──すっかり夜になって、道が正しいかどうか、分らなかった。
地図で見るのと、実際の道とはずいぶん感覚が違っているので、香はすっかり迷ってしまった。
アパート。どこかのアパートには違いない。ハガキにあった名前のアパート……。
でも、街灯の明りに、いくつも小さなアパートが並んでいるのが見えた。
誰かに訊くといっても……。
コンビニがあった。故郷の町には見かけないような、明るくて
香は思い切って中へ入った。
「いらっしゃいませ」
若い男が眠そうな顔でレジに立っていた。
「あの……」
と言いかけたが、カゴを手にした女性が、パッとレジに置いて、
「領収証ちょうだいね」
と言った。
「温めますか?」
カゴの中には、パックのお弁当が五、六個も入っている。
「すぐ食べるか分んないから、いいや」
ジーンズの女性は、まだ二十歳ぐらいに見えた。何だか変ったアクセサリーを首に下げている。
そうか。何も買わないで、アパートの場所を訊くのは失礼だな、と香は思った。
近くの棚から缶コーヒーを一つ取って、レジに並んだ。
「今夜も遅くなりそう?」
と、レジの男性が訊いた。
「たぶんね。景気悪いから、一日で撮り終えないと」
お金を払って、その女性がレジを離れると、香は缶コーヒーを置いて、
「あの──このへんに、〈
と訊いた。
「さあ……。この辺に住んでないんでね」
と、素気なく言われて、
「そうですか……」
小銭で代金を払う。
「ねえ」
と、お弁当を買っていた女性が、店から出ようとして戻って来ると、「今、〈明風荘〉って言った?」
「はい。そうです。明るい風、という字で」
「じゃ、今私が仕事してるアパートだよ」
「本当ですか!」
香の声が弾んだ。「連れて行って下さい」
「いいよ。一緒においで」
「ありがとうございます」
と、行きかけると、
「ちょっと! 缶コーヒー、忘れてるよ」
と呼び止められて、あわててレジに戻った。
「──すぐそこの角、曲った所よ」
と、その女性が言った。「誰か知ってる人がいるの?」
「ええ。学校の先生です」
「へえ。──でも、あのアパート、空いてる部屋が多いんだよ」
「そうなんですか」
じゃ、もうアパートにいないということも……。でも、それなら出した手紙が戻って来そうだ。戻って来ないということは……。
「ここよ」
と、大分古くなった二階建のアパートの前に来て、「何号室だって?」
「それは書いてないんですけど。宮里先生っていうんです……」
「宮里?」
と、その女性が訊き返した。「学校の先生で、宮里っていうの?」
「ええ。──知ってるんですか?」
すると、ドアの一つが開いて、ジャンパー姿の男性が出て来た。
「おい、弁当あったのか?」
「買ってきましたよ」
「──その子は?」
と、男が香を見て言った。
「宮里さんを訪ねて来たって……」
「宮里さんを? 知り合い?」
「あの──高校で先生に教わってたんです。宮里先生、このアパートに?」
「まあ、入れよ」
と、男が促す。
その部屋には〈宮里〉という表札が出ていた。ここなんだ!
でも、部屋の中は何だかいやにざわついている。
「おい! こんなことじゃ、朝までかかっても終らないぞ!」
と怒鳴る声がした。
香はハッとした。あの声……。
▶#1-2へつづく
◎第 1 回全文は「カドブンノベル」2020年6月号でお楽しみいただけます!