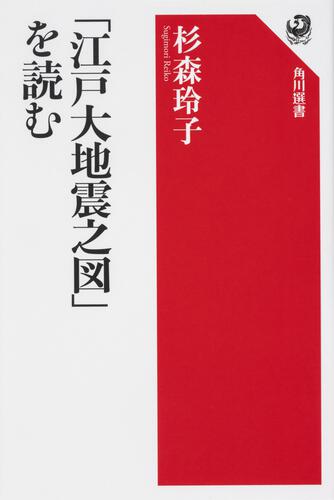書評家・作家・専門家が《今月の新刊》をご紹介!
本選びにお役立てください。
(評者:黒田 日出男 / 東京大学名誉教授)
一八五五(安政二)年十一月十一日夜に、江戸を大地震が襲った。「安政江戸地震」と呼ばれる地震だ。マグニチュード七、最大震度六強と推定されている直下型地震である。この大地震についての絵画史料としては「鯰絵」が有名だが、大地震そのものを描いてはいない。
この大地震の発生から復興に至るプロセスを実にリアルに描いた絵巻(画巻・図巻)が、二つ残されている。一つは島津家旧蔵で、東京大学史料編纂所の所蔵であり、今一つは、近衛家旧蔵で、アイルランドのチェスター・ビーティー図書館にある。なんと両者の描写は瓜二つだ。
冒頭には昼間の江戸の一角が描かれている。やがて夜になり、人々は寝静まった。霞で区切られた次の画面では一瞬にして家々が倒壊し、人々は道路に飛び出している。崩れた家屋には、下敷きになった母子らの姿が見える。この惨状に続いて描かれた大名屋敷の一角(練塀の内側)には畳が二枚敷かれ、殿様と奥方・娘らがおり、侍女や家来が駆けつけてきている。ここには殿様の仮屋が作られるようだ。遠くの町に火の手が上がっている。ここで松の大木によって場面が転換し、町々の炎上が描かれ、町人たちは襖などで扇いで延焼を防いでいる。倒壊を防ぐためのつっかい棒をした家々が続き、焼け落ちた大名屋敷や町家があり、死者の葬送や人々の仮住まいの様子が描かれている。その先は雪景色だ。地震から二、三カ月のうちに大雪が降ったらしい。そこに「め組」の旗を立てた町人の行列が進んでいく。御救小屋が描かれているので、そこへ向かっているのだろう。雪だるまが作られているその先では、土蔵普請が行われている。早くも復興が始まっているのだ。江戸城の門も修復が始まっており、登城する武士の一行がある。こんな具合に「安政江戸地震」の直前・発生・直後の避難生活・御救小屋の存在・復興の息吹などが時系列に沿って描かれており、本当に興味深い絵巻なのである。
この両絵巻については、地震史の研究者と近世史(幕末史)家、文学研究者や美術史の研究者などが関心を持ち、いくつもの解説が書かれてきている。がしかし、どれもあいまいな記述に留まっており、「江戸大地震之図」は絵画史料として読解されていないと私は感じてきた。この絵巻こそ幕末期の稀有な絵画史料なのではあるまいかとも思っていた。しかし、私は幕末史については素人だ。安易に手はだせない。
そもそも、この両絵巻は安政江戸地震をどのように描いているのであろうか? いったい何処が描かれているのだろうか? 二つのそっくりな絵巻が作られたのは何故なのか? 誰が何のために両絵巻を作らせたのか? この両絵巻を見たのは一体誰なのだろうか? これらの疑問を解き明かす本格的な絵画史料読解が試みられるべきだろう。
ところが、「江戸大地震之図」の諸々の謎を周到に読み解いた本書がいきなり登場したのだ。杉森は、「江戸大地震之図」の全体を丁寧に観察し、その細部に着眼点つまり読解の糸口を見つけていく。絵画史料読解にとって何より大切なのは、カギとなる着眼点の発見だが、それが的確になされている。そして、一つひとつの細部の表現の読解にさまざまな地図史料や文献史料が関連付けられ、的確な解釈がなされていく。幕末期の諸史料の縦横無尽な活用によって、「江戸大地震之図」は絵画史料へと変身を遂げていくのである。
本書の読者は、最初は少々まどろっこしく感ずるかも知れないが、直ぐにここまで読めるのかと驚き、納得ずくの読書を楽しめることだろう。「江戸大地震之図」は、杉森の読解によって安政江戸地震だけでなく、幕末の都市社会史や政治史の絵画史料にもなったのである。正直に言って私は、杉森がとても羨ましかった。幕末期の膨大な諸史料の存在は本当に物凄い。これらの膨大な諸史料が、本書のように確実で豊饒な絵画史料読解を可能にしてくれるのだから。
さまざまな視点(関心)による「江戸大地震之図」の読解(発見)は、本書を基盤にして始まるだろう。のみならず、本書は幕末の絵画史料論の起点となるに違いない。
▼杉森玲子『「江戸大地震之図」を読む』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321802000147/