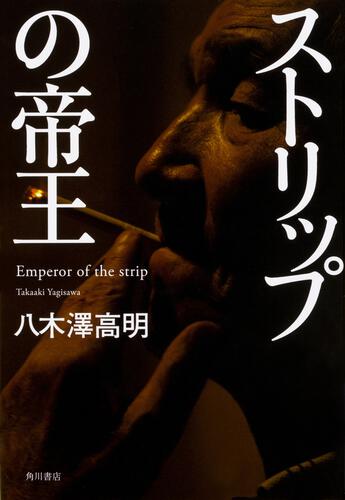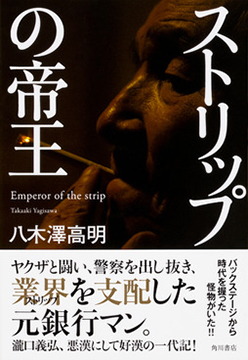平和、安定、停滞、没落。二〇一九年の春に終わる平成という時代を、きっと後世の人間はそんな言葉で総括するだろう。だが、私はこれを「清潔と健康という『正しさ』が社会に蔓延していった時代」だと考えている。
例えばタバコの社会的許容度は大いに低下した。近年は喫煙者側も、世間に迷惑をかけにくく比較的健康的とみなされがちな加熱式タバコを選ぶ。プリン体オフなどと奇妙なメッセージが売りの酒類も市民権を得て久しい。
変化の陰には常に「正しさ」がある。過去数百年の喫煙文化が存在しようともタバコは撲滅されるべきで、吸うなら自身と周囲の健康に最大限の配慮をせねばならない。酒や食事は、たとえ味を犠牲にしても健康のため成分を調整したものが好ましい。ついでに言えば、不倫や浪費は「悪いこと」なので、たとえ自分に実害がなくても当事者を社会的に断罪せねばならない——。いずれも「正しさ」ゆえに反論が憚られる。
だが、低糖質麺を食べてプリン体オフの発泡酒を飲み、味の薄い加熱式タバコをくわえながら私はときに思う。
この「正しさ」のもとで、人生の満足度や幸福度は本当に増進し、人間はより自由になったのか。個人が享楽的なライフスタイルを選ぶ行為は、社会からここまで批判と改造の対象とされるほどの「悪」なのか——? と。
本書の主人公・瀧口義弘が後半生を捧げたストリップもまた、そんな「正しさ」が蔓延した平成の時代のなかで白眼視され、いまや追放される寸前に至った文化のひとつだ。
「ストリップに携わる者というのは、法律の外にいるアウトサイダーです」
そう語る瀧口は、かつては妻子ある銀行員だった。だが一九七〇年代のなかば、現役ストリッパーで劇場主だった姉に誘われて業界入り。やがて全国の劇場の踊り子の手配(「コース切り」と呼ぶ)を一手に引き受ける伝説的存在「ストリップの帝王」となる。ヤクザや警察を海千山千の手管で翻弄し、ときに指名手配を受けながらも業界に頭まで浸かり続けた。
姿勢は古風だ。瀧口を知るストリップ嬢は彼の言葉をこう伝える。
「劇場に足を運んでくれる男性諸君は、お前たちの女らしさに癒しを求めに来ているんだ。礼儀作法を大事にしろ」
「映画やビデオはやり直しがきくけれどストリップはライブショー。すべて一発勝負ですごいことをやっているのだ」
もっとも、瀧口の生き方は矛盾に満ちている。ストリップは一九八〇年代から過激化。やがて舞台上や個室で客に踊り子と格安でセックスをさせるサービスが一般化した。「一回五百円」ともいう安価な報酬で、このショーとはとても呼べそうにない売春行為への従事を余儀なくされた女性の多くは、フィリピンや南米から来た不法就労の外国人だった。
途上国の女性に対する性的搾取をなかば正当化し、自身が管轄するあらゆる劇場でおこなわせ続けたのも瀧口なのである。
仕事の鬼である彼の私生活も崩壊していた。離婚した妻や娘とは極めて疎遠。自分の都合でストリップ業界に引きずり込んだ息子は、結果的に前科者になりやがて父親と反目している。また金銭に執着がなく、ギャンブルで何百万、何千万円を簡単に溶かす。昨今の「正しき」価値観では絶対に許容されそうにない存在・瀧口に象徴されるストリップ業界の衰退は、時代の必然とも思えてくる。
著者は丹念な取材を積み重ね、瀧口に不都合な客観的事実も多数提示するいっぽうで、彼の人生自体については、能う限り肯定的な描写に努めている。大所高所からの断罪は論外としても、取材対象をもう少し突き放してもよかったのではないか——?
そんな思いを抱くのは、私が「正しき」平成の論理に反感を抱きつつも、これに知らぬ間に取り込まれたせいかもしれない。正と悪、逸脱と自由、断罪と寛容の境界線はどこに引かれるべきか、良識の枠に挑戦する一冊だ。
レビュー
-
特集
-
特集
-
試し読み
-
レビュー
-
レビュー