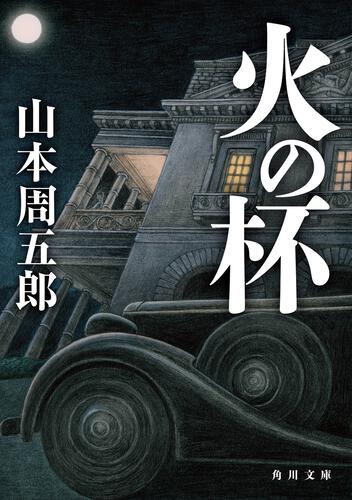没落の際に立つ上流階級たちの欺きあいを描いた、戦後サスペンス。
『火の杯』山本周五郎
角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
『火の杯』文庫巻末解説
解説
かつて〈曲軒〉と
周五郎の人間凝視の眼は、人間の根っこを探り出す徹底して非情なものであったが、庶民の側に立脚してその日常を凝視し、ありのままの姿を描き出すことで、温かな眼差しをも感じさせた。こうした姿勢こそが山本周五郎文学の基本的な態度であった。そこに周五郎の限りない包容力をも感じ取ることができる。周五郎のこうした透徹した人間凝視の眼は、その人生体験から培われていったものである。
1903年(明治36)6月22日に山梨県
下町ものをはじめとする市井もので、周五郎は江戸期の庶民生活を生き生きと描き出して人気を得ていった。江戸の長屋に住む人々の暮らしの実感と哀歓をとらえた周五郎の鋭い視線は、現代小説の中にも見てとれる。日々の暮らしの中で、貧しさの中で、苦悩の中で、人は何を求めて、何を救いとして、それぞれに生きているのか、という命題が現代小説からも感じ取れる。現代社会に生きる人々の赤裸々な生態を見通す鋭い観察眼が小説の核をなしているからだ。
本書『火の杯』は、1951年9月18日から翌年2月29日にかけて「福島民友新聞」に連載された現代小説の長篇である。時代背景は、太平洋戦争末期、敗戦の間際から敗戦直後にかけての混乱の時期。物語は、高原の別荘で催されている退廃的な空気が充満する上流階級の乱痴気パーティーの場面から始まる。主人公の御池康彦は日本最大の財閥・御池家の二男として生まれたが、生母不明の庶子で一族の中では異端者扱いされてきた。こうした出自の秘密に加えて、康彦には5つの年に
敗戦で財閥は解体となったが、財産隠匿のために、康彦は
そんな康彦の傍にいて支えてくれたのは、康彦のかつての恋人・松原数江の娘・夏子であった。康彦の複雑に屈折した内面描写とともに、友田浩二を康彦とは知らずに愛してしまう夏子の揺れ動く心理も並行して描き出されていく。その筆致は純文学的手法と言っても過言ではないほどに、周五郎の筆は隅々にまで及んでいて物語の進行に緊迫感を添えている。こうした緊迫感に加えて、夏子の母・数江が密かに持っていた「康彦の日記」の存在が物語の進行にミステリアスな興趣をもたらしてくる。夏子は母から託されたこの秘密の包みを必死に守ることで、友田浩二=御池康彦への愛を全うするのである。
さらにもう一つ、この作品には、周五郎の遊び心とも言うべき仕掛けがある。悩める夏子が相談に乗ってもらう、馬込に住む小説家・山木周平の存在である。周五郎は1931年から1946年までの15年間、この地に住んでいた。小説の中に夏子が馬込の空襲を体験する生々しい場面が出てくるが、これは周五郎が実際に体験したことである。山木に隣組の組長をさせているのも、やはり体験に基づくものだ。こうした私小説風なものをトッピングさせて興趣を盛り上げているのだ。
この新聞連載開始前の「作者の言葉」が残されている。「敗戦によって、われわれは大きな社会的変革に当面した。現在なおそれは継続されつつあるが、はたして『なに』が『どれだけ』変革されたであろうか」と記されている。これまでの半生はすべて受け身だったと反省する康彦は運命に立ち向かうことを決意し、これまで取ろうとしなかった火の杯を手にしようと思う。康彦にこう決意させることで、「どれだけ」変革されたか、の一つの到達点が示されている。
周五郎の新聞連載は、戦前では『風雲海南記』(「東奥日報」1937年11月~)と『新潮記』(「北海タイムス」1943年6月~12月)の2本だけで、戦後は『
作品紹介・あらすじ
火の杯
著 者:山本周五郎
発売日:2024年02月22日
華麗なる財閥一族の没落を描く、山本周五郎の隠れた名作
日本屈指の財閥・御池家の御曹司に生まれた康彦は、出生に関する秘密を抱え、不遇な青春時代を過ごしていた。敗戦後、GHQの財閥解体によって、御池家は存続の危機を迎える。時を同じくして、お抱え運転手の娘・夏子のもとには、怪しげな男が現れるようになっていた。彼女は康彦の亡父が遺した莫大な遺産に関する重要な情報を握っているというが……。没落の際に立つ上流階級たちの欺きあいを描いた、戦後サスペンス。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322307000516/
amazonページはこちら