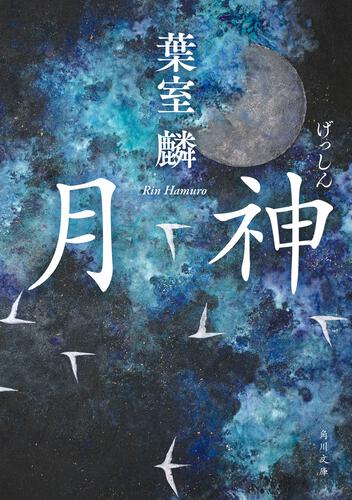葉室麟が遺した、魂を揺さぶる歴史長編。
『月神』葉室 麟
角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
『月神』著者:葉室 麟
『月神』文庫巻末解説
──月が導く夜明けのものがたり──
解説
福田千鶴(九州大学基幹教育院教授)
幕末・維新史を語るときに、欠かせないのは薩摩や長州の動向である。その大筋を欠くならば、幕末・維新史は描けないという大状況があることは認めざるをえない。しかしながら、薩長の目線で描かれる幕末・維新史でよしとするような歴史観からは、そろそろ卒業したい。葉室麟も、そうした思いが強かったのではないか。
『月神』は、薩長のはざまで埋没してみえるような福岡藩にも、語り継ぐべき歴史があることを豊穣に描く作品である。
章立ては、「月の章」と「神の章」の二部構成をとる。「月の章」は、福岡藩の幕末の志士たちの動向を、筑前勤王党(尊王攘夷派)の中心人物であった月形洗蔵を主軸として描いていく。これを前史としつつ、「神の章」では舞台を北海道に移し、月形潔が明治新政府の一員として牢獄建設の使命を全うするなかでの葛藤を描いていく。潔は従兄弟の洗蔵を尊敬しており、無念の死を遂げた洗蔵が残したとする「われら月形一族は夜明けを先導する月とならねばならぬ」という言葉を語り、これが小説全体に通底する伏線となる。
「月の章」の舞台は、九州である。その北部九州に位置する福岡藩は、筑前一国を領する国持大名の黒田氏が支配し、現在の福岡市の中心部にある福岡・博多を城下町として発展した。初代藩主は黒田長政であり、関ケ原合戦の戦功により中津(現、大分県中津市)から福岡に移って以来、幕末まで黒田氏十二代が続くことになった。藩主名をとって、黒田藩と呼ばれることもある。昔の酒席でよく歌われていた「酒は飲め飲め、飲むならば~」の黒田節で知られる黒田藩のことである。
その福岡黒田藩において、幕末の難局の舵取りをしたのは、十一代藩主黒田長溥だった。福岡藩がなぜ薩長のような雄藩化を果たせなかったのか、という疑問に対しては、藩主長溥の失策と指摘されることが多い。『月神』でも、長溥を「智慧があるがゆえの暗君」として描き、月形洗蔵が長州の高杉晋作、薩摩の西郷隆盛になれなかった最大の理由を度量のない暗君長溥に求めている。
長溥はただの暗君ではない。近代化に積極的に取り組んだ開明藩主の一人でもあった。実父の島津重豪は西欧の文化・科学技術に強い関心を示し、和漢書のほかに西洋の学問を学べる造士館を作り、天体観測所の明時館(天文館)を創設し、「蘭癖大名」とも呼ばれていた。その影響のもと、江戸の島津藩邸で長溥は二歳年上の甥孫・島津斉彬と兄弟のように育てられた。福岡藩主になると、長溥は西洋科学技術の導入にいち早く着手し、弘化四年(一八四七)に博多中洲に精錬所を作り、鉱物の試験、ガラス製造などに取り掛からせた。同様の施設に、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の一つ、鹿児島の集成館があるが、その建造に斉彬が着手できたのは嘉永五年(一八五二)である。また、長溥は、優秀な藩士に砲術・医学・西洋科学を学ばせるために江戸や長崎に遊学させ、幕府が慶応二年(一八六六)に海外渡航の禁を解くと、翌年すぐに藩士六人を米国やスイスに留学させるほど教育熱心だった。
その開明藩主がなぜ、暗君の汚名を被ることになったのか。その行動を理解するためには、養子に入った黒田家の事情を踏まえる必要がある。近世中期以降の黒田家は、養子が続いた。六代継高の男子はみな早世した。そこで、七代治之を一橋徳川家から養子に迎えた。しかし、子に恵まれず、八代治高は京極家から、九代斉隆は再び一橋徳川家から養子に迎えた。斉隆は十九歳の若さで没したが、幸い男子が生まれており、御家断絶の危機は免れた。とはいえ、相続したのは数えで一歳の斉清だったため、実の祖父一橋徳川治斉の後見を受けて育った。斉清は二男二女に恵まれたが、男子はみな早世した。そこで、迎えられたのが薩摩の島津重豪の九男(一説には十三男)の長溥だったのである。
長溥は、先代藩主斉清の長女純を妻とした。つまり、家付きのお姫様と結婚したのだが、純は嘉永四年(一八五一)に江戸に没した。三十三歳。子はなかった。長溥には側妾との間に三女一男が生まれたが、いずれも早世した。そこで、純がまだ存命の嘉永元年に藤堂家から長知を養子に迎えた。長知は元服すると、すぐに婚礼をあげ、桑名藩主松平定和の娘豊を妻に迎えた。
このように黒田家は一橋徳川家との縁戚関係が長く続いていたことに加え、佐幕派(徳川幕府を補佐する派閥)の桑名松平家との縁戚関係もあった。長溥が最終的に佐幕派に傾かざるをえなかった背景には、こうした縁戚関係があったのであり、長溥は一橋家出身の十五代将軍徳川慶喜を島津斉彬とともに推した経緯もあり、これを見捨てることはできなかったのである。
長溥は佐幕派となる決断をすると、尊王攘夷派を藩内から一掃した。これが「乙丑の獄」と呼ばれる大弾圧事件である。慶応元年(一八六五)の干支が「乙丑」であったことから、こう呼ばれる。家老の加藤司書以下七名が切腹、藩士月形洗蔵以下十四名が斬罪、野村望東尼以下十五名が流罪、その他、宅牢(自宅監禁)を命じられた者も多かった。
その経緯をみるに、幕府は文久二年(一八六二)になると、参勤交代を緩和し、諸大名の妻子の帰国を許した。福岡では城内下屋敷に新屋敷を造営し、翌三年二月に豊が帰国した。さらにその翌年、鞍手郡犬鳴山に新たな御殿が造営された。犬鳴山別館である。これは、海辺に近い福岡城では異国船からの攻撃が避けられないため、山間部に藩主家族の隠れ家として設けられたものであると、筑前浦の商人が書いた『見聞略記』に書かれている。庶民ですら、そのように理解していたものだった。
また、隣国の長州毛利家でも妻の帰国を契機に、海辺の萩から内陸部の山口に御殿や藩庁組織を移した。そのために萩ではなく山口が県庁所在地となったのである。つまり、海辺から内陸部に御殿を移すという動向は、福岡藩に限るものではなかった。
ところが、福岡藩ではこれが「乙丑の獄」の口実とされてしまう。別館造営の責任者が尊攘派の家老加藤司書だったこともあり、これは別館に長溥を押し込めて隠居させ、世子の長知を奉じて尊王攘夷を実行する計画であるとの噂が流れ、これが主君に対する不忠とみなされたのである。その結果、月形洗蔵ら多くの人材を失うことになり、福岡藩が雄藩として浮上する道は絶たれてしまった。
ただし、これは長溥にとって苦渋の決断だった。というのも、彼はその日以来、髭を剃ることを止めたからである。いくつか残る長溥の写真は、いずれもその頃から伸ばし続けている髭姿である。「乙丑の獄」で散った者たちの死を思わない日はなかったのだろう。
これは月形潔も同じだった。九州から遠く離れた北海道の地で、潔はなんども問いかける。
なぜ、月形洗蔵は死ななければならなかったのか……。
月が夜明けを導くだけでなく、月夜に落ちた一滴が湖面に静かな波紋を広げていく。『月神』は、幕末維新期の激動を描きながらも、そんな清浄な読後感が得られる小説である。
作品紹介・あらすじ
月神
著者 葉室 麟
定価: 726円(本体660円+税)
発売日:2023年03月22日
志士とは灯りのない道を照らして行く者だ――。憂国の志士を描く歴史長編。
明治13年、福岡藩出身の内務省書記官・月形潔は、北海道に監獄を作るために横浜を発った。
明治維新以降、新政府の本流となることができなかった福岡藩出身者には、瑣末な仕事ばかりが与えられていた。
洗蔵さんが、いまのわたしを見たら、どう思われるだろうか――
船上の潔の頭に浮かぶのは、尊攘派志士として命を燃やした従兄弟・月形洗蔵の顔だった。
激動の時代、二人の男の矜持が、時代を越えて交差する。
葉室麟が遺した、魂を揺さぶる歴史長編。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322212000553/
amazonページはこちら