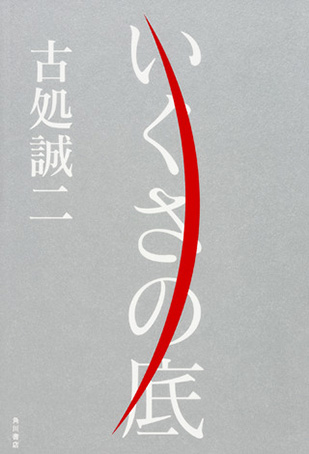文庫解説 文庫解説より
あの古典『ビルマの竪琴』を相対化する、まったく新しい戦争小説の誕生。
古処誠二ほど軍隊を書ける作家が、いま、他にいるだろうか。
軍隊は巨大官庁や巨大企業と同じだ。管理職相当の士官がいる。平社員相当の兵隊がいる。ほんの少しの身分の違いが、越えられない壁、立ち入れない塀をいちいち作り出す。年季の入り方のちょっとした違いも大きく作用する。
しかも、大日本帝国陸軍なら、歩兵も、砲兵も、工兵も、騎兵も、食糧などの輸送を司る輜重兵も、軍の中の警察官である憲兵もいる。それぞれに士官がいて兵隊がいる。タテにもヨコにも細かく割れ、各々に独特の文化がある。言葉や思考法がある。それは単に伝承とか習性とかいった次元にとどまらない。歩兵なら歩兵、憲兵なら憲兵。どのグループにも専門性の高いマニュアルがある。それに従って教育されている。その意味で軍隊は民間企業以上に役所である。軍人や兵隊は武装した役人である。軍隊勤務は決まり事に徹底的に縛られている。
たとえば、臨機応変な対応を求められる戦場での指揮でさえ、戦国時代の武将のようにその場で指揮官が勝手をできるものではない。基本方針はマニュアルによって定められている。速戦即決とか包囲殲滅とか、留意すべき原則は常に与えられている。その原則を今置かれている状況にどうすれば最大限あてはめられるか。自由に裁量でき奇手奇策も勝手次第なんて話では決してない。疫病対策でも何でも、軍組織は想定されるありとあらゆる事柄の手順を定めている。それが近代的軍隊というものである。
そんな軍隊について小説を書く。軍隊の行動する物語を綴る。作家の想像でこなすには限度がある。組織がこのうえもなく複雑なうえ、戦争となれば非常時だから、マニュアルと裁量の組み合わせを描いて真実味を持たせ続けるのはけっこうな離れ業。むろん、小説は生きた人間を描けばいいのだけれど、その生きた人間とは軍隊においては組織の網の目の中でしか生きようがないのだから、網の目のいちいちの大きさから形状までをつかまえずに生きた人間だけをとりだすことはできない。非人間的な軍隊組織のメカニズムの微に入り細を穿たねば、そこに生きる人間に魂を吹き込むことはできない。
したがって、軍組織を描く文学は日本でも、軍組織内で生きた経験のある作家たちの独擅場だった。既に戦前からずっとそうだった。火野葦平や上田廣や棟田博や大岡昇平や島尾敏雄や伊藤桂一などなど。そして彼らが世を去ってゆくとともに、大日本帝国軍隊を描いて真実味を溢れさせる小説の命脈も尽きかけた。何しろ帝国陸海軍という巨大組織は一九四五年の敗戦と共に解体されたのだから。海軍兵学校や陸軍士官学校を卒業するくらいのところまで行って、軍の内実をそれなりに実感した世代は、一九二〇年代生まれが最後なのだから。
ところが二一世紀の日本文学はなおもその道のとてつもないタレントを有している。改めて書くまでもない。古処誠二である。彼がなぜ軍隊を書けるのか。一九七〇年生まれだというのに。やはり自衛隊での経験を血肉とし、そこから旧帝国軍隊を想像し叙述する能力を高い精度で鍛え上げてきたからというほかないだろう。とにかく彼は唯一無二の例外的存在である。しかもその例外性とは、戦後四半世紀も経って生まれた世代だというのに肌で旧軍を知る世代に負けないリアリティで軍隊を書けるから凄いという話には、無論とどまらない。戦後幾十年も経たからこそ改めて問えることがある。再考すべき事柄がある。そうした挑戦的性格を古処の文学はしっかりと有している。そこが凄いのである。
『中尉』はそんな古処文学の中でもキラ星のごとき傑作だろう。この小説は種々の先行作を思い出させる。アヘン中毒かと思わせる軍医の出てくるところは有馬頼義の『赤い天使』とか。だが『中尉』と比較されるべきなのはやはりあの名作だと思う。銃後の東京で旧制高校の教授を務めていた竹山道雄が、敗戦直後から書き始め、一九四八年に完成させた『ビルマの竪琴』である。日本陸軍の水島上等兵がビルマ(ミャンマー)人の僧侶のなりをし竪琴を弾いてビルマの方々を巡り、遠い異国に没した日本軍将兵を慰霊しつつ平和を祈る、戦後の日本と世界の行く道を示した、極めて理想主義的な児童文学である。
『中尉』と『ビルマの竪琴』とのあいだには、幾つもの共通点がある。戦争末期から敗戦直後のビルマを舞台に日本陸軍の軍人や兵士を描いていること。東南アジアの諸民族の中でも日本人と面差しが特に似ると、ビルマ人が「大東亜戦争期」に言われていた事実をふまえ、『ビルマの竪琴』は竪琴の名手である水島上等兵を、『中尉』は題名役である軍医中尉を、ともにビルマ人と見分けのつかないくらいにビルマとなじんだ人物として描き出していること。そしてふたりとも軍隊を離れて失踪してしまうこと。さらに水島上等兵も軍医中尉も白骨街道と称された日本軍敗走の道筋を辿り、日本兵の無数の遺体と出会う過程で人生の運命を動かされてゆくこと。そのほかにも重なる要素はとても多い。
だが『中尉』は『ビルマの竪琴』を単に真似ているのではもちろんない。筋書きを似せて読者に『ビルマの竪琴』を思い出させることで、かえって違いを浮き彫りにし、『ビルマの竪琴』のメッセージを見事に相対化する。『中尉』とはそういう小説ではあるまいか。
両者の相違を乱暴に言ってしまえば、『ビルマの竪琴』は戦争への反省と平和主義への回心という戦後的理想のもとにすべての筋書きをまるめてしまうのに対し、『中尉』は戦争末期から敗戦直後にかけてビルマで過ごした日本の軍人兵士の思想や心情にかなりリアルに同時代的に寄り添っている。水島上等兵も軍医中尉も、確かにビルマ人に似、ビルマ人と心を通わせ、白骨街道にも出向くけれど、その原因・理由・動機には対照性がある。水島上等兵は人類愛的ヒューマニズムを基調として行動するが、軍医中尉は「大東亜共栄圏」の理想主義的確立への夢や軍組織内での軍医としての職責に殉じている。
そもそも『ビルマの竪琴』で水島上等兵の所属する部隊は、音楽家を部隊長として兵士がやたらに仲良く歌い、部隊を構成する軍人兵士の位階や職掌の差もほとんど感じさせない、その意味でまったく奇妙な一枚岩の非現実的・幻想的部隊である。ビルマ人との触れ合いは軍務から逸脱した音楽によって行われ、戦争末期で敗色濃厚になると、いかなる命令に基づくものなのか、「うたう部隊」は戦わずして敵軍に対し退却・逃避行を繰り返す。一方、『中尉』での軍医中尉らとビルマ人との触れ合いは防疫任務の遂行といった現実的設定の中、まさに軍の正規の任務として行われ、敗戦前後も軍の統率は乱れることなく、すべては命令通りに粛々と運ばれる。また『中尉』は熱帯病というファクターを巧みに利用することで、軍医中尉という存在に、本人の思想や心情とは別次元のもっと差し迫ったかたちでのリアリティの付与に成功している。水島上等兵が肉体的制約と関係なく心情にしたがって振る舞うのと、猛烈な対比性を感じさせる。たとえばそこに、物語として表面上の相似した点が数々ある『ビルマの竪琴』と『中尉』との、内奥において相容れざるひとつの懸隔がある。
私は何も『ビルマの竪琴』が戦後平和主義の非現実的な幻影の象徴であり、『中尉』のリアリズムがそれを超克したなどと述べたいわけではない。『ビルマの竪琴』も軍事国家から文化国家への転換を心底から願った戦後初期の「教養ある日本人」にとっての切実にリアルな思念の表現である。その意味で今も『ビルマの竪琴』は名作である。『ビルマの竪琴』で水島上等兵は部隊長や「戦友諸君」に自らの「失踪」するに至ったわけを綿々と手紙に書き綴り、その平和主義的心情告白が物語のクライマックスをなし、部隊長も戦友たちもそれに全き共感を覚える。それこそが戦後日本の出発の頃の美しきひとつの里程標である。
しかし『中尉』における軍医中尉の「失踪」の理由はどうか。何人かの登場人物によって説得力ある推測が示されるけれど、『ビルマの竪琴』のように本人から手紙がくるわけではない。真相は「藪の中」である。
『ビルマの竪琴』は繰り返せば一九四八年の完成。それから二年後、黒澤明監督は映画『羅生門』を撮った。芥川龍之介の『藪の中』が原作である。平安時代の京の都の近郊で起きた殺人事件。その真相がついに明らかにならない。何が本当か分からない。敗戦直後、日本人は素直に平和と民主主義を信じようとした。『ビルマの竪琴』の表すのはその熱気である。だが、すぐに藪の中へと入ってゆく。黒澤の『羅生門』はそういう戦後のニヒリズムを摑まえたと評された。平和を追求してもアメリカの軍事力に守られてこそ。戦争か平和か。文化か経済か。アメリカかソヴィエト連邦か。資本主義か社会主義か。誰が敵で誰が味方か。物事はたちまち単純に信じられなくなる。「藪の中時代」の始まりである。
それからの長い戦後、われわれは『ビルマの竪琴』の美しい理想に心を揺り動かされながらも、藪の中を彷徨い続けているのだろう。同じはずの出来事も人の立場や兵の種類が違えばまったく違って見えてくる。「藪の中時代」の『ビルマの竪琴』。そういう無くてはならない小説がようやく現れた。
『ビルマの竪琴』の隣に『中尉』を置こう。そうすればわれわれは、戦争と戦後について、より深く悩み迷えるようになる。
紹介した書籍
関連書籍
-
特集
-
特集
-
レビュー
-
レビュー
-
連載