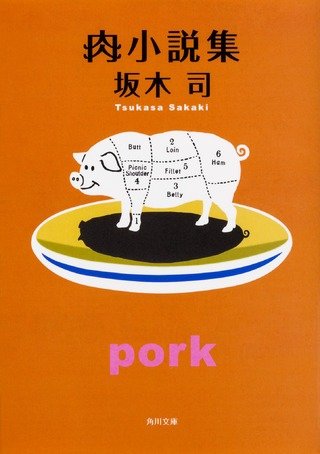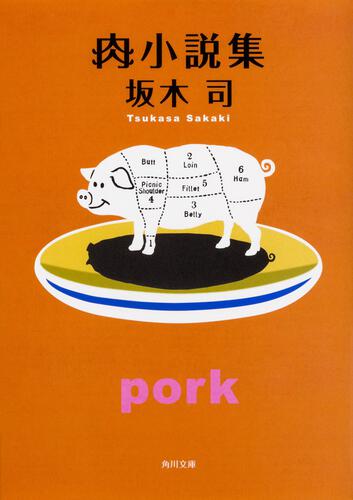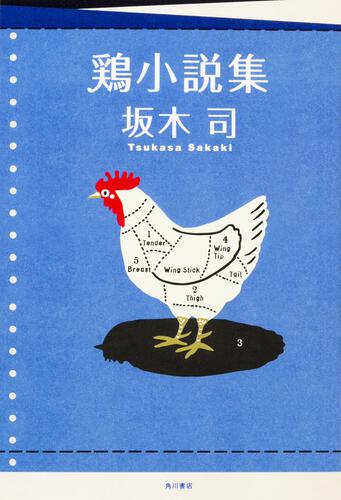肉というのは、食材の中でもどこか特別な気がする。
もちろん、好みはある。だが、多くの人に好まれるし、なによりごちそう感がある。
みんなで食事をしていて、肉の塊がどーんとテーブルに出てくると、うれしそうな声があちこちから上がる。
わたしももちろん肉は好きだ。魚も好きだが、洋食の場合は「肉か魚か」を選ぶ場面になると、肉を選ぶことが多い。
でも、ときどき思うのだ。わたしたちはこんなに身近な肉のことについて、なにもわかっていない、と。
魚をさばいたことがある人は、それなりにいるだろうが、肉を解体したことのある人はほんのわずかだ。もちろんわたしも丸鶏を解体したことすらない。
先日、西安に行ったとき、鶏を丸ごと揚げた料理を食べた。小さい若鶏だったのだが、ここはもも肉、ここは胸肉と目で確認しながら、自分で切り分けて食べていき、ささみがあの形のまま骨から取れたときは、ちょっと感動すらした。
いや、丸鶏のローストチキンなら、まだ焼いたことがある人や食べたことがある人はいるだろう。
鶏を自分の家で絞めて、それを食べたことのある人って、どのくらいの割合だろう。たぶんものすごく少ないはずだ。
たとえば、SNSで「家庭菜園のトマトを収穫しました」と書いても、それを責める人などいないが、たとえばアイドルが「今日、鶏を絞めて食べました」と写真をアップしたら、それが鶏の死体そのものではなく、ちゃんと肉の形になっていたとしても、ネガティブなコメントが殺到するだろう。
わたしは狩猟に興味があり(自分ではやらない。山を歩く体力がないから)、ツイッターで狩猟をやっている人たちをフォローしているのだが、その人たちが自分の獲物について語ったとき、ひどくヒステリックなコメントが飛んでくるのを何度も見た。
そういうコメントをするのがベジタリアンの人なら、賛同はできないがまだ一貫性はある。普段は肉を食べている人たちまでもが、「残酷だ」と言うのだ。
中には、「スーパーに行けばいくらでも肉が売っているのに、自分で殺してまで肉を食べようとするのは残酷だ」と言う人もいた。
どうしてだろう。スーパーに並んでいる肉も、もともとは生きている命だったはずだ。家畜としての鶏や豚や牛を殺すのは残酷ではないのか。鹿や猪は増えすぎていて、駆除が必要だとしても、殺して食べるのは残酷なのだろうか。
議論は簡単にはできない。だが、ひとつ確実なことがある。
肉を前にして、人は冷静ではいられないのだ。
単行本の『肉小説集』の表紙を見たとき、「美味しそうな小説かな?」と思った。
食いしん坊なので、美味しそうな料理がたくさん出てくる小説は大好きだ。(自分でもときどき書いています)
『和菓子のアン』シリーズはとても美味しそうだったし、大好きなシリーズだ。そう思って読み始めたが、予測は一話目の『武闘派の爪先』で大きく裏切られた。
ここに書かれている豚足は、全然美味しそうじゃない。わたしは豚足が好きだけど、「まあ嫌いな人から見たらこう見えるよね」としみじみ納得してしまうような描写だった。それだけではない。小説そのものも相当ヤバイ。生々しく、そしてバイオレンスだ。
坂木さんの筆は、いつも通り柔らかく、ユーモアに満ちているので、するする読めてしまうが、豚足のあのぬるぬるしたような脂が、読後もいつまでもまとわりついてぬぐえない。
続いての『アメリカ人の王様』では、バイオレンス風味こそないが、やっぱり全然美味しそうじゃないし、なにより視点人物に全然共感できない。なのに、すごくそこが気持ちいい。
豚足もそうだったけれど、美味しそうじゃない描写の向こう側に、ちゃんと美味しそうな気配だってするのだ。
ああ、生きるってことはそうだよね、と思った。美味しいものだけを食べられるわけではなく、美味しくないものも食べる。わたしの中には、他の人から見たらまったく共感できないイヤなわたしだっている。でも多くのフィクションはそれを簡単に、共感できる人物と共感できない人物に切り分けてしまう。
『君の好きなバラ』の中学生男子の視点にも唸
『肩の荷(+9)』には同世代としてしみじみ共感し、続く『魚のヒレ』のエロさにどきりとした。
『魚のヒレ』と『ほんの一部』はものすごくエロい。そのものズバリ、誰が見てもエロティックな場面というわけではないのに、ぞくっとする。たぶん、他者との関係が日常を越えてエロティックなものになる、その最初の瞬間を描いているのだ。ちょっと坂木さん、上手すぎませんか? と言いたくなる。
そういえば、性欲のことを肉欲とも言う。それだけではなく、食べるという行為にもそこはかとなくエロティックな部分はある。美味は官能によくたとえられるけど、ある意味、美味しくないものを食べたり、嫌いなものを食べたりする行為にも、どこか性的なものは潜んでいるのかもしれない。
好きなもの、美味しいものは無意識におしゃべりしながら食べられるけど、嫌いなものを食べるときは、無意識ではいられない。舌や口の中に意識は集中する。集中しすぎて、考えないようにして無理に呑み込んだりする。
『肉小説集』の中に描かれている場面や感情は、美しいものや感動的なものではないし、主人公である男性は、みんないろんな意味でダメだけれど、坂木さんの手にかかると、それを心地よく呑み込まされてしまう。
呑み込んだダメな男たちは、わたしの一部になる。いや、もともとわたしの中にあったのかもしれないけれど、うまく呑み込まされてしまったあとでは、どうだかわからないのだ。
『肉小説集』の中には、美味しそうな料理も、全然美味しそうではない料理も出てくる。でも、「美味しい小説」であることは間違いない。
ぜひ、ご賞味あれ。