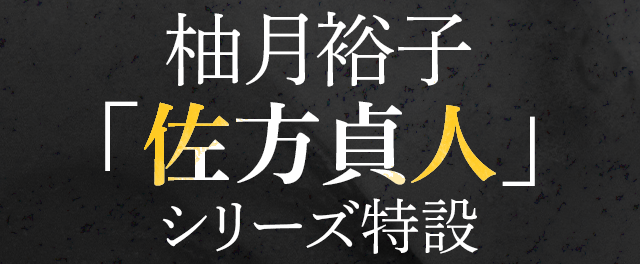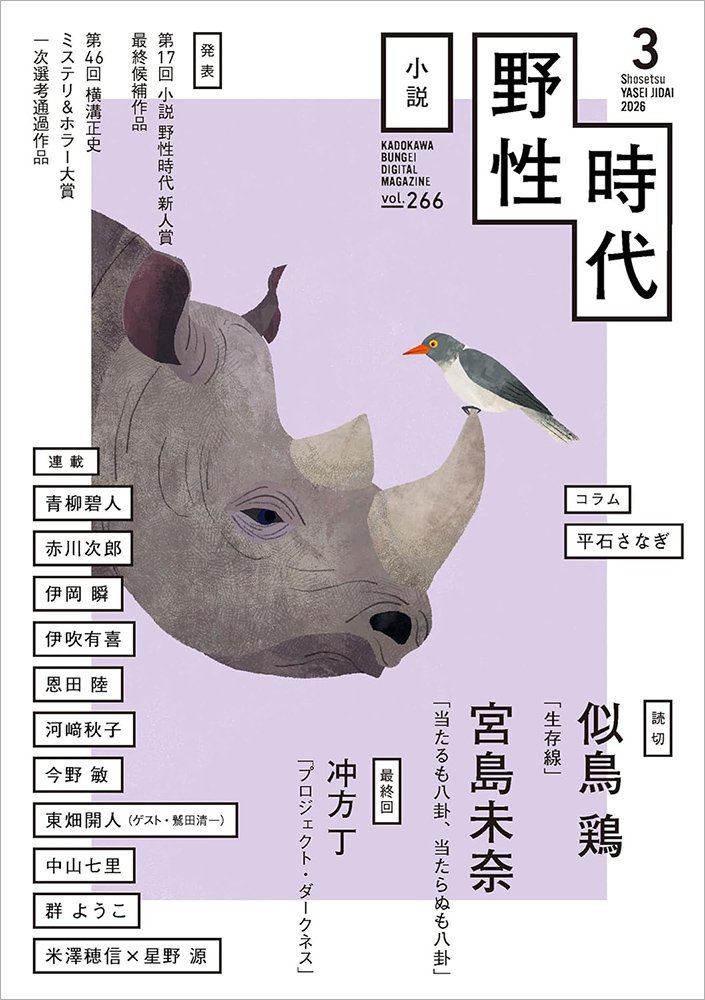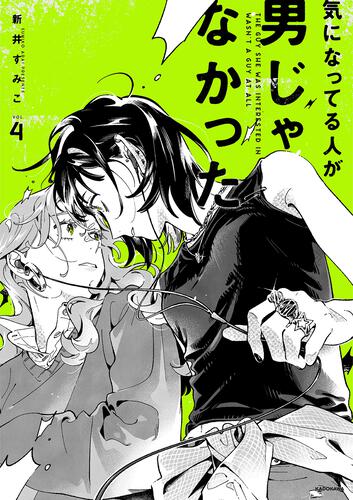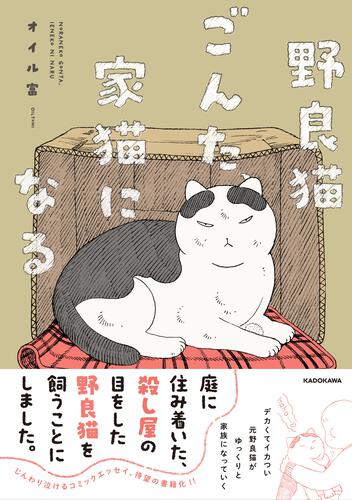昭和五十年(一九七五)前後、私が通っていた関西でも屈指のマンモス小学校の図書室に唯一、置かれていた漫画本が『学習漫画 日本の歴史』全十八巻だった。国語の授業で読書タイムになると、奪い合いになるほどの人気である。だからどの巻も手垢で汚れ、製本も崩れては修繕を繰り返した痕跡が目立ち、ボロボロだった。これは昭和四十二年に集英社が出した、初めての子供向け漫画による日本史シリーズである。
終戦を機に日本史研究は、皇国史観から解放されて著しく進んだ。その成果は昭和四十年から刊行が開始された中央公論社版『日本の歴史』全二十六巻などにより、戦後復興を遂げた日本社会の中に普及した。だが、一方で子供の活字離れが問題化し、漫画はむしろ害毒と見られることも多く、その社会的地位もいまよりずっと低かった。そうした中で、子供向けに日本の通史を漫画化しようというのは、大胆な試みだったはずだ。小学生だった私も、その恩恵を受けた一人だから、大いに感謝したい。
集英社版以後、各社が続々と日本史漫画を競作している。研究の進歩や、画風の流行にも対応しているのだろう。いまや、日本の国民が生まれて初めて出会う自国の歴史書は、学習漫画だと言っても過言ではあるまい。ファースト・インプレッションであり、将来の歴史観の土台となる可能性も高い。そう考えると、作り手の責任は重大である。
さて、今回、角川まんが学習シリーズの『日本の歴史』全十五巻が文庫化されるという。数年前に出た単行本は子供向けだったが、文庫はターゲットを受験生、あるいは一般社会人まで広げているようだ。大人でも数々の発見があることは、言うまでもない。
ひとまず私は、自分が解説を担当する十一巻の『黒船と開国 江戸時代後期』を読ませてもらった。思えば学習漫画を読むなんて、四十年ぶりである。これだけの多岐にわたる情報を、よくぞコンパクトに纏めたというのが、とりあえずの読後感である。
ペリー提督率いるアメリカ合衆国の黒船艦隊が来航する嘉永六年(一八五三)六月が、「幕末」の開幕とされることが多い。しかし本書では、それより四十年ほど前に遡り、幕藩体制の土台が大きく揺らぐところから始まるから理解し易い。天保の改革で水野忠邦により登用されたメンバーの中に北町奉行の「遠山景元」がいるが(三十七頁)、これが時代劇でおなじみの「遠山の金さん」である。ドラマは時代背景などあまり意識せずに作られているようだが、「金さん」は安政二年(一八五五)まで生き、ペリー来航も日米和親条約締結も経験したから、「幕末の人」だったとあらためて気づかされる。
下田からアメリカ密航を企てた長州の吉田松陰が、ペリーと直接会話をする場面がある。史実では、旗艦ポーハタン号を密かに訪ねて来た松陰に応対したのは通訳ウィリアムスであり、ペリーは姿を見せなかった。ペリーVS松陰というのは、漫画ならではの楽しいフィクションであり、このような史実との乖離は大小さまざま、他にもたくさん見受けられる。読者はそうした点を理解した上で、読み進める必要がある。
また、従来の歴史のイメージに引きずられている部分も無きにしもあらず。この巻で言えば、幕府が西洋列強の威嚇に屈し、開国したというあたりだ。八十頁には「幕府はペリーにおし切られ『日米和親条約』を結んだ」とあり、九十六頁には西洋人にヘコヘコと頭を下げる幕府役人の姿などが描かれる。確かに薩長の「志士」たちの目には、幕府の外交は「弱腰」と映った。だから、「勝者」となった薩長閥が編んだ「明治維新史」は、幕府が倒されなければならなかった理由として、外交の失敗を挙げた。
ところがペリーと応対し、日米和親条約を結んだ幕府の林復斎(大学頭)が著した『墨夷応接録』(『大日本古文書 幕末外国関係文書 附録之一』)などを読むと、イメージは一変する。高圧的なペリーはまず、日本が人命を重んじない、不仁の国だと決めつけて非難する。これに対し林は例を挙げ、世界中でも人命を重んじて来た国だとし、だからこそ三百年も平和が続いているのだと反論する。するとペリーは、交易を行えば大きな利益が得られると誘う。すると林は、それは理解しているが、日本は自給自足で良いと言う。また、人道と利益の問題は別だと論破し、ペリーの最低限の要求しか認めなかったことが分かる。つまり、明治維新は外交の失敗ではなく、とりあえず成功から始まったようだ。
後半は、坂本龍馬が主人公の一人になる。しかし、薩長同盟を中心になってまとめたとか、大政奉還を主唱したとか言われる龍馬の功績は疑問視され、「船中八策」という国家構想を著したことも、後世の創作である可能性が高いとされる。このため龍馬が教科書から消えるとかで、話題になっていたのも記憶に新しい。
また、将軍徳川慶喜による大政奉還が描かれた後、「二百六十五年続いた徳川幕府は幕を閉じ、新たな時代に向かっていくことになる」と締めくくられるが、これについても少し解説を加えておく。慶応三年(一八六七)十月十五日、朝廷は慶喜の大政奉還を受け入れた。だが、大政奉還によって幕府は、「幕を閉じ」たわけではない。征夷大将軍の肩書はそのままで、翌十六日から内政も外政も慶喜が担当するのだ。近日中に十万石以上の大名が京都に集まり会議を開き、投票でトップを決め、新政権が誕生する予定である。投票になれば、トップは慶喜になる可能性がきわめて高い。
慶喜を政権から何としても排除したい薩摩の西郷隆盛たちは、諸侯会議や投票の実現阻止を企む。そこで政変を起こし、十二月九日、「王政復古」の大号令を発して総裁・議定・参与から成る新政権を、会議を経ずにスタートさせた。ここで幕府は、完全に消滅。当然新政権の中に、慶喜の名は無かった。それどころか新政権は、慶喜に辞官納地を命じる。慶喜側の怒りは、翌年の戊辰戦争へと発展してゆく。
明治政府は「広く会議を興し、万機公論に決すべし」(『五箇条の誓文』一条目)をスローガンとする。しかし実際は会議を潰し、公論を封じ込めて誕生した政権だった。それもまた、明治維新の興味深い矛盾点なのである。
書誌情報はこちら≫山本博文『漫画版 日本の歴史 11 黒船と開国 江戸時代後期』
☆試し読み公開中→平成最後の年末こそ、まんがで日本史を振り返ろう! 試し読み第一回は幕末前期を描いた「尊王攘夷」
>>シリーズ一覧ページ
レビュー
-
試し読み
-
特集
-
特集
-
レビュー
-
レビュー