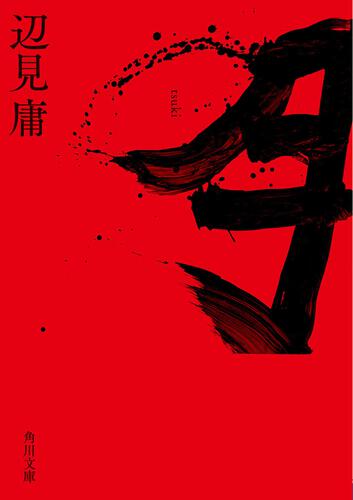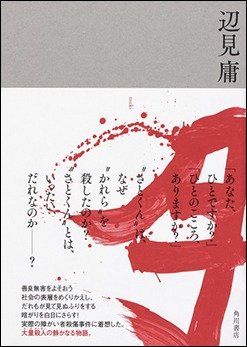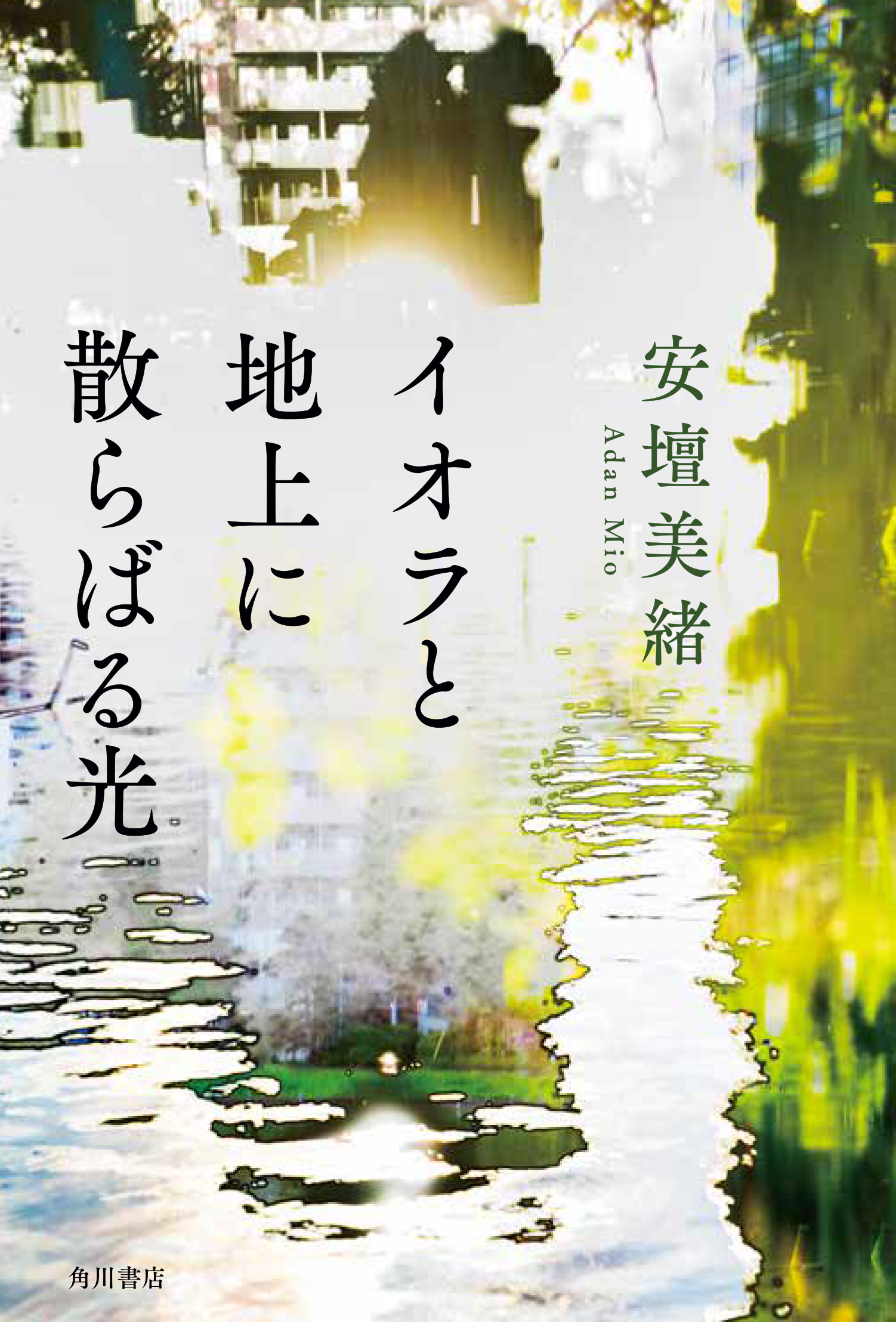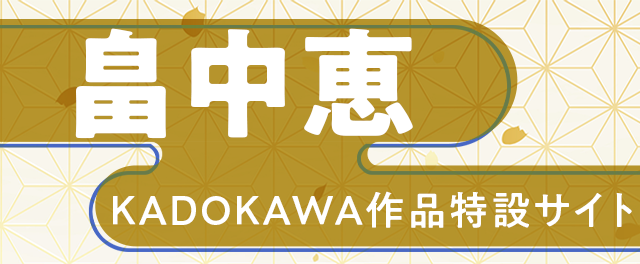辺見庸という作家は僕にとってとても怖い存在であり続けている。もともと共同通信の記者だった頃の『もの食う人びと』という食い物の臭いがしてくるようなルポルタージュや、反時代的な鋭角のエッセイ群を読んできたこともあって、自分のなかでは、氏のジャーナリストとしての側面が常に意識されてきた。マスメディアのありように悪罵を投げつける氏の姿勢は、かつてそのマスメディアのなかにどっぷりと身を置き、その生理を知り尽くしているがゆえに可能な罵倒なのだと思っている。一方で、氏の小説と詩文の豊かな展開も目にしながら、講演会に足を運んでもきた。怖い存在だ。
『月』という2018年月末に刊行された小説は、2016年7月に神奈川県相模原市で起きた津久井やまゆり園事件に想を得て執筆された。重度の障害者19人が殺害され、27人が重軽傷を負ったあの事件である。一人の人間が起こした大量殺傷事件としては戦後最悪の規模の大事件だ。犯行当時26歳だったこの施設の元職員・植松聖被告は、犯行前に予告の手紙を衆議院議長あてに送っていた。そのなかには彼がなぜ犯行に及ぶのかの動機が記されていた。以下、一部を引用する。〈障害者は人間としてではなく、動物として生活を過しております。車イスに一生縛られている気の毒な利用者も多く存在し、保護者が絶縁状態にあることも珍しくありません。私の目標は重複障害者の方が家庭内での生活、及び社会的活動が極めて困難な場合、保護者の同意を得て安楽死できる世界です。重複障害者に対する命のあり方は未だに答えが見つかっていない所だと考えました。障害者は不幸を作ることしかできません。(略)戦争で未来ある人間が殺されるのはとても悲しく、多くの憎しみを生みますが、障害者を殺すことは不幸を最大まで抑えることができます。今こそ革命を行い、全人類の為に必要不可欠である辛い決断をする時だと考えます。日本国が大きな第一歩を踏み出すのです。(略)是非、安倍晋三様のお耳に伝えて頂ければと思います。私が人類の為にできることを真剣に考えた答えでございます。衆議院議長大島理森様、どうか愛する日本国、全人類の為にお力添え頂けないでしょうか〉。植松被告は精神鑑定の結果「自己愛性パーソナリティー障害」と診断された。拘置中の植松被告は、その後、メディア関係者や精神科医らいわゆる専門家らと面会も行い、自筆のイラストや文章も発信している。実は僕も一度だけ彼と手紙を交換したが、独得なタッチの細密画のようなイラストが郵送されてきた。彼の造語「心失者」は、人間であっても、心がない、もはや人間ではない者という意味らしい。「心失者」は社会的見地からは消去してもよいのだと。もっとも重要なことは、植松被告が今現在に至っても自分が起こしたことは基本的に間違っていなかったと確信していることだ。
この事件の取材を僕はあまりやってこなかった。これだけの大事件なのに、継続して取材を続けてこなかった。もちろん事件発生の日やその後一、二か月後くらいのストーリーはつくってきた。だが浅いのだ。僕らは昨日のニュースをすぐに忘れる。そして、この事件の場合、率直に記すのだが、何かマスメディア全体が、不可逆的な方向として、この大事件を忘れよう、遠ざけよう、なかったことにしよう、過去に押しやろうとでもいうような不可視の力が働いているように僕は感じた。曰く、あれは特異な人格の者が引き起こした特殊例外的な犯罪だ、人は誰でもこの世に生をうけた瞬間から人間として平等に生きる権利が与えられていることになっているのだ、健常者と障害がある者が共生する社会はほぼ実現されており、それを否定することなどあってはならない……。それはあたかも、直視するとおのれの存在を揺るがすような深い闇が目の前にぽっかりと口をあけているのを見ないふりをしている所作ではないのか、と思っていたところがあった。メディアを通して提示されたのは、事件は障害者たちの世界に途轍もない衝撃を与えましたという障害者の立場に寄り添ったストーリー、再発防止のため措置入院制度の厳格化が必要ですといった管理する側からの発想丸出しのストーリー、ナチスドイツはホロコーストの前哨としてT4作戦という障害者処分を決行していましたという歴史を顧みるストーリー、障害のある家族をもつ親、兄弟姉妹、親族からの、当事者に近い場所に私はいますというストーリー。
何か決定的なことが回避されているのではないかという思いが心のなかに燻っていた。それは、植松被告の主張するようなあられもない障害者観は、どこかこの日本という国で根をはってしまっている、あるいは共有化されてしまっているのではないか、と。
あの事件に想を得た小説を辺見氏が書いたと聞いて、僕は、大江健三郎の『政治少年死す(セヴンティーン第二部)』のような作品ではないかと勝手に思い込んでいた。浅沼稲次郎暗殺を決行した少年を主人公としたこの作品は、当時は彼の全集には収録されていなかった。僕は地下出版されたそれを故・遠藤忠夫氏の経営する神保町のウニタ書舗で購入していて今も持っている。だが『月』を読了したところ、大江のその作品と言うよりは、セリーヌやドストエフスキーの小説を想起させられた。『月』の主人公は、重度障害者施設のベッドのうえでほとんど体を動かすことができずに横たわり続けている「きーちゃん」だ。彼女は肉体的な痛みと精神的な苦悩のなかで生きている。彼女の精神は繊細にして実に明晰だ。自分たちに注がれている職員たちの、世間の、社会のまなざしの、あるいは物理的なふるまいのなかに潜んでいる「本質」を見抜いている。お気に入りの、あるいは、ついには「恋愛」に近い感情を抱いている介助職員「さとくん」が、次第に孤立化して暴力へと突き進んでいく過程を「きーちゃん」は冷徹に観察しており、やがてワクワクしながら待ちわびるようになる。そしてついにその日の決行へと至る。壁に向かって投げつけられたように塗り込まれた裸の言葉が作品中で続く。この小説空間は、あの施設の内部そのもののような極度の緊張感がみなぎっているのだ。「さとくん」の歌声が随所で流れる。〈ロッカバイロッカバイバイバイロッカバイ〉。「さとくん」と「きーちゃん」の「対話」はまるで大審問官と弱き人間との対話のようだ。〈あのさ、ほんとうは正気のにんげんが狂ったふりをするのと、じっさいには狂ったやつが正気のふりをするのと、どちらがむずかしいとおもう?〉。「きーちゃん」は思っている。〈痛みを消してくれるならば。全人類を敵にまわしてもいい。この痛みがなくなるなら〉。「さとくん」が無意識にひとを対比していることを「きーちゃん」は知っている。〈《まさりおとり》を。優劣をくらべようとするものに、くらべてはならないといってもはじまらない〉。「きーちゃん」は施設の生活のなかで次第にこう思うようになる。あの村上春樹の騎士団長のような言い方で。〈あたしはといえば、じぶんが在られないこと、在られなくなることを、こころのどこかでまっている。望んでいるのかもしれない〉。「きーちゃん」の分身「あかぎあかえ」が作品に唐突に登場する。「あかぎ」は知っている。〈みなれたものが「真実」なのであり、みなれぬものは「奇」なのだ〉と。「さとくん」と「あかぎ」の対話が延々と続く。なぜそんな作戦を決行するのか。〈「ショウドウノダイコウ……かな」と青年はいう。衝動の代行。くりかえす。「かくれた衝動の代行です。かくされた、かな……」「だ、だ、だれの? だれの衝動?」「みんなの。世界の……です」「み、みんなの? せ、世界の? な、なぜ、そういいきれるんだい?」〉〈「ぼくはですね、やるときめたおとこです。ぼくは逃げません、(略)求めをひきうけて実行するんです。あってはならないといわれることをひきおこす、フツウじゃない、マトモじゃない役をやりとげます。ぼくは近々、テレビに映るでしょう。アホバカテレビに、まちがいなく。ぼくは本にも書かれるでしょうね。きっとぼくは有名人になります。新聞や多くのひとたちがぼくをボコボコに非難するでしょう。おなじみの精神科医や評論家たちがテレビで、いかにも憂い顔で、それでも得意げにへらへらとしゃべりだすでしょうね〉〈底のあさい特集番組がNHKをはじめ、いくつもつくられるでしょう。じっさい、ぜったいに底があさくなければならないのです。番組内容の底があさくて、どうじに、底のあさいペラペラの良心をちょっとばかり偽善的に満足させることのできる番組。番組をみるがわもそのほうがたすかる。だって、底の深いものだったら、視聴率がとれないし、内容しだいでは、ぼくの作戦を肯定することにもなりかねないですからね〉。そして決定的な言葉を「さとくん」は「あかぎ」に難もなく告げるのだ。〈優勝劣敗は社会の規準になりました〉(※)。
優勝劣敗は社会の規準になりました? 重く深く突き刺さってくる問いかけではないか。僕は自分の記者生活を振り返る。今から40年前、僕が最初につくった「底のあさい特集」は、東京都の足立区花畑で起きていた障害児の公立小学校への自主登校の動きだった。養護学校義務化の年、地域の小学校に通いたいと車椅子で自主登校した小学生を、学校の教師たちが校門のところで隊列を組んで「阻止」していた。当時はまだ出始めだったVTRカメラを持ち込んで連日取材をした。彼は結局、普通学級への入学が認められ、中学、高校も普通校へと進んだ。その後、一人暮らしをしていた彼はある日、のどに食べ物を詰まらせて死亡した。彼の弟さんとは今でも付き合いがある。1982年から83年にかけて、横浜の地下街などで中学生たちによってホームレスが次々に襲撃されて数人が殺されるという事件があった。若い社会部記者だった僕は、当時の横浜地下街の商店主が取材でこんなふうにインタビューに語ったことを覚えている。「彼らは人間の形はしていますが、人間ではないわけですから、中学生たちがやったことを内心ではみんな喜んでいるんじゃないですか」。夕方の全国ニュース番組『ニュースコープ』で放映された後にすさまじい反響があった。この商店主は許せないと。今現在は、ホームレス襲撃はニュースにもならない。あまりにも頻発しているか、あるいは可視化されない出来事になったからか。2018年、障害者への強制不妊手術の実態がニュースで報じられた。強制不妊手術を法で認めた「旧優生保護法」は実に1996年までおよそ半世紀にわたってこの国には存在していた。障害者雇用の実績が水増しされていた問題が発覚したのも2018年のことだ。省庁や地方自治体などの公的機関で、本来ならば障害者に該当しない者を障害者として雇用し、障害者の雇用率が水増しされていた。みんなつながっているではないか。僕らはしかし直視を避ける。それは自分たちのなかに同じ思想があるからではないのか。ほんとうに『月』は重く、深い。〈ロッカバイロッカバイバイバイロッカバイ〉。
※〈 〉内はすべて『月』からの引用
(TBSメディア総合研究所発行『調査情報』2019年1-2月号「メディア論の彼方へ――83」より転載)