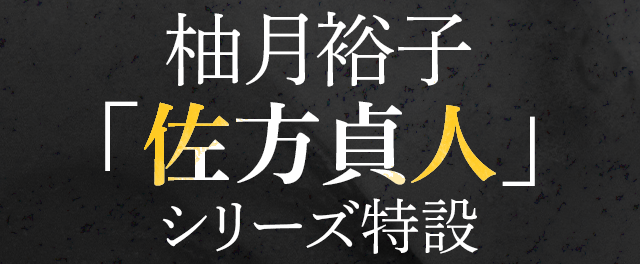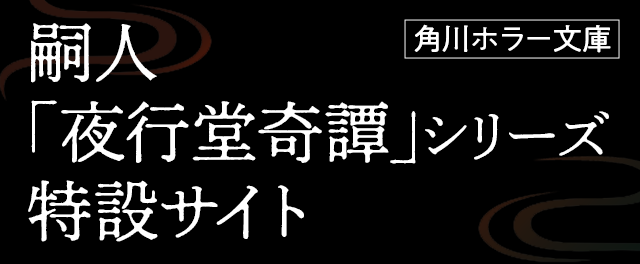青春小説、と呼ばれる少年少女を扱う小説を書いていると、ふと、こんなことを思う。
それは、子どもは成長する時、親以外の大人と出会い、何かを学ぶ必要があるのかもしれない、ということだ。親のような絶対的な血のつながりのない大人は、子どもにとって世界との最初の窓口になる。そんな存在が近くにいる子どもは恵まれている。
そして、今、自分自身が親となり、大人となってからは、こうも思う。
大人もまた、自分より小さなものから多くを学ぶ必要がある。それはもう、子ども時代よりも何倍も切実に。そんな存在が近くにいる大人は、とても幸せなのだ、と。
『バケモノの子』の主人公・蓮は、親と別れ、渋天街と呼ばれるバケモノたちの暮らす異界へと迷い込む。そこでは、彼らを束ねる宗師の跡目争いの真っ只中。蓮はひょんなことから、跡目を狙う一人である熊徹という大男の弟子になり、彼から「九太」という名前を付けられる。
行き場のない蓮は、気が合わないと感じながらも、熊徹のもとで弟子として必死に食らいつく。家事をし、熊徹の動作を真似し、手探りで、世界と渡り合うのに必要な強さを獲得していく。
一方、最初から力を持ち、強い熊徹は、これまで家族や弟子を持たなかったから、弟子となった九太に何をどう教えればいいのかわからない。「グーッと持って」「ビュッといって」という自分には自明の感覚が九太には伝わらず、もどかしさでこう叫ぶ。
胸ん中で剣を握るんだよ! あるだろ胸ん中の剣が!
二人の稽古と生活風景を読み進めるにつれ、読者はだんだんと気がつくはずだ。師匠であるはずの熊徹こそが、九太を通じて、九太の何倍も多くの感情や強さ、ひいては弱さまでもを獲得していくということを。慈しみや気遣い、心配、近くなればなっただけ、今度はまた苛立ち、怒りも悲しみも寂しさも、自分よりずっと小さな九太から、熊徹が学んでいく。どれだけ強く、体が大きくとも、それは、彼にとって初めての気づきと成長だ。
物語のラスト、熊徹と九太は二人とも、それぞれに重大な決断を迫られる。大人と子ども。大きなものと小さなものが、それぞれ互いを対等な立場で思い、慕って下すその決断に、私は息が詰まりそうになった。泣く、なんてものじゃない。苦しいくらいに、胸がいっぱいになって、言葉がなかった。
二人の関係は親子とも似ているが、それだけじゃない。そんな存在が互いにいることが彼らをこんなに強くする。読者それぞれに、彼らの姿と成長を、最後まで見届けてほしい。絶対に驚きに満ちた感動が待っているから。
最後に。
よく、私は原作小説がある映画を観に行く際に「原作を読んでから観るか、観てから読むか」、それとも「観るか読むか、どちらかだけにするか」を迷う。
そして、私は、これまでの経験から、こと細田守作品に関しては、「原作も映画も、どちらも楽しむ」ことをオススメしたい。
『バケモノの子』を読むと、頭の中で絵が浮かぶ。それは、疾走感に溢れ、音や光を感じるほどに生き生きと。しかし、私はそれでも、細田監督の映画が、それを何倍も上回る表情や声を私たちに届けてくれることを知っている。
先に映画を観た人にも、どうか小説を読んでほしいと思う。あの素晴らしいアニメーション映画を、細田監督がどんな言葉で表現し、あれらの感情をどんな思いで紡ぎあげたのかが、ここには全部書いてある。
読むか、観るか。どちらが先か。どちらにせよ、細田守作品がやってくる日本の夏は、幸せな夏だ。熊徹と九太が活躍する今年のお祭りのような夏の熱気を、あなたにも存分に感じ取ってもらえたら、ファンの一人として、とても嬉しい。
>>映画「未来のミライ」公式サイト
紹介した書籍
関連書籍
-
レビュー
-
試し読み
-
試し読み
-
試し読み
-
レビュー