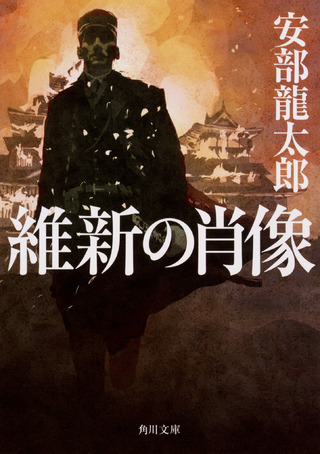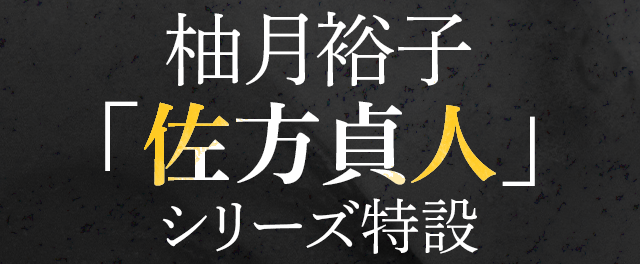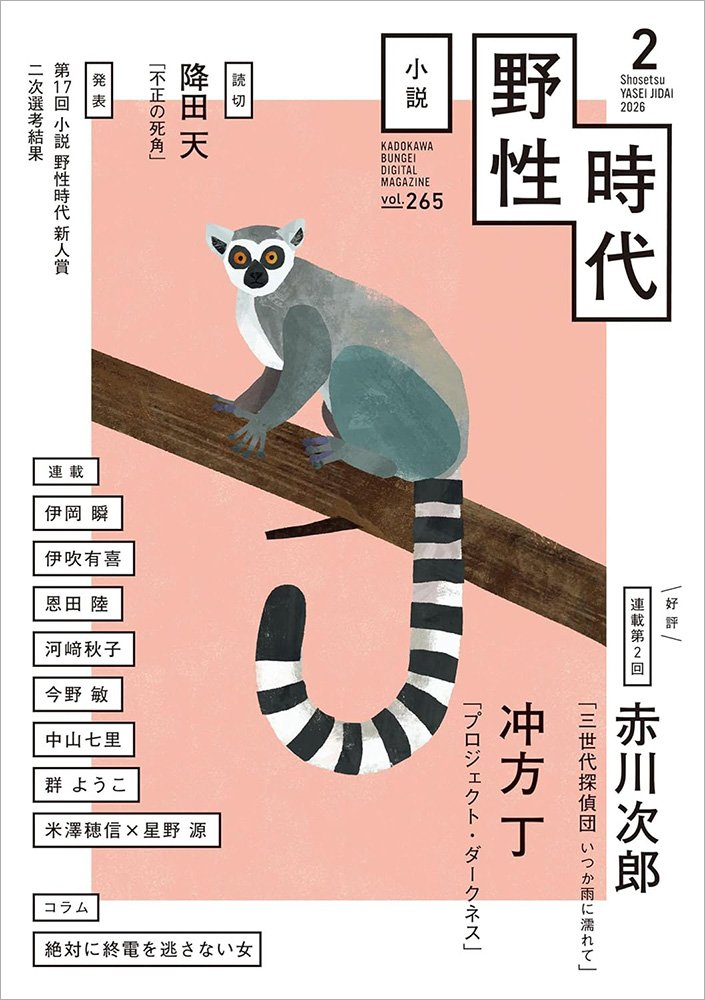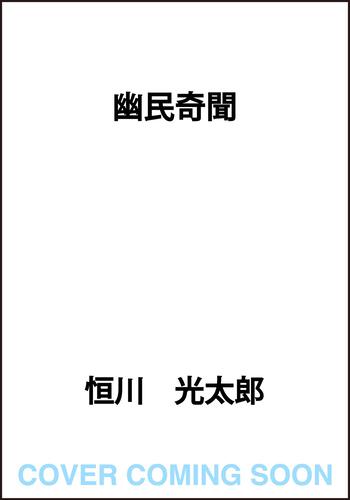わたしが初めて安部龍太郎氏にお目にかかったのは、忘れもしない二〇一二年の一月。拙著が福島県白河市主催の中山義秀文学賞を頂戴し、その選考委員の一人として安部氏が授賞式にお越し下さった折のことだ。
今でもよく覚えている。授賞式開始直前に会場に飛び込んで来られた安部氏は泥だらけの長靴にダウンジャケットを着込み、よほど長時間、寒空の下にいらしたのだろう。頬が真っ赤に上気してらしたのが、ひどく印象的だった。
「いやあ、取材で会津を回ってきたんだけど、すごい雪でねえ。電車がいつ止まるかとひやひやしたよ」
「取材、ですか……」
わたしが思わず呟いたのには理由がある。この日から遡ること十か月前の二〇一一年三月十一日、三陸沖を震源とするマグニチュード九の地震とそれによって引き起こされた津波により、東北各県は死者・行方不明者一万八千四百余名、全半壊戸数四十万余軒という、かつてない被害を蒙った。加えて震災直後に発生した福島第一原子力発電所の事故により、多くの方々が避難を余儀なくされただけに、年が改まっても被災地域の混乱はいっこうに収まる様子がなかった。
実際この日も、白河市のシンボル・小峰城は石垣や曲輪の崩落に伴って立ち入りが禁止され、市内のそこここにも震災の爪痕は無数に残されていた。原子力発電所の事故による風評被害は日を追うにつれてむしろ激しくなり、東北、いや日本じゅうが激しい混乱のただなかにある中、なぜ安部氏はその東北で取材をなさっていたのだろう。
だがそんなわたしの疑問は、その翌年に至り、あっさりと氷解した。震災から丸二年を迎えた二〇一三年の春、安部氏は東北を舞台とした二つの長編を、相次いで雑誌に発表なさったからだ。
一つは豊臣秀吉が天下統一を成し遂げんとしていた天正十九年、奥州で発生した九戸政実の乱に題を取った『冬を待つ城』(新潮文庫)、そしてもう一作が戊辰戦争を生き抜いた二本松藩士・朝河正澄とその息子であるアメリカ・イェール大学教授・朝河貫一、時代も生きた場所も異なる親子二代の戦いを描いた本作、『維新の肖像』である。
そう、一九九〇年のデビューよりこの方、一貫して日本史の中の弱者を描き続けて来られた安部氏は、かつてない災害に見舞われた東北に捧げるべく、かの地を舞台とする二つの物語に挑まれたのだ。
一読していただけばお分かりの通り、『維新の肖像』は日本が軍国主義化への道をたどる一九三二年、歴史学者である朝河貫一が父・朝河正澄の経験した明治維新を小説として執筆するという、歴史小説には珍しい二重構造となっている。だが、精緻な織物のように過去と現在が絡み合う本作には、もう一点、既存の歴史小説と大きく異なる点がある。それは戊辰戦争を生き抜いた二本松藩士たる父と、母国の軍国化を憂う息子という二人の視点を通じて、「維新」とは何かとの問いが、我々に突きつけられていることだ。
幕末および明治維新を描いた小説は、これまでに数多い。しかし誰もが無意識のうちに、維新を近代化への一歩と捉えてきた中、その意義を改めて問い直した作品が、かつてあっただろうか。
本作の冒頭、朝河貫一は日露戦争以降の日本の侵略主義に警鐘を鳴らし、故国がどこで道を誤ったかを知ろうと模索する。そして遂に彼が見出した結論は、日本の失策の根源は、維新が持つ思想と制度の欠陥にあるとするものであった。
つまり安部氏はここで、反日本の気風が吹き荒れるアメリカで孤独に戦い続ける貫一の目を通じ、日本人が知らず知らずのうちに信じ込んでいる「維新史観」の再検討を我々に迫っているのである。
作中、海軍将校による五・一五事件に接した貫一は、彼らを「昭和維新の志士」と誉めそやす風潮を知り、
明治維新は功罪半ばする革命である。
と呟く。
どんな手を使っても勝てばいいという軍部のやり方は、維新の際の薩長勢のやり口とまったく同一。そして維新を成功させた「志士」の驕りこそが、日本から正義の精神を奪い、ついには軍国主義に進ませたとする指摘は、いまだ評価の定まらぬ近代日本を考える上で、きわめて重要な視座ではあるまいか。
ところで現在の歴史・時代小説界において安部龍太郎氏と双璧を成す葉室麟氏は、二〇一七年十月五日に京都新聞に掲載されたエッセイにおいて、明治維新は革命だったのかという疑問を提示した上で、次のように述べておられる。
(前略)外国勢力が迫る中、国内を二分する戊辰戦争を起こしたことが功績であるという考えには疑問がある。あるいは新政府での薩摩と長州の権力を確固としたものにするための戦争ではなかったか。(中略)だとすると、明治革命は〈簒奪〉の革命だった可能性があると思うのだがどうだろうか
来年二〇一八年は、明治維新百五十年。このため、いわゆる薩長土肥――鹿児島・山口・高知・佐賀の四県は、昨年より広域観光プロジェクト「平成の薩長土肥連合」を設立し、様々なイベントを行なっているし、政府は「明治150年」関連施策推進室を設置して、「明治の精神に学び、日本の強みを再認識」すべきと提言している。
そんな時期に、日本を代表する二人の歴史小説家が維新史観からの脱却と明治維新の再検討を提唱しているのは、果たして偶然だろうか。百五十年の時間を経て、我々は明治を近代の中でどう位置づけるべきか、ようやく冷静に語ることのできる時代に立ち合っているのではないか。
若き頃、明治維新を偉大な革命と信じて疑わなかった朝河貫一は、満州事変・上海事変を相次いで起こした母国の姿を見て、明治政府の教育からの脱却に至る。それはまさに百五十年の時間を経て、維新史観の再検討に至る我々の姿であり、いわば本作は歴史小説であると同時に、日本人が当たり前と信じてきた明治維新観の転換を迫る内省の書でもあるのだ。
ところで震災から一年四か月後の二〇一二年七月五日、東京電力が発表した「国会事故調査委員会報告書」の序文には、こんな言葉がある。
100年ほど前に、ある警告が福島が生んだ偉人、朝河貫一によってなされていた。朝河は、日露戦争に勝利した後の日本国家のありように警鐘を鳴らす書『日本の禍機』を著し、日露戦争以後に『変われなかった』日本が進んで行くであろう道を、正確に予測していた。『変われなかった』ことで、起きてしまった今回の大事故に、日本は今後どう対応し、どう変わっていくのか。これを、世界は厳しく注視している。この経験を私たちは無駄にしてはならない。
かつて朝河貫一が母国に向けて鳴らした警鐘はついに届かず、日本は第二次世界大戦へと突入するに至った。しかしそれから百年近くを経た今、かつてない震災を経験した我々は、再び「変わる」ことを迫られている。
自分たちは、何者なのか。何に依って今、ここにいるのか。安部氏が――そして朝河貫一が突き付ける問いに向き合って初めて、我々は真の「近代」を生きることが出来るのかもしれない。