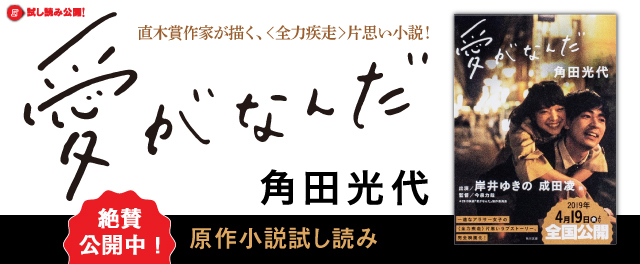
一途なアラサー女子の〈全力疾走〉片思いラブストーリー!
岸井ゆきのさん・成田凌さん主演、映画『愛がなんだ』が本日4/19(金)に公開となります。
公開日まで5日間、カドブンでは角田光代さんによる原作小説の試し読みを行います。(第1回から読む)
<<第4回へ
シャンプーを泡立てていると、洗面所に投げ置いた携帯電話が鳴っているのが聞こえた。頭を泡だらけにしたまま風呂場を飛び出て、クッションフロアにしゃがみこんで携帯電話を捜す。マモちゃんの名がディスプレイに表示されている。やっぱり。私の読みははずれていなかった。
「はい、もしもし」平静をよそおって私は発音する。
「あー、ちょっと今日マジ疲れたー、山田さん何してた? めし、食っちゃった? って、こんな時間だもん、食っちゃったよね」
「それがさあ」すかさず私は言う。「今日超忙しくてさあ、四時ごろ昼ごはん食べて、それきり何も食べられずにさ、今ひもじく家路にたどりついたとこだよ」午前○時二十分に家にいて、四時から何も食べていないという噓が上ランクのものか否かはべつにして、私の噓の思いつき度は、近ごろ天才の域に入ると我ながら思う。
「え、マジ? おれもまだなんだよねー、なんか軽く飲みたくってさあ、友達何人かに電話したんだけどこの時間だから、みんな寝てたり風呂入ってたりして」
そりゃあそうだろう。私だって風呂に入っている。
「でも山田さん、めし食ってないならちょうどいいや。ちょこっと飲まない? おごるよ、おれ」
どちらにしても、マモちゃんは私の噓を信じる。午前○時二十分に、空腹のまま家で何もしていない人間がいるかどうかなどと彼は疑わない。人として品がいいのだ、と私は思う。
「じゃ、飲もうよ、私もちょうどよかったよ、これからなんかつくるのも億劫だったしね。マモちゃん今会社? そっちいこうか? それとも、新宿とか下北方面のほうがいいかな」
「今家でしょ? たるくない、出るの?」
「ぜんぜん。私も飲みたかったし、金曜だし」
「そんなら神楽坂で。あ、飯田橋でも。出やすいほうで。いい?」
「ラジャー。近くにいったら電話する。じゃあね」
電話を切り、ひゃっほう、と私は叫び、素っ裸で飛び上がる。シャンプーの泡が飛び散る。その場で軽くひと踊りしたい気分だったが、速攻で風呂場に戻り泡を洗い流し、風呂から出て体を拭いて下着をはいて服を捜す。体があるということがもどかしい。魂だけだったら今すぐ、マモちゃんの会社の前まですっ飛んでいけるのに。体なんかがあるばっかりに、服は着なくてはいけないわ、髪は乾かさなくてはいけないわ、眉は描かなくてはいけないわの大騒動である。
電話を受けてからタクシーに乗りこむまで、十七分だった。上出来である。行き先を告げ、薄暗い後部座席で私は眉を描く。年若い無口な運転手は気をつかって、車内ランプをつけてくれた。
ついさっき徘徊していた町に、深夜一時二十分、私はいる。午前四時まで開いている居酒屋で、マモちゃんと向きあって酒を飲んでいる。
「あーよかった、山田さんもつかまんなかったら、おれまたコンビニ飯だったよ、昨日もコンビニ飯だったんだよな」
マモちゃんは、四日前に風邪をひいていたことなど、すっかり忘れているようだ。もちろん私もあのときのことを蒸し返したりしない。何が気にくわなくて私を部屋から追い出したのか訊いたりしない。
「なんだ、電話してくれればつきあったのに」
「だってそれ、一時すぎだぜー、電話できないっしょ、良識ある青年男児としては」
「私も昨日は遅くまで残業だったから、ぜんぜんよかったのに」
「へえー、忙しいんだね、山田さんの会社も」
マモちゃんは手をあげビールのおかわりをたのむ。山田さん。マモちゃんは五ヶ月のあいだずっと私をそう呼んでいる。テルちゃん、と呼んだのはただの一度だけ。出会った最初の日だけだ。
マモちゃんにはじめて会ったのは、葉子の友達が主催した飲み会だった。葉子が以前契約していた編集プロダクションの社員だったか、それとも葉子と同業のライター業だったか、よく覚えていないが、その人が自宅で飲み会をして、私は葉子に誘われて参加したのだった。
葉子の友達は私たちより少し年上の女性で、ずいぶん大きなアパートに住んでいた。二十人近くが立ったり座ったりして飲み食いしていたのだから、居間だけでも私の家より確実に広かった。
そのとき私は、交際していた男との関係にいきづまっており、というより、関係は終盤にさしかかっているというのに私ひとりあがいており、見かねた葉子があちこち連れまわしてくれていたのだった。葉子自身はそういう集まりに顔を出す質ではないのだけれど、見知らぬ人間の集まる場所で、ひょっとしたら私を救い出すあらたなる人材がいるかもしれないと、冗談交じりに、半ば本気で言いつのりながら。
果たしてそこで、私はあらたなる人材にめぐり合ったということになる。
そのときのことを何から何までひとつひとつちゃんと覚えている。マモちゃんが着ていた服のことも、はじめましてとたがいに挨拶したときの言葉も。
私とマモちゃんは挨拶した次の瞬間にもううちとけて、部屋の隅でしゃがみこみ、一本のワインを真ん中に置いて、たがいにつぎたしながら飲み、他愛ない言葉を交わした。ひょろりと瘦せて小柄なマモちゃんは、私の好みのタイプではなかったけれど(筋肉質のでかい男が好きなのだ)、感じのいい人だと思った。それに、指がきれいだった。重いものを持ったことのない、ピアノを弾くような指に見えた。私たちはかわりばんこに料理をとりにいき、しゃがみこんだままそれを半分ずつ食べた。ミートローフ、ほうれん草のキッシュ、ザワークラウトにいろんな種類のチーズ。ワインを一本空けてしまって、ふたりで背をまるめ、もう一本くすねにいった。
あんたたち、そんなところでしゃがみこんで、不良中学生みたいよ、と葉子が通りがけに声をかけていった。私たちは顔を見合わせて笑った。
ねえ、ふたりでべつのところにいって飲みなおす? 十二時を過ぎてマモちゃんが言った。覚えている。そのときのマモちゃんの、笑いをおさえたような顔も、ふたりのあいだの親密な空気も。
テルちゃんの友達、ここに友達がいっぱいいるみたいだし。きっとテルちゃんが帰っても平気だよ。
離れた場所で見知らぬ男と談笑している葉子を指してマモちゃんは言った。
そうだね。じゃあ、抜け出しちゃおう。
私は言って、それで、葉子の友達のアパートを出、昔からの知り合いだったみたいに手をつないで、しずまりかえった路地を歩き、途中にあったバーであたたかいラムを二杯ずつ飲み、今まで幾度もそうしてきたかのようなキスをして、べつのタクシーに乗ってそれぞれの家に帰った。帰りがたい気持ちなのはたがいにわかった。けれど、十代の少年少女じゃあるまいし、酔いにまかせてこのままどちらかのアパートに直行してしまうのは、やりすぎだと双方が思っている、それも理解できた。
翌朝ひどい二日酔いで目が覚めて、深く安堵した。やりすぎにならなくてよかった。調子にのらなくてよかった。
知らない人の家で知らない人ともりあがって、酒のいきおいで手をつないだりキスをしたり、そんなこと、よくあるのだ。とくに恋愛がうまくいっていないときなんかには。あの子、ひとつ年下の、田中守という平凡な名前の、指のきれいな男の子と、もう会うこともないんだろう、と、そのときは思っていた。
けれどそれから一週間もしないうち、田中守は私の会社に電話をかけてきた。食事に誘ってきた。一回映画を観て、三回いっしょに酒を飲み、そのとき私はすでに田中守に恋をしており、引きずっていた恋愛をきっぱり清算した。四回目に食事をしたあとで、田中守のアパートで性交をした。何もかもうまくいくと思った。今度こそはうまくいくと確信した。田中守は結婚もしておらず、恋人はいないと言っていたし、浮気をくりかえすタイプの男には見えなかった。もし五ヶ月前の私たちを百人が見ていたら、おそらく九十七人は、このままふたりは問題もなく交際をはじめるのだろうと思っただろう(残りの三人は悲劇的な悲観主義者か男と恋愛に深い怨恨を持つヒス女、もしくは本物の予言者だろう)。
「山田さんさあ、こないだ食事買ってきてくれてたすかったよ。おれあのとき、マジでふらついちゃってさあ。四十度超す熱なんか、子どものとき以来っすよ。今日はお礼になんでもおごるから、好きなもの注文してよ。っつっても居酒屋だけどさ、メニュウのなかで一番高いものたのんでいいっすよ。焼き蟹でも河豚鍋でも。でも、これマジで河豚かな、あやしくねえ?」
テーブルに並んだ空き皿の上に身を乗りだしてマモちゃんは言う。
「じゃあ焼酎をもう一本たのみたい」私は言う。
「げ、焼酎はパス。食いものにしてよ」
「えー、なんで? なんでもおごってくれるんじゃないの」
「だって酒飲むとさあ、山田さんぐずって帰らないんだもん」
マモちゃんは何気なく言って笑い、私も合わせて笑ってみるが、帰れと言われているようで深く傷つく。店員を呼び、できるだけ陽気な声で私は注文をしていく。
「焼きタラバ、牛ヒレポン酢ソース、からすみ、あと鮑ステーキお願いしまーす」
「げ、そんなにたのむ? 鮑ってなんだよ鮑って」
交際ははじまらなかった。どうしてなのかよくわからないが、私は未だに田中守の恋人ではない。めし食おうと、気まぐれに電話をよこすのはマモちゃんだけで、私から連絡をしてマモちゃんに会ったことは一度もない。三日か四日に一度のその連絡も、深夜近くのことが多く、いけないと何回か続けて私がことわれば、たぶんそれきりになるだろう。ローテーション。
(このつづきは本編でお楽しみください)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
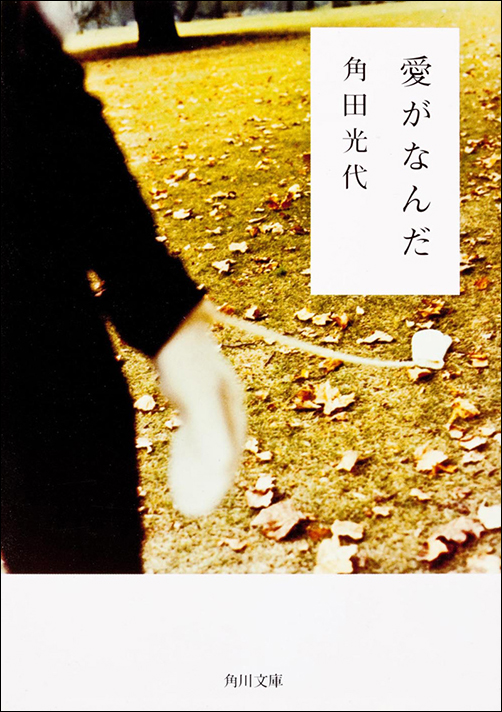
■『愛がなんだ』
角田 光代・著 / 角川書店装丁室・デザイン
直木賞作家が描く、<全力疾走>片思い小説!
OLのテルコはマモちゃんにベタ惚れだ。彼から電話があれば仕事中に長電話、デートとなれば即退社。全てがマモちゃん最優先で会社もクビ寸前。濃密な筆致で綴られる、全力疾走片思い小説。
https://www.kadokawa.co.jp/product/200501000062/
>>映画『愛がなんだ』公式サイト
関連書籍

書籍週間ランキング
熟柿
2026年3月2日 - 2026年3月8日 紀伊國屋書店調べ
アクセスランキング
新着コンテンツ
-
試し読み
-
特集
-
試し読み
-
特集
-
試し読み
-
特集
-
レビュー
-
試し読み
-
試し読み
-
試し読み

























