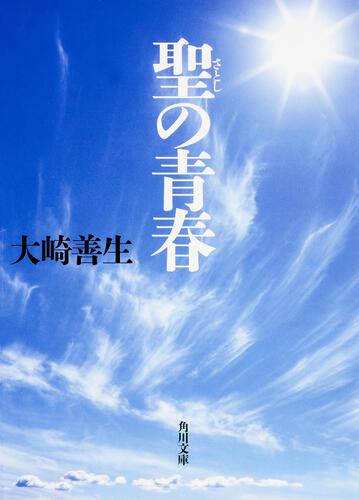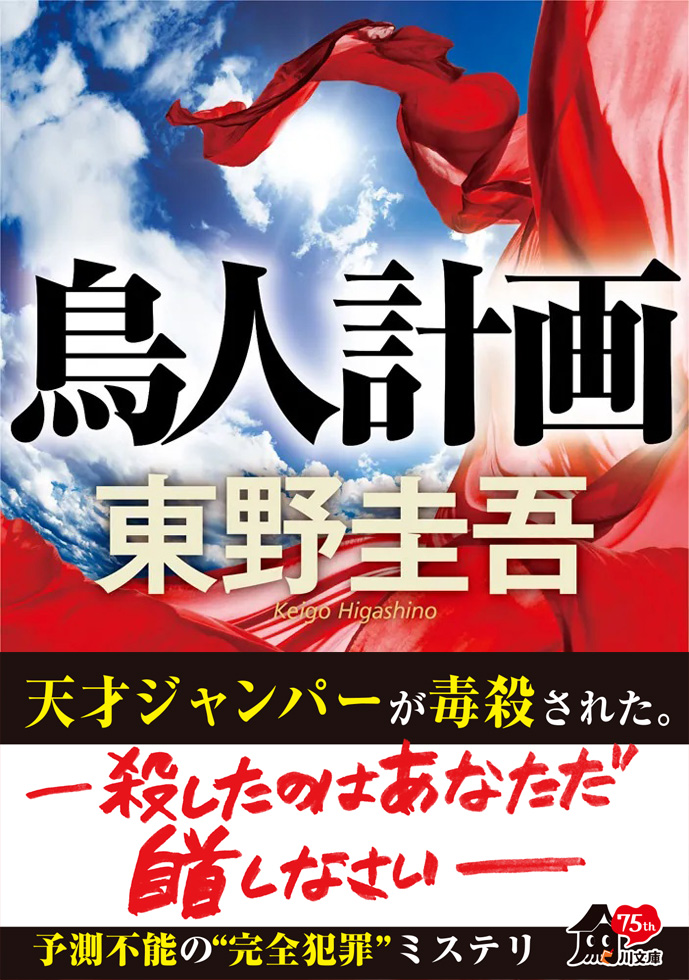小学3年の終わりの3月、聖は
最初はなかなか勝てなかったが、すぐにいい勝負をするようになった。聖の相手をしている大人の顔色がみるみる変わっていった。自分が苦戦しているからではない。実戦らしい実戦をほとんど指したことがないたった9歳の子供が、すさまじいまでの読みを繰りひろげることに驚いたからだ。
自分は三段である。三段といえばアマチュアのトップクラスであり、9歳の子供とは飛車角に桂香を落としたって普通は負けないはずだ。
しかし、いま現実に
この子は天才だ。本当はそう
ただ毎日6時間、本を読んでいただけである。日常の将棋の相手はほとんどが療養所の子供たちで
しかし、聖にしてみれば何回か勝ったことよりも負けたことのほうが納得がいかなかった。療養所に帰り一人ベッドの上で、
もっともっと強くなりたい。そう心の中で強く念じた。
もっともっと強くなって、名人になりたい。
そう思った瞬間、聖の胸はわけもなく熱くなった。名人という言葉が
名人になりたい。
聖は心の中でもう一度そっとそう
ベッドの上にあぐらをかき聖は「将棋世界」を取りだした。強くなるにはまた毎日何時間でも勉強をするしかない。何千題も詰将棋を解くしかない。そう考えるといてもたってもいられなくなったのだ。寝静まった病室で聖は月の明かりだけをたよりに詰将棋に立ち向かった。
今度家に帰るまでにもっと強くなって、そして必ず大人たちに勝ってみせる。
聖の胸はそれまでにない高揚感と希望に満ちあふれていた。強い人間の存在を知ることにより、将棋の奥深さと面白さに改めて気づかされたのである。
ただやみくもに本を読みあさっていたいままでとは違い、大人たちに勝つという具体的な目標ができたことが聖の胸をますます膨らませた。消灯後の寝静まった病室での将棋の勉強は聖の日課となっていった。
揺籃期を終えた聖がその才能を開花させるのには、そんなに時間は必要としなかった。次に帰ったときには前回の相手を破り、そして近所のもっと強い大人を
その相手に敗れても、次の外泊のときにはやっつけてしまう。
そんなことを繰りかえしているうちにいつの間にか近所には相手がいなくなってしまっていた。三、四段ではなかなか聖に勝てないのである。そして、ここにいってみたらいいと紹介されたのが、広島市内の中島公園の近くにある
昭和54年7月、10歳になったばかりの聖はこうして篠崎教室の門を叩いたのである。
腕だめし
篠崎
月に3回の外出日は必ず教室で将棋の
「これは、絶対に強くなる将棋じゃ」と篠崎は伸一に
負かされたある強豪は伸一に向かってこう
聖は篠崎からアマ四段の認定を受ける。小学4年生のアマ四段も驚きならば、はじめて認定された段が四段というのも聞いたことがない。そして何といっても、最大の驚きはまったく将棋を知らなかった超初心者が、本を読んだだけでこれだけの棋力を身につけてしまったという事実である。
昭和55年、11歳になった聖は第14回中国こども名人戦に参加して優勝する。そして、その優勝は第18回まで連続して5回つづくことになる。中国地区の子供の大会では聖の力は抜きんでていてもはや競争相手はどこにもいなかった。
聖の篠崎教室通いはそう長くはつづかなかった。
「ここにいても強くなれん」と突然に聖が伸一に言い出したのである。
聖にとっては月にたった3日しかない貴重な外出日である。そのわずかな時間を最大限に有効に使いたいという聖の気持ちは伸一にはよくわかった。問題は教室にはもう聖の目標になるような強いアマチュアがいなくなっていること。そして教室にくる子供相手に、聖のほうが駒を落として対局させられるというような機会が増えたことなどであった。
「もうあそこじゃ勉強にならん」
聖は強く伸一にそう
どうしたもんかと困り果てている伸一に会社の
広島将棋センターは
しかも、聖が通いはじめたころは、田尻を中心とする学生の強豪が
朝、早くに家を出て1時間かけて聖を原療養所に迎えにいき、そして広島市内に戻り将棋センターに連れていく。そこで午前中から夜まで聖は何番も将棋を指す。その間、伸一は道場の片隅で何をするでもなく、へたりこんで息子の対局が終わるのを待ちつづけていた。
羽生善治も同じころ、毎週日曜日に八王子将棋センターに通いつめていた。母親と妹と三人で朝早くに家を出て、善治は道場へ、母と
昭和56年。小学5年の3月、伸一につきそわれて聖は生まれてはじめて東京にいく。全国小学生将棋名人戦に参加するためにである。
土曜日に出て日曜日に帰れば、普通の外泊許可で東京へいくことができた。
広島から新幹線に乗り、6時間かけて東京に着いた二人は
将棋会館にずいぶんと早くたどり着いた聖は、そこにいあわせた同じ年くらいのお下げの女の子と将棋を指した。
広島では県代表とも互角に戦うほどの実力をつけていた聖だったから、同じ年の女の子なんかに負けるわけはないと思った。しかし、聖は
小学生名人戦といえばプロ棋士への
聖の相手をした女の子は後に女流名人となる
「やっぱり東京はすごいもんじゃ」
広島では大人たちも相手にならないほどに強くなった聖を苦しめる女の子を見て、伸一は驚きを隠せなかった。しかも聖は小学生名人戦で
聖を本戦トーナメントで破ったのは後に名人となる佐藤康光。しかしその佐藤もそして1歳年下で小学5年で参加していた羽生善治ですらも、その大会では優勝することはできなかった。
昭和57年、将棋界は一大
名人戦9
その出現はさまざまな意味で革命的であり、先人たちが築き上げた数々の常識をいともたやすく
とうてい無理と思われた攻めを決然と
たった一人の天才の出現により将棋界が受けの時代から攻めの時代へと転換していったのである。谷川の
谷川の出現はファンにも強い
わずか21歳の青年名人の誕生である。
その天才谷川浩司ですら加藤玉に詰みを発見した瞬間、とめどもない
終盤の詰めの決め手となった7五銀。駒台から放たれたその銀を谷川は真っすぐに盤上に置こうとしたが、手が震えてどうしても
谷川浩司という若き天才の出現により、将棋の考えかたという盤上のできごとにとどまらない大きな変化が確実に起きつつあった。
全国の子供たちがヒーロー谷川の姿に憧れ将棋を指しはじめたのである。子供たちの間で将棋は大ブームとなる。そしてその結果、底辺の広がりと必然的な競争の激化が生まれてくる。
昭和57年、後の将棋界の勢力図をそっくりと