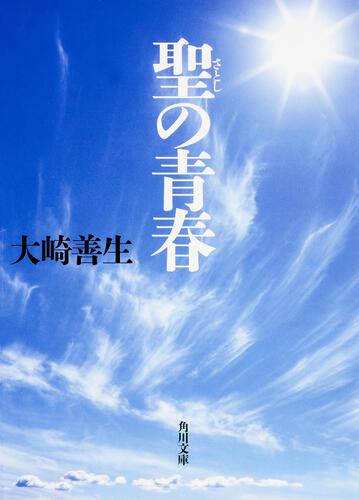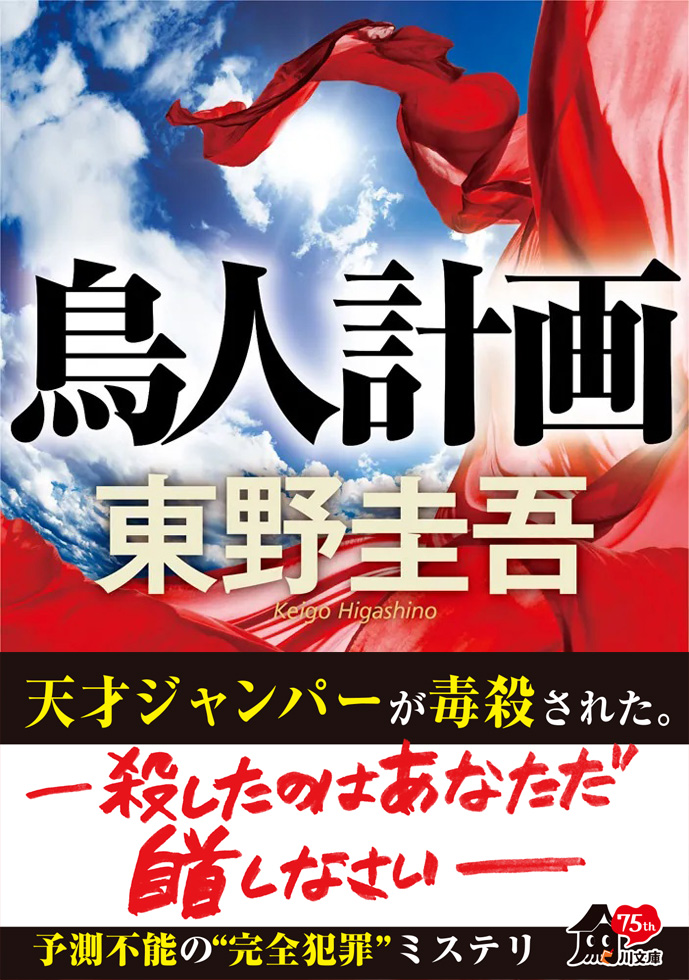第一章 折れない翼
発病
昭和44年6月15日午後1時15分、広島大学付属病院で村山聖は誕生した。父伸一、母トミコにとって長男祐司、長女緑につづく3人目の子供だった。
臨月の診断でトミコはレントゲン写真を医者から見せられた。そこには胎児の大きな頭が骨盤につかえるようすがはっきりと映し出されていた。
「帝王切開になるかもしれません」とトミコは医者に念を押される。体重30キロ台の母親の華奢な体には通常分娩はぎりぎりの線だった。
しかも、トミコには肝臓の持病があった。原爆の後遺症である。投下当日、12歳のトミコは広島県北の田舎に集団疎開をしていたために、最悪の事態は免れた。しかし、その後広島市内に戻りそこで被曝する。広範囲に広がった放射能の見えない手が確実に少女の体を蝕んでいたのだった。後遺症は主に肝機能障害という形で現れ、その後のトミコの人生はそれとの闘いの日々でもあった。
帝王切開という医者の勧めにトミコはついに首を縦に振らなかった。うめき声を上げながらも頑なに自分の意志を貫き通す母の姿にやがて医師も決意を固めざるを得なくなった。
精神と肉体の限界すれすれの苦痛が何時間もトミコを襲った。しかし、トミコは医師も驚くような強<外字>な精神力でがんばりぬいたのである。
母と子の長い長い闘いがやっと終止符を打ったのは午後1時過ぎのこと。産気づいてから10時間がすぎようとしていた。
「男の子ですよ」という看護婦の声がトミコの朦朧とする意識の片隅に響いた。
一呼吸おいて、赤ん坊は母を励ますかのように元気な産声を上げた。3500グラムという母を苦しめた数字は、生まれてしまえばもう母の誇りへと変わっていたのだった。
広島の梅雨は瀬戸内海からの湿り気を帯びた海風の影響でひときわ湿気がひどく、まるでやむことを忘れたかのようにいつまでも雨が降りつづく。
6月の木々の緑はそんな陰雨に濡れていた。
次男誕生の知らせを伸一は広島市内にある会社で聞いた。昼食を終え、自分のデスクでぼんやりと雨の唄を聞いているときだった。
昭和11年に大阪で生まれた伸一は、その後父親の仕事の関係で広島に引っ越す。そして広島県立工業高校から広島大学理学部物理学科へと進学し、エンジニアとなった。工業高校から広島大学に進学するのは年に一人かせいぜい二人、高校の授業終了後に補習校に通い、古文や漢文や英語など学校では学べない勉強をしなければならなかった。そんなハンディを伸一は一つ一つこつこつとした努力で克服していった。
大学を卒業し県立の研究所に入所した後、半ば引き抜かれるような形で市内の会社に転職した。そこで、3歳年上のトミコと出会い恋に落ち、そして結婚した。
聖が生まれたころ伸一は人生の絶頂期ともいうべきときを迎えていた。30歳までは勉強と仕事一筋の人生だったが、このころ急に酒の味を知り、麻雀を覚えた。会社の同僚と酒を飲んでは、徹夜で麻雀をし雀荘から出社という日々がつづいていた。はじめて知る遊びのけだるさが伸一には新鮮な喜びに感じられ、そんな生活をしながらも職場では少しも手を抜くことなくバリバリと働く自分を密かに誇りに思っていた。
雨の音を聞きながら、伸一は生まれてきたばかりの次男の名前を考えていた。今日も徹夜明けだが、頭はしゃっきりしている。
聖徳太子の中から一文字いただこうか、ふとそうひらめいた。
職場や雀荘で「わしの記憶力は聖徳太子のようなもんじゃい」といつも部下たちをからかったり威張ったりしていた。そのことを不意に思い出したのである。その中でも、聖という文字の美しさに伸一は惹かれた。形といい雰囲気といい、実にきれいな文字だと思った。机の上のメモ用紙に「村山聖、村山聖」といくつも書いてみる。何とも流麗ないい座りであると伸一は一人納得した。
しかし、キヨシとかヒジリとかいう読みかたはどうもピンとこない。
「どうしたもんじゃろう」
窓外に広がる6月の緑を眺めながら伸一は腕を組み煙草をくゆらせ、考えあぐねていた。
しばらくそうしているうちに漢和辞典で読みかたを徹底的に調べ上げてみたらどうだろうかというアイディアが浮かんだ。何か見つかるかもしれない。
伸一はデスクの漢和辞典を無我夢中で繰った。そして、聖と書いてサトシと読むことを知った。
これだ、と伸一は心の中で快哉を上げた。「むらやまさとし、むらやまさとし」と今度は何度も声に出してみる。いい響きだなと伸一は思った。
6月の雨のように迷う必要は何もなかった。
村山聖が生まれた昭和44年はアポロ11号で人類がはじめて月面に降り立った年である。
日本国内では東大紛争が激化し、安田講堂事件へと発展していった。のちの浅間山荘事件につながる赤軍派の暴走が表面化し、若者を中心とする左翼運動が大きな壁にぶつかった年でもある。
日本は急激な経済成長下にあった。
そのことを謳歌し、またある部分ではそのことにとまどっていた時代といえるのかもしれない。
広島の街も空前の好景気に沸いていた。
マツダの車が爆発的な売れ行きを示し、トヨタ、日産に次ぐ3番手にのし上がっていた。マツダには勢いがあり次々と設備投資の手を広げ、それが広島県全体に活気と富をもたらしていた。
100年は草木も生えないといわれた原爆投下の日から20年以上の月日がすぎ、広島の街は復興という言葉と現実に溢れかえっていた。
そんな活気ある広島の安芸郡府中町で聖はすくすくと成長を遂げていった。
夜泣きもせず、お乳はぐいぐいと飲んだ。腹を下すことも、熱を出すこともなく健康そのものだった。まったく手のかからない、親にとってはこれ以上ないくらいに愛らしい赤ん坊だった。
歩けるようになると、いつも近所の友達の家で遊ぶようになった。人見知りもせず、誰にでも愛嬌よくふるまい、また誰からも好かれる子供だった。
聖が2歳のときに伸一は家を買った。それまで住んでいた磯部アパートという、板金工場の2階にあった共同住宅では親子5人が暮らすには手狭すぎたからである。
新居は府中町の桜ケ丘という新興住宅地に新築した一軒家だった。小さな山に這うように広がる、日本国内どこにでもあるような住宅地で、村山家はそのてっぺん近くにあった。
3歳になるころには、祐司は聖をどこにでも引っ張り回すようになる。野に山に川に、兄弟は風のように駆け回った。
幼少時の聖がほかの子供と変わったところがあったとすれば、それは集中力である。一度何かに集中するとすさまじい力を発揮した。
大人でもふうふういうような山を登ることができたのも、兄の背中についていくというその一点に集中していたからである。聖にとってそれは登山ではなく、兄から離れないという作業だった。
じっとしておれ、と伸一が頼むと何十分でもじーっとしていた。それは静かにすることに集中してしまった結果であった。
「鯉をつかまえるんじゃ」と言って池に飛びこんでしまったこともあった。中腰で水につかったまま、1時間以上も聖は手で鯉を探りつづけるのだった。
聖が眠るときにトミコはいつも童話を読んで聞かせてやった。「りゅうの目になみだ」や「ごんぎつね」などである。聖は物語が好きで、何も言わずに聞き入っていた。あまりにも悲しい話で、読み手のトミコがつい泣き出すと、聖も一緒になって泣き出してしまうのだった。
トミコはそんな聖がいとおしくてたまらなかった。こんな母と子の幸せな時間がいつまでもつづくことを密かに祈らずにはいられなかった。
こうして両親と二人の兄姉の愛に囲まれて、聖は平凡ではあるが幸せな幼年期をすごした。
しかし、それはあまりにも短い期間だった。3歳の初夏、茶臼山から下山したその日に聖の平穏な日々は突然に終焉を迎える。
生まれてはじめてまむしに遭遇した夜、烈しい高熱が聖を襲った。仕事から帰った伸一を待っていたのはうんうんとうなり声を上げる息子の姿だった。額に手を当てると、火にかけたやかんのように熱い。とりあえず、家に買い置いてある市販の解熱剤を飲ませることにする。しばらくすると、熱は引くのだがすぐにまたそれ以上の猛威でぶりかえすのである。
朝を待ち、近所の医者に駆けこんだ。
風邪という診断だった。しばらくは医者に通いやがて風邪は完治した。
それからはまたいつもの元気な聖が戻ってくるはずだった。しかし、どうもようすがおかしい。あんなに元気だった聖がしょっちゅう熱を出すようになっていた。そのたびに医者に連れていくのだが、医者の診断はいつも判で押したように風邪だった。
熱を出しては医者にいき、風邪薬をもらって帰ってくるということが何度かつづいた。その間も無理をして聖は保育所へ通い、近所の子供たちと遊んだ。しかし、3歳の夏、山に登り高熱を出す前の聖とはどこかが違っていた。
体の奥底から発散するような健康な輝きはかげりを見せていた。元気といえば元気なのだがしかし、いつもどこかけだるそうで、何かをかばっているように見えた。
昭和49年の6月、5歳の誕生日を迎えたばかりの聖は、ひときわひどい高熱に襲われた。
はしかだった。しかし、それもほどなく完治した。ところが、治った後もどこかようすがおかしい。生まれてからただの一度も病気らしい病気もせずにすくすくと育ってきたこと、一瞬もじっとしていない4歳までの活発な印象が思わぬ油断を生み、陥穽となって待ち受けていたのである。
初夏のある日、仕事から帰宅した伸一は聖の顔を見て背筋に戦慄が走る思いをする。
見慣れているはずの聖の顔の形が違っているように見えたのだ。伸一は確かめるために聖を目の前に立たせてみた。そしてさらに愕然とする。違っているように見えたのではなくて明らかに違っていたからである。
熱のせいか薬のせいか、聖の顔は風船玉のように膨れ上がってしまっていた。
「しまった」と伸一は心の中で舌打ちをした。聖の再三にわたる発熱を、わが子が送る危険信号を甘く見てしまっていたことにいまさらながらに気がついたのだ。約1年間、子供の発するサインを看過してしまっていたのである。
翌日、トミコは聖の手を引いて広島市民病院へと向かった。わが子の顔を見ればもう、風邪薬しか処方しない町医者にいく気にはなれなかった。そこでトミコは思わぬ病名を聞かされることになる。
「お母さん、これは大変ですよ」
検尿と簡単な診察を終えた後、白衣をまとった若い小児科医は顔色ひとつ変えずに言った。
「ネフローゼです」
そして、独り言のようにつづけた。
「お母さん、大変な病気にさせてしまいましたねえ」
そうか、とそのときトミコは思った。この若い医者は私に向かってこう言っている。母親であるあなたがこの子をこの病気にさせたのですよ。子供が病気になったのではなくて、親であるあなたがそうさせたのですよと。
この言葉をトミコは胸に深く刻みこんだ。そして、一生忘れないでおこうと決心した。
家に帰りトミコは伸一に聖の病名を報告した。それは、伸一にとってもはじめて耳にする病名だった。
伸一は自分の迂闊さを悔いた。聖の元気さを過信していた自分。風邪と高をくくり尿検査もしてくれない町医者に頼りきっていた自分。その夜、伸一は寝床の中で悶々と自分を責めつづけた。
「あっちこっちいっておれば、医者の見立ても違っていたじゃろうに……」
こうして父は父、母は母、兄は兄で、聖の病気に対する後悔と責任の思いがそれぞれの胸の奥深くに根を張り巡らせることになる。そして誰もが眠れない夜をすごす。
昭和49年7月、村山聖5歳。
広島のある長い夏の夜のことである。