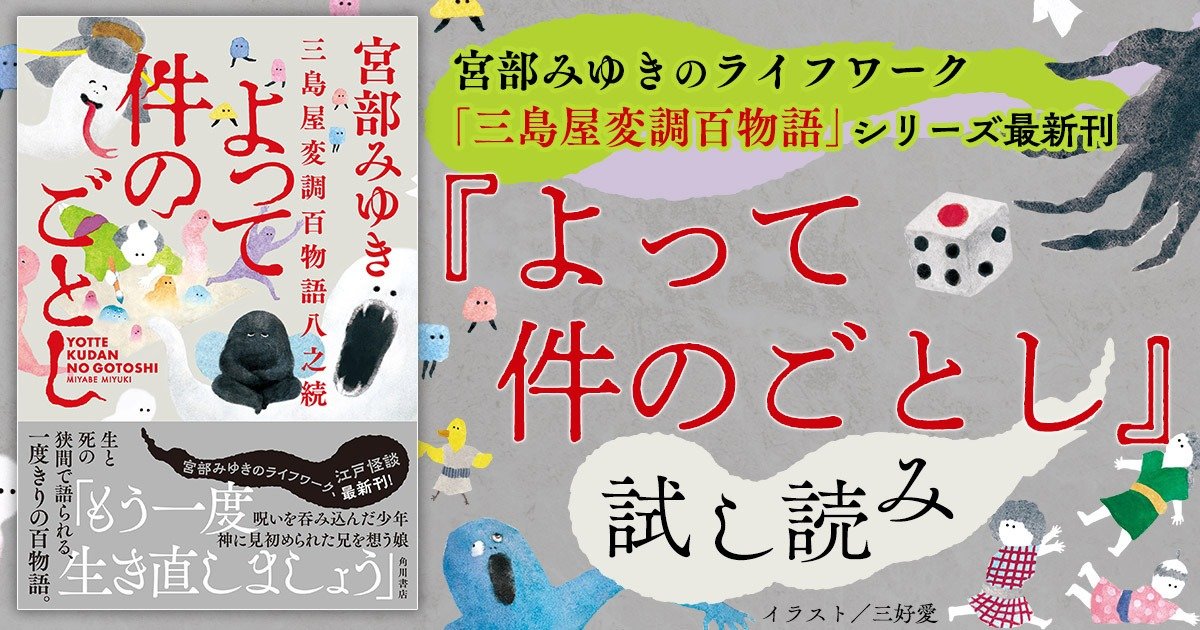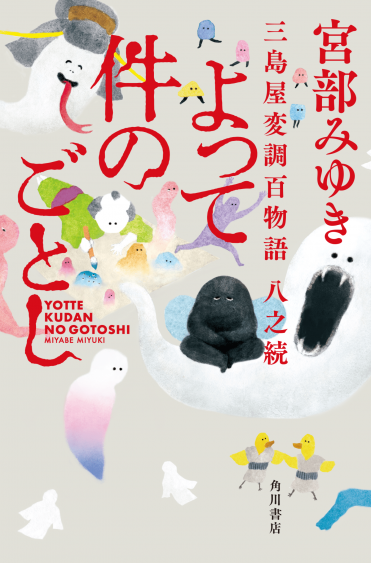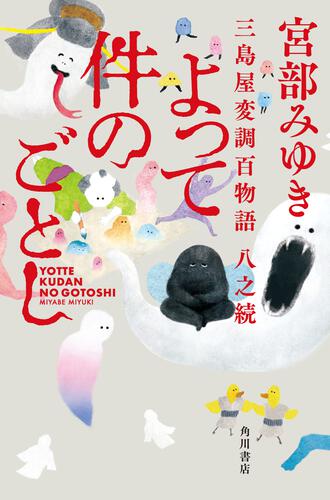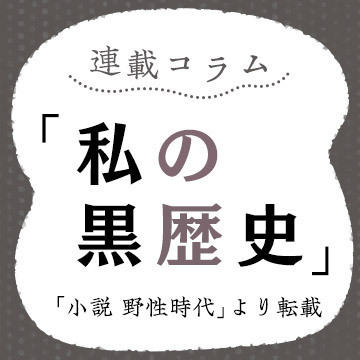子供ながらに腹を決め、己を鼓舞して顔を上げたそのときの胸の内を語る、黒白の間の餅太郎。
富次郎にはまだ彼の歳の見当がつかない。うつむき加減でぼそぼそ語っているときは老けて見えるし、たった今はまさに十一の男の子のような瞳の輝きだ。わからなすぎて、不気味なものも感じてしまう。
「結局、あっしはその一角にある小屋をねぐらにすることになりました」
近くには古井戸もあり、汲み上げてみると、驚くほど冷たく清らかな水だった。
「水を見た途端に、ものすごく喉が渇いてきましてね。
喉の渇きを覚え、水がうまいと感じる。生きているしるしだ。それなら、
「朝、起き抜けに虻に掠われて、それっきりだったわけでしょう。腹は減っていませんでしたか」
富次郎の問いかけに、餅太郎は大きくうなずいた。
「ええ、腹が減って減りすぎて、ふらふらするほどだったんですがね。それも、井戸水を見るまでは忘れっちまってた」
口の端が引き
─十一のときに、笑い方を忘れました。
「水はある。じゃあ食いものはどうなんだと思うでしょう?」
山ほどあったのだ、と言う。
「あっしが連れて行かれたあの里……もう、はっきり申しますけれども、ろくめん様が造った
八百万の神々が、博打に興じる場所である。「胴元も客もみんな神様なんだ。だからまず、胴元のろくめん様に捧げられる食いものがある。キリ次郎が何て言ってたっけな」
「神饌ですかね。神様が召し上がるお食事」
「ああ、しんせんね」
ろくめん様には、好物の餅と餅菓子。
「それと、博打をしに集まってくる神様方も、それぞれのお手元に捧げられた神饌と、あとお供物をね、持ってくるんです。弁当じゃなくて、何て言えばいいんですかねえ」
「手土産でしょうか」
餅太郎は目をまん丸にした。「それ、そうです、そうです。三島屋さんは、さすがこんな繁華なところでお店を張ってるだけのことはある。言葉を知ってるよね」
手土産ですよ手土産。まん丸な目のまんま、餅太郎は両手をぱあっと広げた。
「この国におわします八百万の神様が、てんでに手土産をぶらさげて、ろくめん様の賭場の里へおいでなさる。そりゃ大変なことですよ」
旨いもの好きで、諸国の名産物や美味評判記などもたくさん読んでいる富次郎には、それがどれほど「大変な」ことなのか、やすやすと想像することができた。
「国じゅうの旨いものと旨い酒が集まってくるということですね!」
勢い込んで応じたものだから、餅太郎がちょっとたじろいだ。
「あいすみません。わたしは食い意地が張ってまして、旨いものには目がないんです」
富次郎が慌てて謝ると、餅太郎の口元が歪んで、目がいっそう細くなった。笑い方を忘れた人の、精一杯の笑いもどきだ。
「三島屋さんはいい人だね」
温かみのある声音でそう言った。
「おっしゃるとおり、神様方が持ってくる手土産は、畑間村と大畑村しか知らなかったあのころのあっしなんぞには、この世のものとは思われないくらい
そのほとんどは、旨かったそうである。普通に食べてご
「人の食いものと
人びとが神様に供するお食事として、神饌にはある程度の決まりがある。砂糖や砂糖菓子、白い餅や白飯、里芋、鯛の尾頭付きなどは、国じゅうどこでも神饌となる食べ物だ。
「そういうものはいいんだ─ってか、いいどころか、あっしはもう竜宮城へ行ったような心地でしたよ。村の暮らしじゃ白い
もう嬉しくて嬉しくて、飯を食っているときだけは、辛くも寂しくも悲しくもなかったそうである。
「だけど、まずあのころのあっしは十一歳の小僧、酒には用がありませんでしたからね」
塗りの
「今となっては罰が当たりそうな話ですよ」
「まったくですねえ」
餅太郎の分まで、富次郎は愉快に笑った。
「それと、諸国の名産品を神饌に仕立てたもののなかには、ちょっと面食らうようなものもあった。あくまでも神様の食べ物であって、人がお下がりを
「たとえば、どんなものでしょう」
餅太郎は目を細めると、
「何だかわかんない木の根っこ。白っぽいのと黒っぽいのとがあってね」
「生薬の素かもしれませんね」
「だったのかねえ。鼻をくっつけて
手のひらほどの大きさで、かちんかちんに乾いている丸いもの。土かと思ったら、ほのかに
「苦くって、えぐくって、一口も呑み込めなかったんだ」
「同じ味噌でも、わたしらが食べる味噌とは
意外な困りものは生魚で、
「毎日入ってくるから、食べきれないうちに傷んじまう。だから干物はありがたかったなあ。大きな
「それだけお
餅太郎が見かけた他の「お化け」たち。互いには白い反物みたいに見えていても、正体はちゃんと人なのだ。少なくとも、本人が人であろうと頑張っているうちは。
「酒好きの男だったならば、毎日白い飯をかっくらってた餅太郎さんと同じように、毎日銘酒をかっくらってたって不思議じゃないですよ」
「ああ、そうだねえ。自分には用がねえもののことだから、気がつかなかっただけかもしれねえ」
餅太郎は懐手をすると、うんうんとうなずいた。
「思い出しましたよ。あっしは丸餅が好きなんだけど、時々きれいに失くなってて、
こうして話に聞くだけならば、微笑ましい。「そういう取り合いが起こるということは、神饌は、どこか決まった場所に集められていたんでしょうか」
思い出にひたっていたらしい餅太郎が、はっとなって富次郎を見た。
「そうだよね、あっしは話が下手くそだ。それを言ってなかった」
お社があったのだそうである。
「八百万の神々が遊ぶ賭場の里に、神社があったわけですね」
「ぶっとい古木でできた鳥居も立っててね。立派だけど、おっそろしく変わってた」
まず、どっちからどう見ても常に社殿の正面しか見えなかった、という。
「は?」富次郎には意味がわからない。「そんな建物はあり得ないでしょう」
「あの里ではあり得たんですよ。あっしは毎日通ったからね。社殿のなかに、神饌が集められている大広間があったからさ」
鳥居も、どっからどう見ても社殿の正面に立っている。横から見える場所がない。
「で、くぐってから振り返ると、すごく遠くにあるんですよ」
二、三歩歩いてその下をくぐったばかりなのに、振り返ったら鳥居は半丁(一丁は約一〇九メートル)も遠ざかっている。ぐわん、と
「お社も似たような感じがあって、玉砂利を踏んで歩いていっても、なかなか近づかねえんだよね。で、ふっと息を吐いたりまばたきしたりすると、いきなり目の前に迫ってる」
社殿の正面にはしめ縄が渡されていたが、餅太郎が村の鎮守、ろくめん様のお社で見てきたような渡し方ではなかった。
「裏返しなんですよ。そうとしか言いようがないんだけど、向きが反対なんだよね」
さらに、しめ縄のあいだに挟み込まれている
「まっとうな、
神々が羽目を外して遊ぶ賭場の里にあるお社が、他の神聖なお社とそっくりそのまま同じ造りになっていては、何だか許されないような気もする。
「そうだねえ。実際、なかに入ると、神社じゃなくて
お社のなかには広間がいくつもあって、部屋ごとに様々な供物が積み上げられていたのだという。いちばん広いのは神饌の間、その次に広い衣類の間、ごちゃごちゃしている道具類の間、生け
「い、生け贄というのは?」
「しめたばっかりの鶏や、大きな
ああ、よかった。人ではないのだ。
「三島屋さん、今ほっとなさったでしょ」
「はい。肝っ玉が小さくてお恥ずかしい」
「いや、いや。あっしもあの里で、初めて生け贄の間に踏み込んだとき、同じようにほっとしたんですよ。人がしめられて、ぶら下げられてなくってよかったって」
バカだよね─と、口元を歪める。
「とっくのとうに、自分が生け贄になってるのにさ」
生け贄の間には、いつも獣の血の臭いが漂っていた。大型の魚は
「
いや、ただ心細く、寂しかったのだろう。どれほど親しく寄り添ってくれても、キリ次郎は生きものではない。十一歳の餅太郎は、生きものが恋しかったのだろう。
「お社のなかでは、他の人に出会うことはなかったわけですね」
今ごろになって、丸餅を取りあっていたことに思い至るくらいだ。誰にも会えなかったのだろう。
「うん。それはやっぱり……たまたま出くわしたり、見かけちゃったりすることは勘弁してもらえても、人と人とが寄り添うのは、あそこでは
だって、みんな
「仲良くなって励まし合って、男と女だったら恋仲になっちゃったりしたら、罰にならねえでしょ」
「互いに、お化けのような姿に見えても、仲良くなったり恋をしたりできますかね?」
問いかけた富次郎を、餅太郎はじっと見つめ返してきた。怖いような凝視に、富次郎は座り直した。
「すみません、何か気に障ることを申し上げてしまいましたか」
餅太郎は黙って首を左右に振った。二度、三度と念入りに。
「こっちこそ、あいすみません。あっしがちゃんと笑えるなら、笑いながら言い返せばいいだけのことなんだけど」
笑みという表情を一つ失っただけで、人はこんなに不便になるのだ。
「そんなことをおっしゃる三島屋さんは、まだホントにほんとの独りぼっちになったことがおありじゃないんだねって思ったんだ」
胸をとんと打たれたように、富次郎は感じ入った。
「ああ、おっしゃるとおりです。わかったようなことを口にして、ごめんなさい」
富次郎は頭を下げた。餅太郎はうつむいて鼻をこすり、えへへ、と声を出した。
「今ので、笑ったことにしてやっておくんなさい」
「心得ました。ついでに、新しい茶と羊羹で一息入れましょう」
餅太郎も茶菓に手を伸ばしてくれた。ひととき飲み食いしながらのやりとりで、
「国じゅうの神饌が集まってたはずのあの里でも、羊羹にお目にかかったことはなかったなあ」
「菓子類は、どんなものがありましたか」
「
「その土地へ行けば、その形にする意味がわかるんでしょうね」
「そうそう。あとはね、赤飯ですよ。赤まんま。三島屋さんじゃ、餅米に小豆を混ぜて炊いて、ごま塩をかけて食べるでしょ」
「ええ。ほかの赤飯があるんでしょうか」
「あるんですよ。甘いんだ。小豆を甘く煮てから炊くんだよね。あれ、どこのお国のお供物だったのかなあ」
神饌は捧げ物だから、たいていは三方に載せられている。三方の上には半紙や笹の葉などの葉っぱが敷いてあることが多いのだが、
「昆布が敷いてあるのを見つけたときには、びっくりしましたよ」
三方ではなく、絵付きの大皿や素焼きの鉢、
「何よりも珍しかったのは
「筏? 丸太を組んだ、あの筏ですか」
「さすがに、そこまででっかくはありませんよ。半畳ぐらいの大きさかな」
その上に生米と小豆、大きな伸し餅に、干した果物と砂糖菓子、酒と味噌の瓶、大小の生魚が一匹ずつと、絹糸の束と木綿の反物が並べられていたのだそうだ。
「きっと、豊かな土地の捧げ物だったんでしょうね」
「そうだよねえ。大畑村の鎮守のお社にだって、あんな山のようなお供物があったためしはなかったから、ガキなりに、うちのろくめん様は
旨いもの好きとしては、食べ物の話はずうっと聞いていても飽きないが、他の広間にあった供物のことも気になってしょうがない。
「衣類の間には、神様に捧げられたお着物が集められていたわけですよね」
がぶりとほうじ茶を飲み干して、餅太郎はうなずいた。
「小袖、羽織、帯、足袋、浴衣もあれば、
神様の、おふんどし。
「腰巻きもありましたよ」
「ってことは、女の神様が博打をしに来ていたと?」
「息抜きにね」
下帯や腰巻きとなると、神々の手土産というよりは、
「道具類にはどんなものがありました?」
「およそ人の世にあるものは、ほとんどみんなありましたよ」
人は、人の世にあるものほとんど全てを神々に捧げて、平穏な暮らしを祈るのだ。
「あれは髪結いの神様のだったのかなあ。かもじがわんさと積んであって、パッと見には気持ちが悪かった」
髪結いさんを守護する髪結いの神様に、富次郎は何の文句をつけるつもりもないけれど、
「かもじは、手土産になってるかどうか怪しいですねえ」
「広げると、広間いっぱいになりそうな、でっかい網。縁に重しがついてて」
「あ、それはたぶん地引き網漁の網ですね」
「あのころのあっしの背丈ぐらいありそうな、でっかい木べら」
「大きな
「三島屋さん、やっぱり物知りだねえ!」
絵馬の間には、当然のことながら絵馬ばっかり。まっさらの何も記してない絵馬だから、いつも木の香がしたそうである。
「ろくめん様の絵馬は、本社のでも分社のでもみんな同じで、六角形なんですよ」
筋が通っている。
「六角形なんてさ、ろくめん様のだけだろうと思ってたんだけど、この国は広いから、あるところにはあるんだよね。六角も五角も、三角のもあった」
賭場の里に遊びにくる神々にとっては、自分の社の絵馬は、一種の通行手形だったのではあるまいか。我はこうして衆生に拝まれている神であるぞという
思いつきだが、富次郎がそう言ってみると、餅太郎はまたぞろ目をまん丸にした。
「三島屋さん、すごいねえ」
そうだよそうだよ、そうですよ! 手をぱんぱん打って、ぶんぶんうなずく。
「あのころ、あっしはそんなことまで頭のまわるガキじゃなかったからね。でも、キリ次郎に訊いてみたことがあったんだ」
─なあ、この里には、悪い神様が寄りつくことはねえの?
「悪い神様が、博打したさに入り込んできたらおっかないと思ったからね」
すると、キリ次郎はこう答えた。
─神様に、善い悪いはごじゃらん。
人に有り難がられているから善い神で、怖れられているから悪い神ではない。神々に、人の物差しで測る善悪はあてはまらない。
「ただ、
「……なるほど」
居候の虻の神も、餅太郎の故郷では拝まれていた。愚かだから、人の悪しき願いをかなえてしまうけれど、じゃあ悪神なのか? 人の側がそんな線引きをしていいのか。
富次郎はゆっくりとうなずいた。
「一種の通行手形だったのは、絵馬に限らないんですね。神々の手土産は全て、誰かに拝まれていることの証だ。そういう意味があるから、賭場の里を訪れる神々はかもじでも下帯でも持参されるし、ろくめん様もお受け取りになり、広間に納めておかれたんでしょう」
それらの品を見渡しては目を白黒させている十一歳の餅太郎の姿を思い浮かべると、富次郎は自然と微笑んでしまう。
「そっかぁ、う~ん」
餅太郎は腕組みをすると、遠いところを見やるような
「あの里にいたころは、そんなふうに思いもしなかったなあ」
けっこう忙しかったし。
「広間にある食いもののおかげで飢えることはなかったけど、毎日掃除が大変でね。傷んだものは捨てなきゃならないし」
「そういうお務めを、下僕である賽子の皆さんと一緒にやっていたんですね」
賽子の皆さんという言い方でよろしいか。
「ろくめん様の下僕は賽子だけですからね。ただ、さっき言ったでしょ、人形の間って」
その人形とは「ひとがた」、紙を折ったり切ったりして作られた紙人形だった。
「あれだけは、ずうっと同じ形のやつしか見当たらなかった。丈が二寸ぐらいだったかねえ。目鼻もついてなくて、真っ白な折り紙のお人形でしたけど」
それらが、下僕である賽子たちの手下になって、よく働いたのだという。
─にんぎょうども~、起きよ~。
「毎朝、キリ次郎が大声で呼ばわると、人形がひらひらって起き上がってくるんですよ。で、あとをくっついてくる」
そうして仕事に励み、一日のお務めが終わるころには、人形どもは汚れて破れてよれよれになって、
「日が暮れると
その正体は何なのだ。人の形をしていることを踏まえると、富次郎は、つい怖い方へ想像してしまう。
「正体は……ねえ」餅太郎はつと目を細めた。
「先に言っちまうと面白くないから、おいおい語りましょう。確かにヘンテコで、あっしもすぐには
「こいつらさぁ、働き者なのはよくわかってんだけど」
道の両脇にずらりと並んでいる石灯籠を、紙人形たちが浄めている。一晩じゅう油を灯していてこびりついた
「おいら、ちょっと気味が
「そんなら、突っ立って見ておらず、穢れ水を打ってきておくんなしゃい」
「そっちはもっと嫌だ」
「働かぬ餅太郎しゃんには、今朝、広間から持ってきた丸餅をあげましぇん」
お天道様の姿はいつもおぼろにかすんでいるものの、賭場の里にも朝昼晩はある。今はちょうどお
餅太郎がこの里に連れて来られて、今日で五日目。
─まだまだ、里の真ん中には近づいちゃいけましぇん。
餅太郎のやれることといったら道の掃除とごみ拾い、賽子と人形たちが拭き掃除をするための水汲み(これがもう果てしなく何回も汲んでは運び汲んでは運ぶ)、それが済んだら
天水桶の穢れ水は、いっぺん空にしても、翌日には縁まで一杯に満ちている。キリ次郎の口真似をするならば、人の穢れの尽きることはごじゃりません。
「じゃあ、水を汲み替えてくるさ」
よっこらしょと手桶を左右に提げて、水場へと引き返す。
餅太郎の住処のそばにある井戸とは違い、牛馬をつなぐ柵の隣にある水場は、広さが畳一枚ぐらい、深さは餅太郎の膝丈ぐらいで、まわりは石で固められているところに、きれいな水が溜まっている。水を引き込んでいる
ざぶん! 空っぽの手桶を水場に入れて、水を汲む。あたりは静かで、鳥の声も虫の声もしない。この里では風も吹かないから、森の木立が鳴ることもない。
ざぶん! 水飛沫がきらきら光る。まるっきり当たり前のようにきれいだ。
水場の縁の石の上に手をかけて、餅太郎はしゃがみ込んだ。四角い
─今朝は団子にありつけた。
神饌の間にきび団子があったのだ。いったい、何串食べただろう。きびのいい香りがして、甘くって旨かった。
笑ってみよう。嬉しかったんだ。笑えねえはずがない。
四角い水面の揺れが止まった。しかし、そこに映る餅太郎の顔は歪んだまんまだ。
笑おうとしているのに、目元が上下するだけ。小鼻が開いたり閉じたりするだけ。口元がへの字になったり戻ったり、ほっぺたが引き攣ったりするばっかり。こんな歪んだ表情になってしまう。
駄目だ。今は無理なんだ。もうちっとこの里に慣れたなら、大きな虻に捕まる夢を見なくなったなら、キリ次郎がいなくても、一人でいてもびくびくしなくなったなら、また笑い方を思い出せる。きっときっと。
目を閉じて、自分に言い聞かせる。頑張れ、餅太郎。なのに閉じた瞼の隙間に涙が溜まってきてしまう。泣くのはこんなに造作ない。
─父ちゃん、兄ちゃん、姉ちゃん。
おりんは虻の呪いから逃れられただろうか。自分のやったことは無駄じゃなかったか。
おいら、帰るからな。きっと帰るから、みんな元気でいておくれよ。
瞼を開く。水面の自分の顔を確かめる。泣きっ面じゃ駄目だ、きりっとしねえと。
餅太郎の顔の隣に、別人の顔があった。
女だ。お団子にした髪。下ぶくれで、くちびるが厚い。右のほっぺたに大きな
知らない顔だ。どこの誰だ。
「おい、あんた!」
大声で呼びかけた瞬間、水に映る女は汚いものを見たかのように顔を歪めて、消えた。
え? え? え? 今の誰だ?
餅太郎は固まってしまって動けない。
ぶう~ん。
後ろの方で、重たく、大きな羽音がたった。虻の羽音だ。はっと
見当たらない。人の姿も、飛び回る虻も。
狐につままれたような心地というのは、まさにこういうときのための言葉だろう。しかし、この里に狐はいない。神々と下僕と、お化けにならないように必死に働く哀れな人びとしかいない。
今の女も、人である以上は、ここに閉じ込められている仲間であるはずだ。どうしてお化けに見えなかったんだろう。水に映すと、本来の人の姿で見えるのかな。
手桶を提げてキリ次郎のところに戻ると、きれいな水を求めて人形たちがわらわらと寄ってきた。こいつら、水に濡れても平気なんだ。汚れたら洗い、汚れたら洗って、掃除を続ける。人形たちの水浴びを眺めながら、
「キリ次郎、おいらたち人も、水に映すとお化けじゃなくなるのか」
「何を寝ぼけたことを言いなしゃる?」
だってさ─と、さっきの出来事を話して聞かせると、キリ次郎はくいっと
「どした? びっくりしたのかい」
なにしろ賽子なので、そこそこ気心が知れてきても、感情がわかりにくい。
「……けしからんしゅうねんぶかい」
キリ次郎は早口で小さく
「しょうわるなりにはじるところがあるのならなしゃけをかけてやらぬでもないがなにしろごうがふかいしまつがわるい」
「ん? 何言ってンの?」
唐突にきりきりっと回って、キリ次郎は大声を張り上げた。
「さあ人形ども、次の仕事じゃ。こっちにおじゃれ!」
(この続きは本書でお楽しみください)
作品紹介・あらすじ
よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続
著者 宮部みゆき
定価: 2,090円(本体1,900円 + 税)
発売日:2022年7月27日
老人が語る、村を襲う「ひとでなし」の恐怖とは――三島屋シリーズ第八弾!
江戸は神田三島町にある袋物屋の三島屋は、風変わりな百物語をしていることで知られている。
語り手一人に聞き手も一人、話はけっして外には漏らさず、「語って語り捨て、聞いて聞き捨て」これが三島屋の変わり百物語の趣向である。
従姉妹のおちかから聞き手を受け継いだ三島屋の「小旦那」こと富次郎は、おちかの出産を控える中で障りがあってはならないと、しばらく百物語をお休みすることに決める。
休止前の最後の語り手は、商人風の老人と目の見えない彼の妻だった。老人はかつて暮らした村でおきた「ひとでなし」にまつわる顛末を語りだす――。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322109000584/
amazonページはこちら