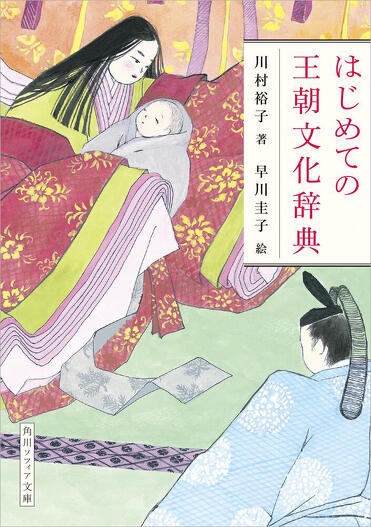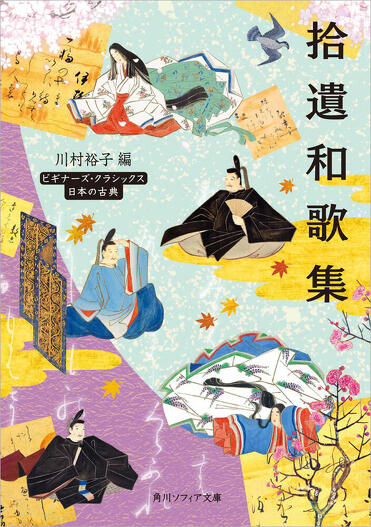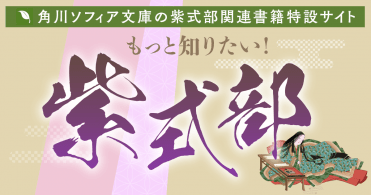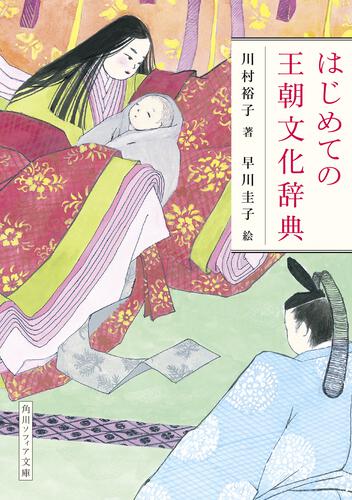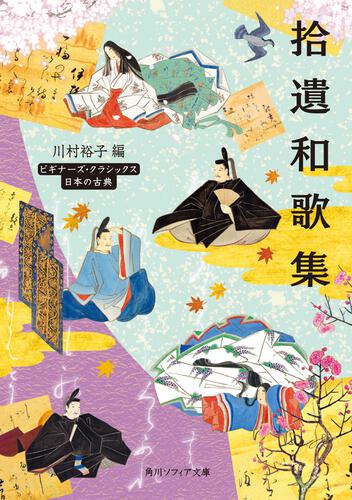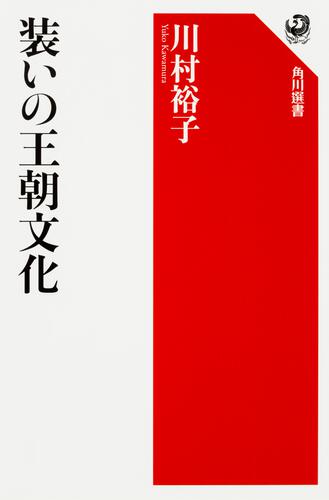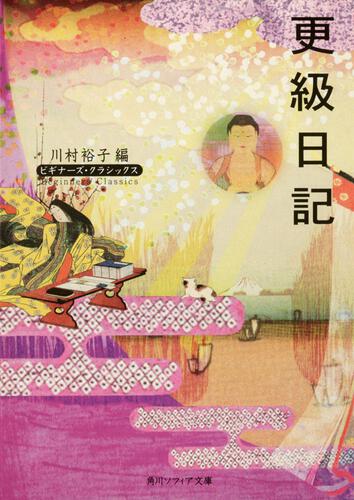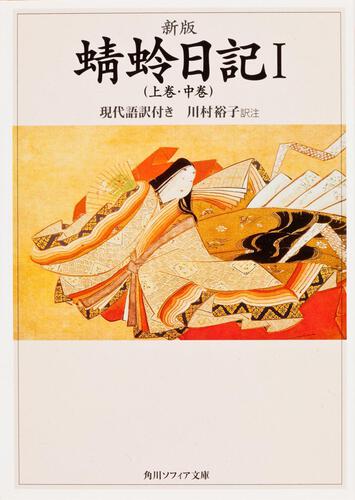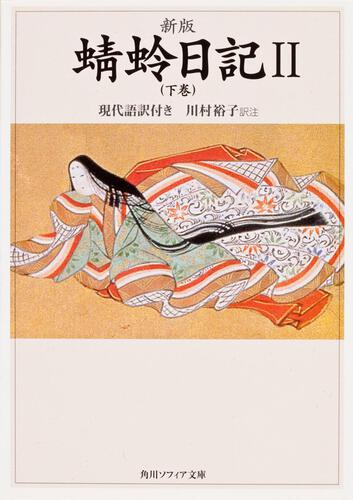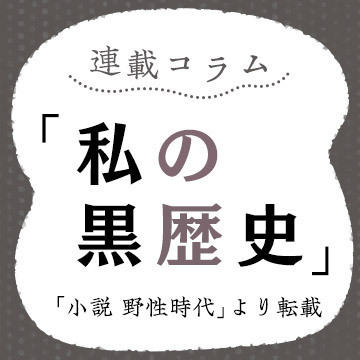第五回 藤原道綱母(兼家の妻の一人)【大河ドラマを100倍楽しむ 王朝辞典 】
大河ドラマを100倍楽しむ 王朝辞典
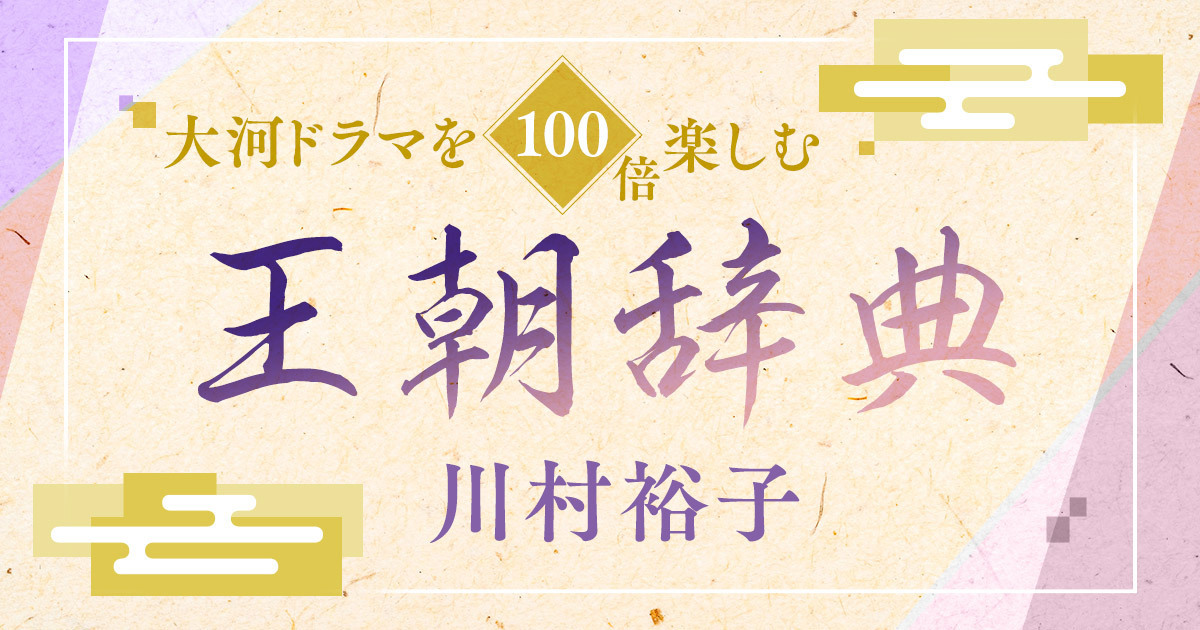
第五回 藤原道綱母(兼家の妻の一人)【大河ドラマを100倍楽しむ 王朝辞典 】
また彼女の評判として有名なのは、「
また大変なことを書き忘れてました。『更級日記』の作者・
さて、最初に『蜻蛉日記』の作者と言いましたが、『蜻蛉日記』は二十一年間の日記なんです。毎日毎日のことが柱になって、いろいろな出来事が
そして、彼女が他の人たち(清少納言や紫式部)と違う点、それは、家に居た、ということですね。清少納言たちは働いていました。
それで思い出しましたが、道綱母の得意なことがありました。それは兼家の装束調達。離婚しても兼家は装束の依頼をあれやこれやしてくるのでした。それほど道綱母は装束の仕事に秀でていたのです。
それでは、最後に彼女の代表歌を挙げておきましょう。
それは「嘆きつつ一人寝る夜のあくる間はいかに久しきものとかは知る」(嘆きながらたった独りで寝ている夜。その夜が明けるまでの時間がどんなに長くどんなにつらいものだか、あなたにはおわかりにならないでしょうね。戸を開けるのも待ちきれないでいるあなたには。)です。兼家に新しい愛人ができてしまいました。そのような時に兼家がやって来るのですが、道綱母は戸を開けません。その翌朝、このような歌を送ったのでした。
歌の内容もさることながら、これは「うつろひたる菊」に付けられてました。「うつろい菊」というのは冬になると再度菊の色が美しく変わること。そう、再度きれいに咲く、つまり、私はまだきれい、といった意味なんですね。「よれよれの菊」ではありません。
というわけで、これが『百人一首』にも採られた彼女の代表歌となってます。
さて、彼女の書いた『蜻蛉日記』。二十一年間の日記は何のために書かれたのか。まだまだわからないことが多いのです。ただ、兼家との心理的なすれ違い。それは『源氏物語』にも叙述のうえで影響を与えている、といわれています。
家族なのに、いや、家族だから通じない言葉を彼女は書き続けました。だから心理小説のようになっています。「暗い」と思ったら作品の意図に、はまったことになりますよ。なぜなら「暗く」書いているからね。
そして、紫式部は『蜻蛉日記』を読んでいました。
だから、二つの作品の似ている所などをさがしてみると、おもしろいことが出てくると思いますよ。
※参考
角川ソフィア文庫『新版 蜻蛉日記Ⅰ』『新版 蜻蛉日記Ⅱ』
プロフィール
1956年東京都生まれ。新潟産業大学名誉教授。活水女子大学、新潟産業大学、武蔵野大学を経て現職。立教大学大学院文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程修了。博士(文学)。著書に『はじめての王朝文化辞典』(早川圭子絵、角川ソフィア文庫)、『装いの王朝文化』(角川選書)、『平安女子の楽しい!生活』『平安男子の元気な!生活』『平安のステキな!女性作家たち』(以上岩波ジュニア新書)、編著書に『ビギナーズ・クラシックス日本の古典 更級日記』『ビギナーズ・クラシックス日本の古典 拾遺和歌集』(ともに角川ソフィア文庫)など多数。
作品紹介
王朝の文化や作品をもっと知りたい方にはこちらがおすすめ!
『はじめての王朝文化辞典』
著者:川村裕子 絵:早川圭子
https://www.kadokawa.co.jp/product/321611000839/
『源氏物語』や『枕草子』に登場する平安時代の貴族たちは、どのような生活をしていたのか?物語に描かれる御簾や直衣、烏帽子などの「物」は、言葉をしゃべるわけではないけれど、ときに人よりも饒舌に人間関係や状況を表現することがある。家、調度品、服装、儀式、季節の行事、食事や音楽、娯楽、スポーツ、病気、信仰や風習ほか。美しい挿絵と、読者に語り掛ける丁寧な解説によって、古典文学の世界が鮮やかによみがえる読む辞典。
『ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 拾遺和歌集』
編:川村裕子
https://www.kadokawa.co.jp/product/322303001978/
『源氏物語』と同時期に成立した勅撰和歌集。和歌の基礎や王朝文化も解説! 「拾遺和歌集」は、きらびやかな貴族の文化が最盛期を迎えた平安時代、11世紀初頭。花山院の勅令によって編まれたとされる三番目の勅撰和歌集。和歌の技法や歴史背景を解説するコラムも充実の、もっともやさしい入門書。
角川ソフィア文庫の紫式部関連書籍特設サイト
https://kadobun.jp/special/gakugei/murasakishikibu.html