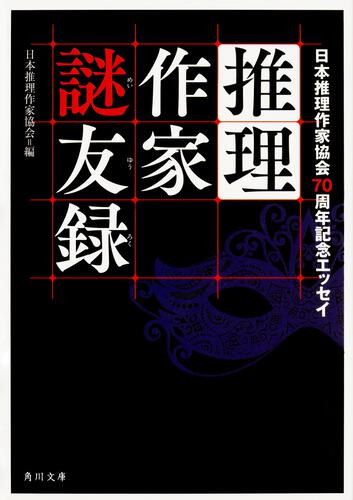中3の死は、事故か、自殺か、それとも事件か。そして新たな事実が。第10回山田風太郎賞受賞の著者、最新作!「白日」#1-4
月村了衛「白日」

>>前話を読む
しかしその日は、倉田常務との面会は叶わなかった。常務には終日社外での予定が入っているというのである。また秋吉にも、社外に出向く用が何件もあった。
午後七時半頃社に戻り、常務の秘書である
直接の上司である部長の小此木を飛ばし、課長が連絡してくることを上山秘書は
もしかしたら帰社するかもしれないと思い、九時頃まで待ってみた。しかしどうやら本当に社に戻る気配はないようだった。
秋吉はやむなく九時半過ぎに社を出て帰宅の途に就いた。
翌朝、一番に常務の執務室へと向かった。その日は一旦出社してから外に出る予定だと上山から聞いていた。
「困るなあ、秋吉君」
常務の執務室へと続く秘書室で、上山とともに待っていたのは、倉田ではなく小此木であった。
「常務はお忙しい身なんだ。君だってそれくらい分かるだろう」
さして立腹した様子もなく、小此木は妙に淡々とした口調で言った。
「何かあったら、僕に言ってくれよ。これじゃ上司の立場がないじゃない」
はっはっはっ、と棒読みに近い発音で笑った。不自然極まりない下手な芝居だ。
「それで、常務に一体なんの用なの? もしかして僕の悪口?」
面白くもない冗談は無視するのが一番である。
「局長のご子息の件で……」
「そうだろうと思ったよ」
秘書の方を横目で見ながら小此木が言う。上山は聞こえていないふりをして自席でパソコンを見つめている。
「詳しい事情を伺わないことには、皆も落ち着いて仕事ができませんので、一刻も早くと思い……」
「うん、分かるよ。一課を直接指揮しているのは、なんてったって君だものね」
小此木は〈話の分かる上司〉の顔を作り、
「僕がちゃんと説明できなかったのがいけなかったんだね。不信感を抱かせちゃったみたいで申しわけない」
「いえ、そんな」
「いいからいいから。社内に変な噂が流れてるみたいだし、この際はっきり言おう。僕だけじゃない。常務も専務も、警察からの連絡待ちで、よく分からないというのが本音なんだ。ご子息がどうしてそんなビルに行ったのかとか、自殺するような心当たりは本当になかったのかとかね」
さすがにこのときばかりは真面目な顔で小此木が続ける。
「昨日駆けつけた倉田さんの話では、そもそも梶原さんご自身がよく分からないとおっしゃっていたらしい。なんと言ってもご子息を亡くされたばかりだ。倉田さんもそれ以上追及するわけにいかず、困っておられた」
視界の隅で、いつの間にかこちらを見ていた上山が「本当だ」と言うように頷いた。
「いいか、秋吉君、これはここだけの話にしてほしいんだが、警察の調べによっては、自殺とか、もしかしたら、こんなことは言いたくないけど、何か事件に巻き込まれた可能性だってあるわけじゃないか」
殺人事件──ということか。
「そうなってくると、対外的にどう対応するか、社としても大変難しい問題になってくる。僕の一存で適当なことを言うわけにもいかなかったんだよ」
「そうだったんですか……」
「たぶん、もう少しすればはっきりしたことが分かると思う。君も大変だろうけど、それまでみんなを抑えててくれないか」
「分かりました。微力を尽くします」
小此木と上山に一礼し、部屋を出た。
事情は分かった。しかし、すべての霧が晴れたとは言い難い。
第一に、秋吉の知る幹夫は、自殺などするような少年ではない。また、事件に巻き込まれるような人間関係とも無縁としか思えない。
第二に、小此木の対応の変化である。基底にある小此木という人物の本質に変わりはないが、昨日までの曖昧さと、先ほどの明瞭さの間にはかなりの隔たりがあった。倉田常務に自分がしつこく迫ったため、その防波堤になろうとしたとも考えられるが、どうもそれだけではないように思える。倉田と小此木との間にそこまでの信頼関係があったなら、第一課の職場環境はもっと違ったものになっていたはずだからだ。千日出版の教育事業局は社内で孤立、とまではいかないが、少なくとも浮いた存在であることは間違いない。そのことは天能ゼミナールとの合併、独立という発案の前提ともなっている。今日まで教育事業局を支えてきたのは、常務でも専務でもなく、あくまで梶原局長なのだ。
まだ何かある──
エレベーターを待ちながら、秋吉はそんな疑念を深めていた。
六階の第一課に戻ると、部下達の視線が一斉に自分へと注がれるのを感じた。
「課長、ちょっとあちらでご相談が──」
すばやく近寄ってきた沢本が、自分を室外へ連れ出そうとする。一呼吸遅れて亜寿香も慌てて立ち上がる。
だが遅かった。
「待って下さい、課長」
主任の新井を先頭にした一団が、興奮した面持ちで詰め寄ってきた。
「お話があります」
「言ってみろ」
「倉田常務は結局なんと?」
「それが、まだ会えずにいるんだ」
秋吉は小此木から聞いたばかりの説明を繰り返した。しかしそれは、新井達にさしたる感銘を与えなかったようだ。
「いかにも部長や常務が言いそうですね」
会社員にあるまじき
「何が言いたいんだ、君達は」
「課長は梶原局長の息子さんが引きこもりだったって知ってますか」
新井の発したその言葉は、秋吉の中の〈何か〉に触れた。
「馬鹿を言うなっ」
我知らず怒鳴っていた。
「おまえ達は幹夫君の何を知っているって言うんだっ」
新井に駆け寄って胸倉をつかみ上げる。
「あの子はな、うちの娘を気遣って、励まして、あんなに心配してくれたんだ。ああ、そうだ、おまえ達も知ってるだろう、引きこもっていたのは俺の娘だっ。娘が立ち直る手助けをしてくれたのが幹夫君なんだっ。その幹夫君が、引きこもりなわけないだろうっ」
自分はどうしてこんなに
行動に反し、心の奥でぼんやりとそんなことを考えた。
娘を励ましてくれた幹夫への侮辱は許せない。だがそれを侮辱と感じるということは──
狭い自室に閉じこもったきり、秋吉や喜美子の呼びかけにまったく応じなくなってしまった春菜。保護者の間を走り回り、ようやく娘がいじめられていたという事実を知った瞬間の放心。学校や教師の無責任さに
「おまえは、それを梶原局長に言えるのかっ」
そうだ、これは自ら先頭に立って引きこもりをなくそうとする梶原局長への侮辱でもある──
「課長、やめて下さいっ」
背後から沢本が懸命に引き剝がそうとしている。他の部下達も一斉に割って入った。
「放せ、沢本っ」
部下達を振り払い、大声で叫ぶ。
「幹夫君が引きこもりだなんて、そんなデタラメ、どこで聞いてきたっ。言えるもんなら言ってみろっ」
「
新井が怒鳴り返した。
新創書店もまた由緒ある老舗出版社であり、同社のベテラン編集者である緒形は秋吉もよく知る人物である。決して根拠のないデマや偽りを振りまくような男ではない。
「新創の緒形さんは梶原局長のご自宅近くに住んでて、息子さんは小学校まで幹夫君と一緒だったそうです」
息を弾ませながら、新井が続ける。今や全員が声もなく聞き入っていた。
「中学校は別々ですが、近所だから噂が耳に入ってきて……幹夫君は、夏休みに入る少し前から、学校には行かなくなっていたって」
「それがどうした。やっぱりただの噂じゃないか」
「噂じゃないからこそ、上は動揺してるんだ。引きこもり対策を
「新井、言っていいことと悪いことがあるぞっ」
「僕達は残りの人生をこのプロジェクトに懸けて今日までやってきたんだ。課長は僕達の気持ちが分からないとおっしゃるんですか。いや、もしかしてすでに上から何か言われたんじゃないですか」
「貴様っ」
再び激情に駆られた秋吉を、沢本と亜寿香が全力で室外へと連れ出そうとする。
「聞いて下さい、課長っ」
「聞こえますか、幹夫君は……幹夫君は……」
「幹夫君がどうしたっ」
ドアの外に出た所で、亜寿香が囁くように、またきっぱりと言い切った。
「幹夫君が引きこもりだったというのは本当です」