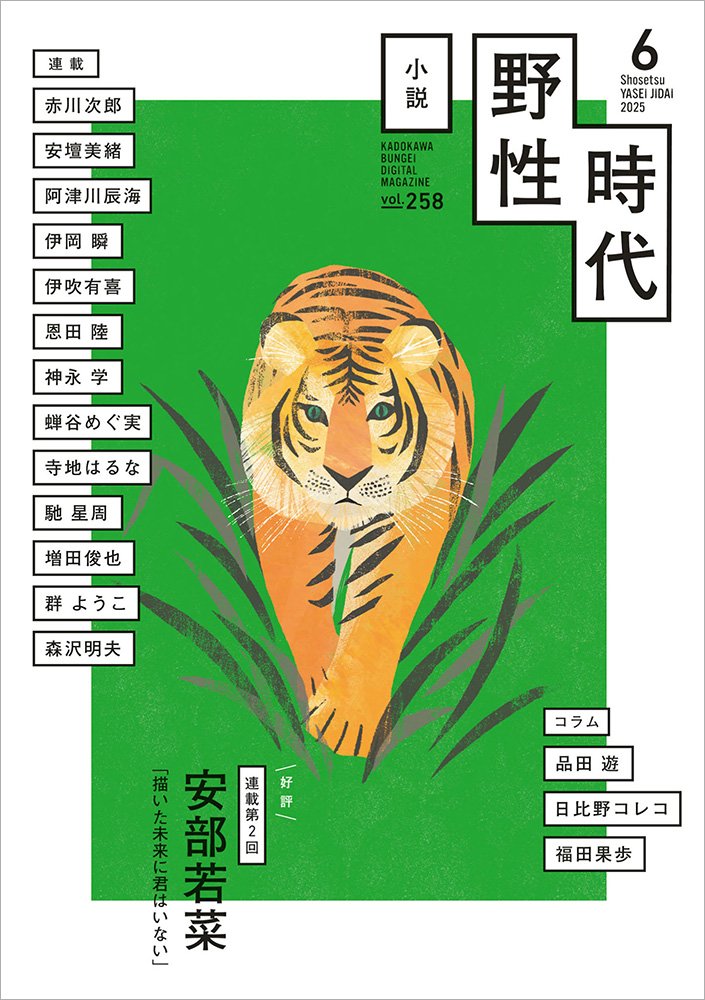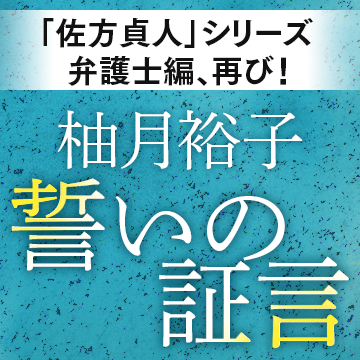【連載小説】少女失踪事件の手がかりを探るべく、有里と村上刑事は〈Kビデオ〉のオフィスを訪れる。赤川次郎「三世代探偵団4 春風にめざめて」#8-3
赤川次郎「三世代探偵団4 春風にめざめて」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
「君のお母さんに散々叱られたよ」
と、村上が言った。
「ごめんね」
と、有里は両手を合せて拝む恰好をした。「でも、ちゃんと話して来たから」
「しかし、電話でたっぷり十五分も文句を言われた。『有里の身に何かあったら、どう責任を取ってくれるんですか!』ってね」
「村上さん、何て言ったの?」
「切腹します、って言ったよ。他に言いようがない」
──ともかく、二人は〈Kビデオ〉のオフィスへ、鍵を開けて入って行った。
しかし、何といっても、何を捜すか分らずに捜そうというのだから……。
二人して、床に散らばった書類やプラスチック片をかき分けてみたが、一時間近くたって、
「腰が……」
と、二人とも異口同音に言った。
「腰が痛い……」
と、有里が伸びをする。「こんな狭苦しいオフィスなのに、隅から隅まで見ようと思うと大変だね」
「全くだ! ──おい、気を付けて!」
と、村上が言ったときは遅かった。
有里は床に転っていた、口の欠けた花びんを踏んで、みごとに転んでしまったのだ。
「いたた……。お尻を打った……」
「大丈夫か?」
村上が駆け寄って、助け起こす。
「うん……。何とか……」
有里の踏んだ花びんは、コロコロと転って行き、引っくり返った机に当って止った。
「だが、割れたのを踏んでたら、足を切ったかもしれない。転んで良かったよ」
「まあね。──スカートが……」
「音って?」
「あの花びんが机に当って止ったとき、何か音がしなかった?」
「気が付かなかったが……」
有里はその花びんを拾い上げると、逆さにした。床に落ちたのは……。
「鍵だ」
と、有里は拾い上げて、「村上さん、これってたぶん──」
「ああ。どこかのコインロッカーの鍵だな」
村上は苦笑して、「これぞ、『転んでもタダじゃ起きない』って奴だな!」
13 古びたカウンター
引き戸がガタついて、まともに開けられない、古い居酒屋だった。
「まあ、どうも……」
割烹着姿の
「以前、おいでになったことが……」
と、充代を見て言った。
「ええ」
充代は肯いて、「医者の久我先生を捜しに来たことがあります」
「そうそう。そうでしたね。──今日はずいぶん早いですね」
店はまだ支度をしている途中という様子だった。
「捜してるんです。久我先生」
と、充代は言った。「ご存知ありませんか?」
「さあ……。このところおみえになりませんけど」
と、女将は言った。「そちらの方たちは……」
村上が名のろうとすると、
「一人の女の子の命がかかってるんです」
と、有里が進み出て言った。「何かご存じなら、教えて下さい!」
「女の子の命?」
「女将さん、知ってるでしょ。久我先生は、ビデオの撮影のとき、けがをしたりすると、いつも呼ばれていました。こっそりと内緒ですませたい事故には、必ず久我先生を、と言われてました。それが──今、先生の所へ行ってみると、もぬけの殻です」
と、充代は言った。
「じゃあ……引越したのかしらね」
と、女将は言った。「私は何も……」
「何か重大な事故があったんです」
と、有里は言った。「久我さんが急に姿を消したのは、その話をされては困るからです。でも、危険です。この件では、人が殺されているんです。久我さんも、口をふさぐために、殺されるかもしれません」
「まさか……」
「事実です」
と、村上が言った。「警察の者です。久我さんだけでない、吉川マナという女の子の行方も捜しています。彼女に何が起きたのか、久我さんはおそらく知っているんです」
「でも、あの人は……」
と言いかけて、女将は口をつぐんだ。
「久我さんは、ここに寄ったんじゃないですか?」
と、有里は言った。「しばらく身を隠そうとしたら、ここにも来られない。黙って行ってしまうことはないでしょう」
女将は、フッと息をついて、
「刑事さん。あの人を刑務所へ入れたりしないで下さいね」
と言った。
▶#8-4へつづく
◎第 8 回全文は「小説 野性時代」第206号 2021年1月号でお楽しみいただけます!