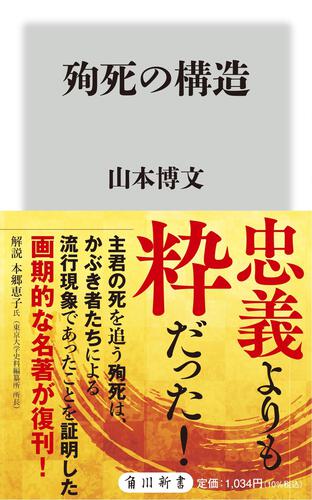主君を追う殉死は、かぶき者たちによる流行現象であったことを証明した、画期的な名著が復刊!
本書巻末に収録の「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
山本博文著『殉死の構造』
【解説:本郷恵子(東京大学史料編纂所所長)】
「殉死」とは、高貴な身分の人や主君などの死に際し、その従者や妻子が死者に随従するために自殺する行為である。戦場で主人とともに討死や切腹などするならともかく、畳の上で死んだ主人のあとを追って、わざわざ自死するという行為は、自然の摂理に反する過剰なものと感じられる。
本書は一九九四年、弘文堂から「叢書 死の文化」の一冊として刊行された。これは、「人間生活のあらゆる側面から死のあり方を考え、動植物や宇宙の多様な『死』にも目を向けつつ、死を通して生の本質に迫るシリーズ。文学、芸術、歴史、医学、自然科学、人類学、民俗学など多方面の著者が生と死の姿を描き出す」というもので、一九八九年から九五年にかけて、全部で二〇冊を世に送り出した。多様な分野の専門家が、さまざまな「死」を論じており、近年推奨されている分野融合的で社会への訴求力が強い学術の発信を先取りするような叢書だったようだ。そのような企画にふさわしく、本書は、豊富な歴史史料の提示・精緻な専門性と、読みやすさ・理解しやすさを兼ね備えた内容となっている。「死の文化」のなかでも、最も過激な部類に属すると思われる「殉死」を扱いながら、殺伐としすぎないところは、著者の力量と高度なバランス感覚の賜物であろう。
さて、著者は冒頭で、森鴎外の『阿部一族』をとりあげている。明治天皇の大喪の礼当日に、乃木希典が殉死した事件に影響を受けて書かれた作品である。舞台は熊本藩、寛永十八(一六四一)年三月の、藩主細川忠利の死にあたって、藩士らが命がけの忠義や面目を示す顛末が語られる。忠利との感情的な行き違いによって、殉死の許可を得られなかった阿部弥一右衛門は、周囲からの悪意に満ちた噂に耐え切れず腹を切る。弥一右衛門の息子たちに対する藩の処遇は罰則的であり、それを不当として思い切った行動に出た長男の権兵衛は、新藩主光尚の判断で縛り首になる。遺された兄弟たちは権兵衛の屋敷に立てこもり、光尚はこれに討手を差し向ける。表門からの討手を命じられた竹内数馬もまた、討ち死にせずにはおさまりがつかない立場に置かれていた。加えて攻守それぞれの武士の下には、やはりさまざまな事情で死に急ぐ小姓や被官が従っている。屋敷内での槍や刀を振るっての戦いの様相は、「裏表二手のものどもが入り違えて、おめき叫んで衝いて来る。障子襖は取り払ってあっても、三十畳に足らぬ座敷である。市街戦の惨状が野戦より甚だしいと同じ道理で、皿に盛られた百虫の相啖うにも譬えつべく、目も当てられぬ有様である」と描写されている。阿部一族の掃討を終えたことを藩主に報告する、裏門攻手の高見権右衛門の姿も、「黒羽二重の衣服が血みどれになって」という凄まじいものだ。この凄惨な状況に平然としていられること、特段の鈍感さを保っていられることこそが、武士の嗜みであったとみえる。命を惜しまぬどころでなく、いさんで死んでいく――自他問わず「命」に対して軽侮にのぞむことを推奨する価値意識だったようだ。
この解説を書くために『阿部一族』を再読したのだが、武士相互の猜疑心や、ほとんど猟奇的と感じられる戦闘描写など、厳粛な文体に似合わず、健全でないという印象を禁じえなかった。今日の私たちからは不健全に見える価値観や行動規範こそが、武士道であり、主従関係における献身の道徳であると、日本人は長らく受け止め、それらを美化してきたのだ。著者は、このような雑駁な通念に対し「あまり先入観をもって殉死をとらえるべきではない」と述べている。殉死を歴史的文脈の中で実証的に検討し、日本人と忠誠の観念とのかかわりをあきらかにすることが、本書の主題である。
『阿部一族』は鴎外の作品の中では「史伝」という分類に入るようだが、歴史叙述ではなく、あくまで小説である。著者によれば、鴎外が拠ったのは『阿部茶事談』という史料だが、全体の筋書きは共通するものの、要所に鴎外の個人的体験に通じる創作が入っている。なにより『阿部茶事談』そのものが脚色や作為的な辻褄合わせの産物であるという。『阿部茶事談』よりも確実と評価される『綿考輯録』(細川家の家譜)も、阿部弥一右衛門の一件に関しては信頼できない。どちらも歴史研究者の史料批判に耐えない文献というわけだ。
そこで著者は熊本藩の政務日誌である『日帳』から史実の再構成を試みる。あとから編集されたものでない同時代史料で、まさに一次史料といえるものである。ただし、一次史料とは、往々にしてすべてを都合よく説明してくれるものではない。事件の現場にいる者にとって、事件の全体像が見えにくいのと同じことである。後世の編纂物は、情報が欠けている部分をフィクション等で補って物語として一貫させるわけだが、歴史研究者は、まず史料を渉猟して事実をあきらかにしなければならない。著者は第一章で、この歴史学の基礎作業を行い、阿部一族の悲劇の真相を捉える。阿部弥一右衛門の殉死は順当なもので、その後の一族の悲劇は殉死に起因するわけではない。新藩主光尚の政治体制に対する一族の不満が、自滅的な結末を招いたのだという。
第二章以降では、確実な史料から殉死の実例を探り、殉死者の動機や、背景となる事情を分析していく。その過程で著者が注目するのは下級家臣の殉死の多さであり、彼らに死ぬほどの義理も利もなく、それどころか犬死に近いとさえ見える場合が少なくない点である。彼らは自らの身分の軽さと、それにもかかわらずたまさかに与えられたわずかな主君からの温情との懸隔の大きさに感激して、躊躇なく腹を切るらしい。忠義というより、主君の死を好機として、死を恐れないという意地をみせる、究極の自己主張であり、独善的な美学の表明である。そこに著者は、合理性から逸脱した「かぶき者」的武士の姿を見る。殉死の動機に「かぶき者」の気風を見出し、それを展開していったところが、本書の真骨頂だろう。
殉死を近世初期の流行現象と明確に位置づけ、そのうえで、戦国の荒々しさを残す時代から、幕府による管理や秩序の時代への移行、並行する武士の心性の改変や武士道書の出現など、時代の潮流と社会や思考の変化をひも解いていく著者の筆致は鋭い。
殉死は寛文三(一六六三)年、四代将軍徳川家綱の「武家諸法度」公布の際に禁止され、その後はほぼ途絶えたといってよい。ただし、主君と武士との関係における理不尽な死がなくなったわけではない。武士道書にみえる通り、武士は常に死の覚悟を持つことを求められた。武士が些細なことで切腹を命じられる事例が、江戸時代を通じて絶えなかったのは、著者の『切腹』(二〇〇三年に光文社新書として刊行、二〇一四年に光文社知恵の森文庫として再刊)に詳しい。問題を論理的に解決するのでなく、関係者を切腹させて帳消しにしてしまう。切腹が、主君や組織が管理責任を免れるための便利な落としどころになっていたのである。著者は同書の中で、近代の軍隊が唱えた「武士道精神」のなかに、この上位者の責任逃れの論理を見出し、さらに官僚組織や会社組織にも同じ構造が引継がれているのではないかと述べている。本書第八章「『忠臣蔵』の本質」でとりあげられている赤穂事件は、一八世紀に入ってからのことで、厳密には殉死ではないが、武士の面目・忠義・死が結びついた事件として、殉死を連想させるものであるのはまちがいない。このように江戸時代初期から、殉死・切腹・武士道は一連のものとして継続しており、そのまま近代の乃木希典の死につながっているように理解されがちだ。本書は、それが正しくないことを歴史的分析によって示したのである。
殉死者の心情について著者は、打算や計算ずくではなく、忠誠心とも異なる「もっと非合理的で衝動的」で、「不可解」な「非合理的情念」であると述べている。さらに、心から殉死を決意している武士の心情は「現代人の想像の範囲を超えているのだと思う」とも言う。現代人に理解できるような理性的な「忠義」は、戦国時代の余燼を帯びた「かぶき者」的心性を改変することによって成立した。そして『阿部茶事談』の作者も、森鴎外も、殉死時代の武士の心性を共有していなかった。
著者は、一七世紀の武士が心の底から願って殉死する心理を、現代人には理解しがたいものと明言している。過去の人々の意識が、現代の私たちのそれと異質であることを認め、その拠ってきたるところを明確にすることこそが歴史学の使命である。過去から現在へと、変わらぬ何かが連綿と繋がっていると、「伝統」のような曖昧で安易な言葉で説明するのは正しくない。とくに形にあらわれない「心性」については、時代を超えた一貫性があると強調する論者も多いが、厳に慎むべきだろう。
私の専門である中世史にひきつけて言えば、鎌倉幕府に始まる武家政権は「主従制」を軸とする組織だと規定される。だが「忠誠心」や「主従制」などの概念が、政権を支える規範として機能するためには、さまざまな作りこみが必要である。殉死禁止後の徳川の平和の時代は、その完成形のひとつと考えられるが、一方で無理筋の構造物を、抑圧や共同幻想によって、なんとか維持しているようにも見える。
原本あとがきに、著者は「江戸時代の武士の心性というのは、私にとって、あこがれのテーマであった」と記している。私も「中世人の心性」ということを、くりかえし考えているので、この一文は胸に響いた。著者の山本さんは、私にとって三〇年以上にわたる職場の先輩であったが、もはや直接教えていただくことはかなわない。山本さんのあこがれのテーマだった「過去の人々の心性」を探ることを通じて、今日の世界へと私たちを導いてきた道のりと、これから進むべき方向が見えてくるのではないかと考えている。
【作品紹介】
『殉死の構造』
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322205000698/
amazonページはこちら