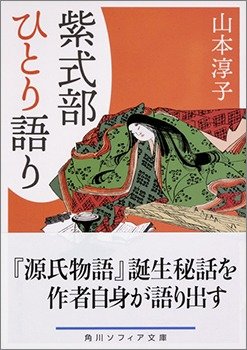書評家・作家・専門家が《新刊》をご紹介!
本選びにお役立てください。
(評者: 小峯和明 / 立教大学名誉教授)
本書の著者ハルオ・シラネ氏に関してはあらためて説明する必要がないかと思うが、『源氏物語』の卓抜な研究で颯爽とデビューし、ついで近世の俳諧論に転じ、その後『創造された古典』の共同研究で、自明のことのように扱われていた古典そのものの根源を問い直し、後世の享受や再生にこそ古典の意義があることを究明し、文学研究全体の動向を大きく変える推進役を果たしてきた。今や内外を問わず、日本研究の第一人者といえる。
著者は、生まれは日本人であっても文化的には英語圏のアメリカ人であり、欧米の文学や人文学を教養の土壌とする。そうした複眼的な視座が日本語圏の研究者を瞠目させ、挑発し続けている。著者の真摯で旺盛な好奇心や知識欲は並外れており、周囲の者は質問攻めに遭い、何が何故そうなるのか説明に窮し、それまで考えてもみなかった問題に気付かされることが少なくない。
著者が『創造された古典』以降、時間をかけて追究してきた課題の一つが〈環境文学〉である。2012年に“Japan and the Culture of the Four Seasons” と題してコロンビア大学出版部から英文で刊行された。副題に“Nature,Literature,and the Arts”とあるように、日本文化の特性を自然や四季を通して、文学や芸術から本格的にとらえなおす意欲的な労作であった。本書は待望久しい、その日本語版である。
英語版刊行前後の動向を身近な事例からたどると、1990年代前半にアメリカを中心に始まったエコクリティシズム研究がアジアにも及び、日本でも文学・環境学会(ASLE)が発足、2010年代には中国・韓国・台湾各地の活発な研究交流が始まっていた。日本の環境文学をリードする野田研一・渡辺憲司氏を中心に2010年に立教大学で「エコクリティシズムと日本文学研究―自然環境と都市」のシンポジウムを開催、それをもとに英語版刊行の前年、シラネ、野田、渡辺、小峯編の『環境という視座―日本文学とエコクリティシズム』(勉誠出版・アジア遊学)が公刊された。もともとエコクリティシズムは欧米文学や英語圏の研究者から始まったこともあり、近代文学に限られていたが、この特集は前近代と近現代を通底する広範なフィールドを提起している。そのシンポジウムの基調講演を担当したのが本書の著者シラネ氏であり、「二次的自然」論の問題提起は画期的な意義を持っていた。
またそれより前の2008年には、シラネ、渡辺、小峯の共編で『文学に描かれた日本の「食」のすがた―古代から江戸時代まで』(『国文学解釈と鑑賞』別冊、至文堂)も刊行し、食文化も〈環境文学〉の一環として重要な領域であることを提起した。著者の「二次的自然」論のまったき影響下から私自身の〈環境文学〉研究も始まったといえる。2018年には、再び立教大学で「日本と東アジアの〈環境文学〉」のシンポジウムを開催、再度シラネ氏に基調講演を依頼した(論文集の公刊を予定)。
しかしながら、英語版だけでは一般に充分対象化されず、「二次的自然」の語彙だけが曖昧なまま一人歩きし始めており、翻訳本の実現が待ち望まれたのである。本書に限らず、近年、海外の日本研究者による優れた成果が増えてきているが、翻訳がなかなか公刊されないため、我々日本語圏の研究者の視野に入りにくい。いつの間にか海外で日本研究が進展し、その動向とは無縁なまま国内で逼塞しかねない、「井の中の蛙」状態に陥っている。この度の本書の公刊にふれて、あらためてその思いを深くする。この翻訳が出ると出ないとでは、研究の最前線の風景がまったく異なってくることを痛感させられる。
本書は表題の通り、日本の自然観とりわけ四季の文化や表現を通して、日本文化の形成と展開を根源的に跡づけようとした意欲作である。四季は自然の状態のまま目の前にあるのではなく、人間によって創造される文化としてあった。これも『創造された古典』を具体的に敷衍する変奏にほかならず、著者の視座はゆらぎがない。
日本の四季や自然観をめぐる研究は従来から少なくないが、「自然」とは、「四季」とは何か、言語表現の問題として根源的に構造的かつ体系的に追究する姿勢がなく、むしろ自明の与えられた事象として無媒介に論ずる傾向が強かったように思う。本書がそれらと一線を画するのは、四季を言語表現と文化の問題としてとらえ返し、時代と社会階層、地域、文学ジャンル等々の相違に即した、豊富できめ細かい事例の収集と分析を試み、さらに文学だけを特化させることなく、絵画や建築など多面的な媒体と複合させて有機的に読み解く力量を備えているからである。
著者の視座は一貫して前近代の古典にすえられるが、古代、中世、近世の時代ごとの差異化に等価に目配りし、その上で近現代に対比させていく。むしろ現代や現実を見極めた上でそこから遡行して問題を投射しているというべきだろう。自戒をこめて言えば、日本の古典研究者は時代やジャンルの枠組みの呪縛が強く、自らのフィールドの枠内に閉じこもりがちであるが、著者の時代のジャンルを超えたフットワークの軽快さや造詣の深さは本書でも随所に発揮されている。特に四季や自然のテーマには、文学ばかりか絵画や建築、工芸、陶磁器、服飾、食文化等々への視野も欠かせない。まさに文学と無縁なものはないことを再認識させられる。
本書の鍵語「二次的自然」に関してみれば、欧米のネーチャーライティング研究から始まった〈環境文学〉論は、自然を単一の野生とみなし、それと人間・文化とを対比させる傾向が強かったが、日本ではそういう対比は成り立ちにくい。自然とか四季とか言っても、それは人工林であり、庭園であり、盆栽や園芸であり、絵画であったり等々、人間が創り出したものであって、それらをもとに歌を詠んだり、自然風景として描いたり、造型したりしている。わずかに『風土記』など古代の神話や伝説に、荒ぶる野生の自然が出てくるかもしれないが、日本文化を成り立たせる基調は、おしなべて「二次的自然」にほかならない(一方で災害の問題はあるが)。本書は、時代や社会共同体やジャンルごとにその「二次的自然」がいかに受け継がれ、再創造され、統合されて今日に及ぶかを執拗なまでに波状的に論述していく。
著者の慧眼はたとえば、「歳時記」への注視に典型化される。日頃それほど意識化されない「歳時記」こそ年中行事や四季の季節感を体系化した百科全書であり、そこに網羅された語彙体系が自然をかたどり、創出している。東アジア世界に浩瀚に蓄積された「類書」の典型であり、実際に詩歌を詠むための手引きにとどまらず、世界認識、知の殿堂を体現している。そこには『万葉集』『古今集』以来の和歌をはじめ、今日の新しい風俗、慣習までが呼び込まれる壮大な言語宇宙が現出しており、長い歴史に及ぶ人々の累々たる生活そのものが織り込まれている。キリスト教の聖人など人に焦点がある西洋の年中行事との対比なども興味深い指摘である。
「二次的自然」論で大事なのは、それが日本の文化を造ると同時に、詩歌が「二次的自然」を造り出した相互作用を持つことだろう。奈良時代から平安時代にかけての貴族層の確立に伴い、屋敷を構え、池水を引いて庭園を造り、梅などの樹木や草花が植えられ、季節ごとにそれをながめては歌に詠むようになる。野生の自然は埒外にある。歌と人工的自然が相互に共鳴しあう。歌はやがて高度に洗練され、短歌形式の歌が「やまと歌」として全盛期を迎え、気象、動物、植物などが季題を表わす景物となり、次第に固定化して歌を詠む方途としての「本意」を生み出す。「本意」とは詠歌の表現指向や規範であり、おのずと動植物や自然は美意識のもとに峻別され、体系づけられる。桜なら散るのを惜しむ、といった詠みぶりが定まっていく。
とりわけそうした四季の美意識を醸成したのが十世紀の『古今集』であり、さらには中世の連歌にも継承され、近世の俳諧、俳句にも及ぶ。まさに和歌は「王者のジャンル」(76頁)となった。「二次的自然」即ち「文化的自然」を創ったのは和歌、連歌、俳句であり、短詩型文学は日本の文芸の骨格をなした。名称は和歌から短歌に変わり、時代の節目ごとに批判されることはあっても、今日までゆらぐことがなかった。それが文化の記憶であり、「自然や季節をめぐる表現が持ち続けてきた巨大な影響力」を思うべきであろう。
(詩歌における)自然や季節のイメージが美的、宗教的、政治的表現の重要な回路となった。和歌が創造し、高度に体系化された季節の表現は、時代を重ねるごとに複雑化し、多層化した自然観や季節感に不朽の基礎を築いたのである。(255頁)
本書では、和歌だけに止まらず、近代に衰退したため一般的にはその意義を忘れ去られつつある連歌についても行き届いた解説を加え、さらに俳諧、俳句への展開も周到に検証している。同時に著者は短詩型文芸と密接にかかわる視覚文化や視覚メディアをも注視する。特に建築への着眼が重要で、中世における書院造りや茶室など人間の空間と自然の空間との連続性をふまえた「床の間芸術」によって、自然が屋内化する。とりわけ、中世の茶の湯は立花などとも合わせ、「二次的自然」の発展の典型で、「屋内化された自然や四季の表現を歴史的にみてもっとも高いレベルにまで到達させた」(131頁)とする。
それに対して、近世には都市化の進展によって、花見などの名所が都市空間に造られ、小屋がけ、舞台劇場など娯楽施設が普及し、屋外に向かう。古代・中世の屋内から近世の屋外への転換という「二次的自然」の位相の変転の指摘も示唆的であり、近世以降、双方が併存して、より多面的に展開するといえよう。
近世に屋外化する名所に関しても、たとえば和歌に詠まれる歌枕など当初は実際に現場で詠むわけではなく、観念的なもので「田舎の風景を自らの詩的な庭に取り込むこと」(240頁)だったが、次第に実体化され、現場としての名所となる。名所は宗教など聖地の問題とも密接に関わると思われるが、こちら側が担うべき課題でもあるだろう。
いずれにしても、詩歌は「文化の記憶を伝える重要な手段」(243頁)で「失われた過去を取り戻す方法を提供」(108頁)し、「自然の文化的機能」を担い、「言語的、視覚的、触覚的、食物的手段を通して理想的環境を作り出」(31頁)し、「人間の思考や感情を強く示唆する優雅な表現として機能」(75頁)するのである。
こうした「二次的自然」に必然的に作用するのは、「見立て」であり、広義のパロディである。何かを何かに見立て、あらたな意味を与える表現行為で、見立てられる元の対象が分からなければ意味をなさず、作り手と受け手との知の共有が欠かせない。庭園における須弥山や塩竃浦をはじめ、歌合の象徴にもなる州浜台、盆栽などが典型例である。
このようにみてくると、十六、七世紀辺りの中世から近世への転換が大きな節目になっているようだ。たとえば、近世には食文化もせり出し、特に江戸や大坂など港町の発展にともない、海産物が流通し、魚が身近な食材になり、詩歌の対象にもなる。著者はこうした変転をふまえて、「季節のピラミッド」という言い方でとらえる。頂点は和歌で培われた古典系の伝統的な季節であり、底辺は新しい生活に即した日常的な光景、風物である。近世は特にこの底辺が拡張し、それに応じた文芸が必要になり、やがて季節から離れた狂歌や川柳にまで発展する。
また、近世は従来の鎖国観に反して、近代の始まりの意義を持ち、西洋文化が導入され、遠眼鏡や顕微鏡が入ってくる。動植物や鉱物を医薬から観察、研究する本草学が飛躍的に進展し、科学に立脚する詳細な図譜が描かれる。リアリズムの世界といえる。本草学の実用性と汎用性が一方は医薬学に専門分化し、物産学にもなり、一方は知の体系の枠組みを再編成する博物学になる。本草学は東アジアにひろまる伝統的科学といえるが(西洋でも同様だが)、これが博物学に展開するのが近世といってよいだろう。自然と四季の古典的な連想が自然科学にもとづくあらたな自然観と重なり合い、花鳥画はもとより錦絵や狂歌絵本などにも投影する(歌麿の『画本虫撰み』など)。雅と俗の反転ないし合一である。あるいは微細な虫なども表現の対象になるのが興味深い。
鳥の文化でも、貴族の鳥と庶民の鳥という対比が、ホトトギスと雀のごとく、前者は和歌に、後者は説話に登場する、といったジャンルの対比にも通ずる指摘がなされる。特に室町時代以降、博物学的指向を持った物尽くしの世界が著しくなる。名寄せの文化とも言うべき知の枠組みへの指向性も関わってくるわけで、この物尽くしなどもさらに追究されてよい課題であったろう。
中世から近世への転換で顕著になる動向に動植物の擬人化がある。お伽草子の物語や狂言の世界に際立つが、この背景には都市化にともなう土地開発や戦乱による自然破壊が進み、環境が大きく変転したことが想定される。人と自然との溝を埋める手立てとして、これら動植物の文芸が発展したと思われる。これは以前から私的に主張している課題であるが、著者も自然破壊によって、お伽草子などは「自然環境の代用品」としてあり、「動物や(中略)森や林を慰撫する必要」(157頁)や「再現された自然によって、ある程度、「自然」が取り戻され、再生産される傾向」(228頁)があったとする。
本書には日本の文化総体にかかわる鍵語がちりばめられている。たとえば、「参加型芸術」。これは連歌や俳諧、歌会に句会をはじめ、立花(生け花)、茶の湯等々、特に中世以降盛んになり、今日に及ぶ文芸や芸術の本質を言い当てている。近代の自我観やオリジナル幻想にもとづく個的な作者・作家の創作を絶対視する文学・芸術観を根本から相対化する意義を持つ。作り手と受け手が交互に自在に入れ変わる、連、衆、講といった集団文芸の型であり、今日の少女マンガの創作と享受の世界などにも通ずる。そのような「参加型芸術」こそが王朝和歌の美意識に始まる「二次的自然」を継承発展させてきたことになるだろう。
また、「二次的自然」に関してもう一つ、自然を「護符」とみる視点が重要である。これには梅や桜のように季節にかかわるものに限らず、むしろ一年中変わらない松や竹の緑の力に対する想念や、神が降りてくる依り代の松のごとく宗教信仰に支えられるものもある。唐草文様や鳳凰、鯉と鯛のように吉兆にかかわる例も少なくない。「参加者が宇宙の生命力の源や神々と結びつけられる」(247頁)のである。また、祝儀の贈り物をはじめ、お供えとしての四季の和菓子なども該当し、儀礼にも深く関わるし、一方で娯楽にも通ずる。生活に密着する「護符」としての自然という観点は見のがせないであろう。
さらには、「四季のイデオロギー」も重要な鍵語となっているが、著者はこの用語を特に「社会階層的な権力関係を強化するために四季の文化を用いること」(239頁)と定義する。これについて管見の範囲で附言しておくと、この用語を早くに指摘したのは、おそらく美術史の大西廣氏であり(1995年前後・絵本の会)、それを受けて小峯編『日本文学史』(吉川弘文館、二〇一四年)のⅥ「環境と文学」章の第2節で「四季のイデオロギー」と題して取り上げ、和歌と四季、四方四季、仏画などから検証している。『古今集』以下の勅撰集が四季の部立を第一にすえるのも四季の運行が天子の支配によるとの観念にもとづくわけだが、同時に私見では、権力関係にとどまらず、「四季は人の生活や共同体を左右する美学」として機能する概念ととらえ、より広義に用いている(『日本文学史』320頁)。
たとえば、著者もふれる四方四季に特徴的である。つとに『うつほ物語』『源氏物語』や『今昔物語集』など、平安時代の物語や説話集にうかがえ、中世以降のお伽草子などに特徴的で、昔話の口頭伝承にも及ぶ。ある面で日本の四季観を最も象徴すると思われる。東南西北と春夏秋冬の四季を結びつける発想はもともと中国からきているが、それが時間の循環ではなく、一度にすべて空間化して同時に眼前に現出するのが四方四季であり、物語趣向として欠かせないものになっていた。一種の理想郷の具現や吉兆の証しでもあり、『浦島太郎』の龍宮など異界の表象にもなっている。こうした四方四季こそ、人々の日常の中で無意識のうちに理想化されたイメージを象徴する、「四季のイデオロギー」の典型といえるだろう。
本書の認識の枠組みの基本は、二項対比の構図にある。野生の自然と「二次的自然」、都市と田舎(特に里山)、貴族と庶民(上層と下層)、それぞれに対応する文学ジャンルとしての和歌・連歌・王朝物語と説話・軍記・お伽草子、ハイカルチャーとポップカルチャー、優雅な美的風景と里山の実体風景といった二元の構図が随所にうかがえ、立論を明快にしている。ジャンルに関する見解は、『平家物語』などはその両面をそなえていることが指摘されてはいるが、やや図式化が過ぎる面も感じさせる。
本書で物足りない点は、随所にふれられる豊富な錦絵、浮世絵の例証に対し、具体的な図版の提示が少ないことだろう(図版は二章と七章のみ)。図版は資料としてのみならず、今や研究論文の表現媒体としても欠かせない。著者の提起するイメージが読者には共有できない憾みが残るのである。
最後の「日本語版へのあとがき」も重要な提言に満ちている。先ほどふれた自然の擬人化をめぐって、虫送りなどの動物供養の問題や海外との対比からみる畜産文化の差異などと関連づけており、今後の有益な展望といえる。そして今日の環境問題との関わりが説かれ、「自然や環境をめぐる日本文化の多彩な歴史を振り返ることが必要」(276頁)と強調する。著者は〈環境文学〉という用語を用いていないが、本書はまさに「二次的自然」を核とする〈環境文学〉論にほかならず、そのまま優れた日本文化論となっている。〈詩学としての環境文学論〉と言い換えてもよいだろう。
しかし、そうであればあるほど、著者もふれるように、本書の裏側から、世界規模に拡大してしまった新型コロナウィルス禍の現実が透けて見えてくる。四季の文化を創造してきた人々の営みの背後から、災害や疫病と常に闘い続けてきた人類の歴史文化が同時に問い直される。その意味でも今後は〈災害文学〉への視座がさらにもとめられるだろう。
災害に合わせて言えば、あとがきでふれる『方丈記』への短い読解が重要である。前半には人生のはかなさをはじめ、火災や地震など五大災厄の制御できない時間と空間が描かれ、後半は草庵の閑居という制御できる時間と空間が配される、いわば二重化した時空を見出す。後者こそ「二次的自然」の四季の文化であり、その先の浄土も合わせた時空間との間に人間を位置づけているとする。『方丈記』の仮構性をより際立たせる読みとして貴重な提言である。私見を加えれば、後者の閑居は一種の理想化された四方四季に近いと思われ、浄土への指向は「それとなく」ではなく、その閑居をも比定した先の阿弥陀に帰依する絶対的な境地としてあるだろう。『方丈記』はまさに〈環境文学〉の象徴的な古典でもあった。
地球温暖化への危惧が叫ばれて久しい。新聞記事(朝日・5月12日付)によれば、温暖化が今後も増長すれば、列島に桜が咲かなくなる時代が来ることが予想され、げんに品種によってはそういう事態が生まれつつあり、将来に備えて気温が上昇しても花が咲く品種を改良しているとのこと。四季の文化がいつしか架空の世界だけにならないよう、季節の解体や喪失が進まぬよう願うばかり。逆に本書はその警鐘となり続けるはずである。〈環境文学〉研究のあらたな地平を拓いた本書が、末永く読み継がれることを切に期待したいと思う。
▼ハルオ・シラネ『四季の創造 日本文化と自然観の系譜』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321812000852/