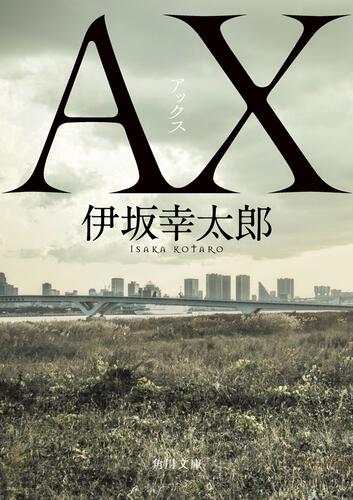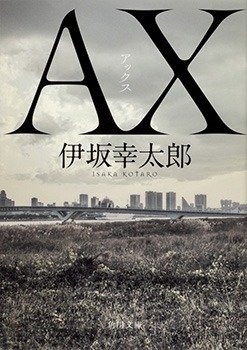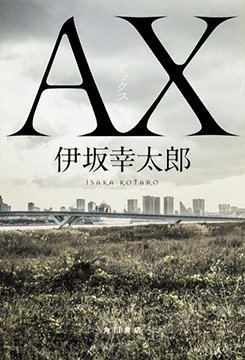伊坂幸太郎犯罪小説リブート完了。
二〇〇四年に発表された長篇『グラスホッパー』を読んだ際、この作者によって日本の犯罪小説は新たな局面を迎えることになる、と直感した。それから十三年が経ち、新作『AX』によって当時の思いは現実のものとなった。ただし、ちょっと予想とは違う形で。
『グラスホッパー』、『マリアビートル』(二〇一〇年)、そして『AX』と続く連作は、一口に言えば殺し屋小説である。社会の片隅に、誰かの命を奪うことで生計を立てている特殊な職業人が棲息している。その異質な存在に触れてしまった一般人が味わう驚きや恐怖を描いたのが前二作であった。体温が感じられないような徹底した冷ややかさ、あるいは砂漠に転がっている石の表面を思わせる乾いた手触りは、伊坂が得意とする武器である。そうした筆致が貫かれた物語は、恐怖を転じさせた笑いを誘う。その感覚が楽しかったのである。
『AX』も基本的にはユーモラスな小説だ。他の作品に登場する鯨や槿
といった殺し屋たちと同様、本作の主人公も兜という業界内の通り名を持っている。彼が他の殺し屋と違うのは、家庭生活が描かれる点である。妻を異常なほど恐れていて、彼女を怒らせないことが兜の生活における第一方針となっている。たとえば深夜に帰宅した際は絶対にドアの開け閉めの音をさせないし、台所をごそごそやるなど論外だから、夜食には音をさせずに噛むことのできる魚肉ソーセージを選択する。そんな彼が、一人息子の進路相談と殺人依頼のスケジュールが重なってしまったために、大慌てで仕事を片付けて帳尻を合わせて妻を怒らせないようにする、というのが巻頭に置かれた表題作である。
続く「BEE」も同じ路線で、スズメバチと呼ばれる同業者から命を狙われ出した兜に、別の悩みができる。自宅近くにスズメバチが巣を作ったのである。殺し屋よりも蜂の巣、というかそれがあることによる妻の怒りのほうが怖い、という奇妙な価値基準が笑いを誘う仕掛けになっている。伊坂作品にはやたらと心配性だったり、陰謀論に怯えたりする人物がよく登場するが、兜もその仲間である。そうした人物が実は腕利きの殺し屋だ、というのがたまらなくおかしいのである。読者によっては故・藤田まことが演じた同心兼殺し屋の剣豪・中村主水を連想する人もいるかもしれない。私は、本書が連作形式であることや、日常生活と殺人場面の非日常とがなめらかに連続して描かれることなどから、ローレンス・ブロックが『殺し屋』(二見文庫)で登場させたプロの殺人者・ケラーの姿が重なって見えた。つまり、いつもは間抜けで、ときどきドキリとするほど冷たい顔をする男の話なのだ。
それが三つめの「Crayon」から微妙に転調し始める。兜が自分と同じような恐妻家と出会って親しくなるという内容なのだが、ここから彼の内面に読者が注目したくなるような文章が増えていく。続く「EXIT」は『重力ピエロ』『オー!ファーザー』などの過去作と同路線の、父子関係を主軸とする話である(ついでに書いておくと、密室内の戦闘を扱ったくだりは伊坂作品屈指の緊迫感がある名場面だ)。ここで『グラスホッパー』に始まる硬くて暗い物語の路線が、『チルドレン』などの情愛を描いた作品の系譜と合流する。ひんやりと冷たいのにしばらく手に取っていればほんのりとした温度を感じるようになる。そんな不思議な小説は、あまりよそで読んだことがない。伊坂の完全なオリジナルである。
以前の殺し屋小説では三人称多視点が採用されていたが、本作では兜が視点人物としてほぼ固定されている。その理由は最後の「FINE」で判明するのである。出会い頭の衝突事故を思わせる終盤の展開については、ここでは書かない。ミステリーにおける驚きはしばしば狂おしい感情の動きを誘う。そうしたたぐいの小説である。殺し屋に心を射止められた。
レビュー
紹介した書籍
-
試し読み
-
特集
-
特集
-
特集
-
特集