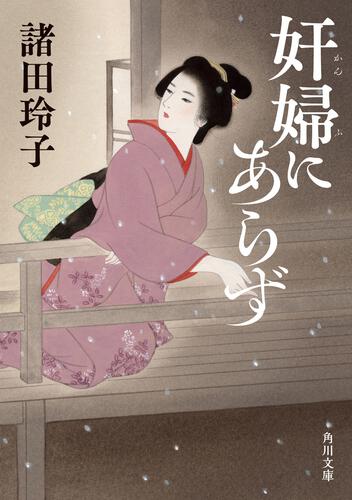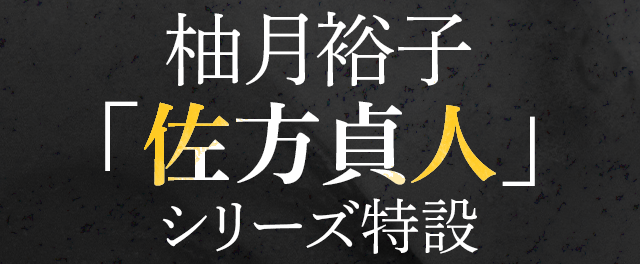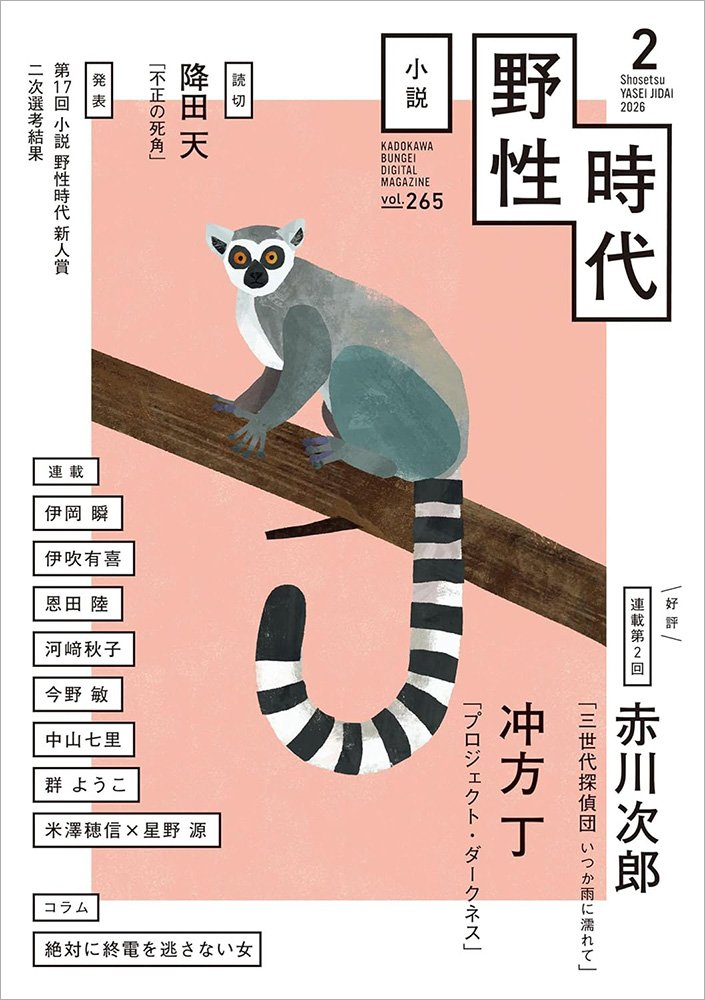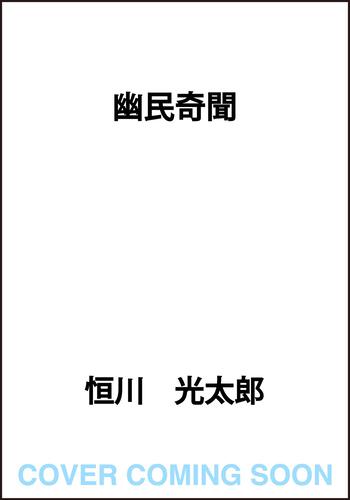角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
『奸婦にあらず』諸田玲子 文庫巻末解説
解説
松本 侑子(作家・翻訳家)
諸田玲子氏は、人気の時代小説家である。四季おりおりの江戸の市井にくらす人々、なかでも粋な女たちの想い、その笑い声やすすり泣き、煮炊きをする物音や下駄の足音まで聞こえるような情緒ゆたかな物語をつむぎだす名手である。
と同時に、あまたの歴史資料を調査し、ゆかりの地を訪れたうえで、今までにない新しい視点による創作、大胆な仮説や推理を史実にもりこみ、たしかな筆力で骨太の文芸作品をつくりだす歴史小説家でもある。その才能と努力の結晶のひとつが、本作『奸婦にあらず』、第二十六回新田次郎文学賞受賞作である。
井伊直弼(一八一五~六○)といえば、開国をすすめた幕末の大老であり、それに反対する攘夷派の志士や公家を大粛清した「安政の大獄」で反感を買い、桜田門外で水戸・薩摩の浪士に暗殺された人物として知られる。
吉田松陰らを死罪にした強硬な弾圧や、いまに残る肖像画の顔つきなどから、直弼には、徳川幕府に逆らう者を容赦なく処刑する冷徹非情な男、将軍家の威光を重んじる保守的で老獪な男、といったイメージがつきまとう。
村山たか(一八○九~七六)については、私はかつて幕末小説『島燃ゆ 隠岐騒動』を書いたとき、直弼の恋人だった彼女が悪人として捕らえられ、みやこの三条大橋で生き晒しになった絵図を見たことがあった。色白のおもざしに、そこはかとなく漂う色香が印象に残ったが、本作を読むまで、くわしい人となりは知らなかった。
『奸婦にあらず』は、そのたかと直弼の熱い恋から始まる。
二人が出会ったとき、直弼はまだ二十二歳。彦根藩主の十四男として生まれ、兄や弟は、格式ある家の養子になったが、彼は捨て扶持をあてがわれ、埋木舎とみずから名づけた屋敷にすまい、お役目もないまま、国学や儒学、茶道、和歌、禅、焼物の教養をふかめ、剣術をきたえる。大老の直弼とは別人のような、初々しく風雅な貴公子を、著者は生き生きと描きだす。
一方のたかは女ざかりの二十八歳。江戸時代までの神仏習合の多賀大社において、高僧を父に、巫女を母に生まれる。本作での多賀大社は、井伊家、幕府、朝廷に密使をおくりこんで情報をあつめ、それをふるい分けて、また各所に伝えることで立場を守っているとされる。そんな大社に生まれたたかは、密偵となるべく、忍びの訓練をうけて育ち、和歌、歌舞音曲、男心を虜にする閨の術まで教えこまれたと著者は描く。魅惑の女密使たかは、直弼に近づき、井伊家の内情を聞きだすはずが、二人は恋におちる。
本作のはじまりは、「後朝」。これは男女がたがいの衣をかけて一夜を共寝し、明くる朝、別れるときに身につける着物、または後ろ髪ひかれる暁の別れをさすみやびな言葉である。著者は、二人が恋をかわす場面を艶めかしく描き、たがいに惚れあう心と体の歓び、絆と信頼が深まっていく歳月を、小説の前半でていねいにつたえる。
このように彦根の埋木舎で、文武の鍛錬、たかとの逢瀬に暮らしていた直弼が、宿命のさだめに導かれるように彦根藩主となり、江戸に住まい、幕府の大老となる。そこへペリーひきいる米国艦隊が浦賀に来航すると、ご存知のように、日本は開国へ舵を切る幕府側と、夷狄排斥をうったえる攘夷派の真っ二つに分かれ、そこに将軍の継嗣をめぐる分裂もからんで、対立は激化していく。
たかは密偵として御所の後宮に入りこみ、攘夷派の動きを探り、同志に伝える。同志とは、美男の国学者にして、やはり密偵である長野主膳である。直弼、主膳、たかの三人は、和歌の師弟であり、かつ佐幕の志で結ばれている。この三人がたどる幕末の波乱を本作でじっくり読まれたい。
以前、諸田氏から、本作についてうかがったことがある。私が企画と司会をつとめた文学トークショー「作家が自作を語る」(日本ペンクラブ主催、二○一九年)にご出演いただいたとき、諸田氏は、ご自身の歴史小説『今ひとたびの、和泉式部』について語られ、次のようなお話をなさった。
「 ……平安時代の歌人、和泉式部もそうだが、歴史に残る女性たちが、小説にどう描かれているのか、そこに長い間、疑問を感じてきた。私は、井伊直弼の恋人だった村山たかの小説『奸婦にあらず』を書いたことがある。直弼は〈安政の大獄〉で大勢を処刑した悪いイメージがあり、たかも悪女とされてきた。しかし私は、直弼の位牌を守りぬいた彼女には、純真で、情深い一面があったと考えて小説化した……」
本作のたかは、まさに純真で、情深い。思いが深く、しかし腹黒いところがない。直弼と別れてもなお、彼を守るために、直弼に敵対する者たちの情報をあつめる。そのために尊攘派からは悪女とされたのだ。
本作は、奸物ではない直弼とたかの人間像の見直しであり、歴史の見直しでもある。
従来、幕府は、外圧に押され、不平等な条約を結んだ無能の弱腰とされてきた。しかし近年の研究によれば、幕府は、米国艦隊の来航を一年前にオランダより伝えられ、国際法や条約について準備している。大国である清国が、イギリスと戦って負け、半植民地化されたアヘン戦争(一八四○~四二)の失敗も知っている。そこで直弼は、米国と対決するのではなく、まずは国をひらき、文明の進んだ西洋列強に学んで国力を高めてから、また鎖国もできようと考えていたようだ。幕府は、争うことなく平和裏に、無血で港をひらき、ほかのアジア諸国のように植民地化されることもなかったのである。
幕府を倒した新政府は、明治になると、積極的に開国をすすめ、諸国と条約をむすぶ。異国を排斥せよ、と叫んだ攘夷は、いったい何だったのか……。そして明治四年には、公家の岩倉具視らが欧米視察に旅立っていく。
こうした時流の変化をくぐりぬけ、小さな寺の尼となったたかは明治まで生き延びた。亡き人々を供養しつつ、政府の変節を見とどけたたかは、争いのむなしさを悟ったのではないだろうか。だからこそ著者は、最後に、佐幕派だったたかと、尊攘派だった紅蘭との温かな邂逅を描いて、筆を置いたのであろう。
本作を読んで、私は彦根を旅したような気持ちになった。彦根城から見はらす琵琶湖は砂金を撒いたように夕陽に輝き、直弼とたかが忍び会った天寧寺の眼下には城下町が広がる。美しい近江とみやこの風景のなか、息子の帯刀、また泰造、昌造、源左衛門と、たかをそばで見守った男たちの真心が胸をうつ。幕末の激流を生きた二人の生涯、結ばれなかった若き日の恋、幕府への忠義と誠を描いたこの名作が、角川文庫から再版される幸いを慶びたい。
追記
本作が二○○六年に単行本として刊行された後、直弼がたかに宛てた恋文が、京都市の井伊美術館で発見されたと「京都新聞」(二○一二年二月十三日付)が報じている。その文には、直弼の和歌が書かれていた。
名もたかき 今宵の月は みちながら 君しをらねハ 事かけて見ゆ
名高い中秋の名月よ、今宵の月は満ちているが、君がいなければ、その月も欠けて見え、わたしの心も物足りなく思われる……と読もうか。たかとの恋を藩に反対されていた直弼二十七歳ごろの歌で、「たか」の名前が入っている。たかはどんなに嬉しかったろう。直弼がいかに彼女を想っていたか、若者の心が愛おしい。
作品紹介
奸婦にあらず
著者 諸田 玲子
密偵として生きた女性の激動の人生を描く、第26回新田次郎賞受賞作!
その美貌と聡明さを武器に、忍びとして活躍する村山たかは、ある時、内情を探るために近づいた井伊直弼と激しい恋に落ちる。だが、苛酷な運命が二人に襲いかかって……。著者の代表作が新装版で登場!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322104000326/
amazonページはこちら