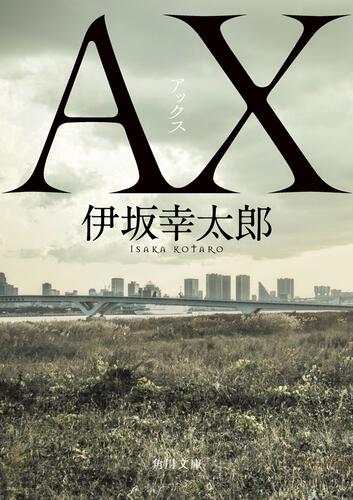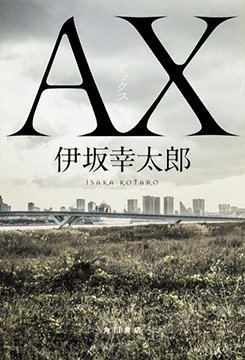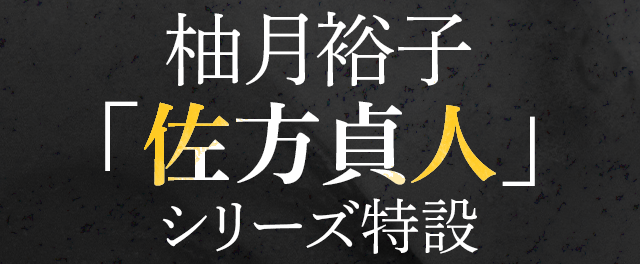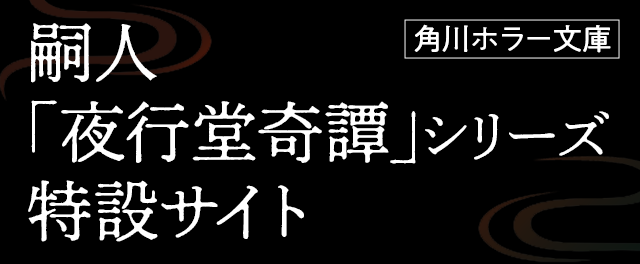恐妻の顔色を常に気にする、気弱な父親の裏の顔は「殺し屋」だった。
「兜」は暗殺のプロだ。冷静に「殺人」という仕事を全うする。一方、家庭では、物音一つ立てるのも気を遣い、何を言うにしても妻の顔色をうかがうような、気弱な男だ。また、家族を心から愛し、仕事と家族サービスとを天秤にかけ悩んでいる、どこにでも存在する父親なのである。
そんな普通の父親たる兜を、プロの殺人家にする一つ特徴があった。それが思い込みの強さだ。「暗殺の相手はきっと悪者」と思うことができるのだ。
そんな兜にも、多くの人を殺(あや)めてきたことに対する良心の呵責を感じることがある。また、暗殺業を辞めたいが後任が現れないことへの不満やいらだちを感じている。
そんな中、ある男との出会いが、暗殺業を辞める決定的なきっかけとなるのであった。
暗殺を仕事とする人物が出てくる作品や、殺人犯を主人公にした小説は数多くあるが、ここまで怖さや悪さといった闇の部分のない、人間味あふれる殺し屋はいただろうか!!
主人公の兜は、いかにも人間らしい悩みを持っている。妻帯者の多くが抱く感情の最たるもの、妻への怯えだ。
殺人を悠々とこなすようなプロの殺し屋が、一度家に戻れば妻に気を遣ってばかりいる。このような生活を送っているのは、誰かに脅されて強制されているわけではなく、愛する妻との関係を保つために、自らが進んで怯える生活を選んでいるのだ。「いかに妻の機嫌を損ねないか」に注力したやり取りを読んでいるだけで、結婚生活の大変さを思い知る。
さらに興味深いのは、兜は二面性を上手く使って日常と仕事を分けているのではなく、常に妻の存在に怯えているのだ。暗殺家としてターゲットと向き合っているときでさえ、妻の存在が頭にちらついてしまう。妻から電話がかかってこようものなら、出ることができない言い訳まで考えるという徹底ぶりも、同じ男性として非常に愛らしさを感じる。
プロの暗殺家と、恐妻に怯える夫。一見かけ離れたイメージを持つ2つの顔が、同じ人格によってストーリーを成す様が、魅力的に描かれている。また、妻だけではなく、息子との会話に出てくる兜のポリシーは、暗殺の場面においても通ずるポリシーでもある。こちらは本作を読んでご確認いただきたい。
家や会社といったさまざまな場面で私たちは、その時々に応じた顔を使い分けているが、兜はどんな場面でも同じ顔。使い分けていないのだ。
自分たちのまわりにもいそうな愛しき不器用さ、そして家庭でも仕事でも言動が統一されていることで、より兜というキャラクターに共感するだろう。それが暗殺者と恐妻家という両極端の属性であるからこそ、一層興味深く感じるものがある。