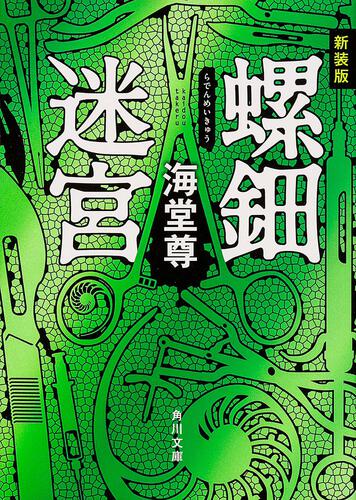医療と司法の正義を問う、リーガル×メディカル・エンタテインメント!
本日7/31(水)発売、海堂尊さん・著『氷獄』より、表題作の試し読みを特別公開。
『チーム・バチスタの栄光』のその後を描いた、待望のシリーズ最新作をお楽しみください。
氷獄 2019年 春
01 正義 2019年4月某日 都内某所
私が貧乏くじを引き続けるような人生を歩むことは、父が名前を付けた時に決まっていた。
日高正義。父は何を考えていたのか。正義だなんて窮屈すぎてちっとも魅力がない。そんな名のせいで小学校の頃から優等生を演じ、学級委員とかを引き受けさせられた。
今思い出しても、級友や先生に都合良く使われていた気がする。
自分の名前が大嫌いだった。どうせなら正義よりも勝利の方がよかったのに、と思った。幼くして母を亡くした私は、男手ひとつで育てられた。父は仕事と子育てを両立させていたがある日、空き巣に入られ全財産を盗まれた。悪いことは重なるもので、叔父が事業に失敗して失踪し、連帯保証人の父は借金をかぶった。私が中学生の頃だ。
空き巣は半年後に捕まり、有罪になったと警察から報告があった。盗まれた財産が戻ってくれば借金も返せてやり直せる、と父は喜んだ。だがそうならなかった。犯罪者が捕まるのと盗んだものが返ってくるのは別で、取り戻したければ民事裁判に訴えるしかない。だが裁判で勝っても泥棒をやるような不届き者に資財があるはずもなく、返そうという誠意もないからムダだと忠告され、心底驚いた。盗んだものを返す義務がないのなら、窃盗で三年服役してもペイするではないか。そんな法体系が泥棒稼業を成立させているのだ、と私は思った。
この世には正義なんてない、と思い知らされた。
叔父の借金を返すため無理をした父は、私の大学合格を見届けた直後に亡くなった。天涯孤独になった私は苦学生になり、奨学金とバイトで何とか大学を卒業し大手メーカーに入社した。当時一九八五年のプラザ合意で誘導された狂瀾怒濤のバブル景気は、一九九〇年三月に大蔵省が通達した総量規制によって衰退しつつあったが、まだバブルは崩壊しておらず、就職戦線は売り手市場だった。入社後、二年ほど製造ラインや営業を経験した後で配属されたのは、今でいうコンプライアンス部門だった。当時そんな用語はなかったが、カスタマーのクレームを収めたりなだめたり誤魔化したりする部署で、対応は担当者の裁量に任されていた。こういうと権限がありそうに聞こえるが何のことはない、うまくやり過ごして当たり前、問題をこじらせたら担当者の責任という、やり甲斐のない業務だ。これも貧乏くじの一種だろう。
私は入れ替わりの激しい部署でうまくやっていた。普通半年も勤務すると自律神経失調症や出社拒否になるが、私は自分の名のおかげで得をした。クレーマーも私が名乗ると鼻白んだ。こういう仕事は最初の一歩が肝心で、そこで主導権が取れればラクになる。
その部署には八年近く勤め、そろそろ転属が近いと言われた頃、私は致命的なドジをした。
人がいいだけの父に植え付けられた中途半端な正義感のせいで、利益第一主義の上役と衝突してしまったのだ。顧客に頭を下げるのは多少理不尽でも我慢できるが、上役の些細な不正は見過ごせなかった。
どう考えても逆にすべきだった。こうしたことも自分の名前が影響していたのだろう。
私が甘かったのは、勤続十年の中堅になったその頃も、最後は正義が勝つなどという青臭いことを信じていたことだ。現実は、人の防衛本能の方が社会正義より強い。そうした現実を認識したのは会社から自己都合での退職を押しつけられた後だ。
もともと理不尽な目に遭って家庭が崩壊したというのに、何たるお人好しだったのだろう。
やはり、ここでも正義なんてなかった。
二〇〇三年の暮れ、十年勤めた会社を辞めた。辞める時はあっという間で三十三歳のクリスマス・イブは無職で過ごした。辞める寸前、会社に対し、不当解雇で闘ってみようか、とちらりと考えたが、結局しなかった。自分自身のため権利を振りかざすのは、正義とほど遠い、と感じたからだった。加えて当時の私は結婚もしていなかった。だから会社を辞め、更に身軽になるのは魅力的に見えた。
父の相続を放棄したため借金は消え、酒や女にも溺れず業務に励んでいたので貯金もあった。
独身の身なら失業保険があれば二、三年は食いつなげる。だがその間に次の就職先を見つけないと大変だ、という危機感くらいはさすがに持ち合わせていた。
職探しをしていた私の目に飛び込んできたのが新司法試験制度の記事だった。法科大学院の卒業者の八割を司法試験に合格できるようにすべしという政府の諮問で日弁連もPRした。
これだ、と思った。
国立大の法学部を卒業した私は法学既修者で、法科大学院は二年で卒業でき法務博士という学位と司法試験の受験資格を得られる。学費は二百万掛かるが貯蓄はあるし、業務上、六法全書はあらかた理解していたので有利なスタートを切れる。何より私は勉強が得意で、特に暗記には自信があった。五年以内に三回までの受験で合格しなければ失格するというリミット、いわゆる三振ルールはプレッシャーにならず、私は司法試験に一発で合格した。
二〇〇六年司法試験の合格率は四十八パーセントでほぼ五割だった。その年に合格できたのは私にしては珍しくラッキーだった。一年間の司法修習は和光の司法研修所で座学を行ない、司法研修所の卒業試験、所謂二回試験にも悠々合格して晴れて弁護士バッジを手にした。
この試験を二回試験と呼ぶのは一回目が司法試験だからだ。試験は難しいが落第者は毎年一名とか二名しかいない。こちらは逆にプレッシャーだった。
関連試験を一発で合格できたことで、これが私の天職だと思ったし、これでツキのない人生から解放されたと舞い上がった。だがそれは三十七歳の苦労人の大いなる勘違いだった。
その後法科大学院は凋落し、司法試験の合格率が低い学校は淘汰され、私の母校も数年後になくなった。それは国のグランドデザインが粗悪だったせいだ。弁護士を増やせというアメリカナイズされた思想にかぶれた法曹界の一派ががむしゃらに推進したおかげで、確かに弁護士は増えた。だが弁護士が扱う事件や訴訟は思うように増えず横ばい状態だった。それなら過当競争になるのは、小学生にもわかる理屈だ。こうなると国家的な資格詐欺だと思うが、誰も声を上げない。囲われた牧場に追い込まれた羊は、牧草地が貧しくても、そこで生き存えることに必死になるだけだ。
>>第 2 回へ
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
ご購入はこちら▷海堂尊『氷獄』| KADOKAWA