すべてが鮮やか、すべてが心に残る——杉江松恋の新鋭作家ハンティング『残月記』
杉江松恋の新鋭作家ハンティング
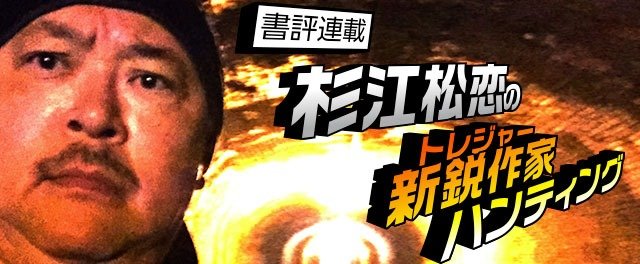
『残月記』書評
書評家・杉江松恋が新鋭作家の注目作をピックアップ。
今回は、作家業12年目にして著者3冊目の作品。
月影によってのみ照らし出すことが可能な陰の世界。
小田雅久仁『残月記』(双葉社)に描かれているのはそうした情景である。
三篇を収めた幻想小説集で、月が共通項になっている。一人の男が突如として人生からはじき出される「そして月がふりかえる」、叔母が遺した石が主人公に奇妙な夢を見せる「月景石」、
小田をこの連載で取り上げることに異議を唱えられる方もいるだろう。二〇〇九年に『増大派に告ぐ』で第二十一回日本ファンタジーノベル大賞を獲得してデビュー。すでに十年以上の筆歴がある作家だからだ。その受賞作は、ひずんだ物の見方と価値基準を持つ男を主人公に据えることにより、人間の抱えるルサンチマンを具現化することに成功した、見事な観念小説であった。
小田の名を一躍有名にしたのは、二〇一二年に発表した第二作『本にだって雄と雌があります』である。同作で描かれたのは、書棚で生物のように自己増殖していく本という、愛書家ならば誰もが一度は妄想したことがある題材だ。その現象を軸として、ある家族の系譜が描かれていく。そこから九年間、読者が熱望したにもかかわらず、小田の著書は刊行されなかったのである。なんとこれが作家業十二年目の第三長篇だ。「どんな作家でも三冊目の著書まで」という〈新鋭作家ハンティング〉が始まるのを待ってくれていたのか、と妄想したくなる。
三篇に共通するのは寂しさ、と書いた。どの作品にも絶望の瞬間が訪れる。人間の存在は小さく、どうしても覆すことができない運命というものがある。三篇それぞれで絶望の種類は違う。
「そして月がふりかえる」は自分の人生に裏切られた男が時間の流れの重さを知る。どんな人間でも歴史の流れの中で生きている。普段は意識しないが、歴史の流れこそが自分自身を作り上げてきたものなのである。月の絡んだ異常な現象が起き、大槻高志はそこからはじき出される。そこから彼がとる行動を綴った部分は、犯罪小説としても秀逸だ。決して他人とは共有できない動機によって、許されない行動を高志はとる。未解決のある有名な事件を思い出して、私は戦慄しながらページをめくった。すべてを理解したときに綴られる「けっして手に入らず、すれ違うことだけがゆるされた何かが、終わった気がした」の一行が主人公の到達した諦念を的確に表している。この小説の恐ろしい点は、高志が自分の人生から出て行かざるを得なくなるという異常極まりない瞬間と、絶望の底に到着した者だけが見るであろう彼岸の情景とを、現実としか思えない筆致で描き出していることである。
続く「月景石」の展開を書いてしまうと読者の驚きを減じてしまいかねないので控えておきたい。カットバックの手法を用いることにより作者は、主人公がすることになる往還の、気の遠くなるような距離を読者に認識させることに成功している。ここでの絶望とはつまり、遠さなのだ。この手にかき抱きたい人は、あまりにも遠い場所にいる。そのことを知らされたときに主人公を襲うであろう眩暈の感覚が、本作の読みどころのはずだ。冒頭に書いたような石を巡る奇譚と見えた話が、ある一点でまったく違った物語へと変じるという驚きが本作にはある。そこから描かれていく奇想の場面には、登場人物たちを待ち受ける運命の残酷さに胸が張り裂ける思いがするものの、一方で興奮を覚えざるをえない。世界の姿があまりにこの現実とかけ離れているからだ。どこか遠いところに読者を誘うのが幻想小説の役割だとすれば、これほどその名にふさわしい物語はないだろう。ちぎれて引き離されたはずの世界が再び一つになる結末は、予想をはるかに超える規模の大きさであり、宗教的な荘厳さえも感じる。
そして表題作である。これは社会と人間の関係を描いた小説だ。社会の強大さの前には、人間は蟻のように小さい存在となる。残月という雅号によって知られることになった男の生涯を描いた、列伝小説である。舞台となるのは今から数十年後の日本、西日本を襲った大震災によって一千万人超の犠牲者が出てしまう。壊滅的な打撃を受けた日本の人々は、国を救う道を知っていると称する男・下條拓の率いる救国党に運命を委ねるのである。下條は経済成長と引き換えに警察国家体制を作り上げ、思想統制と暴力による弾圧を日常のものとした。
本作には歴史改変小説の要素がある。不治の病である月昂という病がこの作品独自の設定だ。月昂に感染した者は、月齢の中で頭脳が明晰になり身体機能が最高潮に達する明月期を迎えるが、新月の夜に昏冥期に入ると、眠りについたまま百人に三人が死を迎える。治療不可能な死病なのだ。これへの感染を防ぐために政府は、月昂者たちを発見次第逮捕し、終生隔離することを選んだ。残月こと宇野冬芽は、この月昂者なのである。明月期に抑えがたい性欲を感じた彼は風俗店に足を運んでしまい、そのために逮捕される。
物語の大半で冬芽は収容所に囚われている。本書は収容所小説の性格を帯びているのだ。日本にはかつて間違った医学知識によって感染病患者を隔離施設に送り込んだり、優生保護法に基づいて許されない処置を送ってきたりした過去がある。その歴史が月昂病には重ね合わされるのだ。そうした意味では医療小説でもある。施設に送られた冬芽は、ある提案をされる。独裁者である下條拓は、不可視領域に追いやった月昂者たちを使って、ある非人道的な遊戯に耽っていたのである。未来へのわずかな望みをちらつかせることで、人間を意のままに操ろうというわけだ。他に選択肢のない冬芽はその提案を受け、瑠香という女性と出会う。この冬芽と瑠香の関係は実に美しい。恋愛小説としても秀抜である。
もう一つ胸躍る要素があるのだが、それは読んでのお楽しみである。作者はスリラーのプロットを用いて、冬芽を大きな動乱の最中へと連れ出していく。中盤からの展開の速いこと、速いこと。もうすでに要素は出揃ったと思っても意外極まりない幻景を突きつけられる。少しも先の読めない展開であり、圧倒的な想像力が結末まであっという間に読者を連れて行ってくれる。そして、こんなに救いのないディストピア小説なのに、驚くほどに穏やかな場面が結末には描かれるのである。ここに読者を誘うために物語を書いたのか、と喝采したくなるほどだ。
小田雅久仁に見せられる情景のすべてが鮮やかであり、すべてが心に残る。小説を読む楽しみを存分に味わわせてくれる一冊であり、これ以上の予備知識は入れずに本を手に取るべきであろうと思う。
主人公たちの運命を知る月はどれも残酷に見えるが、「残月記」には心の寂寥を埋めてくれる優しい月が描かれる。物語終盤、「荒涼たる冬枯れの森のなかで、張りめぐらされた枝越しに」冬芽が見ているかもしれないと書かれる月がそれだ。切なくなるほど美しい。























