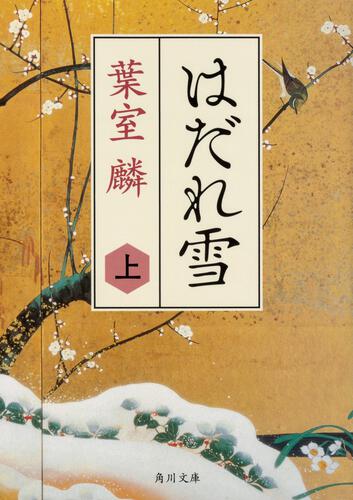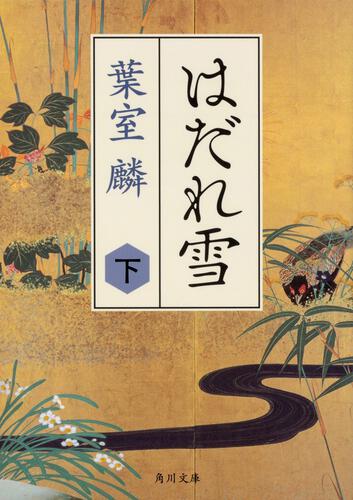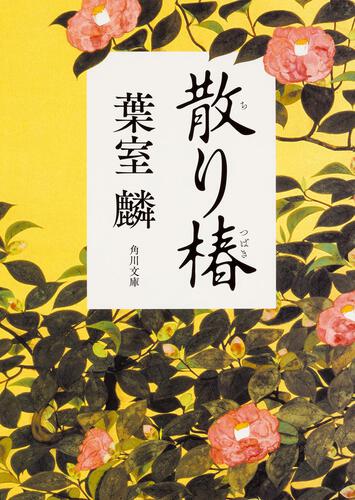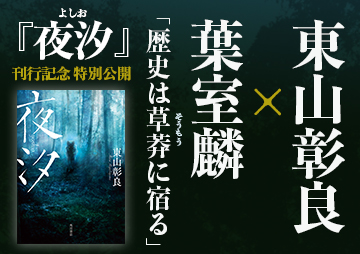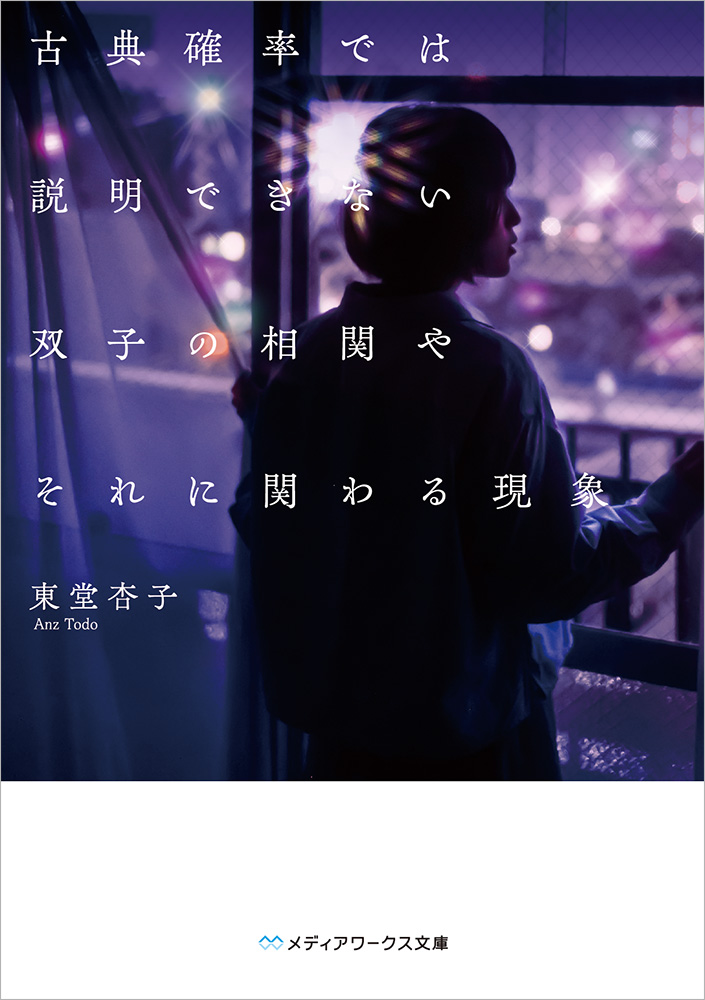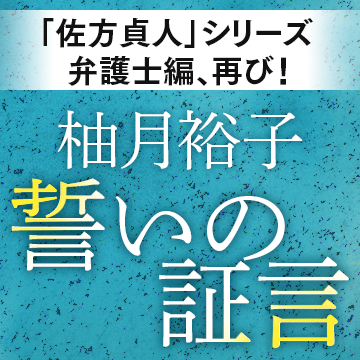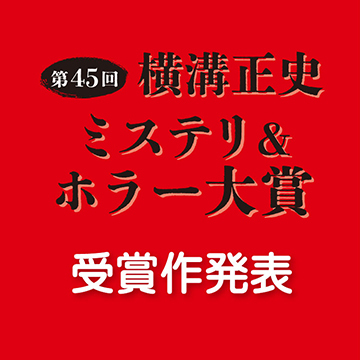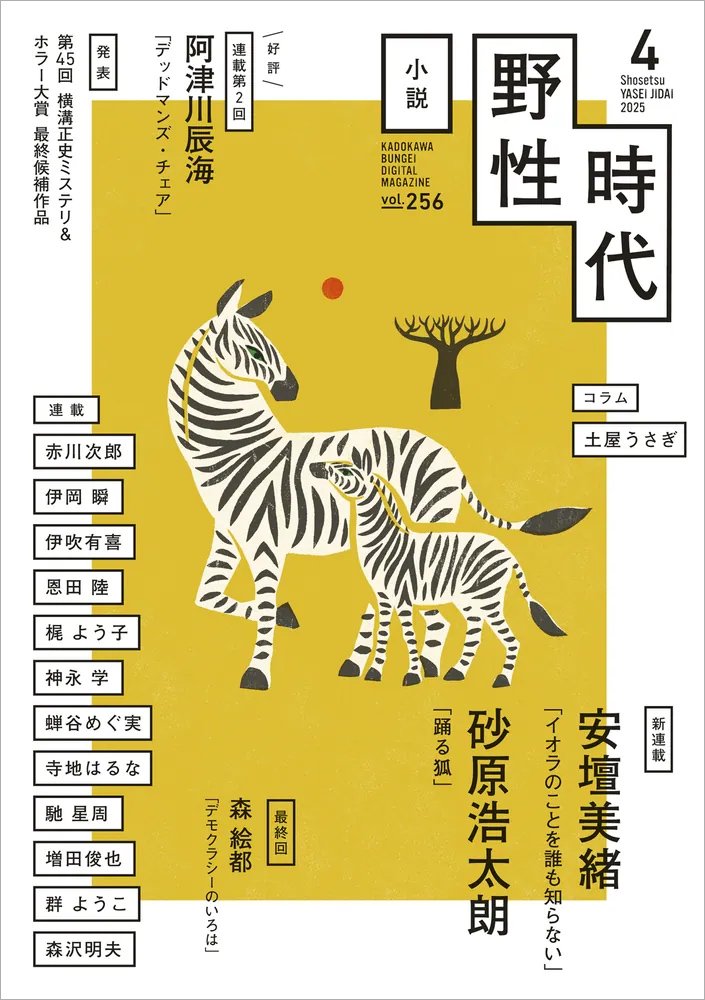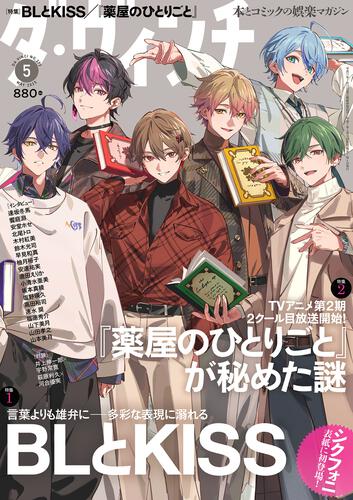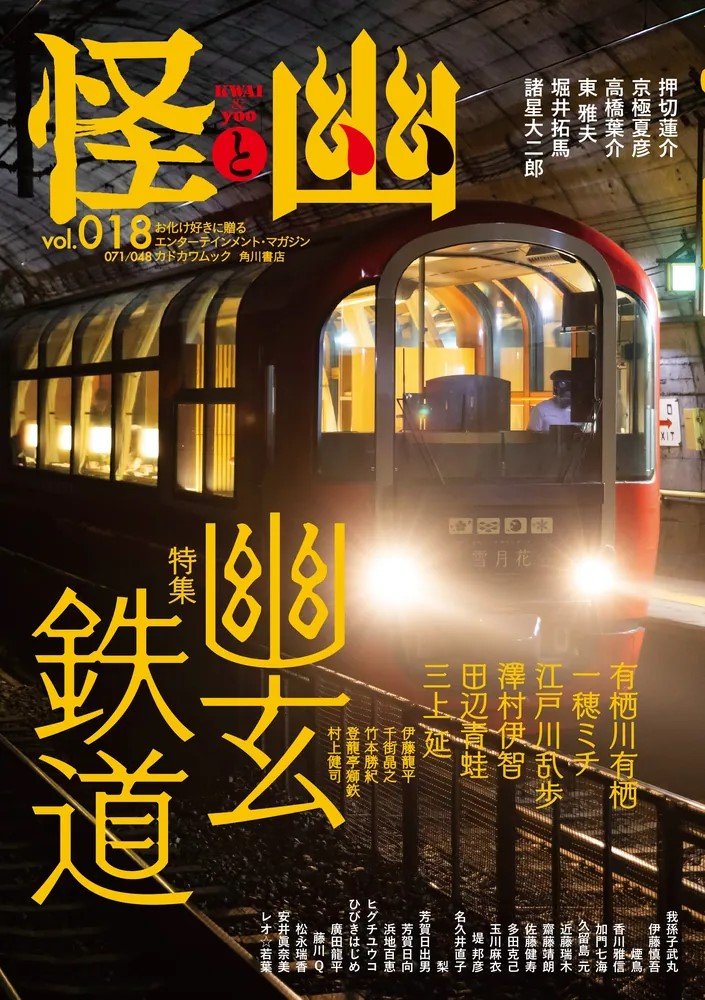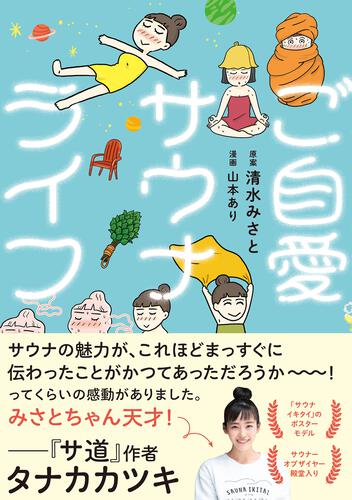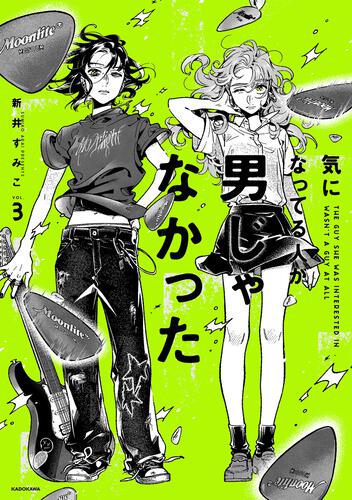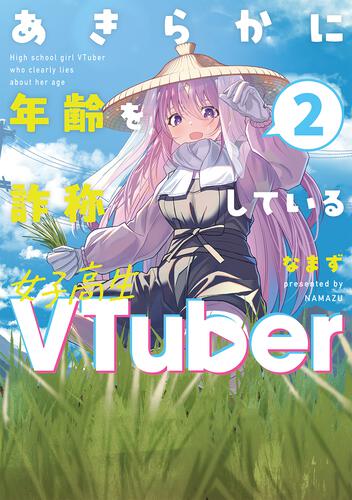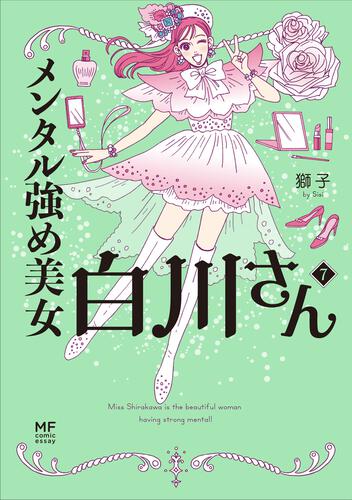二〇一七年十二月二十三日、歴史時代小説の名手だった葉室麟さんが亡くなられた。享年六十六という、あまりに早すぎる死だった。五十四歳の時に短編「乾山晩愁」で第二十九回歴史文学賞を受賞してデビューした葉室さんは、『銀漢の賦』で第十四回松本清張賞を、『蜩ノ記』で第一四六回直木賞を受賞するなど、驚異的なペースで、高いクオリティの作品を発表していった。葉室さんの数多い名作の中でも中核をなしていたのが、架空の藩・扇野藩を舞台にした一連の作品である。
時代背景も主人公も異なる扇野藩ものは、上司の不正を訴えるも認められず藩を追われ妻と京で隠棲していた瓜生新兵衛が、病で死んだ妻の最期の言葉に従って故郷に帰り、不正の真相と亡き妻の真意を探ろうとする『散り椿』、藩の重臣・有川家の長女で弓が得意な伊也が、藩随一の弓上手の樋口清四郎と競い合ううちに惹かれていくが、清四郎に妹との縁談が持ち上がったことで心が揺れ、藩の派閥抗争にも巻き込まれていく『さわらびの譜』と書き継がれていった。扇野藩ものの三作目となる本書『はだれ雪』は忠臣蔵の外伝にもなっているので、忠臣蔵ファンも満足できるだろう。
葉室さんは、牢人の雨宮蔵人と妻の咲弥を主人公に、忠臣蔵の背後にあった朝廷、幕府、大奥の確執を浮かび上がらせた忠臣蔵外伝の『花や散るらん』を発表しているので、扇野藩ものにして忠臣蔵ものでもある本書は、葉室さんの持ち味が一冊で楽しめる贅沢な作品といっても過言ではあるまい。
元禄十四年。江戸城内で、赤穂藩主の浅野内匠頭が、高家の吉良上野介へ刃傷に及んだ。五代将軍徳川綱吉の信頼が厚い側用人の柳沢吉保は、原因を究明しないまま内匠頭を切腹させた。と、ここまでは誰もが知る有名な史実だが、葉室さんはその先に、刃傷が起きた経緯がはっきりするまで切腹を見合わせるべきと考え、それを老中の稲葉正通を通して吉保に進言した旗本がいたとのフィクションを織り込んでいく。この旗本こそ、本書の主人公・永井勘解由である。
自分の提言が退けられた勘解由は、秘かに内匠頭が預けられている田村右京大夫の屋敷を訪ね、切腹を前に一室に閉じこめられていた内匠頭と言葉を交わした。それを知った綱吉は機嫌を損ね、勘解由をお役御免にして、扇野藩へのお預けとした。
困ったのは、実質的に流罪となった勘解由の面倒を見ることを命じられた扇野藩である。勘解由は幕閣の中枢に返り咲く可能性があるので粗略に扱えないが、綱吉の勘気が続いた場合、罪人をもてなしたとして幕府の心証が悪くなる。何より、内匠頭の仇討ちをするとの噂がある旧赤穂藩士が、主君の最期の言葉を聞こうと勘解由に接近してきた時は、どう対処すべきなのか? 頭を悩ませた藩首脳は、勘解由の屋敷として藩主が鷹狩に出たおりの休憩所をあてがい、結婚して三年たつも子供ができず、夫が不名誉な死を遂げ実家に戻っていた紗英を接待役にすることを決める。琴が得意な紗英は、風雅の道に長け龍笛を吹くという勘解由の人柄に想いを寄せる。その一方で、藩首脳は若くして妻を亡くした勘解由が、紗英に手を付けることを期待していた。
様々な思惑が錯綜するなか、護送役の佐治弥九郎に連れられた勘解由が到着する。当初は紗英の世話を固辞した勘解由だが、お互いにどこにも居場所がない身だと分かると好意を受けることにする。その折りに勘解由が口にしたのが、遠江の武士で歌人の藤原(勝間田)長清が編纂した『夫木和歌抄』に収録され、タイトルの由来にもなった「はだれ雪あだにもあらで消えぬめり世にふるごとやもの憂かるらん」である。
日本には、古い歌の一部、またはすべてを引用して自分の心情を代弁する「引歌」という技法がある。勘解由が行ったのも「引歌」である。このほかにも作中には、『源氏物語』や『平家物語』の逸話やそれに関係する詩歌、赤穂藩士が残した和歌や俳諧が自在に引用され、勘解由と紗英、赤穂四十七士の変わりゆく心情を的確にとらえていくが、これも「引歌」を使ったからこそ可能になったといえるだろう。
『花や散るらん』も、能「熊野」に出てくる「いかにせん都の春も惜しけれど馴れし東の花や散るらん」からタイトルが採られ、西行の「風に散る花の行方は知らねども惜しむ心は身にとまりけり」が引用されるなど「引歌」が効果的に使われていた。
実は忠臣蔵と和歌の関係は深い。水戸藩の儒者・青山延光が赤穂四十七士の詩歌をまとめた『義人遺草』(一八六六年刊行)には、和歌が七十一首収められているが、これは(辞世の句が多いこともあるが)俳諧四句、漢詩三首と比べても圧倒的に多い。それほど赤穂四十七士は、和歌に自分たちの志を込め後世に残そうとしたのである。
吉良邸に討ち入った旧赤穂藩士が〝義士〟として高く評価されるにつれ、四十七士が残した詩歌は書物や展覧会の形で広く知られるようになった。そうすると、詩歌を自分なりに解釈して赤穂四十七士の心に触れた人たちが、〝義士〟を讃え、その偉業を後世に残すために詩歌を作るようになった。こうした歴史上の人物を題材にした詩歌は「詠史」といわれる。江戸時代は「詠史」を和歌で詠むことが流行し、長沢伴雄編『詠史歌集』(一八五三年刊行)などが編纂されている。『詠史歌集』には、大石内蔵助を題材にした長沢伴雄の「うずもれしその山科の大石は雪ときえてぞあらわれにける」、大高源吾を詠んだ岩崎精芳「山をぬくちからもともに松の雪きえてもきえぬ君がみさおや」など、忠臣蔵ものが十二首採られており人気の高さがうかがえる。
おそらく葉室さんが、日本に古くから伝わる文化的な伝統に着目し、赤穂四十七士の和歌や「引歌」で登場人物の心理を表現したのは、『万葉集』の昔から連綿と続く正統的な日本文化の奥深さを示すことで、昨今の浅薄な日本礼賛に一石を投じる意図があったように思えてならない。葉室さんは、江戸急進派の堀部安兵衛と儒者、書家として高名な細井広沢(忠臣蔵ファンには、討ち入りの口上書の添削をした人物として知られている)が剣の同門だった史実に着目し、大石内蔵助が、広沢の持つ文化人のネットワークを使って、やはり教養を重んじる吉保を動かそうとしたとしている。文化が政治を左右するパワーを有していた事実を指摘したところにも、深い教養を身に付けた為政者が減り、それが日本の文化的な荒廃に拍車をかけている現状への嘆きが感じられる。
何より葉室さんは、本書全体を「詠史」になぞらえ、吉良邸へ討ち入ることで武士としての「誠」を尽くそうとする赤穂四十七士、罪に問われることを覚悟して旧赤穂藩士を支えようとする勘解由と紗英を通して、現代人は歴史から何を学ぶべきかを突き付けているのだ。
扇野藩に落ち着いた勘解由のもとには、大石内蔵助を筆頭に、旧赤穂藩士が訪ねてくるようになる。紗英は、旧赤穂藩士を追い返すことなく真摯に向き合う勘解由に魅かれていく。だが旧赤穂藩士が吉良を討ったとなると幕府の裁定を蔑ろにしたことになり、それに勘解由が協力したとなると、扇野藩も処罰される危険がある。藩内では、勘解由を擁護する馬場民部と、批判する才津作左衛門の対立が激化。才津派は、非常時には刺客になる監視役として、由比道之助を勘解由のもとへ送り込む。
物語は、吉良を狙う旧赤穂藩士の動向、勘解由と紗英の恋の行方、扇野藩の派閥抗争が複雑に絡み合い、内匠頭が最期に残した言葉とは何かも鍵になるだけに、恋愛小説としても、政治ドラマとしても秀逸で、静かながら圧倒的なサスペンスがある。
紗英は武家に生まれた女として、藩の命令に従うのが当然だと思っていた。しかし、旧赤穂藩士の心に沿うためなら、幕府の命令に反しても、命を捨ててもいいという信念を持っている勘解由と接するうち、理非を明らかにし、自分の良心に従って物事を考える重要性を学んでいく。紗英の成長は、生活のため組織の指示には唯々諾々と従うべきか、法令や倫理に反した命令であれば左遷や解雇を恐れず拒否すべきかを問い掛けている。食品の産地偽装、大手メーカーの会計・検査データの改竄、国家公務員の公文書偽造といった不祥事が相次ぐ現代の日本では、いつ紗英のような立場になるか分からない。それだけに組織と個人はどのような関係にあるべきかを問うエピソードは、宮仕えをしている読者はとても他人事とは思えないだろう。
中盤までは、藩の命令に絶対服従し、任務を達成するためなら平然と汚い手段を使う道之助と、組織とは一定の距離を置き、紗英に影響を与えるほど強い信念と良心を持っている勘解由の対決に向けて進んでいく。組織を重んじる道之助と個を大事にしている勘解由の戦いは、作品のテーマを際立たせているので強く印象に残る。
ただ葉室さんは、強い信念を無条件で称賛しているわけではない。信念は、自分が正しいと信じる考え、または行動の原理となる思想なので、道之助のように組織に隷属し、陰謀をめぐらせてでも金を稼ぎ、出世をするという信念もあり得る。さらに極端な例を出せば、日本の安全を守るために、すべての外国人を排斥することさえも信念といえるのである。葉室さんは、勘解由に、武士は「農民や町人たちの範となる心構え」を持たなければならない、「ひとをいとおしむ心がなければ、この世は成り立たないのが道理」と語らせているが、ここにこそ良き信念と悪しき信念を見分けるヒントがあるのではないか。残念ながら現代の日本は、弱者へのいたわりを忘れた人、差別と偏見を助長する言葉を平然と口にする人など、見習いたくない人が増えている。それゆえに読者は、葉室さんのメッセージを心に刻みつけておく必要がある。
忠臣蔵は赤穂四十七士が切腹し、〝本懐を果たした〟、〝武士の鑑〟ともてはやされる場面で幕を降ろすのが一般的である。ところが本書は、赤穂四十七士が果てた後、残された関係者が何をしたのかにも焦点をあてているのだ。
赤穂四十七士が吉良邸に討ち入った日、吉良の嫡男・義周は長刀を持って戦ったが深手を負って気絶した。討ち入り後、赤穂四十七士の人気が高まったため、幕府は義周を「未練」と断罪し、信濃の諏訪家に預けた。配流先へ向かう義周が、勘解由に会うよう近習を扇野藩に向かわせるエピソードは、この世には勧善懲悪などなく、物事を善悪にわけてしまうと見失うことも多いと教えてくれるので、考えさせられる。また勘解由が赤穂四十七士の名声を後世に伝えるだけでなく、吉良の復権も果たそうと奔走する終盤には、寛容と和解の大切さが描かれており、深い感動がある。
主君に忠義を尽くし、領民の範となるように生き、面子のためなら命懸けで戦う武士にも、愛する人を想う、家族をいとおしむ〝情〟はある。こうした〝情〟は戦士としての武士を弱くするが、そこにこそ幸福があるのではないかと葉室さんは問う。
後世に名を残して華々しく散った赤穂四十七士とは対照的に、勘解由は消え残った「はだれ雪」のように、美しくないが泥にまみれてでも生を全うしようとする。弱さを認め、それでも懸命に生きる勘解由は、厳しい時代に直面している読者に勇気と希望を与えてくれるのである。
扇野藩ものは、『散り椿』が黒澤明監督の薫陶を受けた小泉堯史(脚本)、木村大作(監督・撮影)によって映画化され、葉室さんの死で最後の作品になってしまった第四作『青嵐の坂』が刊行されている。藩札の発行による財政再建という現代的なモチーフを描いた『青嵐の坂』も、人間の果てしない欲望とどのように向き合うべきかというアクチュアルな社会問題に切り込んでいた。本書と併せて読んで、葉室さんが読者に伝えたかったテーマを、もう一度、考えて欲しい。