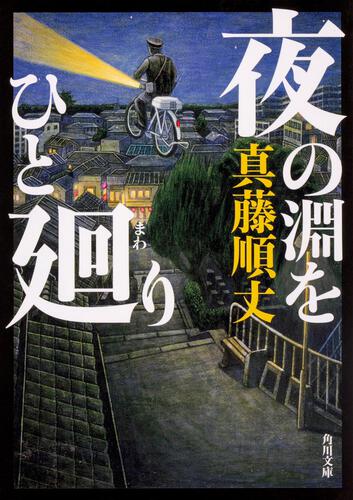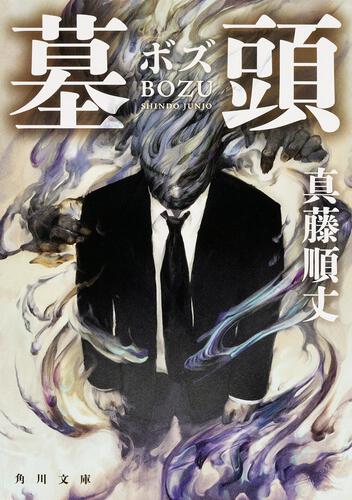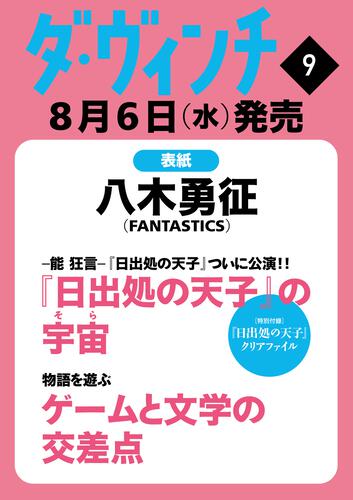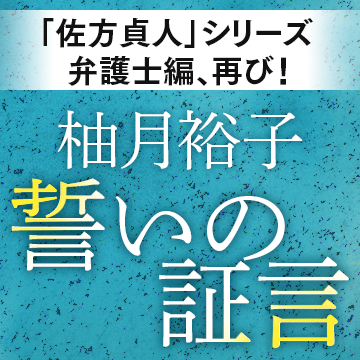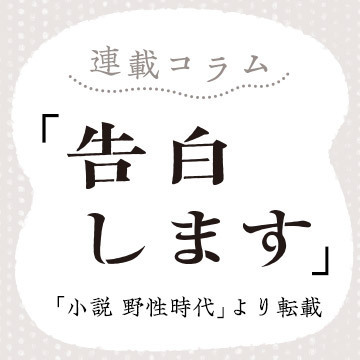技能実習生の女性が、謎の死を遂げた。移民国家・日本の様相を直木賞作家が描く! 真藤順丈「ビヘイビア」#1-2
真藤順丈「ビヘイビア」

Chapter.1
「ご乗車ありがとうございます、どちらまで?」
月末の土曜日ともあって、家族連れやカップル、結婚式に向かう正装のグループも目立ったが、乗ってくるのは三分の一ほどが他国の観光客だった。そのほとんどが端末機器で目的地の住所を示してくるし、運転中も話しかけられることはめったにない。支払いも各種カードや交通系電子マネーですませるので、運転手がたとえ外国語に通じていても宝の持ち腐れになる。二度目の東京オリンピック・パラリンピックを一ケ月後に控えたこの時期にもかかわらずだ。
おかげさまで儲けは上がっている。
その日の午後だけでも、複数の外国人を乗せた。
新宿
新宿駅西口のそばのコンビニでおにぎりや巻き寿司、夜食用のカップ焼きそばや替えの靴下を買って、ユニクロの入ったパレットビルを冷やかすとそこでもたくさんのアジア系の従業員が立ち働いていた。その裏手にあるしょんべん横丁もとい〈思い出横丁〉もめっきり観光地となって、アジア系の若い男女がカメラをぶらさげた白人にホッピーやハイボールを供している。わざわざ軒先に日の丸を描いて〈日本人のみで営業してます〉と貼り紙をする店舗もあるぐらいだった。
(こういうときだからこそ、一人ひとりのふるまいが問われるのよ)
妻の
そりゃそうだけどさ、と返すのが常だった。
この国を訪れる外国人たちは、ガラパゴスと化した列島の言語をしゃべれない。十にも満たない簡単な挨拶しか覚えない。そんな人々が働くとなれば、他人に接することの少ないバックヤードや厨房、深夜の工場の仕分けなどがメインになってくるが、かたやコンビニや飲食店で接客をこなす外国人は、一定の日本語能力を身につけて採用され、単純なレジや品出しだけでなく公共料金の支払いや宅配便の預かりといった煩多な業務をこなしている。私たちが日常でいちばんよく顔を合わせる店員たちは、在留外国人のなかでも
(だって
そりゃそうだけどさ。理屈ではわかるが、これだけ増えればままならなさもある。無節操さへの腹立ちとかちぐはぐなアウェイ感とか。これだから外国人は、と
大衆文化のカーニバル、景気回復のカンフル剤、街頭モニターでは競技選手たちがうまそうな食べ物や速い車やつやつや光る美容品を売るためのドラマを演じている。十五秒に一度のハッピーエンド。全都道府県をめぐりめぐって開会式場に着くという聖火は、いまごろどの地方にあるのやら?
こっちは数年前から、JPNタクシーで都内を走っている。
低い床と高い天井のトールワゴン型、電動式の
車椅子のままで乗り降りできるシームレス設計、ハイブリッドで地球にも優しい。
乗務員証に貼った写真の映えはそんなに悪くない。
乗りこむ事業車のグレードは標準の〈
都内を漂い、縫うように進み、乗ってきた客にどこそこに行けと告げられて、そこに行く。すべての目的地は偶然に支配され、決定権はこちらにはない。城之内がそこにいる唯一の
「……えっ、それはご勘弁を、もちろん経路は頭に入ってますので。それでその目印というか、そういうものは……」
事業所からの無線の指示ではなかった。丸の内の商業ビルのトイレにこもり、スマートフォンで話をしていた。ついでに用を足しておきたかったが、緊張感をおぼえると出るものも出ないのは昔からの性分だった。
それとなしにペーパーを取ろうとして、手が滑った。
「おわっ」
腰を浮かせたはずみに、スマートフォンが便器の中に落下した。
城之内は泡を食って、壁に頭突きする勢いで手を伸ばす。
水没したスマートフォンの液晶表示は消えていた。
「もしもし、もしもし」
通話も切れている。なんの応答も聞こえない。
悪い歯で
「いやいやいや、それはない、まずいまずい……」
恐ろしい相手なのだ。歯の透き間から
さしあたって公衆電話を探すか、だけど番号を暗記していない。こういうときはいたずらにオン/オフしないほうがいいんだっけ、だけど主電源を切ったと勘違いされたら、次に会ったときに何をされるかわかったものではない。
夜の十一時を回っている。左手にJRの高架、
東京国際フォーラムの側の歩道に、往来の流れに乗らない人影があった。
壁を食い破って場違いな空間に出てきてしまった
繁華なビルの灯の外側、繊細な夜の陰影のなかで身をこごめている。
五人か六人ほどの男女は、いずれも国外出身者のようだった。
城之内はタクシーを出さず、反対側の路肩から様子をうかがった。東南アジア系や中国系も交ざっている。国籍こそばらばらのようだが誰もが若く、
おたがいにたえまなく言葉を交わしながら、いつまでたっても歩きださずに、何かを待っているような気配があった。
あれは技能実習生じゃないかと城之内は思った。薄黒く
丸の内のどまんなかに、ちいさな荒野が出現していた。
地図も持たず、頼れる身内や案内人もいない、異国の遭難者がさまよう荒野だ。
城之内は
待っていれば乗ってくるか? それはないだろう。JPNタクシーが体現するのは〈日本人のおもてなしの心〉だけれど、若くて懐がさみしくて自由もない技能実習生や留学生がタクシーを拾うことはめったにない。彼らはそれこそ〈おもてなし〉の
>>#1-3へ
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
※「文芸カドカワ」2019年7月号収録「ビヘイビア」第 1 回より