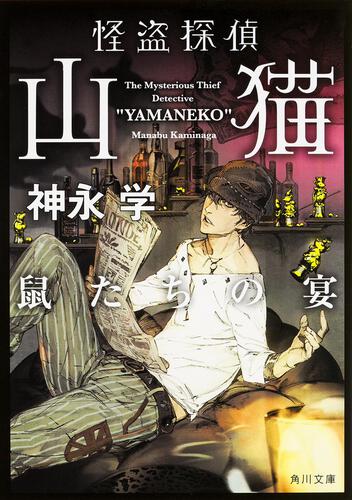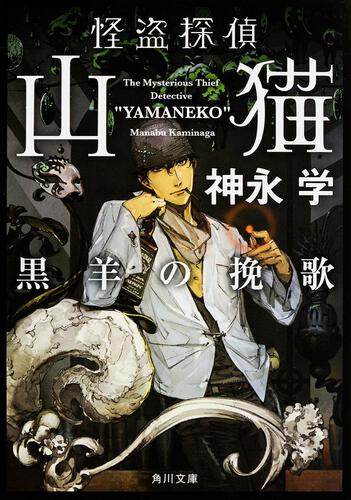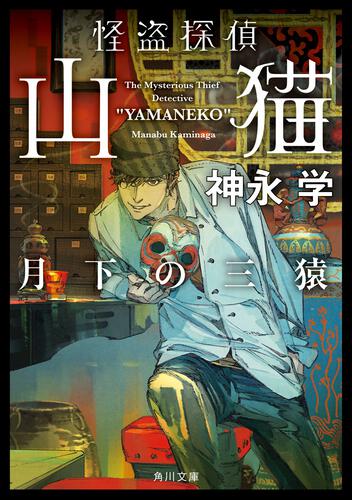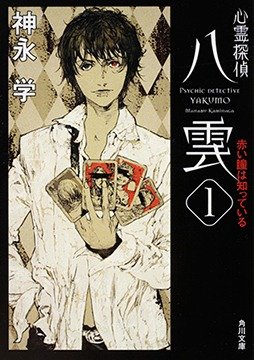「準備はいいか?」
山猫に声をかけられ、勝村は顔を上げた。
作戦の概要は把握した。機材も揃っている。でも──心の準備は全然ダメ。
謎を解くために、ネックレスを取り返す必要があることは分かっている。彼らが、話し合いで返してくれるような、優しい人間たちでないことも実証されている。
だが、やっぱり覚悟が決まらない。
頭に載った暗視ゴーグルと、左肩のロープが重くのしかかる。
「いざとなったら、俺は逃げるからな。お前は捕まっても、絶対に俺のことを
山猫は、薄ら笑いを浮かべながら言った。
──笑えない冗談だ。
「よく、そんな冷酷なことが言えるね」
「まったく。寒くもねぇのに、息子が縮んでんじゃねえのか?」
山猫は、言いながら勝村の
「ちょ、ちょっと……」
「冗談だよ、冗談。この俺様が、逃げるわけねぇだろ」
山猫は、誇らしげに胸を張った。
残念だが、窃盗犯の言葉をあてにするほど
山猫は、ポケットの中から板チョコを取り出し、一口かじると、勝村にも差し出してきた。
心遣いはありがたいが、勝村は、それを口にする気にはなれなかった。
緊張で
「じゃあ、行くとしますか」
山猫は、散歩する猫の如く
勝村は、山猫の陰に隠れるように進む。
マンションのエントランスの前にたどりついたが、オートロックになっていて、ドアは開かない。
ここを開けるためには、ドアの脇にある
「ど、どうするんだ?」
勝村は、山猫に
モラルを無視して考えれば、こんな間近で、窃盗犯の手口を見学できる機会など、まず無い。
「よく覚えとけ。オートロックなんて、ただのオモチャだ」
山猫は、得意気に勝村を見て笑うと、ポケットから千円札を取り出した。
「チップでも渡す気?」
「バカだろ、お前」
「冗談だよ」
むきになって反論する勝村を、山猫は鼻で笑った。
「この手のオートロックを開けるのに、工具や偽造鍵は必要ない。紙切れ一枚で充分なんだ」
「紙切れ一枚?」
──魔法使いじゃあるまいし、そんなものでドアが開くわけがない。
山猫は、
そのまま手を上げ、高い位置からドアの隙間に千円札を差し込むと、勢いをつけてエントランスに向かって放り込んだ。
それと同時に、ウィーンと低い音がしてドアが開いた。
「え? 何で?」
勝村は、あまりのことに、声が裏返ってしまった。
山猫は、悠然とマンションに侵入すると、床に落ちている千円札を拾う。
「センサーを作動させただけだ」
山猫の一言で、勝村にも事態が飲み込めた。
マンションのオートロックは、外からは、鍵を使わないと開かない。
しかし、中からの場合、自動ドアと同じ仕組みで、センサーが感知してドアが開く。
だから、ドアの隙間を使い、外側から内側に紙を投げ込めば、内側のセンサーがそれを感知して、ドアが開くというわけだ。
店舗のように、内側から出るときに、ボタンを押す形式にすれば、こんなことは起こらない。利便性を追求した結果として生み出された、セキュリティーの穴──。
「早くしろ」
山猫が、
エレベーター前で待っている山猫は、いつの間にか黒い覆面を
山猫に続いてエレベーターに乗り込んだ勝村は、思わずぎょっとする。
天井に、半球形の防犯カメラが取り付けられているのに気づいたからだ。
「これ、マズイんじゃないの?」
勝村は、カメラの死角になる場所に移動しようとしたが、狭い空間の中では、どうにもならず、オロオロしてしまう。
「気にするな。俺たちの姿は、録画されないように細工してある」
山猫がのんびりとした口調で言った。
「細工って?」
「転職するなら教えてやってもいいぜ」
山猫が、覆面の向こうでニヤリと笑う。
──誘いはありがたいが、遠慮させてもらう。
勝村が、心の中で
山猫は、最上階である八階のボタンを押し、開いたエレベーターのドアが閉まらないように、レールの隙間にドライバーを差し込む。
これで、しばらくは誰もエレベーターを使うことができない。
「行くぞ」
山猫は、作業を終えると先陣を切って歩き始めた。
その足取りには、迷いも
──自分のやろうとしていることは、本当に正しいことなのだろうか?
迷いから、足取りが重かった。地震でもないのに、地面がグラグラと揺れている気がする。
「勝村」
「え?」
山猫に、突然名前を呼ばれ、勝村は足を止めた。
「何で、今井は、お前にメッセージを託したんだと思う?」
山猫は、ダンスのステップのように、軽快に身体を回転させ、勝村に向き直った。
「何でだろう……分からない」
今井と親しかった人物は、他にもいるはずだ。
「俺にも、なぜお前に託されたかは、分からない。今井がどんな男かも知らないしな。だがな、一つだけ分かることがある。それはな、このメッセージを託すのは、お前じゃなきゃダメだったってことだ」
山猫の一言で、勝村は、泥沼から救出されたような気分になった。
──悩んでいる場合ではない。
勝村は、自分に言い聞かせる。今井が、何を伝えようとしていたのか? それを知るのは、託された者の義務だ。
筋肉がぶるっと震えたあとに、身体の無駄な力が抜けた。
「いい顔になったじゃねえか」
山猫が楽しげに勝村を指差した。
勝村も、笑い返す。
「今度こそ、本当に行くとしますか」
山猫は、サキの部屋のインターホンを押した。
それが作戦開始の合図だった──。
勝村は、山猫と入れ替わりで、ドアスコープの前に立つ。
山猫は、エレベーターと外廊下の中間位置にスタンバイする。
しばらくの沈黙があった──。
緊張はあったが、焦りはない。奴らは、ドアの前に立っているのが、勝村だと知れば、必ずドアを開ける。その確信があった。
やがて、鍵とドアチェーンを外す音が聞こえる。
──やっぱりだ。
勝村は、それを聞くなり、消火栓が収納されているスペースに身体を滑り込ませる。
ゆっくりとドアが開いた。
少し身体がはみ出してはいるが、ドアの陰になっているので、部屋の中からは見えないはずだ。
ドアから男が顔を出した。白シャツの男だ。彼の視界に入るのは、勝村ではなく、山猫の後ろ姿だ。
「おい! 待て!」
白シャツの男が声を上げた。
山猫を、勝村だと勘違いして、必死にその背中を追いかけていく。
外廊下の角に男の姿が消えるのを待ってから、勝村は狭いスペースから身体を出した。
頭の中で作戦を反復する。
白シャツの男は、山猫を追って外廊下を走り、エレベーターホールに出る。
山猫は、エレベーターを止めていた、ドライバーを外して身を隠す。
上っていくエレベーターのランプを見た白シャツの男は、上層階に逃げたと錯覚し、必死に階段を上っていくはずだ。
その間に、山猫は階段を下りて外に出る。
そして、マンションの裏手にある配電室の鍵を開け、マンション全体の電源を落とす。
勝村が、頭の中でシミュレーションを終えるのとほぼ同時に、ブツッ──と大きな音がして、マンションの明かりが一斉に消えた。
──ここまでは作戦通り。
勝村は、メガネを外し、額の位置にある暗視ゴーグルを、目の位置に移動させる。
真っ暗だった世界に、緑がかった映像が飛び込んで来る。
裸眼なので、多少視界はぼやけるが、認識はできる。
「行くぞ!」
勝村は、両手で頰を打ち、自らを
音をたてないように注意しながら、ドアノブを回す。
さっき白シャツの男は、慌てて部屋を出て行った。予想通り、鍵は開いていた。
息を潜めながら部屋の中に侵入すると、白シャツの男が戻ってこられないように、内側から鍵をかける。
礼儀知らずかも知れないが、勝村は靴のまま、玄関を上がり、廊下を奥に進んでいく。
廊下先に、十畳ほどの広さのリビングルームがあった。
リビングのソファーに座っている男の姿が見えた。
アロハシャツの男だ。突然の停電に動揺したらしく、落ち着きなくあたりをキョロキョロと見回している。
リビングの戸口のところに立った勝村は、息を止めて部屋の中を捜す。
ネックレスはすぐに見つかった──。
アロハシャツの男が座るソファーの前にある、ガラス張りのテーブルの上。
勝村は、身を
──あと少し。
ピリリリッ。
ネックレスが、指先に触れるのと同時に、電子音が響いた。
──しまった。
携帯電話だ。電源を切るのを忘れていた。
勝村は、慌ててジャケットのポケットに手を突っ込み、電源を切る。だが、手遅れだった。
アロハシャツの男は、ライターの火を
勝村は、薄明かりの中で、アロハシャツの男と目が合った。
「誰だ!」
アロハシャツの男が、声を上げる。
サアッと音を立てて、血の気が引いていく。
勝村は、パニックに陥る寸前で踏みとどまり、ジャケットのポケットに手を突っ込み、山猫から渡されたスプレー缶を取りだし、アロハシャツの男に吹きつけた。
「ぎゃっ!」
アロハシャツの男は、両目を押さえて倒れ込み、床の上を転げまわった。
痴漢撃退用のスプレーだ。しばらくは、痛みで目を開けることができないはずだ。
だが、ぐずぐずしている余裕はない。
勝村は、テーブルの上のネックレスを
そこで、見てはいけないものを見てしまった。
部屋の隅に座り込み、祈るように両手を胸の前で合わせ震えているサキの姿──。
左の頰に、
前に会った時、彼女が言った「ごめんなさい」、それは、勝村を白シャツの男たちに売ってしまったことに対する謝罪だった──。
あんな目にあったのだから、怒りの気持ちがないと言ったら噓になる。
だが、自分だったらどうだろう──と考えてしまう。
あんなガラの悪い男たちに囲まれて、最後まで噓がつき通せるだろうか?
勝村は、結論が出る前に、サキの病的に白く細い腕を摑んでいた。
ロープのフックをベランダの手すりに引っ掛け、その先を中庭に垂らす。
「さあ。早く降りて」
勝村は、ゴーグルを外して、サキに顔を近づけた。
サキは、暗闇の中で勝村の顔を認識したらしく、驚きと
「あの、私……」
サキが震える声で何かを言おうとしている。
勝村としても、
「いいから、早く降りて!」
勝村は、口調を強め、サキにロープを握らせる。
小さく
「大丈夫だから。そのままゆっくり」
サキは大きく頷くと、ゆっくり、だが確実にロープを降りていく。
彼女が地面に足を着けたのを確認してから、勝村もベランダの外側に出てロープを手に取った。
「くそっ、何処に行った!」
痛みから解放されたのか、闇夜にアロハシャツの男の
勝村は、ロープを降りながら、上に目線を向ける。
目を
「お前!」
アロハシャツの男が、勝村の存在に気づき、飛び出しそうなほどに両目を
「勝村、跳べ!」
山猫の声が
勝村は、下に目線を向ける。
すでに、二階くらいまで降りて来ている。この高さなら山猫の言う通り、跳べないことはない。
「うわぁ!」
勝村は、思い切ってロープから手を離した。
一瞬の浮遊感の後、両足に鈍い衝撃が走る。運動神経が人並み以下の勝村は、前のめりに転倒して胸を強打した。
「まったく、どんくせえな」
煙草を
勝村は、身体を起こしながら、四階のベランダに視線を向けた。アロハシャツの男が、ベランダの柵を越え、ロープを摑んでいる。
追いかけてくるつもりだ。
「早く逃げよう!」
勝村は、すぐに駆け出そうとしたが、山猫に慌てた様子はなく、マッチを擦り煙草に火を点ける。
「彼にも、跳んでもらおうじゃねぇか」
そう言った山猫は、まだ火種の残っているマッチをロープに近づけた。
ぼっ!
音を立てて、ロープに火が点いた。
導火線を
「わっわっわっ!」
アロハシャツの男は、迫り来る炎から逃げようと足をバタバタさせて抵抗を試みたが、無駄だった。
「あつっ!」
拍子抜けする悲鳴と共に、アロハシャツの男が地面に落下した。
下は芝生だし、死ぬことは無いだろうが、骨の一本や二本は折れたかも知れない。
「はい。チーズ」
山猫は、痛みに表情を
勝村は、
「待て! こらぁ!」
マンションのエントランス前を通り過ぎようとしたところで、
「逃げよう」
走りだそうとした勝村を、山猫が制した。
「慌てんなって」
山猫は
オートロックのドアの前に立った白シャツの男だったが、肝心のドアが開かない。
考えてみれば当たり前のことなのだ。停電中に自動ドアが開くわけがない。
「電化製品に頼りすぎると、こういうことになるんだよ」
山猫は得意げに
白シャツの男は、ドアの隙間に指を入れて、こじ開けようとする。
だが、それでも山猫は動じない。その自信を裏付けるかのように、白シャツの男が、どんなにあがこうとも、ドアはびくともしなかった。
「原始的な方法は、意外に役に立つんだよ」
山猫の言葉で、勝村も気が付いた。
自動ドアには、外側からつっかい棒がしてある。
確かに原始的な方法だ。
勝村は、今までに味わったことのない高揚感に、陶酔してしまいそうだった。
試し読み

書籍週間ランキング
1
管狐のモナカ
2025年12月8日 - 2025年12月14日 紀伊國屋書店調べ
アクセスランキング
新着コンテンツ
-
特集
-
特集
-
特集
-
試し読み
-
レビュー
-
文庫解説
-
特集
-
レビュー
-
文庫解説
-
連載