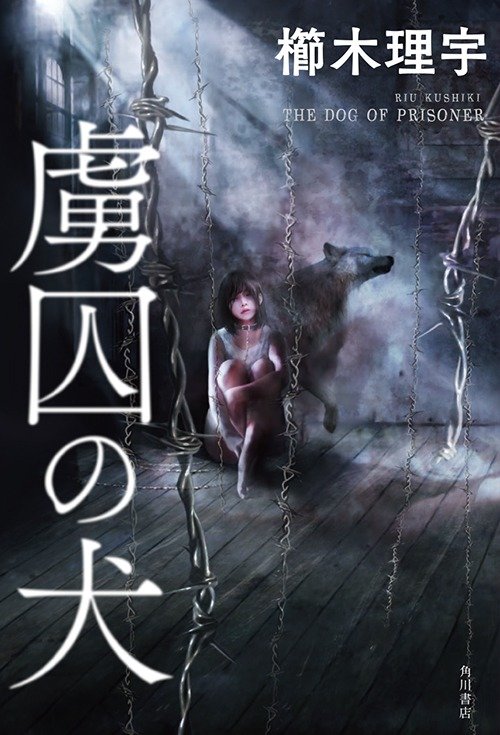カドブンで好評をいただいている、ミステリー『虜囚の犬』。
7月9日の書籍発売にあたり、公開期間が終了した物語冒頭を「もう一度読みたい!」、「ためし読みしてみたい」という声にお応えして、集中再掲載を実施します!
※作品の感想をツイートしていただいた方に、サイン本のプレゼント企画実施中。
(応募要項は記事末尾をご覧ください)
◆ ◆ ◆
>>前話を読む
7
三橋家は閑静な住宅街の奥に建っていた。
いわゆるデザイナーズ建築というやつなのか、真っ黒な直方体の建物だった。遠目には、突き立った木炭さながらだ。ちいさな丸窓が、壁のあちこちで奇妙な角度にひらいている。庭らしい庭はなく、駐車場ばかりがだだっ広い。
一歩入る。想像したより中は明るかった。
側面の窓ではなく、天窓からおもに光が射しこむ造りになっているらしい。内装は白とシルバーを基調に統一されており、生活感が乏しかった。家というより、
だが生活感がないのは、家だけではなかった。
未尋の四歳の弟、睦月もまた浮世ばなれしていた。未尋の話では「生意気なうるさいガキ」だった睦月は、薄茶の髪を肩下まで伸ばし、ベビーピンクの部屋着をまとっていた。いとも無邪気に、笑顔で海斗にじゃれついてくる。
「女の子かと思った」
どぎまぎしながら海斗が言うと、
「この服か?
未尋は応えた。
「ああ、亜寿沙っていうのはおれの母親な。うち、親を『お母さん』だの『ママ』だのって呼ばす習慣ねえんだ。……おれの見てくれでわかるとおり、亜寿沙は白人系ダブルのモデル男に弱いんだよ。それでもって、『美はジェンダーにとらわれず、本人の資質に重点を置くべき』とかなんとか言うのさ。要するに男女の区別なく、可愛けりゃ可愛い格好をさせとくってわけ」
「いいと思いますよ」
ベビーシッターの森屋は、五十代はじめに見える女性だった。彼女は背後から睦月を抱き寄せて、
「未尋ぼっちゃまも睦月ぼっちゃまも、とってもおきれいですもの。きれいな子がきれいな格好をするのは素敵なことです」
と
海斗は三橋兄弟と森屋の四人で、ボードゲームで遊んだ。
睦月は聞きわけのいい子だった。意外にも未尋は、
思いもよらぬ和やかな時間に、海斗は面食らった。
──でも、こういうのもいいな。
そうだ。けして悪くない。
モダンでスタイリッシュな家。やわらかな空気。夕方には天窓からオレンジの
三橋亜寿沙が帰ってきたのは、午後八時過ぎだった。
「あらめずらしい。ヒロのお友達?」
と言って目を見ひらいた亜寿沙は、けして〝美人〟ではなかった。美人の規格に当てはめるには目鼻のパーツが大きすぎ、そばかすが多すぎた。
だが彼女には、一般的な美醜のレッテルなど吹き飛ばすオーラがあった。赤いリップに縁どられた大きな口が笑うと、息子そっくりの完璧な歯並びが覗いた。中学三年生の息子がいるとは思えないほど、若くいきいきしていた。
「紹介してよ、ヒロ」
「友達の國広海斗だよ。どう、亜寿沙の好みだろ?」未尋が言う。
亜寿沙は海斗を上から下まで眺めまわしてから、
「うん、合格。ヒロはやっぱ、あたしとセンスが似てる」
と親指を立てた。
どうしていいかわからず立ちすくむ海斗の前で、三橋
「ヒロ、あんたたち夕飯どうするの。ピザでも取る?」
「べつに決めてねえけど」
「じつは今日、森屋さんを本格的にお迎えする記念に、すき焼きにしようと思ってたのよ。よかったらお友達も一緒に食べてけば?」
「はあ? 初対面ですき焼きかよ。てか、安もんの肉じゃねえだろうな。海斗の前で、恥ずかしいもん出さないでくれよ?」
「失礼な子ね。
亜寿沙がふたたび海斗を見やる。
「ねえきみ、お肉好き? 食物アレルギーとかあったら、いまのうち教えといて」
「な、ないです」
海斗は口ごもりながら答えた。
「アレルギーも、好き嫌いもありません」
「あらそう。育ちがいいのね」
亜寿沙は笑った。真っ白すぎる歯がふたたび覗く。
育ちがいいなんて言われたのは、生まれてはじめてだ──。海斗は陶然と思った。
すき焼き鍋を囲む夕飯は、約一時間後にはじまった。
「海斗くん、卵いる?」
「あ、いえ。いいです」
手を振って断ってから、海斗は「ありがとうございます」と付けくわえた。
──すき焼きなんて何年ぶりだろう。
実母が生きていた頃は、おそらく何度か食べたはずだ。だがおぼろげにしか記憶がなかった。後妻が来てからは、鍋を家族で囲んだ夜なんて一度もない。
甘い割下で肉が煮える匂いに、思わずつばが湧いた。未尋が笑う。
「うちのすき焼きって、亜寿沙の好みでつくるから具が独特なんだよ。春菊なし、白滝なしで、えのき
「ごめんねえ。生まれが田舎だから、春菊より白菜のほうが慣れてるの。割下でくたくたになった白菜、
「作るのは森屋さんなのにさ。注文ばっかうるせぇんだぜ」
「はいはい。すみませんねーだ」
亜寿沙が顎をそらして、つんと言う。
テーブルに笑いが沸いた。海斗も笑った。
「やっぱ肉にはビールよねえ。ヒロ、立ってるついでにビール持ってきてよ」
「いいけど、おれと海斗も飲むぜ?」
「あら、海斗くんもいける口なの。んじゃビアグラス、三つ持ってきてちょうだい」
「奥さま、グラスはわたしが」森屋が立ちあがる。
鍋から立ちのぼる湯気越しの光景を、海斗は夢のようだと思った。
非現実的なほど美形の兄弟。若くファッショナブルな母親。彼らが醸しだす、和気あいあいとした親密な空気。
「はい、かんぱーい」
当たりまえのようにビールが
煮えた肉は甘く、舌の上でとろけるほど柔らかかった。嚙んでも、まるで繊維を感じなかった。
亜寿沙は水のようにビールを干し、けろりとしていた。未尋は常のクールさが噓のようによくしゃべった。森屋は「ムっちゃん、お肉大きかった? お箸で切れる?」と
亜寿沙の言うとおり、くたくたに煮えた白菜は
いったいビールを何杯飲んだのか、見当もつかない。勧められるがままに飲んだ。目の前に、みるみる空き缶が並んでいく。数えるのは途中で放棄した。
亜寿沙が問う。
「海斗くん、締めは雑炊派? うどん派?」
「あ、いえ。どっちでも」
海斗は答えた。
派もなにも、すき焼きの締めだなんて初経験だ。実母が生きていた頃は幼稚園児で、すこしの肉でご飯を一膳食べれば終わりだったはずだ。
「いまどきの子にしちゃ遠慮がちねえ。ヒロのお友達とは思えない」
「うるせえよ」
三橋母子が、顔を見合わせて笑う。森屋が立ちあがる。
「では今日は、おうどんにしましょうか。ただいま用意いたします」
海斗はうっとりと湯気の向こうの彼らを眺めた。
映画のように美しく、幸せな光景だった。
(つづく)
連載時から話題沸騰! 書籍を読みたい方はこちらからどうぞ
▶amazon
▶楽天ブックス
▼櫛木理宇『虜囚の犬』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000319/