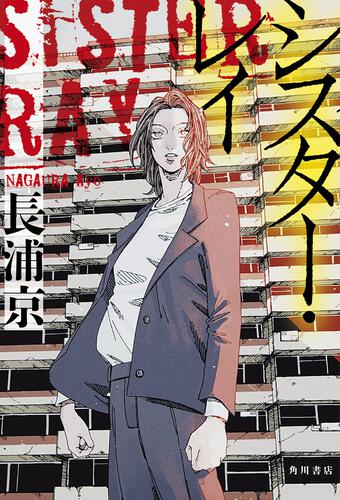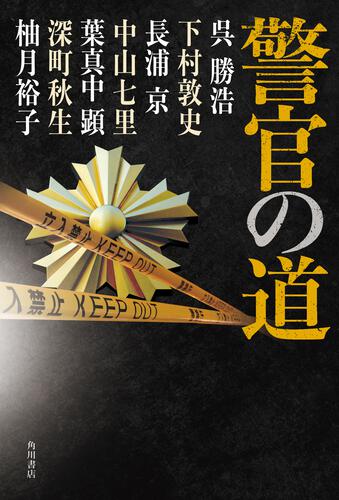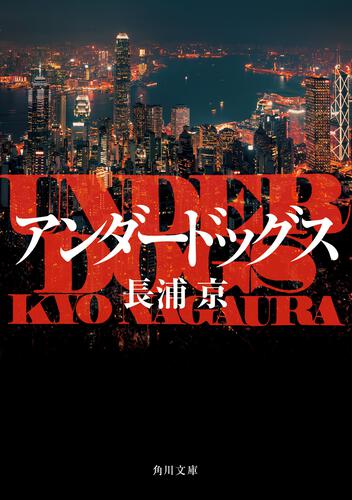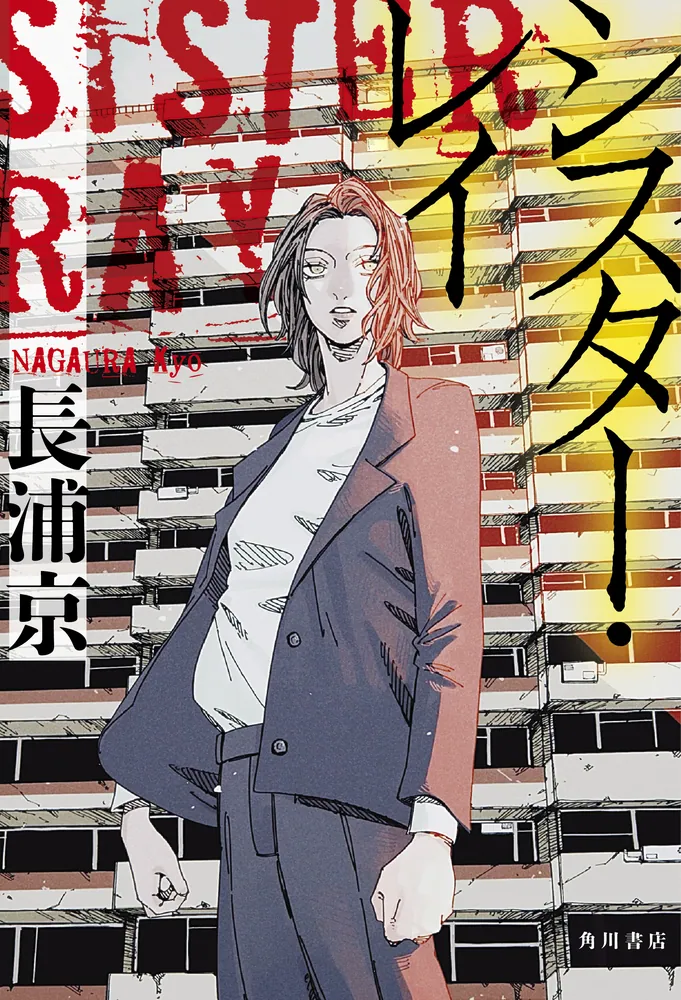直木賞候補作となった『アンダードッグス』や、大藪春彦賞を受賞し映画化もされた『リボルバー・リリー』など、さまざまな時代を舞台に展開される巨大な陰謀と華麗なアクションを描く話題作を次々に刊行し、今、最も注目される小説家・長浦京さん。
最新作『シスター・レイ』は現代の東京下町が舞台だ。日常に潜む裏社会の組織の数々の陰謀から、身の回りの大切な人を守るため、元フランス特殊部隊のエースという隠された経歴を持つ予備校講師、能條玲が奔走する。アクションと陰謀、さらには多国籍・多人種化の進む現代日本のリアルを描いた意欲作だ。
本作の着想と込められた思いについて、長浦さんにお話を伺った。
取材・文:タカザワケンジ 写真:干川修
『シスター・レイ』長浦京インタビュー
日常に近いところで起きている「事件」
――『シスター・レイ』は驚きの連続でした。主人公の玲に驚かされ、玲が巻き込まれる事件に驚かされ、それがチェーンのようにつながっていきます。着想はどのように?
長浦:驚きと言われましたけど、基本的には僕の日常なんですよね。
――え? そうなんですか。
長浦:事件の規模はともかく、僕の身の回りで似たようなことが起きていて、いまここにあるものを書いてみるのもいいかなと思ったのが始まりです。小説ですからデフォルメしてはいますが。
僕の子どもたちが小学生の頃ですから数年前ですけど、クラス30人中5人ぐらいは外国籍でした。その子たちがうちに遊びに来ると、手に持った袋の中から手紙を出すんです。
親御さんからの手紙で、ムスリムだからハラール(イスラム教徒に許されている食物)じゃないものが食べられない。飲み物は水道水、お菓子はこれを食べさせてくださいとあって、お菓子が一緒に入っていました。
じゃあ、みんなで食べられるものを食べよう、と外に出た。ちょっと歩けばハラール認証を受けたお店があって食材や雑貨を売っています。そこで買ったお菓子を子どもたちみんなで食べました。
そんな風に身近に国際化が進んでいるんです。
――たしかに外国人は珍しくないですし、ハラール認証のお店もよく見かけるようになりました。
長浦:そういう日常の中から、小説で書いたような「事件」を思いついたのは、実際に目撃したことがきっかけです。
近所の団地の3階ぐらいから裸足の男が飛び降りてきたのを目撃したんです。
彼がダァーって走っていったところに警察官がうわあっと集まって逮捕した。
あとで聞いたら、外国人窃盗団の本拠地が団地の1室にあって、逮捕劇になったそうです。
こんなに外国人が溢れているんだから、外国人犯罪があるのも当然。そう思ったところから着想したというか、そういう現実を淡々と書いてみようと思ったのが始まりです。
――たしかに私たちの身の回りが大きく変化してきているのはたしかですね。こうして小説に書かれると、社会の変化が客観的に見えてきます。それと同時に不法移民に対する批判が高まったり、差別が問題になったりしている、いまの社会のことも考えながら読みました。
長浦:タテマエでは「みんな仲良く」って言うんだけれど、実際にはなかなかそう簡単には行かないですね。
日本人、外国人の双方に問題があって、お互いに自分たちの文化や道徳を譲らないところがある。同じ街で生活しているとそういう軋轢は確実にあるわけです。
人道的な立場に立って受け入れようって安易に言えない現実があって、僕たちは否応なくその中で暮らしている。
『シスター・レイ』を書くうえで踏み外さないようにしたのは、フィクションではあるけれど、これは僕らの日常なんだということです。
「強い」ヒロインの弱さ
――外国人に対する偏見と差別、それと同時に外国人の犯罪が起きている。その両方を視野に入れているのが『シスター・レイ』の特徴ですね。同時に、エンターテインメントとして、想像力を飛躍させる設定もあります。主人公の玲は元フランスの警察官で、対テロ作戦や人質救出作戦に従事するGIGN(国家憲兵隊治安介入部隊)に所属していました。しかも日本では同居する母を介護しながら予備校講師として働いています。このギャップに驚かされたのですが、主人公を女性にしようと思われたのはなぜですか。
長浦:ぶっちゃけて言ってしまうと、編集者に求められたんです(笑)。強くてかっこいい女性を書いてくれって。
逆に言うと、主人公をそう設定すればあとはどこまで風呂敷を広げても怒られないだろう。じゃあ書いてみようと。
もっと言ってしまえば、もともとは警察小説アンソロジー(『警官の道』角川文庫)の中の1作だったんです。冒頭の「I」にあたる部分がそれです。
その短編がありがたいことに好評で、じゃあ次はもっと日常感の溢れるストーリーをこの主人公で書いてみませんか、と編集者から提案されたんです。
いざ書いてみたら、時間はかかるわ、スケールは大きくなるわで、こうなりました(笑)。
――『シスター・レイ』っていうタイトルから、映画化された長浦さんの『リボルバー・リリー』を連想する読者もいるかなと思います。共通するのは強いヒロイン。お書きになっていてどうですか。
長浦:強いヒロイン……強いってどういうことなんでしょうね。
そうか。戦うという意味では強いですね。でも、身体的、技術的な強さと、心の強さはまったく別物です。
玲は強くなろうとしていて、実際、戦闘能力という面では強いけれど、内面は妙に弱いっていうか、だらしないところがある人間なんですよ。というか、書いてるうちにそうなっていったんです。
実際僕の周りにいる人々でも、身体を鍛えている人、強くあろうとする人って、内面的には弱いというか、優柔不断な人が多いなと思っていて。
強そうに見えて弱いところがあったりするのは、自分にとって親しみがわくキャラクターの像の1つなのかもしれません。
たぶん、僕自身が優柔不断で弱いからなんでしょう。
――玲の設定が、予備校講師で元テロリスト対策のプロってどういうこと? と思って読み始めたんですが、読んでいてなるほどと思いました。海外で実績があったとしても日本でそれが通用するとは限らない。つぶしが効かないって話はたしかによくあるなと。
長浦:実はちょっとしたモデルみたいな人がいるんです。アメリカで生まれた日本人とアメリカ人のハーフの女性で、アメリカで空手をやっていて、極めたいからと日本に来たんですけど、空手だけじゃ食っていけないからと仕事を探そうとしたんです。
ところが、観光ガイドや語学の先生をやろうとすると、見た目がアジア系の彼女は敬遠されるんですね。ちゃんとした白人じゃないって。それで彼女は大手の塾の講師になったんです。そのエピソードがベースにあって予備校講師という設定にしました。
ネタとキャラクターには困らなかった
――突飛に見えるけど、実は裏付けがあるんですね。玲だけでなく、登場人物にそれぞれのバックグラウンドがあって、人物像を裏打ちしています。登場人物に関してかなり作り込まれていると思いましたが、どうでしょう。
長浦:逆に作り込まなくて済んだんです。今回は登場人物の9割が実在する人をベースにしているので。
――そうなんですか。
長浦:区役所のくだりで嫌なやつが出てくるんですけど、あれもほとんど全部実話。外国人の友人に女の子の双子が生まれて、届を出しに行ったら、姉妹の名前を逆に登録されそうになったんです。「逆です。直してください」と言ったら「どっちも女で外国人だから同じでしょ」って言われて、その対応にびっくりしたんですよ。
また別の話では、外国人の友人が子どもの支援金の申請に行ったら窓口で軽くあしらわれたんですが、一緒に行った日本人が厚生労働省の関係者だとわかったら急に態度を変えてペコペコするなんてこともあったりして、ひどいもんだなと。
――ひどい話ですね。外国人をめぐる報道は偏見差別の被害者か、犯罪の加害者のどちらかに偏っていて、極端だなあと感じることがよくあります。『シスター・レイ』はどちらかに偏ることなく「日常」を描いていると感じました。
長浦:当然のことですけど、外国人の中にもいい人もいれば、悪い人もいる。外国人同士でも利用したりされたりしている。
身近なところでも、夜道で外国人同士が殴り合っている場面に年に何回か出くわしたり、日本人の女の子に執拗に声をかけて車に引きずりこもうとしていたこともありました。
人道的な立場に立って外国人を受け入れよう、と安易に言えない現実があるんですよね。そういうところは嘘をつくべきじゃないと思うので、現実に起きていることは小説の中でも書いていこうと思っています。
そこにある素材をどこまで展開できるか
――身近な日常を題材に書いたそうですが、それが小説になるとドラマチックなエンターテインメントになる。『シスター・レイ』には日常から飛躍する面白さがあります。
長浦:大昔、音楽雑誌の編集とかをやっていたことがあって、取材で奥田民生さんと話した時に印象的なことをおっしゃっていたんです。
民生さんが井上陽水さんと楽曲を共作された際、陽水さんは本当に見たままを歌詞にしていて驚いたって言っていたんです。
花瓶があったら花瓶を書く。モチーフは花瓶だけど、そこからどこまで飛躍させるかがプロの技だと。モチーフの選び方よりも、その飛躍のさせ方を鍛えたほうがいいんじゃないか、と民生さんが言っていて、本当にそうだなと思いました。
今回もそこにある素材をどこまで展開させて、どこに結びつけていくかっていうことには気を使いました。
逆に言うと展開が二転三転して大きく飛んでいくものだからこそ、出発点は身近なもののほうがわかりやすい。伝わりやすいんだろうなと思います。そこは大事にしているかもしれないですね。
――『シスター・レイ』にはフィリピン系日本人、ベトナム人の半グレ、中国の秘密警察、日本のヤクザ、警察など、さまざまな組織の人間が出てきますね。利害関係が複雑に入り組み、そこにサスペンスが生まれています。
長浦:これもこのごちゃごちゃが現実なんです。嘘みたいな話ですけど、秘密警察に誘われたとか、圧力をかけられたっていう日本在住の中国人に会ったことがありますよ。夜の街で。
外国人には外国人の、日本人には見えていないネットワークがあるんです。だからぜんぜん遠い話じゃない。世界の縮図というか、民族間の紛争とか揉め事っていうのはすぐ隣にあるんだと思いますね。
――その中に、主人公の玲が巻き込まれてくるわけですが、彼女がなぜ関わってしまうのかが、『シスター・レイ』の謎でもあり、魅力でもあると思います。
長浦:玲は自分の立ち位置がはっきりしていないんですよ。
日本人で、日本のモラルがあって生きているならいいけれど、日本で生まれて、フランスに行って、また日本に帰ってきている。何を信条に生きていくかが定まっていない。
唯一あるのが、優しくしてもらったから優しくするとか、これだけの気持ちを向けてくれるから、私も同じくらい返さなきゃ、くらいしかないということ。
でも、実際、外国人とつきあっていく時の共通項ってそれしかないなとも思いますね。
日本人としてのモラルとか倫理は、外国人のコミュニティの中では通用しない。国ごとの正義の形があるわけで、日本人の正義の形とは違う。日本人と生活圏が重なった時、それが衝突する原因にもなります。
玲のように、母親の介護を一生懸命してくれる人がいるから、彼女が困っていたら恩返ししなきゃいけないという考え方が、いちばんシンプルで、共通項になりえると思います。
――貸しと借りは万国共通だと。
長浦:日本人でも海外に住んだことがある人や、長く旅行に行った人ならわかると思うんですが、共通の規範がない中で人間が守る最低限のことがそれなんですよ。古い言葉で言えば義理です。玲はそれを欠くまいと戦う女性なんです。
作品紹介
書 名:シスター・レイ
著 者:長浦 京
発売日:2025年03月31日
東京下町に隠された巨大な裏社会。元特殊部隊の“シスター”が闇を駆ける!
東京墨田区の外国人たちの相談役的存在で、「シスター」と慕われる、予備校の英語講師、能條玲。フィリピン出身の友人女性からの頼みで彼女の息子を探すことになった玲は、彼を探すうちに、ひょんなことから暴力団と外国人半グレ集団とのトラブルに巻き込まれてしまう。普段はただの一般人としてふるまう彼女だが、元フランス特殊部隊のエースという隠された経歴があった。前職の技術を活かし、暴力団と半グレたちを制圧して事件を解決に導く玲。その後も相次ぐトラブルに巻き込まれた外国人たちを助けていくうちに、玲は下町に隠された国際的な陰謀に巻き込まれていく。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322211000505/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら
関連記事
▼ 試し読みはこちら!
【試し読み】東京下町に巣くう犯罪と陰謀!――長浦 京『シスター・レイ』第Ⅰ章全文特別公開!
https://note.com/kadobun_note/n/n20002bf0b600