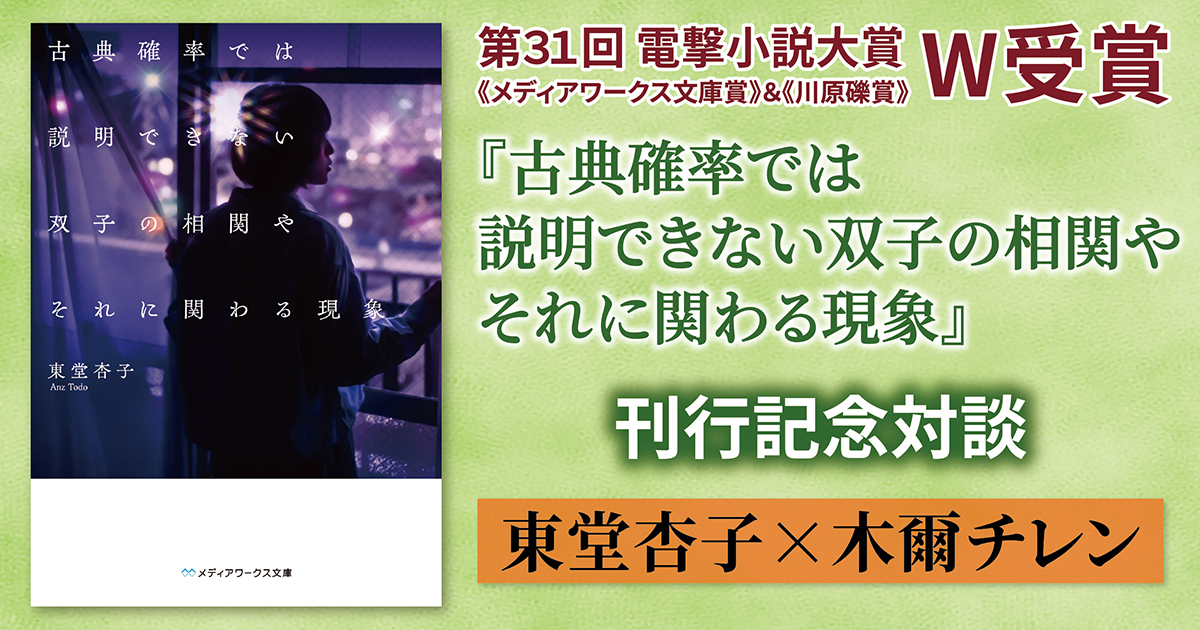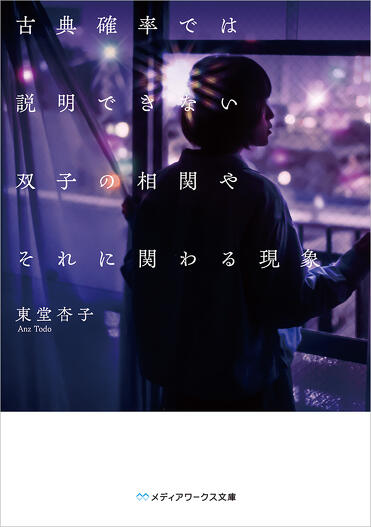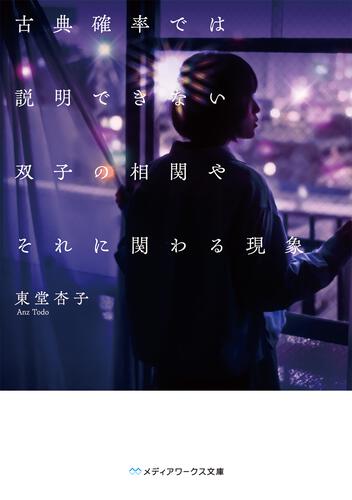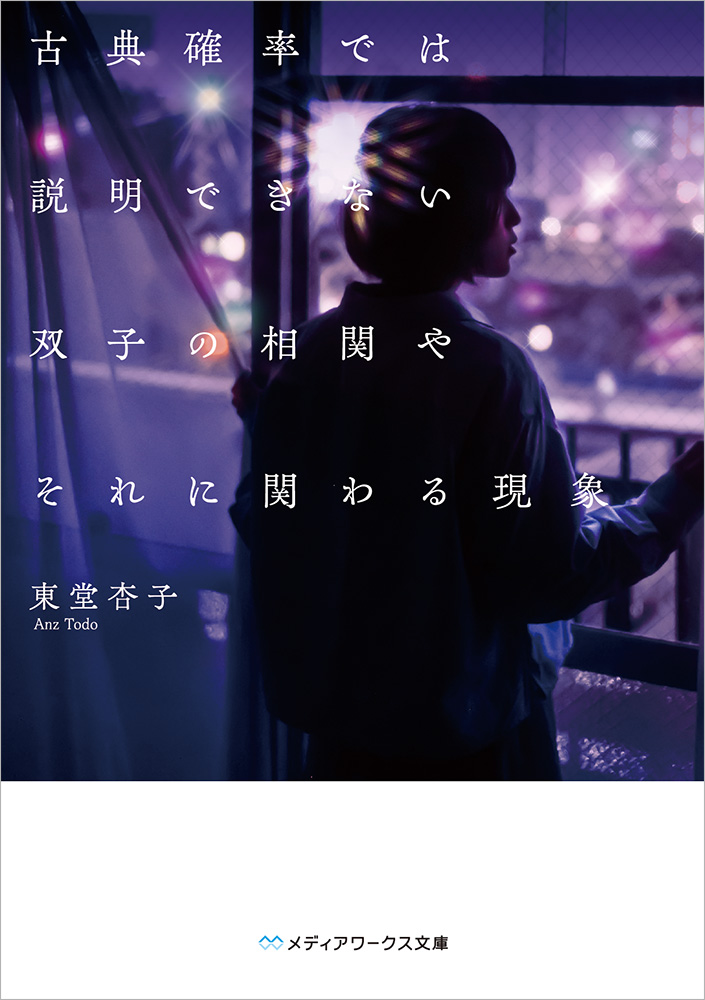第31回電撃小説大賞 《メディアワークス文庫賞》&《川原礫賞》をW受賞した東堂杏子さんと、最新刊『二人一組になってください』がベストセラーになっている人気作家・木爾チレンさんの緊急対談が実現! 受賞作の感想をはじめ、小説の作り方や今後書きたい物語など、熱く語り合っていただきました。
構成・文/高倉優子
『古典確率では説明できない双子の相関やそれに関わる現象』刊行記念 東堂杏子×木爾チレン 対談
いままでにない
新感覚の青春小説の誕生
――まずは受賞作『古典確率では説明できない双子の相関やそれに関わる現象』の感想をお願いします。
木爾:いままでにない新感覚の青春小説だと思いました。いろんな形の恋愛が描かれていますが、私が一番好きだったのは叔母の理恵に恋しているヒロインの真魚の物語です。こういう設定は文芸界隈ではあまり見かけないですが、それをライト文芸に落とし込んで書いてらっしゃったのが印象的でした。
東堂:今作は「恋の話が書きたい」と思って書き始めました。私が読んできたBL小説などでは近親者に恋をしてしまうイケナイ恋やタブーの恋愛がたくさん描かれていて、それに慣れていたせいか、深く考えずに書いてしまったんです。
木爾:確かにBL小説では割とあるかもしれませんね。私も腐女子だったのでわかります(笑)。でも姪が叔母に恋をするってすごくいいと思う。私も書きたいくらいです。こういう設定にすると「リアリティがない」と言われてしまいがちですが、東堂さんはリアリティを持って堂々と書かれていた。そこが素晴らしいと思います。男女の双子を主人公にしようと思ったのはなぜですか?
東堂:男の子のための恋愛小説と、女の子のための恋愛小説を足して割らないようなお話が書けたら面白いかなと思ったのがきっかけです。そういう話が自分でも読んでみたいな、と。
木爾:ひとつの恋愛を男性側からと女性側から描くということは私もしたことがありますが、ふたつの恋愛を描くって確かにあんまり見ない構成かもしれません。また双子には共鳴する不思議な力のようなものがあると言われますし、そういった部分を効果的に物語に組み込んでらっしゃったと思います。
勇魚の隣の部屋に住む飯田さんも魅力的な女性ですよね。親友から「やきもち焼きの年上女って、なんだかエロくていいな」と言われたのに対して、勇魚が「でもキレたら面倒くさい。それさえなければ、ぼくにはもったいない」と答えるシーンがありましたが、「私も夫から同じことを思われてそう!」と思いました(笑)。夫が11歳年下なんですが、私は全然しっかりしていないし、落ち込んで彼の前で泣き叫ぶこともあるんです。だから飯田さんのことを年上だからと型にはめて、しっかり者のお姉さんのように描いていないところにリアリティを感じたし、共感もしました。
東堂:飯田さんはルックスも性格もかわいらしい人として描こうと思いました。それで元アイドルという経歴にしたんです。最初はもう少しメンヘラ気味だったんですが、少し抑えて。
木爾:メンヘラすぎると共感できないし、ちょうどいい塩梅だったと思います。私の周りには芸能界をかじった人がけっこういるんですけど、そういう人たちとトップ・オブ・トップにいる人とでは大きな差があるんですよね。飯田さんも美しい人だけど、自分の能力を理解していて、芸能界への諦めもついている。そのあたりの感覚も絶妙でした。
――キャラクターの名前について、どのように名づけられたのかお聞かせください。
東堂:クジラの古名が勇魚だと知ってかっこいい、いつか主人公の名として使いたいなと胸に秘めていました。またそれと対になる名前として考えたのが真魚です。旧約聖書のなかで、神が飢えた民のために空から降らせた食べ物のことを「マナ」というそうですが、意味も響きも気に入ったので決めました。チレン先生は普段、どんな風にキャラクターの名前を考えていますか?
木爾:その物語にふさわしい名前というのを意識して付けるようにしています。たとえば映画「アマデウス」をオマージュして書いた作品『神に愛されていた』に登場する冴理と天音は、サリエリとアマデウスから取ったものです。
また『二人一組になってください』の場合は、登場人物が多いので名前とキャラクターを考えるだけでも1か月かかりました。キラキラネームになりすぎないように気をつけつつ、個性的な名前をつけないと覚えてもらえないかもしれないから○○にしよう、とか、平凡なキャラクターだから○○にしよう、とか、一軍の子には、それらしい名前をつけようとか。あえて型にはめながら考えていきました。
東堂:たくさんのキャラクターが出てくるから、さぞ交通整理が大変だっただろうと思いました。しかも、デスゲームにはいくつものルールがあり、それがまったくムダがなくて、最後には泣けて……。本当に素晴らしかったです。
木爾:ありがとうございます。プロットだけでも100枚くらいは書いたでしょうか。過去で一番、時間をかけて考えた作品なので嬉しいです。
東堂:どんなプロットだったのか気になります(笑)。チレン先生は、アマチュアのときからプロットを立てて書かれていたんですか?
木爾:デビュー作も、デビューしてからもプロットは立てずに書いていました。でも、テーマやメッセージ性は明確にしておいたほうがいいと思い、ここ数年は細かくプロットを立てるようになったんです。
東堂:私はすぐ書きたくなって、先を考えずに手を動かしてしまうんです。今作も、思いついたことを全部入れたので改稿するときにすごく苦労しました。
木爾:駆け出しのときはそれでいいんだと思います。感性のまま書ける時期ってとても大切ですから。私もアマチュア時代の作品を出版するために改稿していると、ムダな部分がたくさんあって驚きます。でも「どこが不要か」を考えて改稿するうちに力がつくと思いますし、私の場合は、プロットを立てておいたほうが効率的だと気づいたんです。
東堂:すごく参考になります!
キャラクター作りは
お人形遊びの延長にある
木爾:キャラクター設定についても、人間性が定まっていないと物語が動き出さないと思っているので、プロットの段階でしっかり決めています。たとえば「自己肯定感は低いけれど才能がある人」など。また、性格は容姿に表れると思うので、その人の外見についてもしっかりイメージしてから書いています。
東堂:私のキャラクター作りはお人形遊びの延長。自分の中に、男女それぞれ3人が所属している脳内劇団があって、いろいろな演目を演じているというイメージです。
木爾:作家になっている人って、小さいころ「ごっこ遊び」をしていた人が多いらしいんですよ。私もそうでした。自分の中に6人くらいの人格がいて、「今日はこの子でいこう」という感じで遊んでいたんです。
東堂:やっぱり!「ごっこ遊び」って楽しいですもんね。私がキャラクターの容姿について詳細を書かないのは、いつも同じ脳内劇団のメンバーが演じているからかもしれません。中高生のとき、大学ノートに書いた小説を友だちに読んでもらっていたんですが、「どんな服を着て、どんな顔をしているのかわからない」と言われることがありました。自分の妄想を人に伝えるのってすごく難しいですよね。
木爾:確かに。いくら自分の頭に容姿や表情が浮かんでいても、それを描かなければ読者さんには伝わらないですもんね。でもそれができるようになると、もっともっといろんな作品が書けるようになるかもしれませんね。なんて上から目線ですみません(笑)
東堂:いえいえ、ありがたいです。小説って本当に難しい(笑)。改稿しながら、「こりゃ面白くないな」と思う部分もあって。
木爾:それは私にもありますよ。『二人一組になってください』の中で、「やや陳腐かな」と懸念していたシーンがあったんです。でもフタを開けてみたらそこが一番人気だった。そんな風に作者の意図に反したところが好評だったり、面白いと思ってもらえたりすることもあるので、あまり気にしすぎなくていいんだと思います。
東堂:チレン先生の作品はタイトルも秀逸ですよね。『みんな蛍を殺したかった』を手にしたときも、「殺したかったから殺したのかな?」「じつは殺さなかったのかな?」と、気になって一気に読みしちゃいました。タイトルって大事ですね。私はタイトルが決められなくて、空欄にしたまま書き始めてしまいます。
木爾:私はタイトルから決めて書くタイプです。『みんな蛍を殺したかった』は初のミステリ作品だったので、「こんなにド直球のタイトルでいいのかな?」と迷いましたが、それがヒットしたということは、タイトルはキャッチーなほうがいいんだな、と。タイトルの大切さを自分の作品から学びました。
東堂:今後は私もタイトルについてしっかり考えて書こうと思います。
自分の気持ちを伝える場として
物語を使っている
――小説を書く上でおふたりが大切にしているモットーがあれば教えてください。
木爾:私は辛いときに、Xにそのまま「しんどい」とは書きたくないんです。だから物語を使って、痛みや膿を吐き出している感覚があります。たとえば『みんな蛍を殺したかった』のストーリーはフィクションですが、キャラクターたちが抱く感情は自分の中から出てきたものが多いです。小説を書く上でストーリーはもちろん大切ですが、心の機微を書くための器だと思っています。その器のなかに入れたいのは「少女の痛み」であり、それが私の創作のテーマのひとつなのだと思います。
東堂:痛みって相対的なものじゃなく、絶対的なものじゃないですか。自分の痛みは自分にしかわからない。私は出産を経験していないので、人生で一番辛かったのは胆石の痛みなんです。でも別の人から「出産の痛みに比べれば大したことはないよ」と言われてすごく傷ついた。だから私も小説のなかでは、「あなたの痛みはあなたのもの。痛いって言っていいんだよ」というメッセージが伝えられたらいいなと思っています。
木爾:私は小説を書いていないと生きている意味がないとさえ思います。書くこと自体は辛い。でも書いていないときや書けないときのほうがもっと辛いんです。しゃべることが上手じゃない私にとって、小説は本音で自分の本当の気持ち伝えられる唯一の場所なんです。書いているときだけ息ができているなと感じます。
東堂:私も何度か小説を書くことをやめようと思いました。でも、ほかの趣味を始めてもすぐ飽きて小説に戻ってしまう。小説を書くことがすっかり自分の人生の一部になってしまっているんです。「今日は何を食べよう?」くらいの感覚で、物語の続きを書く生活をずっと続けてきたので。今後、本が売れても売れなくても一生書き続けていくんだと思います。
木爾:ダメだよ、売れなきゃ!(笑)売れない時代が長かったからこそ感じますが、売れるからこそ、いろんな仕事がさせてもらえるし、作家として大切にしてもらえるんです。私はずっと小説家でいたいので本を出し続けたい。そのためにも売れる本を書かないといけないと思っています。
東堂:自分自身と自分が書いた小説を肯定できないというか、自分で手放しに褒められないような人間だったので、これからは「うちの子(小説)が一番」と言えるようになりたいと思います。
木爾:それがいいと思います。作者が「自信作ができました」と言っていたら読みたくなる方もいる。いいものが書けたときは「読まないと損だよ!」ってくらい、堂々と言っていきましょう! 私は今後も「少女の痛み」をテーマに書き続けたいですが、37歳のいま等身大の物語も書いてみたいと思っています。私も東堂さんと同じく出産を経験していないことをコンプレックスのように感じています。その気持ちを物語に落とし込んで書くことで、同じような悩みを抱えている方の痛みを和らげられたらいいなと思う。模索しながら書き進めているところです。
東堂:素晴らしいですね。早く読みたいです。私は当事者じゃない人にスポットを当てた物語が書きたいです。たとえば大きなトラウマを抱えているとか、社会からこぼれてしまったとか、そういうことではなく、それを近くで見ているだけで何もできずに苦しむ人たち。そういう人たちが救われるようなお話が書けたらいいなと思っています。
著者プロフィール
東堂杏子(とうどう あんず)
福岡県北九州市生まれ。2000年頃より個人サイトを運営するも閉鎖。長い沈黙を経て、2019年より紅玉いづき主宰の同人誌『少女文学』に参加し文筆活動を再開。2024年、『古典確率では説明できない双子の相関やそれに関わる現象』で第31回電撃小説大賞 《メディアワークス文庫賞》・《川原礫賞》を受賞し商業デビュー。冷めやすく飽き性で、趣味は浅く広く。
木爾チレン(きな ちれん)
1987年京都府生まれ。2009年、大学在学中に執筆した短編小説「溶けたらしぼんだ。」で新潮社「第9回女による女のためのR-18文学賞」優秀賞を受賞。2012年、『静電気と、未夜子の無意識。』(幻冬舎)で作家デビュー。2021年『みんな蛍を殺したかった』(二見書房)をはじめ、2024年『二人一組になってください』(双葉社)もベストセラーに。他の著書に、『私はだんだん氷になった』(二見書房)、『そして花子は過去になる』(宝島社)、『夏の匂いがする』(マイクロマガジン社)などがある。
作品紹介
書 名:古典確率では説明できない双子の相関やそれに関わる現象
著 者:東堂杏子
発売日:2025年04月25日
レーベル:メディアワークス文庫
二十も離れた弟の誕生――それがすべての始まりだった。
斉藤勇魚と斉藤真魚。男女の双生児でともに二十歳の大学生。二人の人生は、年の離れた弟の誕生で一変した。
広島の大学に通う勇魚は親友に恋人を奪われ荒んだ日々を送り、北九州の実家で暮らす真魚も最愛の人に突然捨てられ世界に絶望する毎日。
そして二人は、奇しくもそれぞれの隣人との奇妙な交流に救いを求めていく……。
やがて気付いてしまった家族の真実。親子、恋人、親友――すべての日常が絶望と綯い交ぜとなった双子の青春の行き着く先とは?
大人になることの「痛み」をリアルに描き、第31回電撃小説大賞で《メディアワークス文庫賞》《川原礫賞》をW受賞した、ままならない愛と青春の物語。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322410001612/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら
書 名:二人一組になってください
著 者:木爾チレン
発売日:2024年09月19日
卒業式直前に始まったデスゲーム(特別授業)
あなたに本当の友達はいる?
「このクラスには『いじめ』がありました。それは赦されるべきことではないし、いじめをした人間は死刑になるべきです」
とある女子高の卒業式直前、担任教師による【特別授業(ゲーム)】が始まった。突如開始されたデスゲームに27人全員が半信半疑だったが、余った生徒は左胸のコサージュの仕掛けにより無惨な死を遂げる。
自分が生き残るべき存在だと疑わない一軍、虚実の友情が入り混じる二軍、教室の最下層に生息し発言権のない三軍――。
本当の友情とは?
無自覚の罪によるいじめとは何か?
生き残って卒業できるのは果たして誰か?
詳細:https://www.futabasha.co.jp/book/97845752476880000000