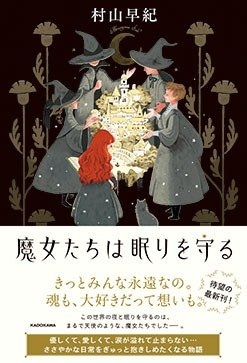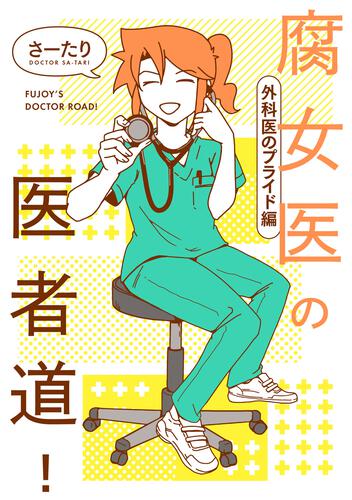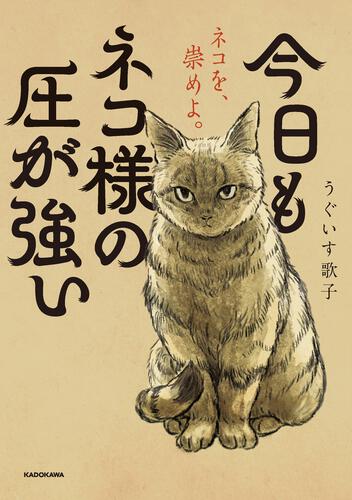この世界の夜と眠りを守るのは、まるで天使のような、魔女たちでした――。
人気作家・村山早紀さんの待望の新作小説『魔女たちは眠りを守る』が4月16日に発売!
今回特別に、全7話の中から、第1話「遠い約束」をお届けします。
懸命に生きて、死んでゆくひとの子と、長い時を生きる魔女たちの出会いと別れの物語、ぜひお楽しみください。
◆ ◆ ◆
第1話 遠い約束
その街は、古い港町。
海からの風が街とひとびとを包み、見えない手が優しくその身を撫でる、その繰り返しが数え切れないほどに続いてきた、そんな街だ。
年々
いまは春。街のあちこちで桜が一斉に花開き、白や薄桃の花を咲かせ、時折吹く強い風に、数え切れないほどの花びらを散らせる、そんな季節だった。
さて、桜の花びらは港のそばの、古い駅の空にも舞い落ちる。
丈が長く古めかしいデザインのコートを着て、これも古めかしいブーツを履いた小柄な若い娘がひとり、大きなトランクを引きずるようにして降りようとする。トランクもまたよい感じに古びていて、時を超えていくつもの旅を経てきたのがわかるようなもの。その娘が持つには大きすぎるようにも見える。トランクに比して、白いてのひらは小さく、背丈もずいぶん低いのだ。娘は片方の腕に、ふさふさとした毛並みの黒猫のぬいぐるみを抱いていて、トランクよりも、そのぬいぐるみの方が、よほど娘には似合っているように見える。
それでも娘は楽しげに、大きなトランクを力を込めて持ち上げて、プラットフォームへと、はずむように足を踏み出す。
「よいしょっと」
トランクと一緒に、半ば飛びおりるようにホームに降りると、長く赤いくせっ毛が、背中で翼のように広がり、跳ねる。
まだ十代か、それとも二十代に入ってはいるのか、年齢がわからないのは、くるくると変わる表情と、いろんなものに視線を投げる、大きな薄茶色の瞳のせいだろう。あるときは思慮深く見え、そしてあるときは、無邪気な幼い子どものように見える、そんな娘だった。
そんな娘の様子を、少し離れたところから、老いた駅員がひとり、必要なときは手を貸そうと、優しげなまなざしで見守っていたのだけれど、娘はそれに気づいたかどうか。
駅員は、通り過ぎていく娘を見送って、ふとまばたきをした。
(おや、あのお客さんは、猫なんて連れていたろうか?)
いつの間にか、娘の足下をふさふさとした
(猫連れならば、猫は
駅員は首をかしげる。猫連れの旅人ならばそうするものだ。そういえばあの娘は、さっき腕に黒猫のぬいぐるみを抱いていたように見えたけれど、腕にはもう何も抱いていない。まさかあれが、おもちゃではなく、生きている猫だった──?
(いやあれは、ちゃんとぬいぐるみだったぞ)
黒猫が駅員の方を振り返り、金色の瞳でにやりと笑ったような気がした。でもそんなことあるわけがないから、やはり自分の気のせいなのだろう、と駅員は思う。認めたくはないが、自分もすっかり年老いた。
何にせよ、そんな子ども向けの本の世界の中で起こるようなこと、現代日本で起こるはずもない。
黒猫を連れた娘は、大きなトランクを提げて、駅の改札の方へと歩いていこうとする。
駅にほど近い公園の時計台が時を告げる、その鐘の音が風に乗って空を流れた。
娘が立ち止まり、鐘の音の響きを目で追うように、空を振り仰ぐ。
「わあ、懐かしい。昔のままね」
それはまだ子どものような、甘さと幼さのある声で、けれど落ち着いた、優しい響きを持つ声でもあった。
「ずいぶん久しぶりなのに、中央公園の時計台の、あの鐘の音は変わらないのね」
『そうね、ナナセ』
娘の顔を見上げ、金色の目を細めた黒猫が、甲高い声でそういったように聞こえたのも、駅員の気のせいだっただろうか。
「
『さあねえ。どうかしらねえ』
改札の方へと、娘は長いコートをなびかせて歩み去っていき、黒猫もまた、ふさふさした尾をなびかせながら、それについていく。
老いた駅員は、口の中でまさかねえ、と繰り返しながら、娘たちを見送ったのだった。
改札口の向こうには、夕暮れの光に包まれる、繁華街の情景。背の高いビルが輝く森のようにそびえて見える、そんな景色の方へと、娘と黒猫は歩を進めていく。ちらほらと桜の花びらが、その姿に降りかかる。娘と猫を迎えるように。
物語の時間は、少しだけ進んで、その日の夜となる。
古い港町は、店々に
春の宵、吹き過ぎる夜風はまだたまに氷のようにひやりとしながらも、どこかにふくらんできた木の芽や花の香りを隠している。
行き交うひとびとは、夜風の冷たさに急ぎ足になり、春の軽やかで薄いコートの前をあわせたりしつつも、その季節特有の、何かよいことや不思議なことがありそうな気配に、胸の奥をわくわくさせているような、そんな夜のことだった。
ひとびとの頭上には大きな満月が輝いていた。降りそそぐ光を受けて、街は金銀の粉を散らしたように、ほの明るく、淡くひんやりと輝いて見えた。その夜は、海からのもやが薄くかかっていて、そのせいで、街全体が小雨に打たれたようにうっすらと濡れていた。
やがて、人通りが途絶えた。大きな道路を光の尾をなびかせながら行き交っていた車の群れまで、魔法のように途絶え、まばらになっていた。
もう夜も遅い時間だ。繁華街の灯りもひとつふたつと消え、働いていたひとびとも店を片付けて、からだを休めるために帰っていく、そんな頃合いになっていた。
さてその街には、駅や繁華街からはやや遠く、海にとても近い場所に、古く小さな商店街があり、その名を三日月通りという。
その辺りの建物からならば、多少背丈が低くとも、窓を開ければ海が見えるような、それほど海に近い場所だった。街外れ、ともいえる。
新旧の様々な倉庫や、見捨てられたような古い建築物(いまは所有者もわからない建物が多いといわれている)が並ぶせいもあって、その辺りはどこか薄暗く、人通りもない。
倉庫と船乗りのための宿や酒場、食堂が並ぶような通り、この街の住人よりも、遠方からの旅人を客に迎えることが多かった歴史を持つそんな通りは、かつては真偽のわからない物騒な話や恐ろしげな噂がつきものの場所だった。実際、戦後のある時期は、
さてその三日月通りにほど近い、海にそそぐ
冬物の重そうな灰色のコートを身にまとい、長身を猫背気味に折り曲げて、足下だけ見ながら、とぼとぼと歩いていた。雑に束ねた髪は重たげ、今風ではない黒いフレームの眼鏡も重そうで、月の光を背に受けて歩く様子は、ひとりきりの葬列のようで、そんな生気のない、悲しげな様子なのだった。
背中にしょった大きなリュックサックと、腕に提げた鞄には、いつもの仕事帰りと同じに、たくさんの本が入っている。
彼女の名前は
いわゆるカリスマ書店員と呼ばれるような日の当たる存在ではないけれど、職場から信頼され、自分なりに仕事に自信も誇りも持っている、そんな働く女のひとりだ。仕事はひたすら忙しく、しかし給料は上がらず、
この店と業界とそして老いていく自分のこれからを考えると、明るい要素が見出せず、不安になるときもあるけれど、本と書店が大好きで、一心に働いてきた。後悔はしない、と、ときに不敵に笑い、ときに歯を食いしばりつつ、ひとり生きてきた、のだけれど──。
今夜の彼女は、ため息をつく。
「──なんかもう、消えちゃいたいな」
夜の闇にいまにも引き込まれて消えてしまいそうな、そんな弱々しいささやくような声だった。昼間の彼女、ふだん店で顔を上げ急ぎ足で働いている彼女を知るひとが見れば、別人のようだと思うような、そんな声だった。
「少しだけ、疲れちゃったなあ……」
満月の光を映す、水路の暗い水面に視線を落とす。懐かしいような海の香りがした。夜風がほつれた髪をなびかせ、首筋の辺りの熱を奪う。寒気がした。
ふいに、嵐のように強い風が吹き過ぎ、髪を巻き上げて、水面にさざなみを立てた。どこからか吹いてきた桜の花びらが、踊るように、たくさん夜空に流れ、水に落ちた。
春のはずなのに、もう桜も咲いているのに、いつまでも寒いなあ、と思った。今年の冬はいつまでも終わらないような気がする。ふと、ずうっと昔にも、こんな冬、いや、寒い春があったような気がしたけれど──記憶違いだったろうか。強い風が、嵐のように吹き荒れた春。
(ええと、あれはたしか、高校二年生になったばかりの春──だったと思う)
子どもの頃に読んだ宮沢賢治の、『風の又三郎』を思い出した記憶がある。
ガラスのマントを身につけた、不思議な子ども、又三郎が空を駆け抜けていくような、そんな風が吹いていると思ったのだ。あれは春ではなく秋の嵐とともにやってきて去っていった、不思議な転校生の物語だったけれど。
子どもの頃の叶絵は、いまと同じに本好きで、でも家族は本にも本が好きな叶絵にも興味と理解がいまひとつなかったので、家には本がなく──彼女は学校の図書館で宮沢賢治全集を読んだのだった。
「そう。不思議な転校生に会ったんだよね。高校生だった、あの春に」
叶絵は再びため息をつく。最近のようなずっと昔のような、あの時代。
そんな記憶と経験があるような気がするのだけれど、それもこれも錯覚で、いつの間にか脳内で生まれていた、いってみるならば「噓」の記憶なのだろうか。
ここのところ、疲れのせいか、それとも年のせいか、自分の記憶に自信がまるでない。
「昔から、無意識のうちにお話を考えて、自分でそれを信じすぎて、夢と現実がごっちゃになることもあったし……」
本が大好きで、本の世界に没頭することが多かった。学校の行き帰りには、通学路で本を読んでいて、車に
(それで余計に本なんて読むなと叱られて、本、買ってもらえなかったんだよね)
叶絵の方は、それで余計に本への執着が増し、のめり込んでいったのだけれど。子どもというのはそういうものだ。親の愛、家族の愛に気づかなかったのも、そういう年頃だったからかも知れない。ひとりぼっちのような気分になっていたのを覚えている。ほんとうの両親がどこかにいて、いつかは迎えに来てくれるんじゃないかとか、そんな物語にあるような妄想をよくしていた。何しろ、物語が──本が大好きな子どもだったから。妄想も空想も、得意中の得意というもので。
(そのまんま、おとなになったんだよな)
風に揺れる
風が背中を押すように吹いた。疲れた足下がよろけて、冗談のように簡単に、水路に転がり落ちそうになった。
「やば」
慌てて踏みとどまったけれど、瞬間、それもいいか、と思った。ほんの一瞬だけれど。
どうせ自分なんて水に落ちても、それきりこの世から消えてしまっても、心配するひとも嘆くひともたいしていないだろう。
店もこの街も日本も世界も、叶絵がいてもいなくても関係なしに回っていって、いつか叶絵の存在など覚えているひとはどこにもいなくなり、最初からいなかったのと同じことになってしまうのだ。
「いてもいなくても、おんなじかあ」
暗い水面を眺めながら、小さく呟いた。
自分がこの世界に生きている意味って、ないような気がするなあ、と。
(つづく)
▼村山早紀『魔女たちは眠りを守る』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000467/