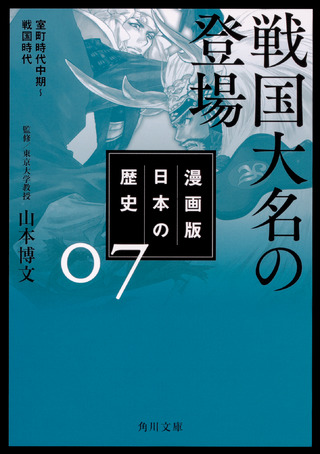書評家・作家・専門家が《新刊》をご紹介!
本選びにお役立てください。
(評者:桐野作人 / 歴史作家)
著者の大西さんとは二回り以上齢が違うが、不思議な関係が長く続いている。じつはお会いしたこともないし、いつ頃から何がきっかけで知り合い、交流するようになったか、今となっては記憶もおぼろげである。
それなのに、彼の膨大な著作や論文はおそらくほとんど全部もっているのではないか。対象こそ違えど、私も歴史を生業としているせいか、彼の仕事ぶりをずっと横から観察していた気がする。
一言でいえば、大西さんは取り憑かれた人である。何にかといえば、郷里岡山の宇喜多氏という大名のすべてを調べ尽くさずにはおられないという鬼気迫る探究心にである。
その意味で、本書は彼の真骨頂が結実した作品である。豊臣秀吉の縁者ながら関ヶ原で敗北して八丈島に流された宇喜多秀家という貴公子とは何者なのかを明らかにしようと、膨大な史料を博捜して徹底的に突き詰めた考証の書である。
彼の執念に向き合うため、当方もメモを取りながら拝読したら、膨大な量になってしまったほどである。新書ながらも本書の濃密さに圧倒されたのである。
宇喜多秀家を成り立たせていたのは三つだと感じた。宇喜多家を大名に押し上げた父直家の遺産、後見人となった秀吉、そして妻の樹正院(豪姫のほうがなじみがある)である。秀吉はなぜか幼い八郎(秀家の通称)を気に入り、男だったら関白にしたかったと語って実子同様に可愛がっていた養女の樹正院と娶せた。秀家が樹正院の夫だったため、秀吉から格別に引き立てられたという面もあった。大西さんは有名な樹正院の狐憑きを取り上げて、「彼女がこときれた場合、秀家はその政治的地位を従前通り維持しうるかどうか、はなはだ微妙」とさえ書いている。
秀家はまわりのあらゆるものをお膳立てされ、すべてが他律的だった。大西さんは秀吉という絶大な後援者の存在が秀家の大名としての成長を妨げたと指摘する。
当然、血気盛んだった若い秀家ももがき葛藤する。大名として武将としてのアイデンティティの確立に悩んだ節がある。文禄の役で朝鮮に出陣すると、秀吉から苦戦する日本軍の総大将に任命される。秀家は、秀吉の厚遇や官位に見合った働きをしようと気負い、前線への出陣を望むが、秀吉から首都漢城(現・ソウル)への駐屯を命じられてしまう。その落胆は察するに余りある。漢城からほど近い幸州山城の戦いでようやく出陣し、矢傷で負傷したとき、秀家はむしろ武将としての喜びさえ感じたのではないかと思える。
豊臣大名としての秀家の評価に関わるのが、大老就任と宇喜多騒動である。大西さんの力も入る。大老就任については、秀吉の親族大名が早世し、秀家だけ残ったという外在的な事情があったとする。それでも、秀家は自分に与えられた役割を忠実に守ろうとした。通説では若年のために大老と奉行の調整役を命じられていたといわれるが、大西さんはそれに飽き足らず、秀家は前田利家とともに、親族の立場から幼君秀頼を支える格別の地位にあったことを肝に銘じていたと見ている。その具体的な表れがあえて太閤遺命に背いた徳川家康との起請文に示されている。衰弱した利家に代わり、その嫡男で秀家には義兄にあたる利長を大老の地位に引き上げ、豊臣政権の安定のため、家康と利家・利長との勢力バランスを保つことにつとめたとする。
一方、宇喜多騒動は豊臣大名としての秀家の「脆弱性」を示した事件だった。大西さんはこの事件の通説を疑い、再検討して訂正する。一方の当事者である中村次郎兵衛は樹正院の実家、加賀前田家の家来ではなく、播磨の地侍の息子だったという。またこの騒動がキリシタンの出頭人と仏教勢力の一門重臣の抗争という構図とする通説も否定する。個人的に興味深かったことは、事件後、次郎兵衛が前田家に召し抱えられても能吏として働き、新井白石に賞賛されていたことである。
秀家に抵抗、致仕した一門重臣のなかで面白いのは宇喜多忠家・浮田左京亮(のち坂崎出羽守)父子の奇矯ぶりである。父忠家は朝鮮の碧蹄館の戦いで、諸将が長軍議をしているのにしびれを切らして勝手に先駆けして勝利を収める放胆さ。息子左京亮は大坂夏の陣での千姫事件で知られる。そのわがまま勝手で周りを巻き込んで自滅していく。
最後になるが、大西さんが樹正院の実家、前田家がある石川県に居を移したことが本書にさらに厚みを加えたと思える。八丈島に流罪となった秀家主従を幕末までじつに二六〇年の長きにわたって援助した前田家の膨大な史料との出会いが、秀家の「寂寥たる後半生」を活き活きと描くことに成功している。
ご購入&試し読みはこちら▷大西泰正『「豊臣政権の貴公子」宇喜多秀家』| KADOKAWA