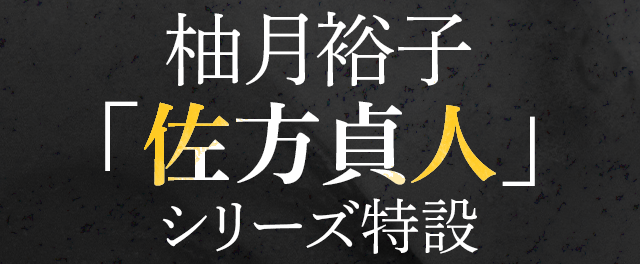桜木紫乃が書くものは、いつも凄い。が、『砂上』の桜木紫乃は、もの凄い。
札幌から電車で約三十分の地方都市・江別に暮らす四十歳の柊令央が、雪の降る日の喫茶店で、のちに五歳年下だと判明する女性編集者の小川乙三と初めて会うシーンから物語は幕を開ける。公募エッセイの優秀賞に選ばれた令央は、わざわざ東京からやって来た乙三に対し〈会いたいと言われてから「本当は最優秀賞だったんですが何かの手違いで」という展開をずっと期待している〉。着座した乙三がコーヒーを頼んだのを見て、令央は「同じものを」と店員に告げた。すると、〈水をひとくち飲んだあと、彼女がするりと言った。「主体性のなさって、文章に出ますよね」〉。こちらの放つ言葉がすべて、負の要素に変換されて打ち返される、「期待」とは真逆の会話が始まる。やがて来訪の目的が明かされる。実は、令央は過去に何度も、小説の新人賞に応募していた。下読みを担当していた乙三は、二年前に令央が応募した『砂上』という短編に目を付けた。「自分が十六で産んだ娘を妹として育てる女と、その母との生活が柱でしたね」。題材はそのまま、『砂上』を長編小説として全面的にリライトする、という提案を半ば強制で呑み込まされる。
幼馴染みの男がシェフを務める、家族経営の小さなビストロでアルバイトをする日々。母が亡くなったばかりの一軒家で、妹の美利と十数年ぶりの二人暮らしを始める日々。三年前に別れた元夫と、月額五万円の慰謝料減額を巡って交渉する日々……。彼女はこの世界の片隅で本当に息をしている、と感じさせる日々の描写の中に、少しずつ少しずつ、新たな『砂上』を構想し執筆する日々の描写が入り込む。ギアを上げるきっかけとなったのは、乙三から来たメールの一文だ。〈経験が書かせる経験なき一行を待っています〉。虚構とは、経験した現実を再現するものではない。だが、現実は、虚構のネタになり、エサとなる。『砂上』と共にある日常は、令央の五感をセンシティブに作り変える。より面白くより刺激的な経験ができるよう、それまでのルーティーンとはまるで異なる言動を放つようになる。虚構と現実の境界線が揺らぎ出し、「主体性」とはほど遠かったはずの令央が、変わる。
この物語が描いているのは、乙三という他者(メンター)の存在を引き金に、小説という表現手段によって実現した令央の変化感触がより近い言葉を選ぶならば、進化だ。ただし最終盤で明かされる、令央の出産にまつわる真実を吟味したならば、印象が変わる。令央は現在の人間性を別のそれへと変化や進化させたのではなく、人生のある時点から抑えつけていた本性を、解放したのではないか、と。『砂上』の何よりの魅力は、ここにある。読み返すことで伏線を拾い上げ、疑問点を解消し理解度を高める、というのが通常の読書であるならば、本作は読むたびに不確定性が増していくのだ。例えば令央にとって乙三との出会いは幸福だったのか? 分からない。だから、また読む。分からなくなる。一生読める、それだけの価値とタフさを伴った、これはもの凄い小説だ。

『ふたご』
藤崎 彩織
(文藝春秋)
4人組バンドSEKAI NO OWARIのSaoriこと藤崎彩織の初小説は、中学2年の頃から始まり、とあるバンドを結成しデビューの端緒を掴むまでを描く。バンドのヒストリーを知る人ならばお馴染みのエピソードが多数盛り込まれながらも、〈経験が書かせる経験なき一行〉の感触が持続している。
紹介した書籍
関連書籍
-
連載
-
試し読み
-
試し読み
-
レビュー
-
試し読み