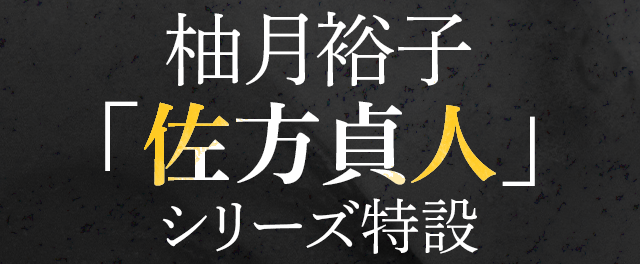『オリンピックがやってきた 1964年北国の家族の物語』は、青森県のとある町に住む前田家のエピソードを中心に一話完結形式で六つの物語が綴られています。
前田家は、アパート経営をする祖父と元気で気丈な祖母・ツナ、警察官の父・
家族は社会の中で一番小さな集団です。子どもも大人もそれぞれがそれぞれの人生を必死に生きていて、それは前田家の人々も同じです。
どんな自分でいたとしても、家族はありのままの姿をそのまま受け止めてくれる。どんなに疲れていても、家に帰ればゆっくりと自分を取り戻すことができる。そんな安心感があるからこそ、前田家の人々は悲しいことやつらいことや大変なことがあっても、みんなでごはんを食べてテレビを観る、ごく普通の毎日を過ごすことができているのでしょう。
手元にある岩波国語辞典で「家族」をひくと「同じ家に住み生活を共にする血縁の人人」とあります。理想の家族像は人によって様々ですが、私が理想の家族をイメージするとしたら、自分が自分らしくいられる前田家のような家族になるのだろうと思いました。
本作には、先の国語辞典には載っていない家族の形も描かれています。前田家と同じ町の西洋館に住む〝奥さま〟と呼ばれる西洋婦人と、住み込みのお手伝いのおトキ、そして奥さまの飼い猫のアーニャです。
二人と一匹にはもちろん、血縁関係はありません。奥さまとおトキは言いたいことを言い合うような関係で、ゆえに相手に腹を立てることもあります。しかし、心の深い部分ではお互いを尊重しあい、その存在に救われています。前田家と同様、西洋館の住人たちもまぎれもない家族です。
ふたつの家族に共通しているのは、よく会話をするという点です。メールもLINEもSNSもない時代において、主なコミュニケーションの手段は会話だった。前田家と西洋館の住人たちの様子から、そんな当たり前の事実にあらためて気づかされました。
家族の会話が多いのは、共通の話題が豊富にあるからなのでしょう。近所の人にまつわる噂話はもちろん、物語の舞台は一九六四年。十月に東京オリンピック開催を控え、日本中が沸いている時期です。前田家でも家族全員が東京オリンピックに並々ならぬ関心を持っており、折に触れてその話題が出ています。
一九六四年は、私が生まれるほんの少し前の時代です。にもかかわらず、戦争の影を引きずっていたり、カラーテレビが貴重品だったりと生活を取り巻く環境は現代とは大きく違っています。一家に一台のテレビの前で、家族そろって同じ番組を観る。モノも情報も少なくて、今よりもずっと不便な生活を送っているはずなのに、そこには私たちがうらやましく思ってしまうほどの幸せな空気が満ちています。
読後にほっこりとした温かさと同時にせつなさも感じたのは、前田家のような家族も、かつての日本が抱いていたような希望にあふれた未来も、少しずつ遠ざかっていることを心のどこかで察知しているからなのかもしれません。
最後に、ものすごく個人的な感想なのですが、全編にわたって繰り広げられる青森弁は東北出身の私の心に沁み、前田家と西洋館の食卓には大いに食欲を刺激されました。
紹介した書籍
関連書籍
-
試し読み
-
試し読み
-
レビュー
-
試し読み
-
試し読み